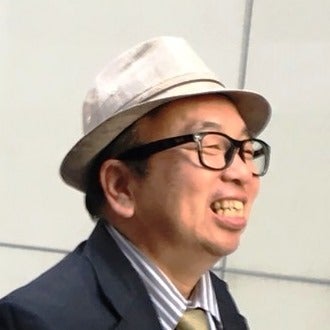人が成長する時には承認要求と言う欲求は必要なものです。
・尊敬されたい
・好かれたい
・賢いと思われたい
・才能があると思われたい
・面白いと思われたい
・信頼されたい
・理解されたい
・仕事ができると思われたい
・良い人だと思われたい
・誠実だと思われたい
・支持されたい
・センスがいいと思われたい
・気が利く人だと思われたい
・人間的に器が大きいと思われたい
・優しいと思われたい
・自分が中心でいたい
・価値があると思われたい
こういった承認要求を満たすために精神を鍛え、自身がスキルアップの努力をするものです。
一つずつでも良いので実現させることを薦めます。
しかし、この努力もせずに嘘や見せ掛けの言動で周りの人たちを誤魔化そうとすると、それはただの自己中な考えに陥り、大抵の場合は逆の評価をされることになります。
・尊敬させよう
・好きと思わせよう
・賢いと思わせよう
・才能があると思わせよう
・面白いと思わせよう
・信頼させよう
・わからせよう
・仕事ができると思わせよう
・人格者だと思わせよう
・誠実だと思わせよう
・人気があると思わせよう
・センスがいいと思わせよう
・気が利く人だと思わせよう
・人間的に器が大きいと思わせよう
・優しいと思わせよう
・思い通りに操ろう
・価値があると思わせよう
思わせようと考えてはいけません。
自分の努力で真の評価を受ける様になりましょう。
見ている人には分かってしまうものです。
そして誰もが同じような承認要求を持っている事も理解してあげましょう。
(小林 音子さんからの受け売りです)