●日本に初めて仏教伝えた聖王
「日本人ブロガー公州・扶余・青陽の旅」、レポート第4弾。私たちは、百済の1番目の首都・漢城のあったソウルを発って、百済の2番目の首都・熊津があった公州市から観光を始めたわけですが、そこからいよいよ3番目の首都・泗沘があった、お隣の扶余郡に移ってきました。(*´▽`)
ここではまず、公州でお墓を見た「武寧王」の息子である「聖王」が、熊津を捨てて泗沘に都を移した、その百済復興にかける決意と祈りがうかがえる「定林寺址」と共に、「国立扶余博物館」を見ることができます。
ユネスコ世界遺産に登録されている「定林寺址」の「定林寺」は、百済の典型的な伽藍配置方式である一塔一金堂式で、これは古代日本の寺院の伽藍配置の由来でもあります。当然、その中心の「五層石塔」も日本との関連の深いデザインで、植民地時代から日本の学者がその形の驚くべき精巧さを研究しています。
何より「聖王」は、日本では「聖明王」として『日本書紀』などに記されていますが、泗沘に都を移した年である538年に、日本に使者を送り、経典と金銅の仏像一体、幡などを伝えて、初めて仏教を伝播させたということで知られています。そのことに関しては、博物館内の資料で、使者を送った側の立場から学ぶことができますよ。ヾ(≧∇≦)〃♪
●滅ぼされた百済の悲しみを思う
ただし、悲しいのは、この地は百済が滅びた地でもあるために、はるか昔に滅ぼされた国、消えてしまった国の喪失感を実感することになることです。
そもそも、「定林寺址」といっているように、寺の跡地でしかないわけで、博物館内には12分の1スケールの復元模型があって、それなりに立派ではありますが、外の実際の跡地に行ってみると、今度は何もなくてがっかりしてしまいます。
百済敗北当時、木造だった寺は1週間もの間、黒煙を吐きながら燃えたそうで、今は、燃え残った、「五層石塔」と石仏だけが、広い敷地にただ寂しくぽつんとあります。
特に石仏のほうは、今でこそ木造の建物を作って守られていますが、そもそも頭がなくなり、磨り減って原型を残していなかったものとして、とうていありがたい仏像だと思えない姿です。今ある漫画のような頭と帽子は、後から付け足されたものなのだそうですが、それを見ると本当に悲しくなりますよ。(>_<)
その後、気を取り直して、「国立扶余博物館」を見学することになりましたが、ここは何よりも、国宝287号の「百済金銅大香炉」と、国宝293号の「金銅観音菩薩立像」の美しさにうっとり見せられてしまいました。
これらは田んぼの中で掘り起こされたもので、瓦が重ねられたその下に、分解された状態で埋まっていたそうです。当時、国が滅亡しながら、自国の宝を、急いで土中に埋めて隠したものが、1400年の時を隔てて現在に蘇ったわけですよね。そう思うと、特別な感慨を感じざるを得ません。ましてや私たち日本人の中には、その当時の百済の遺民たちの血も多く流れているだろうから、ですよね。(´ぅ_ ;`)
【行き方】 扶余郡で観光した所を表示してみました。やはりここもソウルから「扶余(부여)」行きの高速バスで行くことが可能です。「定林寺址」は特にターミナルの近くですよね。
☆。.:*:・'☆'・:*:.。.:*:・'゜☆。.:*・'゜☆
韓国情報ランキングに、現在参加中です。
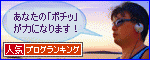
↑上のバナーをクリックするだけで、一票が入ります!
更新を願って下さる方は、よろしくお願いいたします。





























