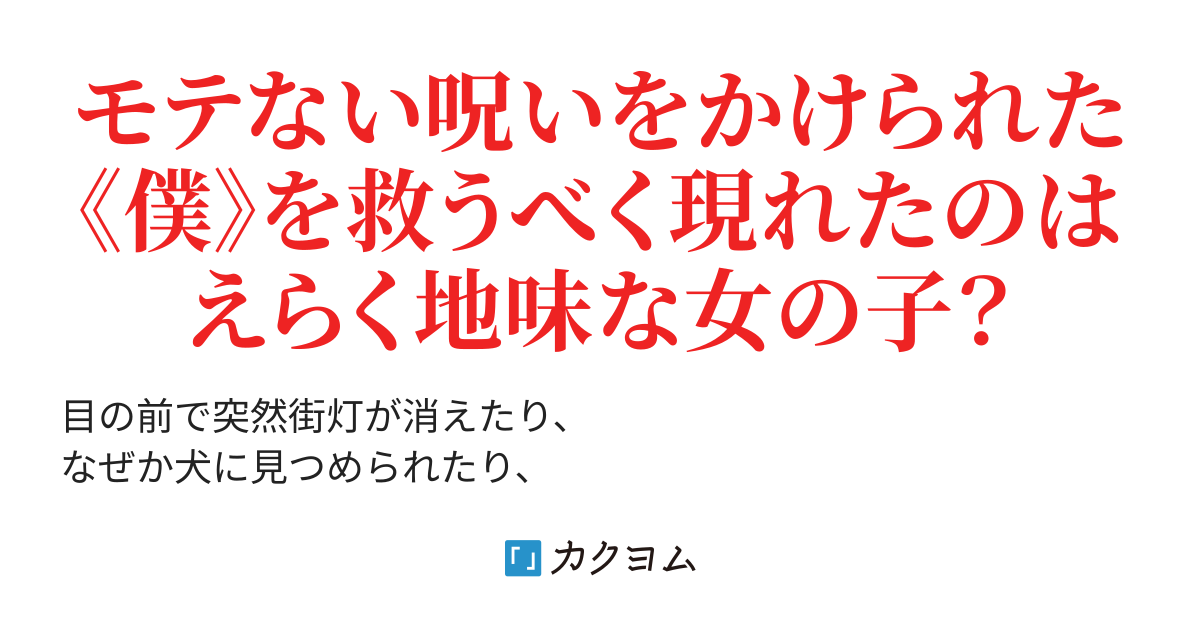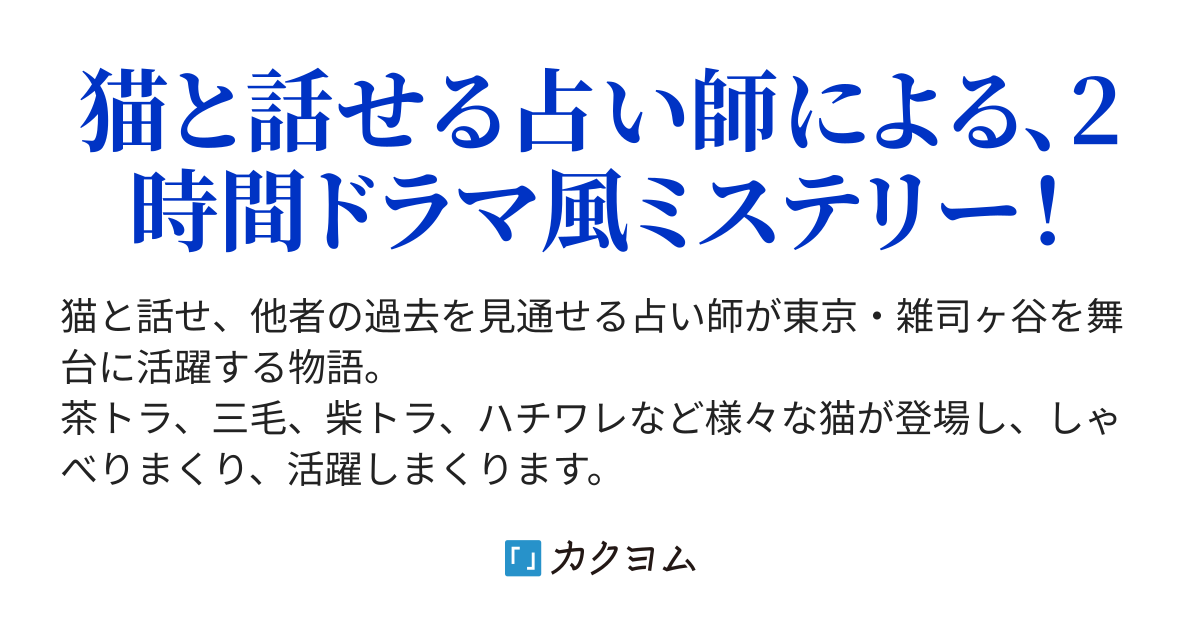教室に残ったのは私と加藤さんだけになった。正午になったからだろう、運動部員の声も途絶えた。陽射しは強く、木の影は濃く伸びている。
「質問があるんでしょ?」
振り向いた顔はすこし青白くみえた。私は首を引いていた。
「あの、加藤さんが先でいいです。私のは長くなりそうなので」
「そう。ところで具合はいいの?」
「はい、大丈夫です」
加藤さんは立ち上がった。声が聞こえてるあいだ私は外を眺めていた。弱く吹く風が空の端から雲を集めてる。それは絡まるようになり、平たく伸びていった。
「ありがとう。私の方は終わったわ」
「あ、はい」
「じゃ、帰るわ。じっくりいろいろ訊いてみたら? たくさん訊きたいことがあるんでしょ?」
薄く笑いながら加藤さんは出て行った。揺れる髪を見つめていると、うわずった声がした。
「で、落合さんはなにが訊きたいの? ――ん、また顔が赤くなってるな。ほんとに大丈夫?」
「あ、はい、大丈夫です」
「そう? あまり大丈夫そうにはみえないな。熱でもあるんじゃない?」
首を竦めながら私は目だけあげた。フルートの音が弱く響いてる。
「あっ、あの、」
「うん、なに?」
「その、タオル返しに行ってもいいですか?」
「え?」
「この前、順子さんに借りたんです。台風の日に」
「ああ、そうだったんだ。でも、」
高槻さんは頬を押さえてる。しばらくそうしてから深くうなずいた。
「うん。じゃあ、そうしよっか。こっちにも相談っていうか、参考にしたいことができたから」
「はあ」と私は言った。その声はすうっと伸びて、床に転がっていった。
坂には誰もいなかった。日はじりじりと照りつけ、蝉の声が辺りを覆ってる。
「さっき、」
そう言って高槻さんは周囲を見まわすようにした。
「うん、さっき加藤さんに言われたんだ。いや、相談されたってことになるのかな? ま、いずれにしても彼女はどうしたらいいかわからなくなってるみたいなんだ」
「はあ」
「うーん、今のじゃわからないよね。その、簡単にいうと加藤さんは二人のうちどっちが好きか自分でもわからないようなんだ。もちろん柳田くんと横森くんのことだよ」
「えっ、そんなこと言ってたんですか?」
「いや、はっきりそう言われたんじゃないんだけど、どうにもそんな感じのことだった。講義のときも言ってたろ? 人を好きになるのは一人でもできるけど、それを発展させるのは一人じゃ無理みたいなこと。あれはまさに彼女の現状なんだろうね。あの二人は強い感情をみせてない。三四郎と野々宮くんみたいに互いの存在の方が気になってるって感じだ。まあ、だから僕も小説のこととして返しといたんだけどね。でも、それで良かったのかなって思ってさ」
コンクリートの壁は短い影を落としてる。私は胸を押さえていた。心臓はとくとくと鳴っている。いつもより激しくだ。
「加藤さんはどうなんです? その、やっぱり両方とも同じくらい好きなんですか?」
「どうなんだろうね。美禰子について言ってたのが本人の気持ちと一緒なら、それこそどっちも好きなんじゃないかな。まあ、それじゃいけないって思ってるんだろうけどね」
「それで先生はなんて言ったんです?」
「いや、ほんとあくまでも『三四郎』の話をしただけだよ。結末も含めてね。揺れ動いた末に美禰子は第三の選択をする。だから加藤さんにもそういう展開があるのかもしれない。来年は大学に行くんだし、新しい出会いもあるんだからね。それに、高校の頃に起こる恋愛問題なんてのはだいたいがそんなものだろ。淡くて、ぼんやりしてて、はっきりした結末には至らないもんだ。かといって、そんなふうには言えないけどね。――いや、それにしても参ったな。創作のための講義をしてるつもりが、いつの間にかこんなことになっちゃって。『三四郎』は僕が好きだってこともあるけど、君たちくらいの年頃の子にはうってつけと思ったんだよ。それこそ淡くて、ぼんやりした恋愛の話なんだからさ」
「でも、そのせいで私たちは少しずつ混乱してるんだと思います」
「ん? どういうこと?」
「あの、なんとなくですけど加藤さんたちはあれを読んでるうちに前よりこんがらがってきたっていうか、いえ、それだけじゃなく、私たち全員が影響を受けてるように思えたんです。丁寧に読んでるうちにそれぞれが気持ちを乱されてきたってふうに」
「なるほど」
顔をあげ、私はすぐにうつむいた。地下鉄の階段はひんやりしてる。
「ま、そういうこともあるだろう。いや、そうあって当然なのかもしれない。優れた小説にはその程度の力があって当然だからね。だけど、そうなるとやっぱり困ったことになっちゃうな」
「どうしてです?」
「だって、あれを持ち出したから、あの三人がこんがらがってきたってことになるだろ。うーん、マズかったかな」
腕を組み、高槻さんは顎を突き出した。私は笑ってしまった。
「そんなに笑わないでよ」
「すみません。でも、ほんとに困った感じだったから」
「いや、ほんとに困ってるんだよ。どうしたものかな」
電車はすいていて、私たちは並んで座った。向かいの窓には二人の影が映りこんでいる。輪郭のはっきりしないぼやけた像だ。たまにあらわれる明かりが消し去らせたけど私はそれをじっと見つめていた。
「ま、しょうがないか。さっき落合さんが言ったこと、ほら『三四郎』が影響をあたえてるっての、それはあると思うんだ。美禰子の心情を丁寧に追ってくと、どうしても寂しさみたいのにぶち当たる。なんていうのかな、どこにも誰にも属していないっていうか、宙ぶらりんっていうか、まあ、そういうのを感じるんだ。でも、それは彼女だけにあらわれてるんじゃない。広田先生なんかにも顕著にあらわれてる。あれに出てくる人たちの多くは孤独なんだ。それも徹底した孤独だよ。孤児のようなね。そういうのを感じると人恋しく思うものなのさ。いや、それ以上に僕が刺激したってのもあるけどね。篠田さんにけしかけられた部分はあるにせよ、乗ったのは僕だからな。――うん、こうやって自己の行為は自らに罰を下すってわけだ。これはまさにアレだね。『われは我が愆を知る。我が罪は常に我が前にあり』ってやつだ。僕の罪も目の前にぶら下がってる。それも講義のたびに目に入ってくるってわけだ」
前屈みになり、高槻さんは腕を組んだ。私はその顔を覗きこんでいた。
「ほんとに『三四郎』が好きなんですね」
「ん? ああ、まあね」
「どうしてそんなに好きなんです?」
「そうだなぁ、なんて言えばいいかわからないけど、あれを読み終えたとき僕は真剣に小説を書きたいって思ったんだ。ちょうど電車に乗ってるときだった。高校一年の秋だったから、いまの落合さんと同じ年だね。僕はその頃、栃木にいたんだ。家にいろいろあって祖母ちゃんのとこへ預けられてたんでね」
電車が停まった。高槻さんは身体を起こし、ひらきかかったドアを見た。
「着いたね。降りよう」
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》