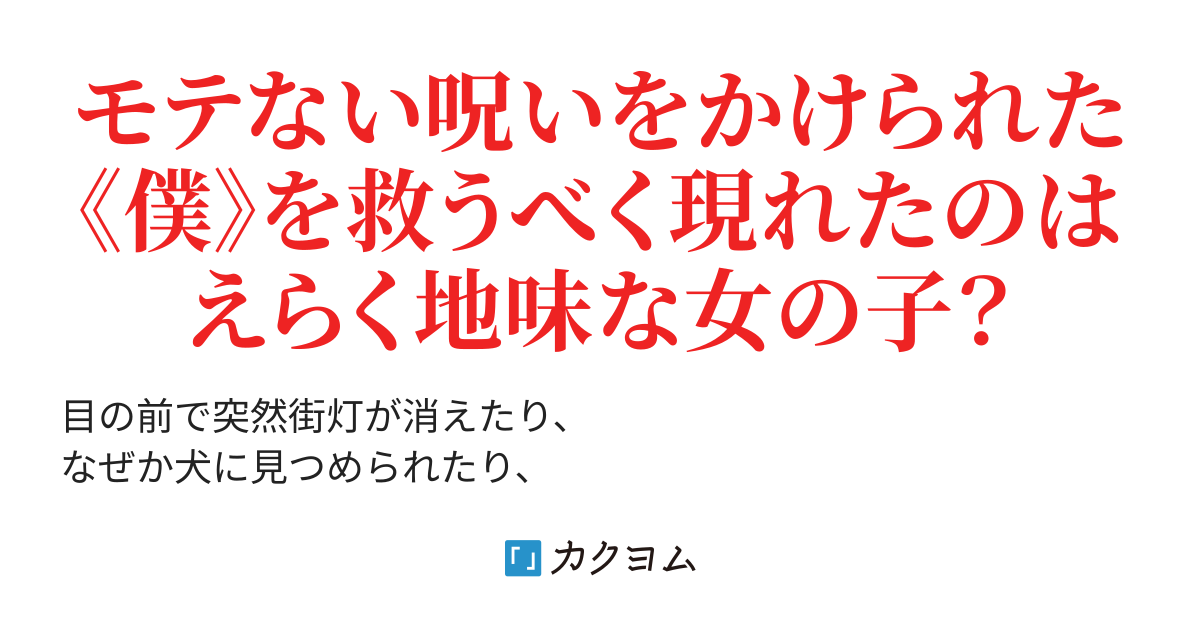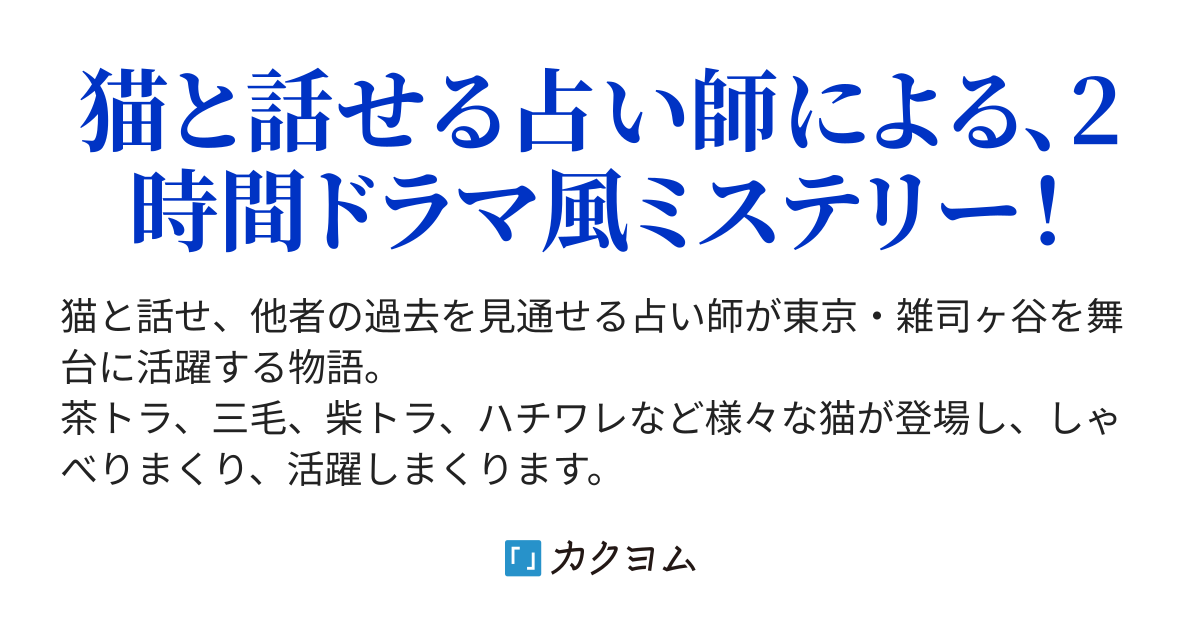階段をのぼると高槻さんは額を押さえた。むっとした空気が辺りを覆ってる。
「母さんは驚くだろうな」
「どうしてです?」
「落合さんだけ来るのは初めてだろ。いつもは煩いのが一緒だからね」
頬は自然とゆるんでいった。私たちはゆっくり歩きだした。
「それで、さっきの話なんですけど」
「ああ、『三四郎』のね。さっきも言ったけど僕は栃木の高校に通ってたんだ。その帰りのことだったな。ところで、その電車ってのが凄くってね。僕の高校はそこそこマトモなとこだったけど、二駅向こうに名うての不良高があってさ、帰りの電車がくると中がけむりで見えないくらいだったんだ」
「けむりですか?」
「煙草のね。あそこの生徒はほぼ全員がスモーカーだったんじゃないかな。いや、もちろん喫っちゃ駄目なんだけど、あの辺は治外法権があるみたいだった。電車がきてドアがひらくだろ、そうすると演歌歌手が出てくるみたいにスモークが流れるんだよ。車掌のアナウンスも振るってた。高校生の喫煙は法律で禁止されてますとか言ってたもんね。だけど、誰もそんなの気にしないでぷかぷか喫ってたよ」
「ほんとですか?」
「ほんとだよ。それだけじゃない。爆竹を鳴らしてる奴もいた。窓から外に放り投げるんだ。それが遙か後方で鳴り響く。まったくどうしようもない連中だ」
声をあげて私は笑った。通りにはまあまあ人がいる。幾人かが私たちを見ていった。
「ま、そういう中で最後の章を読んでたんだ。『ただ口の内で迷羊、迷羊と繰返した』ってとこをね。夕暮れ時で、窓の外はオレンジ色に染まってた。雲がね、こう、左右に棚引いてて、そのところどころは灰色にも青にもみえた。最後まで読み切ってから顔をあげたんだ。電車は鉄橋に差し掛かってガタガタ揺れてた。そのとき見たものも聞いた音も全部残ってる。どういうわけかすべて残ってるんだ。僕はそのオレンジ色の中で、――ま、煙草のけむりや不良どもの喚きがある中でもあったけど、自分もこういうのを書いてみたいって思ったんだ。いや、書いてみせるって思ったんだよ」
高槻さんは頬をゆるめてる。ただ、目には光が入っていた。
「それが失敗のはじまりだったんだろうな。講義のときも言ったけど、あれってさらっと読めちゃうものなんだ。高校生でも理解できるくらい平明に書いてある。だから、これくらいなら書けるって思ったんだろうね。今から思えば大胆っていうか、野放図っていうか、世間知らずっていうか、まあ、大失敗だよ。さすがは漱石先生だ。あんなの書けっこない。だけど、いや、だから僕はいつまで経っても好きなんだろうな。乗り越えられない壁って感じだからね」
「でも、先生の小説もよかったですよ」
私は顎を引いた。そして、こうつけ足すときに顔をあげた。
「私は好きです」
「ありがとう。落合さんはなにを読んでくれたの?」
「はじめに『十五年』を読んで、『活けられた花』というのも読みました」
「そう。それならまだマシなやつだ。とはいってもまだまだだけどね」
私は顔をあげたままでいた。硬い痼りができたのはわかっていた。それは存在を誇示するように脈打っている。
「それから、」と言って、私は顔が向けられるのを待った。
「まだ他に読んでくれたの?」
「はい、『蛇』というのを」
「ああ、あれね」
「未玖が読んで、私にも読めって渡してきたんです」
「なるほど。いかにも篠田さんのしそうなことだ」
「タイトルを見たとき、びっくりしました。私が書いたのと同じだったから。私、あれも好きです。なんていうか綺麗に思えたんです。その、書いてあるのはああいうことだけど文章が綺麗で、――その、どう言ったらいいんだろ? ――そう、透明な感じ。透き通ってて、硬くて、冷たい感じがしました。全体的に美しい印象があったんだと思うんです」
「ありがとう。あれがそこまで言われるものか別にしても嬉しいよ。だけど透き通ってて、硬質で、冷たい文章か。やっぱり落合さんは表現が巧いね。でもさ、あれを読むのは早すぎたんじゃないかな。新井田さんも考えて持ってくりゃいいのに」
「いえ、早すぎるなんてことないです」
はだかるように立ち、私は顔をあげた。
「あれくらいなら私にだってわかります。それに、私はそんなに子供じゃありません。人を好きになるってこともわかるし、ああいうのだって理解できます」
高槻さんは黙って歩きだした。頬は平坦になっている。
「それこそ子供の言うことだよ。ああいうのにしたって恋にしたって理解するもんじゃない。それを理解できるって思うのは子供だからさ」
私は溜息をついた。そのときに、ふと思った。いまの声と高槻さんの文章には似たところがある。冷たさ、――いや、強い拒絶なのかもしれない。美しい文章ではあるのだけど他者を寄せつけない雰囲気があるのだ。私は手を伸ばせば触れられるくらい先にある背中をじっと見つめていた。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》