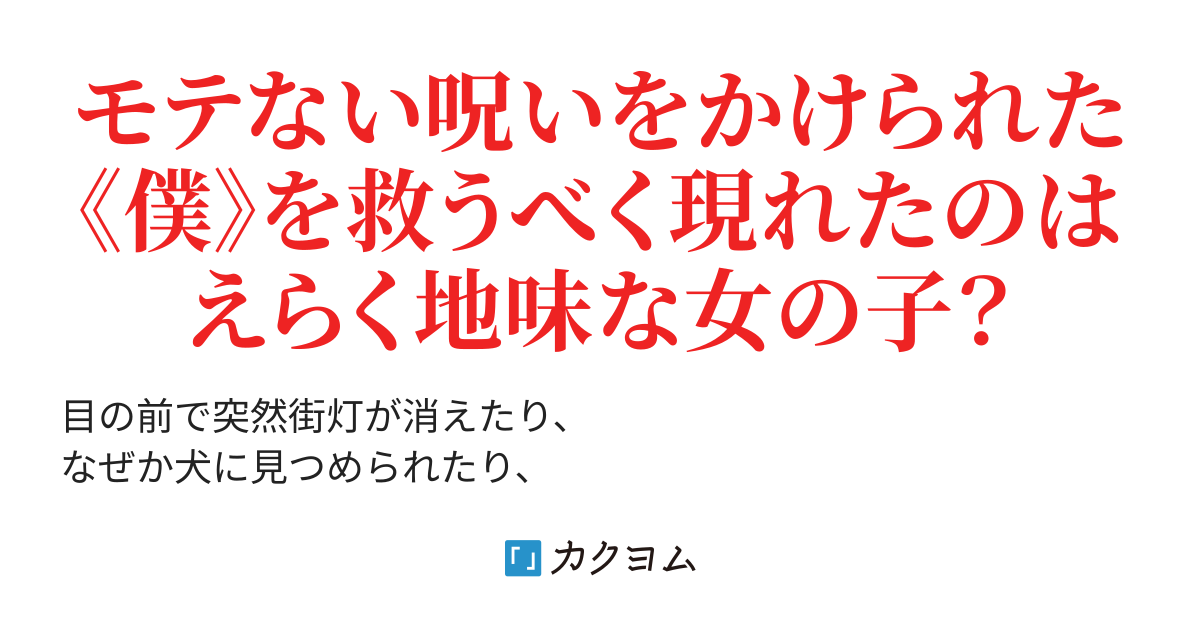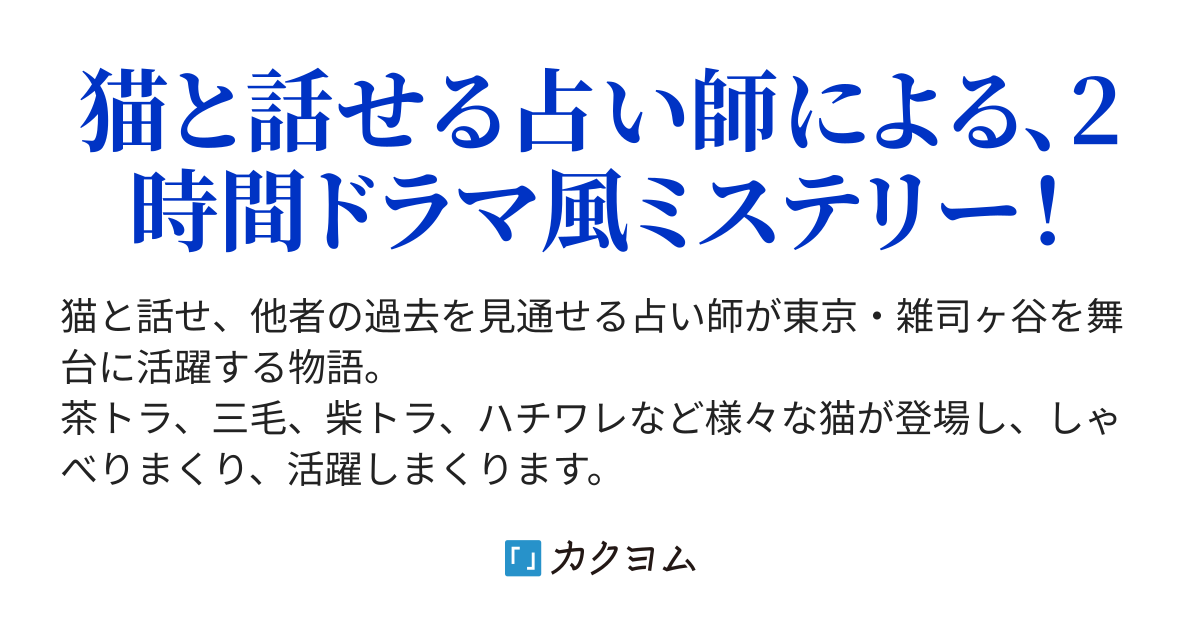「え? あ、はい」
「いえ、立たなくても大丈夫ですよ。思わぬところで彼女は気になる男・その一に出会したんです。傍らには気になる男・その二がいる。そこで彼女はその二に無意味な耳打ちをしてみせる。なぜそんなことをしたのでしょう?」
「あの、」
安川さんは細い身体をさらに縮めさせている。高槻さんは笑顔を強くした。
「あなたならきっとわかりますよ。あなたの書いてるのは素晴らしい。非常に力のこもった作品だと思ってます。もっと自信を持ってください」
「は、はい。あの、三四郎を愛してるからだと思います。ただ、その感情は単純なものではなく、常に野々宮を意識してのものなんでしょう。だから、見せつけるようなことをした。でも、ええと、」
「いいですよ、非常にいい。さあ、その後がさらに重要です。きっとあなたは気づいてるんですよね? それを聴かせてください」
静かに歩き、高槻さんは机の前に立った。欅は波うつように揺れている。二人の姿はそれを背景にしていた。
「はい。でも、美禰子はそれを意識せずにしてしまってるのだと思います。理由まではわからないけど『無邪気』と書いてあるのや、『何故かああしたかった』みたいに言ってるのはそういうことだと」
「うん、ほんと素晴らしい。非常にいいですよ。そう、美禰子がただ単に野々宮くんの気を引くために三四郎をだしに使ったのなら、『野々宮さん、ね、ね』なんて言うはずがありませんものね。それじゃあまりにも馬鹿にしています。では、なんで種明かしみたいなことを言ったのかという問題が出てきます。いやぁ、言うべきことを全部言われてしまったみたいだな」
前髪を押さえるようにして安川さんは椅子に背をつけた。口角はすこしだけ上がってる。
「いま安川さんが仰ったように美禰子のディスプレイは三四郎へ向けられたものでなく、野々宮くんにたいしてのものなのでしょう。つまり自分が愛してるのはこの人なのだと見せつける行為というわけです。しかし、どうしてそんなことをしなければならないのか? それも安川さんが言ったように美禰子の愛情が単純なものでないからです。彼女は二人の間を揺れ動いてるんですね。理屈でいったら野々宮くんを選ぶべきなんです。なにしろ世界に認められる学者なんですから。ただ、三四郎のことも好きになってしまったんですね。で、その場合、美禰子の心情はより三四郎の方へ傾きが大きいといえるでしょう。なぜって、こっちは大学に入ったばかりのこれからどうなるかわからない男なんですから。いえ、とはいっても帝大生ですので何年かすればそこそこの地位にはなるのでしょう。ただし美禰子はそれを待てないんですね。まあ、その程度にしか傾けられない感情なんです。これだって今もよくあるシチュエーションですよね。好きは好きなんだけど先行きの見えない男、もう一方は地位のある男、二人のうちどちらを選べばいいかわからないといった感じですよ」
教卓に戻り、高槻さんは水を飲んだ。目はノートへ向かってる。
「そういう中で美禰子は無意識に演じてしまってるんです。直接言えずに、――ま、言えるわけないですよね。『あなたは好きだけど結婚は無理』なんて言えないでしょう? 言ったところでどうなるわけでもないですしね。ただ、愛情があることだけは示したいんです。これは我が儘な行動なのでしょう。しかし、人間ってそういうことをしてしまうものだと思います。いや、もしかしたら美禰子自身も不思議に思ってるのかもしれません。理屈で割りきれない感情を持ってしまったことに狼狽えてるともとれます。それはこの一連のシーンでみせる行動にあらわれています。『縋るように付いて来た』とか『「だって」といいながら、寄って来た』という部分に彼女のか弱さが出てますよね。漱石はそれを意識して書いてるようにも思えます。三四郎が見下ろすところなんかもその一部でしょう。美禰子はブレまくってるんですね。強さと弱さが同時に出てるんです。で、三四郎はやっとそのことに気づく一歩手前くらいまではたどり着けるんです。では、章の最後を読みましょう。
『少し待てば歇みそうである。二人は大きな杉の下に這った。雨を防ぐには都合の好くない樹である。けれども二人とも動かない。濡れても立っている。二人とも寒くなった。女が「小川さん」という。男は八の字を寄せて、空を見ていた顔を女の方へ向けた。
「悪くって? 先刻のこと」
「いいです」
「だって」といいながら、寄って来た。「私、何故だか、ああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼するつもりじゃないんですけれども」
女は瞳を定めて、三四郎を見た。三四郎はその瞳の中に言葉よりも深き訴を認めた。――必竟あなたのためにした事じゃありませんかと、二重瞼の奥で訴えている。三四郎は、もう一遍、
「だから、いいです」と答えた。
雨は段々濃くなった。雫の落ちない場所は僅かしかない。二人は段々一つ所へ塊まって来た。肩と肩と擦れ合う位にして立ち竦んでいた。雨の音の中で、美禰子が、
「さっきの御金を御遣いなさい」といった。
「借りましょう。要るだけ」と答えた。
「みんな、御遣いなさい」といった』
もどかしいですね。わかりにくいものであっても美禰子は愛情を示したんです。しかし、三四郎はそれをしっかり受けとめてません。『必竟あなたのためにした事じゃありませんか』という訴えを認めてはいるものの、きちんと理解できていないんです。そこにも美禰子の不幸はあるのかもしれませんね。彼女に近づく男は正面から向きあおうとしないんです。三四郎にせよ野々宮くんにせよ、もし心の底から美禰子を愛していたなら関わり方が違っていたはずです。ちょっと迷惑に思われるくらい愛情を示していたら関係は変わっていたかもしれません。まあ、新井田さんみたいにストーカーまがいなことをするのもどうかと思いますが、そこに正しい愛情がありさえすれば気持ちは伝わるんですよ。しかし、三四郎も野々宮くんもそうはしないんですね。遠くから眺めてるだけなんです。――そう、だいぶ前に『花は必ず剪て、瓶裏に眺むべきものである』というのがありましたね。広田先生の引っ越しのとき、木戸をあけて庭へ入ってきた美禰子を見た三四郎の感想として出てきます。これは美しいものを自分のものにしたいという欲求とともに、そのものとの距離を示しています。人間同士の関わりではないのですよ。物と人との関係です」
高槻さんは窓の外を見つめてる。非常に寂しげな目つきだった。ただ、軽く頭を振ると前を向いた。そのときにはいつもの笑顔に戻していた。
「いや、どうも僕は美禰子に甘いようです。そして、彼女をきちんと理解できない三四郎や野々宮くんに厳しすぎるのかもしれません。しかし、美禰子同様に彼らにも限界が規定されてるわけですから、つまり、漱石が彼らをそういった人間と規定してるのですから、彼女にばかり肩入れするのは間違いなのでしょう。さて、いまの部分で質問のある方はおられますか?」
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》