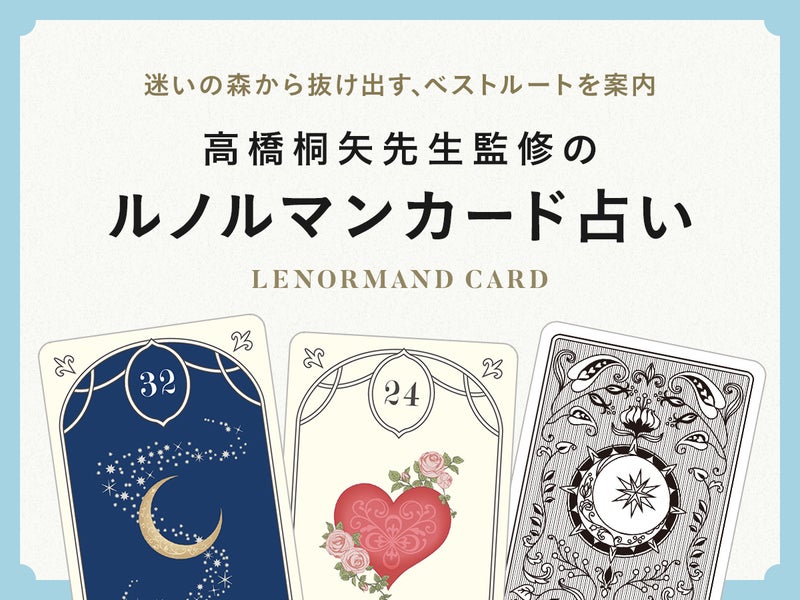西洋占星術の話をなぜ、ブログに書こうかと思ったかというと、実はあるときから「ハウス」問題にぶち当たっていたからなのです。
西洋占星術では、その瞬間の天空を「ホロスコープ」に記して、占いをします。
そのとき、最大のポイントとなるのが、「天体」「星座」「ハウス」の3つです。
(ホロスコープの基礎についてはこちら↓)
「天体」は、太陽と月と、火星金星などの惑星、また小惑星や日食が起きる地点などです。
「星座」は、牡羊座から魚座までの12星座のことです。
ここまでは問題ありません。たしかに複雑ではありますが、テキスト通りに順番に学んでいけばちゃんと理解できます。
残る「ハウス」が、くせ者なのですよ〜💦
ハウスは、1から12まであるのですが、なんと実はハウスの分割方法って、何種類もあるのです。
一般的に日本でよく用いられているのは、「プラシーダスハウス」法ですが、緯度の高い地域では偏ってしまうため、違うハウス方式が用いられることが多いのです。わたし自身、西洋占星術を学び始めてからしばらくの間、疑問も持たずに、プラシーダス方式を使ってきました。
でも、あるときふと、疑問に思ったのです。
どうして、高緯度地域では使えないんだろう、と。
そもそもハウスってどうやって分割されてるんだろう、と。
↓ここにスウェーデン生まれの女優グレタ・ガルボのホロスコープを用意してみました。内側の円の数字が「ハウス」で、真ん中の円に配置された記号が「天体」、外側の円が「星座」です。
まず日本で一般的なプラシーダスハウス方式で出すと、12ハウスと6ハウスが、どーんと広くなってしまいます。
高緯度地方で使われているコッホ法にすると今度は11ハウスと5ハウスが広くなりました。
キャンパナス法ではプラシーダスよりもっと12と6ハウスが広すぎ。
ポーフィリー法だと、こんな感じ。
最後にイコールハウス法。
これぜんぶ、「星座」と「天体」は同じ。(一番内側の天体同士のアスペクトも同じです)
なのに、「ハウス」だけがこんなに違っているのです。
(ちなみに、ハウス分割法はほかにももっとあります)
ハウスは、いろいろな「分野」を表しています。
グレタ・ガルボの例で言えば、人生の目的を表す「太陽」が、プラシーダス法とキャンパナス法だと奉仕の6ハウスに、コッホ法とポーフィリー法だと芸術の5ハウスに、イコールハウス法だと家庭の4ハウスに配置されてしまうわけです。
女優グレタ・ガルボの人生の目的は、奉仕なのか、芸術なのか、家庭なのか?
これは高緯度ホロスコープの極端な例ですが、日本程度の緯度でもやはり、多少は違ってきます。
おかしいだろ…と思いました。
西洋占星術は紀元前から2000年以上かけて精緻に構築されてきた「占いシステム」です。それがこんなにバラバラでいいのかいな、と。
それからしばらくは、「ハウスシステムいらんのでは」と思っていました。
ところがですね、さらにさらに深掘りしていくと、「むしろ、ハウス一番大事じゃん!!!」となったわけです。
次回はそのあたりをざくざく掘り下げていきます。
6月27日(土)13:00~14:30
参加費 2500円
7月18日(土)13:30〜16:00
講座料 18000円(ワークブック付)
7月25日(土)13:30〜16:00
講座料 18000円
【すべてZOOMです】
↓無料でルノルマンカード占いができます
↓作家仲間と、運営しているイジメ対策サイトです
【高橋桐矢の本】
↓副業で占い師をする方々へのインタビュー集
↓ルノルマンカード付き、解説書
↓占い師の裏側が分かります
↓創作読み物。小学5年生の主人公の親は占い師!
↓創作読み物。学校に行けないときのサバイバル術
1巻目
2巻目