スネアドラムは、ボイスパーカッションを初めるにあたって一番最初にブチ当たる壁なんではないでしょうか?
それもそのはず、このスネアドラムの音、ボイスパーカッションの音色の中では一番音の出し方に種類があり、口の使い方もさまざまなのです。
初心者から熟練者まで、自分に合ったスネアドラムの出し方というのは【永遠のテーマ】でもあります。
そもそもスネアドラムとはどんな楽器なのでしょうか?
ドラムセットのドラマー側の真ん中にドデンと置いてある太鼓、これがスネアドラムです。

小学校の音楽の時間では【小太鼓】なんて呼ばれ方もしてました。
そう、マーチングバンドとかでテッテケテッテケいってる小太鼓、アレと同じものがドラムセットの中では【スネアドラム】と洒落た名前で呼ばれてるんです(笑)
スネアドラムの楽器の構造は、太鼓部分はフツーの太鼓と変わりません。
ただ打面と逆の底の【スナッピー】と呼ばれる金属のシャラシャラいうやつが付いてるんです。

これが付いていない状態でスネアを叩いても、”ポンッ”と、小さい和太鼓のような音しかしません。

しかしスナッピーをつけることで、”ポンッ”という太鼓の音と同時にスナッピーのシャラシャラが打面の裏を無数に細かく打ち、”ジャッ”という高い音がします。
コレがスネアドラムの構造です。
つまり、スネアドラムに聞こえる条件としては、
【木製のスティックで叩くので、バスドラムよりカタい、叩いた瞬間のアタック音】
【スナッピーから出る”ジャッ”という高い金属音的な余韻】
【太鼓自身が鳴って出る”ポンッ”という中域の太鼓の響き】
この3つです。
これらが同時に鳴っているとき、その音はスネアドラムの音色に聞こえるわけです。
そして、ボイスパーカッションにおけるスネアドラムの出し方に何でこんなに種類があるかというと、
【アタック音】【高い余韻】【太鼓の響き】
この3つを出す際に口のどこを使うかが違うので、組み合わせの数だけやり方があるというわけなのです。
具体的には
【アタック音】
クチビルを弾いて出す or 舌を使ってタンギングで出す
【高い余韻】
歯擦音で出す or 空気の流れる音で出す (アタック音の出し方で決まる)
【太鼓の響き】
クチビルの振動で出す or 声帯を使って声で出す
さらにコレが
”息を吐きながら音を出す”と”息を吸いながら音を出す”
にも分かれているからややこしい!!
次回、具体的にそれぞれの出し方の紹介と、その出し方のモデルケースを紹介していきたいと思います。
自分に合ったやり方は見つかるのか?!
その2お楽しみに!
- DVDでよくわかる! ボイパ本 (DVD付)/リットーミュージック
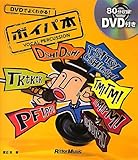
- ¥1,944
- Amazon.co.jp