前回までのお話が完全に飲み込めているのであれば、アカペラアレンジのための基礎知識の準備はほぼ終わっているといえます。
さぁ、あとは前回仕入れたコーラスアレンジのアプローチを、自分がアレンジしようとしている曲にちりばめていくだけですが…
※コーラスアレンジのアプローチなどはその4参照
はて?
なにをどこから手をつけていったらいいんだろう??
ということで、ここでは無の状態からアレンジを進めていく手順をフローチャートにしてお話しようと思います!
※あくまでつるのやり方ですから、これどおりにしなきゃいけないということは全くありません!大事なのは順番ではなくて考え方なのです。
【編曲(アカペラアレンジ)を進めていく手順】
1. やりたい曲のコードが記載してある楽譜を手に入れよう
…本屋、楽器屋などに売ってます。
↓
2. 各種データを揃えましょう
…やりたい曲の音源。
さらに、【midiデータ】と呼ばれるデータがweb上に無料でおちてる場合があります。このデータを楽譜作成ソフトで開くと、商業施設なんかでよく流れている”曲のインストゥルメンタルバージョン”が楽譜となって見たり聴いたりできます。
自分のやりたい曲のmidiデータがある場合は保存しておくと、参考にできて便利です。
↓
3. リードが歌う主旋律を打ち込もう
…使おうとしている楽譜作成ソフト、もしくは手書きするのであれば五線譜に、楽譜を見ながら主旋律を打ち込みましょう。
これは単純な書き写し作業なので、機械的に無心でやってしまいましょう。
※シャッフルなどでハネている曲も、楽譜作成ソフトではあとで一括でハネさせれるので、今は無視してストレートに打ち込んでおきましょう。
ハネとは…また説明しますが、楽譜の冒頭にこんなのがついてればハネの曲です。
↓
4. まずはサビのアレンジを吟味しよう
…サビとは、曲の顔です。ここを一番際立たせたい。盛り上がるようにしたい。
そのためにまずはサビから作り、サビとの兼ね合いでAメロやBメロを作るのが失敗が少ないです。
まずはサビに、自分の持ってる発想力を100パーセントつぎ込みましょう。
↓
5. パートはボイパ、ベースから作ろう
サビのアレンジを考えるとき、まずはベース、ボイパのリズム隊から作っていきましょう。
ボイパ、ベース、リードの3点セットだけで聴いても、やりたいことがわかるように作れたらベストです。3点押し、コンテンポラリーアカペラの真髄です。
自分の中で一番盛り上がるベースラインとリズムをサビに当てはめましょう。そして、3パートだけで聴いてみましょう。
わからない場合は、ボイパは省略して、ベースは原曲から刻み方だけ聴きとって、構成音を当てはめましょう!
※ここでmidiデータが役立ちます。ドラム楽譜の表記の仕方やリズムの作り方、ベースラインの作り方がわからない場合は、midiを参考にしてみましょう。
注意点…ベース、ボイパはmidiからコピペもできるが、なるべくなら自分で作ったほうが良い。コピペで作るとアカペラではうまくいかない場合が多い。
ボイパ、ベースの作り方、動かし方は、また別章でおってお話しようと思います。
↓
6. 完成した3パートに一番合うコーラスラインを、トップのメロディーから考える
ボイパ、ベース、リードの3点を聴きながら、それに合うコーラスを吟味していきましょう。
最終的にはコーラスの一番上、トップが歌っている旋律がコーラス全体のメインメロディーになるので、ここをメロディアスに作ることが重要です。
構成音を参照しながら、採用するコーラスアプローチに沿ってトップコーラスを、単品で聴いてもメロディーが気持ちいいように作る。
↓
7. コーラスの下をコードに沿ってつけていく
コーラスのトップのラインができたら、コードの構成音と優先順位を参照しながら、下のコーラスに音を割り振っていく。
ここもわりと機械的でもよい。ただ、音の移動に無理がないか、隣りどおしのコーラスの幅が離れすぎていないかは気にしましょう。
↓
8. 続いてBメロやAメロを吟味する
まずはベース、ボイパ。続いてコーラス…という流れを、サビに続いてAメロ、Bメロ…というような順番で進めていく。
サビとの盛り上がりの兼ね合いを見ながら、しっかりと緩急をつけるようにアレンジしたほうがうまくいきやすい。
※各セクションのつながりが不自然になったり、唐突になったりしないよう、何度も聞き返して調整しましょう。大幅に緩急をつけたからこそ、つなぎ目の部分でわざとらしくならないように、聴いていて一貫性があるようにしましょう。
↓
9. 間奏、前奏、後奏を吟味する
歌がある場所の流れが一通りできたら、前奏や間奏などを考えましょう。
人間が歌うということを大前提にして、歌では再現不可能なギターのフレーズや鍵盤のフレーズは、コードだけいただいて、思い切って変えましょう。
※長い、いらないと思ったら大胆にカットするのもあり。アカペラでは曲が長くなるとしんどくなるので、カットできるところはしましょう。
大事なのは、全体としてのバランスと一貫性です。
…とはいえ、最初から名作なんて誰しもできないものです。
まずは自分でも笑っちゃうくらい単純なものでいいので、とりあえず1曲書き上げてみましょう!
さぁ、次回はどうやったらアレンジが上手くなるか、アレンジ力の上げていき方をお話したいと思います。
アレンジ講座も、終盤ですね!
その6お楽しみに!
- インターネット Singer Song Writer Lite 8 通常版/インターネット
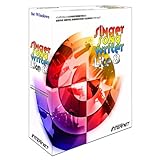
- ¥16,200
- Amazon.co.jp