アカペラを歌い始めるにあたって、皆さんの前に最初に立ちはだかる壁はおそらく『アカペラの譜面を用意すること』だと思います。
売っている楽譜自体もそんなに多くないし、自分たちの声域や人数に合っているとも限りません。ましてや、自分のやりたい曲を自由に歌おうと思えば、ほぼ避けて通れないのが【自分でアカペラの譜面を書く】ということだと思います。
しかし実は、既存の曲のアカペラカバー譜面を書く…ということに限って言ってしまえば、ある程度の基礎を知っていれば、そんなに難しいことじゃないんです。
(オリジナル曲や、リハーモナイズ、〇〇風アレンジ…などを作るときは、もうちょっと知識が必要ですが…)
なので今回は、“既存の曲のアカペラカバー”を前提とした、アカペラの譜面の書き方を書いていこうと思います。
その曲がその曲であるために必要な、音楽を構成する3大要素というものがあります。
【メロディー】
音の流れ。『ドレミの歌』なら、ドレミドミドミ…という流れ。この順番が崩れてしまうと、その曲ではなくなってしまう。
【リズム】
音の長さ、休符の流れ。同じく『ドレミの歌』なら、ドーはドーナツーのードー…と、伸ばす長さが決まっている。これも崩れるとその曲には聞こえない。
【ハーモニー(和音)】
音の重なり。じ『ドレミの歌』なら、ドはドーナツのド…の箇所のとき、後ろでド、ミ、ソの3つの音が同時に鳴っていると、この曲に聞こえる。いわば、メロディーの背景。
【メロディー】【リズム】【ハーモニー】この3つがすべてそろって初めて、その曲と認識できるのです。
しかし今は、既存の曲のアカペラカバー譜面を書く…という視点で話をしてます。つまり、【メロディー】と【リズム】に関しては、皆さんがアタマを使うまでもなく、もう決まってます。
皆さんがアタマをつかって考えなければいけないのは、最後の一つ【ハーモニー】をギターでもピアノでもなく、ヒトの声でどう表現するか??
ここだけなんです。
皆さん、もし初めてアカペラの譜面を書こうと思ってる方がいたら、まずはその曲のメロディー譜かコード譜を手に入れましょう。
楽譜の上にアルファベットなどの記号がたくさん書いてあることが必須です。よっぽどのマイナー曲でない限り、見つかるはずです。
次回は具体的にハーモニーの決め方、ハーモニーを教えてくれる標識、『コード』の話と読み取り方を話していきたいと思います!
その2をお楽しみに!
- 80年代アイドルソング大全集 BEST 299 コードメロディー譜/全音楽譜出版社
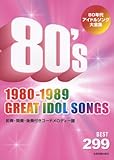
- ¥3,024
- Amazon.co.jp