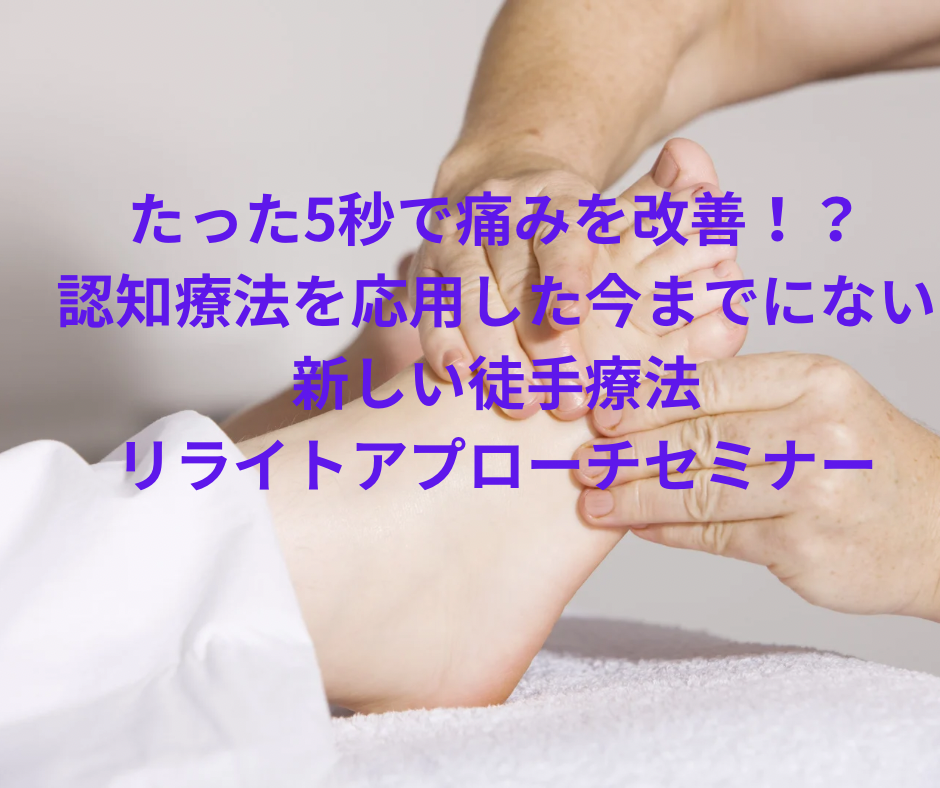こんにちは!
Flexible Perfect Body協会代表安藤一樹です。
今回は、前回の続きとなっています。
まだの方は、最初から読んでいただくと、スムーズになります。
前回は、筋膜の張力には、引力と斥力があるとお話しました。
筋膜の張力は、アライメントに大きな関わりがあります。
一般的に人体の構造は、関節で切り分けて、上腕、前腕や下腿などの複数の体節から成り立っているという考え方をしています。
体節は、曲げたりできず、変形しないものと見立てています。
仮に変形しないと考えれば、形が決まるので、体節の重心位置が決まります。
これを剛体モデルと呼んでいます。
剛体は、変形しない理想の物体ということで、それを人体に当てはめています。
そのため、各体節に重心がありますが、人体を一つの剛体モデルと定義した時、重心が仙椎部にあるため、重心を一つにまとめることができます。
しかし、人体は、変形しないのでしょうか?
変形しないのであれば、OAや円背にはならないと思います。
肘が伸びなくなったという野球選手だっています。
アライメントが変化してしまうのが、人間です。
なので、人体を剛体モデルというのは無理があります。
そこで剛体モデルの代わりに、人体の構造を説明できるのがテンセグリティー構造です。
テンセグリティー構造は、安定した支柱と相互接合したヒモの集まりです。
人体でいうと、支柱が骨で、ひもが筋膜です。
テンセグリティー構造は、外力を受けると、再配置し、力が取り除かれると、最初の形態に戻ります。
この話、前回聞きませんでしたか?
エラスチンは、形状が変わった時に元の形に戻る伸張性を持っています。
収縮伸張しても元に戻るのは、エラスチンによるものです。
そうです。
筋膜を構成するエラスチンには、元の形に戻る伸縮性が備わっています。
そのため、テンセグリティー構造は、アライメントは、筋膜に左右されるという考え方になります。
そして、テンセグリティー構造は、力に対して、全体的に反応します。
下記の画像を見てください。
図 テンセグリティーモデル
テンセグティーモデルでは、構造は筋膜のネットワークに荷重を広げることで、それぞれにかかる力を分散できる。
人の生きた筋膜の構造-内視鏡検査を通して示される細胞外マトリックスと細胞より引用
隣り合うひもを伝って、力が分散されると、構造にかかる力は弱くなり、崩れることがなくなります。
しかし、重力を全て受け切るとなると、構造は簡単に崩れてしまいます。
図 テンセグリティーモデルではないと仮定した場合
テンセグリティーモデルを用いなければ、重力をまともに受けて、構造が崩壊する。
人の生きた筋膜の構造-内視鏡検査を通して示される細胞外マトリックスと細胞より引用
このように、人体は、筋膜によって、力が分散することでアライメントを保っています。
次回もテンセグリティー構造についてお話します。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【治療院】
施術(リリーブ)が受けられます!
たかぎ接骨院
【セミナー】
【仙台開催】
5/25(土)13:45〜16:45
【電子書籍】
・新発売!
・Amazon健康部門7位獲得!!