いま複数の証言が微妙なところで食い違っている案件の最終準備書面を書いている所だが、細部に食い違いがあっても不自然ではないことを合理的に説明する材料に、判タ1294号43頁に濱口浩東京地裁判事が執筆した、<供述の信用性について>という副題のとても興味深いエッセイを見つけることができた。
著者は冒頭で執筆動機を紹介しているが、なるほど裁判官もわれわれ弁護士と同じことを感じながら尋問に接しているのかと知りほっとする。
「民事の判決書を読んでいると、本人や証人の供述を、信用できないとか採用できないなどとして排斥している部分をしばしば目にする。
実際には、判決の上記のような記載は、供述が客観的な証拠に合致しないとか、経験則に反して不合理であるといった理由によることが多く、必ずしも供述者がウソをついていると断定しているわけではない。
思い込み、勘違いなどは誠実な人の供述にも含まれることがあり、また、尋問の仕方によっては供述内容が不正確になることもある。」
著者は、別の裁判官の書いたエッセイの中に、ある新任の任官者同士が民事刑事の配属先割り振りを決めた際にどうやって決めたかを当事者4人にインタビューしたところ、誰の部屋へ集まったのか、ジャンケンで決めたのか、配属を言い渡したのは誰なのかなど、細かい点の供述が4人とも割れていたというエピソードを初っ端紹介する。
真実は一つしかないはずなのに、こんなたわいもない話題について、わざわざウソをつこうと思っている裁判官はいないはずなのに、偏差値の高い人たちの間でも思い込みや勘違いが平気で介入する現象は、回避できないようである。
日本国内の裁判官のエピソードだけでなく、著者はドイツの[ポパーとウィトゲンシュタインのあいだで交わされた世上名高い10分の大激論の謎]という本も紹介していた。
ここでもピーターギーチ教授・マイケルウルフ教授・ピーターミュンツ教授・スティーブントゥールミン教授・ピーターグレイルーカス・スティーブンブライスター・ジョンヴィネロット・ハイラムマクレンドン、名だたる知識人8名が、わずか10分のあいだに同じ出来事を体験したはずなのに、その説明は多くの箇所で一致していなかったのである。
専門家といえどもいざ当事者になってしまうと冷静な判断をすることはなかなか困難になってしまうようである。
続いて、著者は弁護士と証人との関係について展開する。
「自分を応援してくれる人たちの精神的支援を受けて、証人の記憶は確固たるものとなっていく。弁護士が証拠を検討し、一つの可能性として、あるストーリーを提示するとしよう。すると、証人は、そうだ、私が経験したのはまさにそういうことだったのだと確信していく。
誤解を受けないように念のため述べておくと、一般に弁護士が事実をゆがめて証言させようと言っているわけではない。弁護士が証拠に基づいて合理的な主張を構成することは当然のことである。
ただ、信頼している弁護士に、それはこういうことではないのかと尋ねられれば、それに納得してそのまま受け入れてしまうということもあるのではないか」
法廷を離れ物語の話に戻すと、江戸幕末の言論弾圧事件、蛮社の獄を画策した鳥居耀蔵について、稀代の悪人と徹底して描いている小説(中山義秀の天保の妖怪)もあれば、悪役に仕立てられた不遇の人と好意的に書いている小説(平岩弓枝の妖怪)もあることから、同じ素材を用いて何通りかの説得力のあるストーリーを描くことが可能であることが示されている。
ここでは、事実認定のテーマで取り上げられることが多い、芥川龍之介の藪の中(黒澤明監督の羅生門)にも触れられていた。
それから、著者は一般論として、勘違いのメカニズムについて、刑訴法の伝聞証拠が採用されている所以を披露し、勘違いや思い込みを一定限度で回避できる策もあるのではないかと提言する。
「一般に、供述は知覚→記憶→表現の過程を経るとされるが、このすべての過程に過誤が入り込む可能性は否定できない。これらを質すのが反対尋問の目的とされている。
ただ、正確な供述を引き出すという意味では主尋問において、もっと言えば、それに先立つ事情聴取の際の、質問の仕方に工夫が必要である。工夫すると言っても、知覚や記憶の過誤は、誤りであることは判明しても正しい供述を引き出すことまではできないことが多いであろう。しかし、表現の誤りについてはそうとも言えない。」
「ある言葉の意味が多義的であったり不明瞭であったりする場合は、供述者が言おうとしていることをできる限り明確にする必要がある。
現実と思い込みや空想が混じってしまっていないか、純粋な事実の認識ではなく推測や意見を加えたものになってはいないか、他人から聞き知ったことを自分の体験によって知った事実であるかのように言っていないか、後から調べて知った事実をその時知っていたかのごとく述べていないか、などについても供述者が直接体験した事実はどのようなものであったのか上手く質問すれば相当程度ハッキリさせることができ、その結果、供述者が記憶しているとおりに正確に供述させなおすことができる場合も少なくない。」
とはいえ、最後に著者は、供述の信用性を完全に担保することはおそらく不可能ではないかという仮説につながるような指摘をしている。
「供述がどのような立場の人によってされたものかという点は、当然考慮されなければならない。実際の民事事件では、中立的な第三者証人というものは多くはない。たいていは、当事者のどちらか一方の側に立つ人である。言い換えれば、当事者はもとより多くの証人も当初から党派性を備えた存在であるということができる。
供述内容が自己の利害に直接間接に影響するのであるから、自己の記憶が曖昧な部分、どうとでもいえるような部分は、おのずと事故に有利に解釈して語られる。核心部分についてある程度デフォルメして供述されることは何ら珍しいことではない。」
「ただし、供述者があきらかにウソをついていると感じられる場合もないとはいえないが、実際の民事訴訟では露骨なウソをつく人はそれほど多いとは言えない。紛争について自己の記憶を手繰り寄せ反すうしているうちに、有利な部分は増幅され、不利な部分は忘れ去られ変容していくのであろう。」
「日時の経過とともに人の記憶は薄れ消失することもある。しかし、それととともに、その人のその後の人生体験などに基づき、記憶の全部または一部が新たに生成発展し変容することもあるのではないか。これは一種の偽体験の記憶とでもいうことができよう。利益誘導や目的指向、不当な圧力などの要素が無くても、偽体験の記憶というのは起こり得るのではないか。これは仮説であるが。」
濱口浩裁判官が人間観察のためにいろんな方面から勉強されたうえで、このエッセイを執筆されたことを激賞すると同時に、市井の弁護士は、毎週たくさんの証人尋問に接している裁判官が抱いている、証人へのこの感想を適切に自分の仕事に活かすことが大事であろう。
↓ランキング参加中、更新の励みになります。1日1回応援クリックを
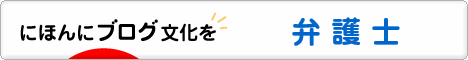
にほんブログ
http://jiko110.jp/