【日本ブログ村】クリック励みになります!
先日書いた記事で、オーガスタさんからのコメントを紹介するといって、記事を先送りしています。当事者さんが、前向きに挑戦するときに、周囲から見れば心配なほど、「できる事」より「やりたい事」に傾いて、突き進んでしまうことに関しての記事です。今日はその続きをお届けします。(前記事はこちらとこちらとこちらです。)
さて、少し話しを振り返ると、
二次障害を抱えた当事者さんが、
中々新しいことに挑戦できずに
周囲がやきもきしてしまうことが多いのに対して、
逆に、前向きになっている当事者さんが、
自分の適正を判断できにくいところで、
「できる事」よりも「やりたい事」を優先してしまった結果、
周囲は心配でしょうがないと言う事になる現象をお示ししました。
さてこのような状態を、オーガスタさんがご自身の体験から教えてくださっています。
>初めて外国で自分で暮らしを立てる、ということを始めたときです。日本にいたときから傾向として、見通しが立たないことは頭からとりあえず突っ込んでいって、ぶち当たった底辺の部分:どのくらいまで行けるのか、をまず見当つけてから、同じ要領で突っ込んでいって、だんだん当たりをつけていく、ということをしていました。
>
>その時は、自分の生まれた国であるがゆえに、無意識に蓄積した情報、セーフティーネットがいっぱいあるので、何かあったとしてもそれほどひどい打撃を受けることはありませんでした。
>
>だから気がつかなかったんですよね、日本を出て同じ方法をとって、何度も文字通り「死ぬ思い」をしました。
>
>私の場合ラッキーだったのは、長年の友人が結婚して住んでいたので、色々その都度教えてもらった、もしくは事前に情報をもらえたので、その分では救われましたが、全く違う言語、環境の中にいきなり入っていったので、特性が最初の2年くらいは悪化しました、日本では考えられないようなミスが最初の1年は多発しました。
>
>で、その都度「頭から突っ込んで」いったので、ある意味ことがなおさら悪くなったというのもありますが、長年それでやってきたので、修正するのは特性の問題もありかなり困難でした。
初めて外国に暮らすという、
定型でも未知の世界には苦労するというのに、
環境も風習も違う中での生活であっても、
それでも、まずはぶち当たっていくという、
そんなやり方だった頃のお話ですね。
>今でもその傾向はありますが、データが蓄積されてきている分だけ、見通しができるので、以前よりは慎重になれるようになりました。
>
>見通しが効かないから、閉じ込められた動物のように、とにかくぶち当たって出口を探す、というパターンもある、という話です。
まずは、試すというところで、自分なりのルールややり方を見つけていくという、これも、想像性に障害を持ち、推測や状況把握が出来にくい状態でも、惑わず進んでいくという行動特性なのかも知れません。ゼロ百のところで、進むとなったときは、極端に動く面もあるのでしょうか。僕も知り合いの当事者さんから、同じようなお話をお聞きしたことがあります。(もちろん、こういった傾向は人により、個人差が大きいですけどね。)
想像性の障害から、新しいことに挑戦するに当たっては、
推測や想像で見通しをつけにくい当事者さんにしてみれば、
そもそも、気後れしてやめておくか、
それとも、どんどん進んでいくかという
二極化しやすいと言う事でしょうか。
ここでお聞きしてホッとするのは、
そんな体験を繰り返す中で、
だんだん見通しが立つようになり、
慎重さも身についてくるというくだりです。
今、お子さんの行動が心配でならないという親御さんには、
ちょっと安心できるお話ではないかと思います。
オーガスタさんは、別のコメントで、周囲のセーフティネットについても触れてくださっています。
>経験からしか導き出せない、確かにそれはそうかもしれません。だから経験することは非常に重要なのですが、問題は「このへんでやめておこう」という見通しが立ちづらいため、もし親がこの方法を使うのなら必ずセーフティーネットが必要になります。
>
>そして、生半可な状況だと本人が理解しきれない場合があり、その場合は未消化ゆえ加減が分からないので、セーフティーネットがない状況下で繰り返してことが悪くなることもあるかと思います。
>
>個人差があるので、全ての人に使えるとは思いませんが、私の場合は「死ぬ」思いまでしないと、ある程度全般に応用できるようなレベルまで理解できませんでした。ただ、やはりそこにはセーフティーネットの存在がありましたが。
>
>親御さん、サポーターの方は、その辺のさじ加減をどう判断するかで変わってくるのではないかと思います。
オーガスタさんが友人の助けで、セイフティネットが有る状態で挑戦できたように、親御さんが当事者さんを新しい挑戦に導くときには、背後にセイフティネットを用意することも大切とおっしゃっているのでしょうか。
でも、当事者さんと支援者(親を含む)の間でこじれてしまうのは、
支援する側が張ろうとするセーフティーネットに、
当事者さんが納得できないことが多いことです。
実際、干渉されたくないと訴える当事者さんも少なくないです。
発達障害という障害は、
周囲の支援や理解が欠かせない障害だと感じるのですが、
二次障害が重かったりすると、
その支援すら拒んでしまうケースも、少なからず見受けます。
僕がそうした事例をたくさん見てきて思うのは、
支援してくれるのが親だけ・・という関係が一番厄介に感じます。
やはり、親以外にも居場所がないと言う事だと、
以前維持にも書いた「依存と恨みの関係」に
陥りやすいのではないでしょうか。
「基本的には本人のやる気を尊重する」
・・・やはりこれは、始めに有りきだと僕は思います。
その上で、親や支援者は、
ぶち当たって傷ついてくる当事者さんを、
いざとなれば受け止める覚悟を持って、
見守る事が欠かせないように感じます。
そんな感覚を、オーガスタさんは
おっしゃってくださっているのでしょうか。
そして、さじ加減の難しさ・・・
これは、悶絶するくらいに悩みますね。
どこまでまかせて、どこまで見守って、
どこから助け舟を出せばよいのか。
答えのないことだとわかっていても、
いつも、考え込むことになるんですよね。
でも、こうして親が安易に考えずに、
悩ん出だす結論というくらいで
ちょうど良いのかもしれませんね。
さて、今日は、オーガスタさんのコメントから、
当事者さんが希望に突き進んでしまうときの様子について、
考えてみました。
皆さんのクリックがとても励みになります。
いつもありがとうございます!
【日本ブログ村】 1日1クリックぽちっとお願いします!
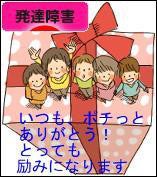


【発達障害者支援団体こころぴあビレッジ 行事ご予約はこちらから】
http://cocopv.jpn.org/yoyaku.html
【発達障害者支援団体こころぴあビレッジ 行事のご案内】
家族限定グループワーク
高機能広汎性発達障害のご家族(親族含む)が
ご参加いただけるグループカウンセリングです。
日常を離れ、ゆったりと過ごす時間の中で、
同じ境遇を持つ人たちの中で、
悩みを語ったり、思いを話したり、
分からないことを聞いてみたり。
互いの経験を交換し合う中で、
問題を一つ一つほどいていく・・・。
そんなグループを目指して、開催しています。
2012.02.15(金)10:00~14:00
大阪市内の貸し会議室で開催
定員10名(要予約)
発達障害を共に考える会
高機能広汎性発達障害の当事者・家族・支援者の
いずれもがご参加いただけます。
共に互いの話に耳を傾け、思いを感じ、
理解を深めていくためのワークです。
「テーマ」を定めてスピーチ付きのワークと、
「ノンテーマフリートーク」のグループカウンセリングのみと、
2通りのワークで開催しています。
2013.02.23(土)13:10~17:00 開場13:00
大阪市内にて
定員25名(要予約)
思いを語り、聴き、感じるワーク。
気付きの時間をお楽しみください!
先日書いた記事で、オーガスタさんからのコメントを紹介するといって、記事を先送りしています。当事者さんが、前向きに挑戦するときに、周囲から見れば心配なほど、「できる事」より「やりたい事」に傾いて、突き進んでしまうことに関しての記事です。今日はその続きをお届けします。(前記事はこちらとこちらとこちらです。)
さて、少し話しを振り返ると、
二次障害を抱えた当事者さんが、
中々新しいことに挑戦できずに
周囲がやきもきしてしまうことが多いのに対して、
逆に、前向きになっている当事者さんが、
自分の適正を判断できにくいところで、
「できる事」よりも「やりたい事」を優先してしまった結果、
周囲は心配でしょうがないと言う事になる現象をお示ししました。
さてこのような状態を、オーガスタさんがご自身の体験から教えてくださっています。
>初めて外国で自分で暮らしを立てる、ということを始めたときです。日本にいたときから傾向として、見通しが立たないことは頭からとりあえず突っ込んでいって、ぶち当たった底辺の部分:どのくらいまで行けるのか、をまず見当つけてから、同じ要領で突っ込んでいって、だんだん当たりをつけていく、ということをしていました。
>
>その時は、自分の生まれた国であるがゆえに、無意識に蓄積した情報、セーフティーネットがいっぱいあるので、何かあったとしてもそれほどひどい打撃を受けることはありませんでした。
>
>だから気がつかなかったんですよね、日本を出て同じ方法をとって、何度も文字通り「死ぬ思い」をしました。
>
>私の場合ラッキーだったのは、長年の友人が結婚して住んでいたので、色々その都度教えてもらった、もしくは事前に情報をもらえたので、その分では救われましたが、全く違う言語、環境の中にいきなり入っていったので、特性が最初の2年くらいは悪化しました、日本では考えられないようなミスが最初の1年は多発しました。
>
>で、その都度「頭から突っ込んで」いったので、ある意味ことがなおさら悪くなったというのもありますが、長年それでやってきたので、修正するのは特性の問題もありかなり困難でした。
初めて外国に暮らすという、
定型でも未知の世界には苦労するというのに、
環境も風習も違う中での生活であっても、
それでも、まずはぶち当たっていくという、
そんなやり方だった頃のお話ですね。
>今でもその傾向はありますが、データが蓄積されてきている分だけ、見通しができるので、以前よりは慎重になれるようになりました。
>
>見通しが効かないから、閉じ込められた動物のように、とにかくぶち当たって出口を探す、というパターンもある、という話です。
まずは、試すというところで、自分なりのルールややり方を見つけていくという、これも、想像性に障害を持ち、推測や状況把握が出来にくい状態でも、惑わず進んでいくという行動特性なのかも知れません。ゼロ百のところで、進むとなったときは、極端に動く面もあるのでしょうか。僕も知り合いの当事者さんから、同じようなお話をお聞きしたことがあります。(もちろん、こういった傾向は人により、個人差が大きいですけどね。)
想像性の障害から、新しいことに挑戦するに当たっては、
推測や想像で見通しをつけにくい当事者さんにしてみれば、
そもそも、気後れしてやめておくか、
それとも、どんどん進んでいくかという
二極化しやすいと言う事でしょうか。
ここでお聞きしてホッとするのは、
そんな体験を繰り返す中で、
だんだん見通しが立つようになり、
慎重さも身についてくるというくだりです。
今、お子さんの行動が心配でならないという親御さんには、
ちょっと安心できるお話ではないかと思います。
オーガスタさんは、別のコメントで、周囲のセーフティネットについても触れてくださっています。
>経験からしか導き出せない、確かにそれはそうかもしれません。だから経験することは非常に重要なのですが、問題は「このへんでやめておこう」という見通しが立ちづらいため、もし親がこの方法を使うのなら必ずセーフティーネットが必要になります。
>
>そして、生半可な状況だと本人が理解しきれない場合があり、その場合は未消化ゆえ加減が分からないので、セーフティーネットがない状況下で繰り返してことが悪くなることもあるかと思います。
>
>個人差があるので、全ての人に使えるとは思いませんが、私の場合は「死ぬ」思いまでしないと、ある程度全般に応用できるようなレベルまで理解できませんでした。ただ、やはりそこにはセーフティーネットの存在がありましたが。
>
>親御さん、サポーターの方は、その辺のさじ加減をどう判断するかで変わってくるのではないかと思います。
オーガスタさんが友人の助けで、セイフティネットが有る状態で挑戦できたように、親御さんが当事者さんを新しい挑戦に導くときには、背後にセイフティネットを用意することも大切とおっしゃっているのでしょうか。
でも、当事者さんと支援者(親を含む)の間でこじれてしまうのは、
支援する側が張ろうとするセーフティーネットに、
当事者さんが納得できないことが多いことです。
実際、干渉されたくないと訴える当事者さんも少なくないです。
発達障害という障害は、
周囲の支援や理解が欠かせない障害だと感じるのですが、
二次障害が重かったりすると、
その支援すら拒んでしまうケースも、少なからず見受けます。
僕がそうした事例をたくさん見てきて思うのは、
支援してくれるのが親だけ・・という関係が一番厄介に感じます。
やはり、親以外にも居場所がないと言う事だと、
以前維持にも書いた「依存と恨みの関係」に
陥りやすいのではないでしょうか。
「基本的には本人のやる気を尊重する」
・・・やはりこれは、始めに有りきだと僕は思います。
その上で、親や支援者は、
ぶち当たって傷ついてくる当事者さんを、
いざとなれば受け止める覚悟を持って、
見守る事が欠かせないように感じます。
そんな感覚を、オーガスタさんは
おっしゃってくださっているのでしょうか。
そして、さじ加減の難しさ・・・
これは、悶絶するくらいに悩みますね。
どこまでまかせて、どこまで見守って、
どこから助け舟を出せばよいのか。
答えのないことだとわかっていても、
いつも、考え込むことになるんですよね。
でも、こうして親が安易に考えずに、
悩ん出だす結論というくらいで
ちょうど良いのかもしれませんね。
さて、今日は、オーガスタさんのコメントから、
当事者さんが希望に突き進んでしまうときの様子について、
考えてみました。
皆さんのクリックがとても励みになります。
いつもありがとうございます!
【日本ブログ村】 1日1クリックぽちっとお願いします!
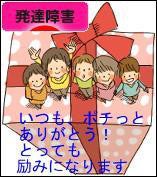
【発達障害者支援団体こころぴあビレッジ 行事ご予約はこちらから】
http://cocopv.jpn.org/yoyaku.html
【発達障害者支援団体こころぴあビレッジ 行事のご案内】
家族限定グループワーク
高機能広汎性発達障害のご家族(親族含む)が
ご参加いただけるグループカウンセリングです。
日常を離れ、ゆったりと過ごす時間の中で、
同じ境遇を持つ人たちの中で、
悩みを語ったり、思いを話したり、
分からないことを聞いてみたり。
互いの経験を交換し合う中で、
問題を一つ一つほどいていく・・・。
そんなグループを目指して、開催しています。
2012.02.15(金)10:00~14:00
大阪市内の貸し会議室で開催
定員10名(要予約)
発達障害を共に考える会
高機能広汎性発達障害の当事者・家族・支援者の
いずれもがご参加いただけます。
共に互いの話に耳を傾け、思いを感じ、
理解を深めていくためのワークです。
「テーマ」を定めてスピーチ付きのワークと、
「ノンテーマフリートーク」のグループカウンセリングのみと、
2通りのワークで開催しています。
2013.02.23(土)13:10~17:00 開場13:00
大阪市内にて
定員25名(要予約)
思いを語り、聴き、感じるワーク。
気付きの時間をお楽しみください!