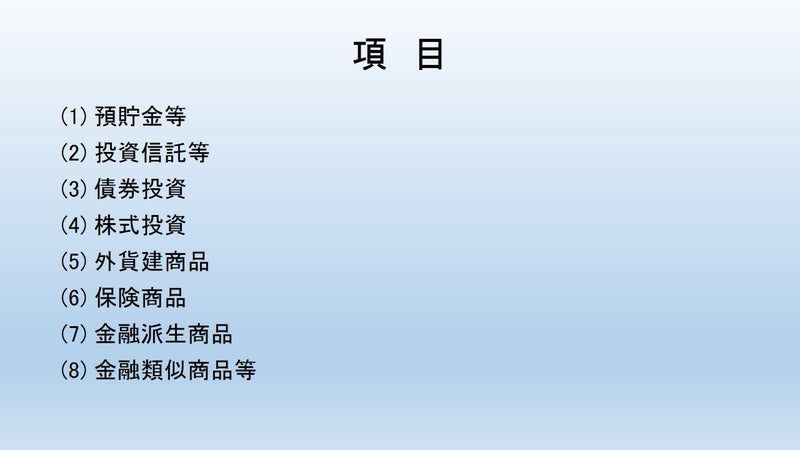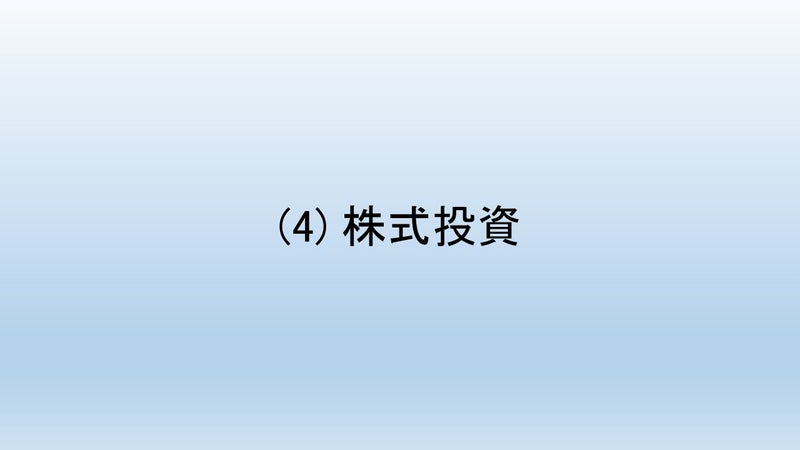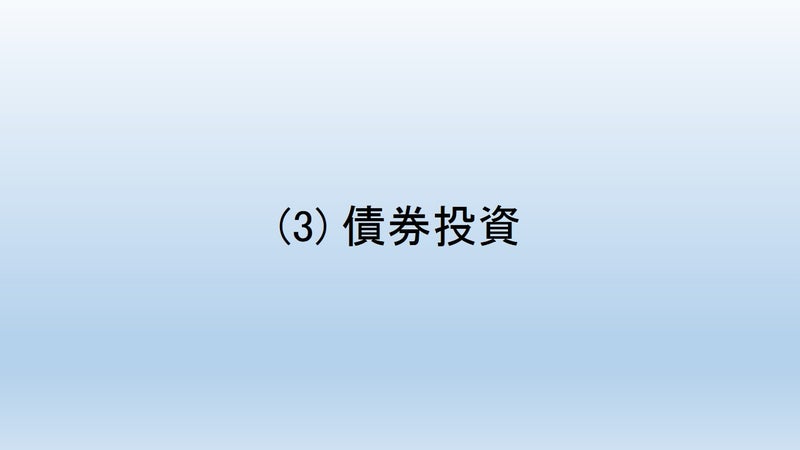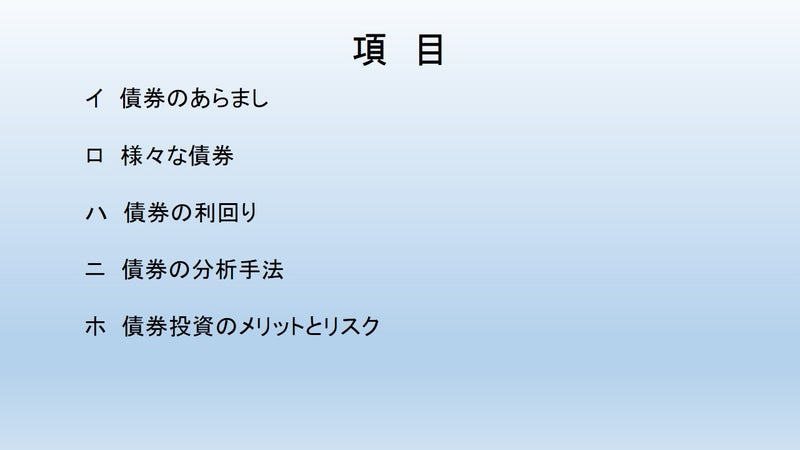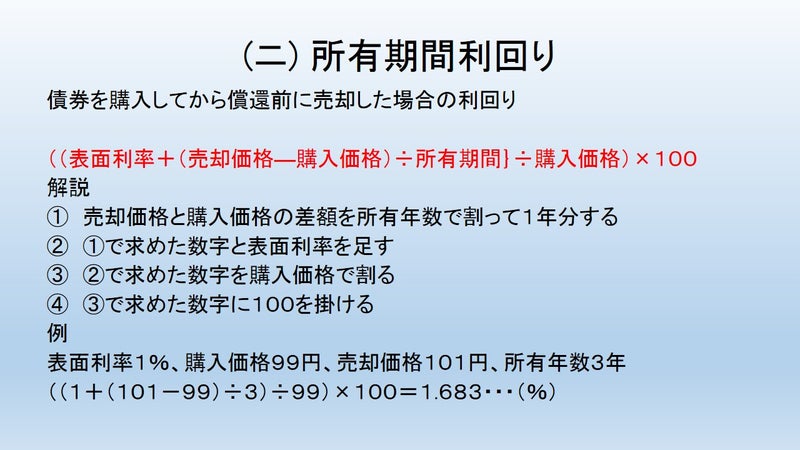始めに
今回は、お金を増やす金融資産運用7つの知識
のうち
項目
1 経済指標と金利の知識
2 利息の計算方法の知識
3 各種商品の知識
4 運用方法の知識
5 税金の知識
6 セーフティネットの知識
7 関連法規の知識
「3 各種商品の知識」
(1) 預貯金等
(2) 投資信託等
(3) 債券投資
(4) 株式投資
(5) 外貨建商品
(6) 保険商品
(7) 金融派生商品
(8) 金融類似商品等
のうち、
(4) 株式投資
項目
項目
イ 株式取引の仕組みと特徴
ロ 信用取引
ハ 株式投資に関する評価指標
ニ ディスクロージャー情報の入手方法
イ 株式取引の仕組みと特徴
(イ) 国内の株式市場の種類
(ロ) 代表的な株式指標
(ハ) 株式の性質と株主の権利
(ニ) 株式投資のルール
(ホ) 株式の種類
(ヘ) 株式累積投資、株式ミニ投資
(ト) 株式投資関連商品
(チ) 株式投資のメリットとリスク
のうち
(イ) 国内の株式市場の種類
からご説明いたします。
(イ) 国内の株式市場の種類
国内の株式市場の種類は、
•東京証券取引所
•大阪取引所
大阪証券取引所から名称変更
主にデリバティブ(金融派生商品)に特化した取引所
•名古屋証券取引所
•札幌証券取引所
•福岡証券取引
があります。
(ロ) 代表的な株式指標
代表的な株式指標としては、
1 日経平均株価(日経225)
東証一部に上場されている銘柄のうち225銘柄の株価を修正して平均したもの
2 TOPIX
東証一部に上場されている全銘柄の時価総額を指数化したもの
3 JPX日経インデックス400(JPX日経400)
東証全体のうち投資家にとって魅力の高い400社の株価指数
があります。
(ハ) 株式の性質と株主の権利
株式の性質と株主の権利について簡単にご説明すると、
株式は、株式会社が発行する出資を証する証券です。
上場株式に係る株券は全て廃止され、証券保管振替機構(ほふり)と
証券会社の口座で電子的に管理されています。
株主の主な権利としては次のようなものがあります。
1 株主総会での議決権
会社の経営方針等を決める株主総会に出席して決議に参加できる
2 剰余金分配請求権
配当として利益の分配を受けることができる
3 残余財産分配請求権
会社が解散した場合、財産があれば分配を受けることができる
但し、様々な種類の株式の発行が認められており
議決権のない株式もあります。
今回のご説明は以上となります。
私が運営しているサイト FPマネースクールには不動産運用を含め、
マネーに関する様々な情報がありますのでココをタップ・クリックして
ご覧いたたければと思います。