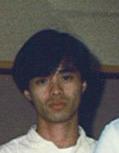KOHの飄々無常庵
映画鑑賞記録が主になりますが、日々の徒然なることを書いていきたいと思います
プロフィール
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
ブログ内検索
このブログのフォロワー
お気に入りブログ
ブックマーク
2010-03-21 13:01:52
「龍馬伝」登場人物紹介 やべきょうすけ演じる「久坂玄瑞」
テーマ:龍馬伝
龍馬伝登場人物紹介 第十九回は、やべきょうすけ演じる「久坂玄瑞」
高杉晋作と双璧をなすと言われ、吉田松陰も「防長随一の人」と評しています。
天保十一年(1840年)萩藩医、久坂良迪と富子の二男として誕生しています。
坂本龍馬が天保六年生まれですので、5歳年下ですね。
龍馬と同じく、年を取ってからの子でしたので、可愛がられて育てられました。
家業である医学を勉強するため、藩校医学所好生館に入学した後、藩校・明倫館に入学しています。
が、嘉永六年から七年にかけて、母、兄、父を続けて亡くし、家督を継ぐことになりました。
もうテレビでは、過ぎ去っていますが、安政三年、18歳で、九州へ遊学しています。
この九州遊学で、肥後藩の宮部鼎蔵(池田屋事件で死亡)を訪ねた際、吉田松陰に学ぶことを奨められ、
この時はじめて、吉田松陰の存在を知ります。
帰藩後、吉田松陰と手紙のやりとりを約1年続け、謹慎中で吉田松陰が開いていた松下村塾の門弟となります。
吉田松陰は、久坂玄瑞の才能を認め、自分の妹、文を嫁にやっています。
松陰は、高杉晋作と久坂玄瑞を競わせるようにします。
久坂は、「高杉晋作、久坂玄瑞、吉田稔麿(池田屋事件で死亡)、入江九一」で松下村塾の四天王と呼ばれるようになりました。
安政六年、吉田松陰が、安政の大獄で、亡くなると久坂は、長州藩の攘夷の先頭に立つようになります。
文久二年(何度も出てくるでしょ、この年)、藩政内部で、頭角を現していた久坂は、藩の方針を
吉田松陰の航海雄略論を周布政之助、高杉晋作とともに推挙し、長井雅楽の航海遠略策を排除します。
これで、長州藩は開国攘夷派が占めることになります。
同年、幕府へ攘夷を促すため、三条実美、姉公路公知と江戸に入ると、
既に江戸に出ていた高杉晋作らと御楯組を結成、有名な品川御殿山の英国公使館焼け討ちを実行しています。
文久三年には、京都翠紅館にて各藩士と会合したり、4月からは京都藩邸御用掛として攘夷祈願の行幸を画策しています。
同年帰藩すると、下関にて光明寺党を結成、首領に公家の中山忠光を迎え、外国艦船砲撃事件を行っています。
※これは、その後二年続くのですが、幕府が賠償金を払ったり、最終的には、英米仏蘭に砲撃を受けています。
久坂は、さらに京に上り、尊攘激派と大和行幸の計画などを画策したりと活躍しました。
同年の八月十八日の政変で、長州藩が失墜すると、久坂は、京都詰の政務座役として在京し、失地回復を図っています。
が、元治元年で池田屋事件が起きると、長州藩内部で、京都進発の議論が起こり、久坂も同調します。
こうして、長州藩が、京へ攻めた、禁門の変が起こります。図式的には、長州藩×薩摩藩、会津藩の戦いでした。
久坂は、この時、負傷がひどく、助けを求めた鷹司邸にも、入ることを許されず、同じく寺島忠三郎と自刃しています。
松下村塾の四天王、吉田稔麿は池田屋事件で憤死、久坂玄瑞、入江九一は、この禁門の変で亡くなっています。
池田屋事件、禁門の変が、長州の有望な人材をことごとく殺しています。
久坂玄瑞の辞世の句は、
「時鳥 血爾奈く声盤有明能 月与り他爾知る人ぞ那起」
訳すと
「ほととぎす ちになくこえはありあけの つきよりほかに、しるひとぞなき」
が残っています。
享年25歳、幕末の動乱でこの国は、多くの人物失いましたが、その中でも、最も惜しいと言える人物の一人でしょう。