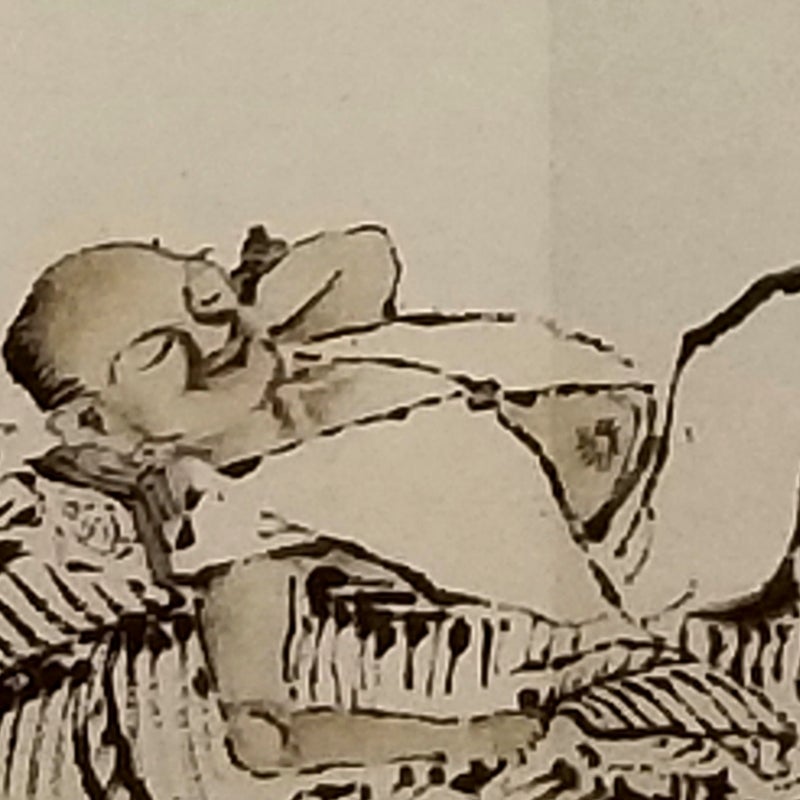“目に見える世界”から ・ ・ ・
これは、、、水辺? 湖畔でしょうか。
まず注目したいのは、画面右下。
珍しく瓦葺きの家が描かれています。第三図や
第四図では茅葺きの庵でした。
また他図では、登場人物は一人か二人でしたが、
今回は部屋に複数の人が集まっていますよ。
客人でしょうか。それとも…
賑やかな雰囲気が感じとれます。
続いて、家の前の大木。アオギリでしょうか。
ずいぶんと左に曲がっています…
よく見ると、
画面奥の木々もみな同じ方向を向いていますよ。
どうやら風が吹いているようですね。
それもかなりの強風のようです。
季節はどうでしょうか。
山の辺りに枯れた木々が見えます、、、あとは、
これは紅葉? 実? 赤く色付いているところも。
秋頃でしょうか。
となると、緑の葉を茂らせているのは常緑樹?
湖の向こうには、小さい山と大きい山がふたつ
並んでいて、その向こうには、
うっすらと五重塔(仏塔)のような建造物が。
画面右下に寄り合った、
木葉、屋根瓦、部屋、人物に施された彩色が、
画全体のコントラストを際立たせています。
竹田が“表現”に込めた想いとは一体 ・ ・ ・
画面下中央に小さな橋が掛かっていますよ。
文人画(南画)における橋は、単なる風景としての
素材のひとつでなく、世俗との“境界線”の役割を
果たしていることもあり、その場合は、
極力小さく幅が狭く描かれているほどいいとされ
ます。(作意にもよりますが)
それは
誰でもかまわず(大勢)来てほしくない示唆。
また物理的にも、
牛車や車馬が通れぬ(来させぬ)ようにと。
(車馬は昔の役人や貴族などの乗り物)
よって、
“社会と距離を置いた暮らしぶり”が窺えます。
わさわざあの場所に橋を描く必要はないのかも
しれません。仮に橋が無かったとしてもそれほど
画の印象は変わらないでしょう。
ですが、あえてあの場所に橋を描き込むことで、
画の外(家の右側=描かれていないところ)に道は
ないことが強調されます。
生活の支えとなっている橋。
実在性というよりも“精神世界”として。
あくまで私の推察。
真相は竹田に訊かないとわかりません ・ ・ ・
画像では見えづらいかもしれませんが、
空と湖面に同じような筆線がみられます。
木々を揺らす風、波立つ湖面を表しているのか、
或いは、
空の薄暗さ、それを映す湖を表しているのかも
しれませんね。画だけでは判断しかねます。
そして、画面左下に賛が添えられています。
さあ、ここからですよ。
まずは賛を読んでみますね。
風雨夕掩門不出妻孥
環坐温酒同酔歓笑達
旦亦復一楽
風雨の夕(ゆうべ)、門を掩(おお)いて出ず。
妻孥(さいど)環坐し、酒を温め同(とも)に酔い、
歓笑し旦(たん)に達する。
亦復(またまた)一楽。
風雨の夜は門を閉ざし、どこにも出かけず。
家族みなで集まり向かい合い、
酒を温め、共に酔って楽しんでいると、
夜が明けてきました。亦復一楽。
(意訳はご参考までに)
江戸時代後期の文人画(南画)家
田能村竹田(たのむらちくでん/1777-1835)の画帖
『亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)』に収録され
ている「第六図」です。
「掩門(えんもん)」とは、門を閉ざすこと。
「妻孥(さいど)」とは、妻と子。家族。
「環坐(かんざ)」とは、複数の人が輪になって、
内側を向いてすわること。
車座(くるまざ)。円居(まどい)。
よって「妻孥環坐」とは、家族団らんの様子を
言います。
団らんの「団」は、円い、欠けがないという意。
「旦(たん)」とは、明け方。夜明けのこと。
元旦の旦ですね。ちなみに「旦」という字は、
水平線から太陽が昇る姿を表現した漢字です。
つまり、元日の朝(歳朝)のこと。
賛を読んでみて、
風雨の夜のひとときだとわかりました。
しかし、、、
画だけでは風が吹いているのはわかっても、
夜に雨が降っているようには見えません…
もしかしたら、雨が上がり夜が明けだしたころと
みたほうがよいのかも。
わざと筆数を減らした=“引き算”をした可能性も
ありますが。
それにしても、、、
第一図から第六図まで順にみてまいりましたが、
ここにきていきなり家族愛をうたってくるとは…
この図は、
“家族との団らんの様子を描いた画”ということに
なりますね。
ちなみに竹田には、
父と母、兄と姉、祖母がいました。
三十二歳の時に結婚。
その後、長男が生まれます。
三十七歳の時には、
政治への疑問から、また病気療養の必要もあり、
隠居の身となっています。
初回の記事で少しふれましたが、
この『亦復一楽帖』に収録されている全十三種の
図の順は、後にこの画帖を竹田からうばいとった
親友の頼山陽(らいさんよう)の手によって意図的に
入れ替えられており、
各作品の成立順も定かではありません。
こちらの第六図も、当初は第五図だったとか。
また、
これまでの回でお伝えしてきているように、
画自体は、竹田が旅の途中に立ち寄った土地の
景色(スケッチ)や旅で得られた感興という実感、
記憶の断片、その他、日々の思索や体験が混ざり
合って創作表現されています。
ありそうでなくて、なさそうでありそうな景色。
竹田にとって
画は“理想”であり、“美的精神の骨頂”の具現化。
“売画(ばいが)生活”をした文人は多くいますが、
本来はお金のためでなく、
“自分が画きたいかどうか”。
文人画は“心そのもの”。
作品(描き終わった画)がどうこうでなく、
積極的逃避=画を描いている(心を旅している)
その最中こそ、
まさしく“自娯の世界”
創作表現されているとはいえ、
『亦復一楽帖』に並ぶ画(“楽しみの数々”)は、
けっして
非日常の世界を描いたものではありません。
それらはどれも、
“何気ない日常の中の一場面”
この「第六図」においても。
どこまでを「家族」と呼ぶのかは人それぞれ。
(私個人的には、
血のつながりは関係ないと思っていますが…)
“閉鎖社会”や“孤立不安社会”といわれる現代。
竹田の時代とでは、「家族」というものに対する
認識やあり方は当然異なるでしょうが、、、
しかし、
本質は変わらないと私は思います。
歳月人を待たず。
明日のことはだれにもわからないのだから、
いまこうして家族全員そろって、
互いに顔をみながら笑い合えることが、
いかに尊いものであるか。
“当たり前じゃない”からこそ、
“楽しめるときは楽しもうよ” ・ ・ ・
なんとな~くではありますが…
この「第六図」の賛からは、
自然を愛し、酒を愛し、菊の花を愛し、
そして家族と友を愛した魏晋南北朝時代の詩人
陶淵明(とうえんめい/365-427)の香りが漂います。
“歳月人を待たず”は、淵明が吐露した言葉。
本質を突いた言葉は、1600年経った今でも、
まったく色褪せていません。むしろ瑞々しく。
淵明は詩中で、“酒は忘憂の物”と言っています。
酒は憂いを忘れさせてくれるものだと。
ただし、
現代で言うところの、“仕事終わりに乾杯”、、、
といった向き合いかたではありませんよ。
中国の詩人で酒好きを三人あげるなら、
文人精神の源流にいつづける陶淵明、
“酒仙”李白(りはく/701-762)、そして、
中唐の詩人白居易(はっきょい/772-846)がいます。
もちろん彼らは
その辺にいる“酒飲み”とは次元を異にします。
この図の賛にみられる
「温酒同酔」ー 酒を温め共に酔う の句からは、
白居易が
故郷へと帰ってゆく友人の王質夫(おうしつふ)に
贈った詩、
「送王十八歸山寄題仙遊寺」
「王十八(おうじゅうはち)の山に帰るを送り
仙遊寺(せんゆうじ)に寄題(きだい)す」
に出てくる、
「林間煖酒焼紅葉 石上題詩掃緑苔」の一節が
思い出されます。
林間暖酒焼紅葉
林間に酒を暖め紅葉を焼(た)く
林の中、落ち葉を焚き火にして酒を温め、
石上題詩掃緑苔
石上に詩を題するに緑苔(りょくたい)を掃(はら)う
石の上に詩を書くため緑の苔をはらう。
季節が移り冷え込んできたら、
友と温かい酒を酌み交わし、秋の風情を楽しむ。
しかしながら、その友が去ってしまうことで、
もうそれができなくなることを嘆いた詩です。
お酒にかぎらずですが、
秋深まる山中で、
木が落とした不要の枝や枯れ葉を燃やし、
泉の水を汲んで湯を沸かし、茶を喫す。
いいですね。
共に情趣を味わえる友の存在 ・ ・ ・
「目に見える世界」においては、
家の中と家の外を描きわけ、
「目に見えない世界」においては、
橋を挟んで“心の置きどころ”を描きわけている。
門を閉ざして(外の世界と遮断し)、
家族みなと部屋で過ごすひととき。
そこには、
いい会話があって、、、いい笑顔があって、、、
そういう夜の過ごしかた。
画面右から画面左へと吹きあれる強風。
木々があれだけ煽られているなか、、、
言い換えれば、
“外の世界がどうであれ、
(世間がいまどれだけ騒がしかろうと)
こうして皆で楽しく和気藹々と過ごしている”
(心をどこに置くかで“今いる世界”は変わる)
根がしっかりしていれば、
(家族がみな安泰であれば)
そう簡単には倒れない。
(もうそれで十分だよ)
もし家の前の木が真っ直ぐ立っていれば、
部屋の中の様子は隠れて見えなかったでしょう。
(普段はなかなかじっくり話す機会もないけど)
“強風が吹いて、家族の顔を見ることができた”
“真っ暗で不安定な外”と“明るく円満な家の中”。
外の世界とはまるで対称的な内なる時空間。
それは“何でもない日常”かもしれない。
“風雨の激しい夜は訪ねて来る人もいない。
そんな夜は門を閉ざし、家族みなで集まって、
酒を酌み交わし、楽しく笑い合って、、、
気づけばもう夜明けだよ ・ ・ ・”
楽しい時間はあっという間に。
これもまた“ひとつの楽しみ”
…と。
ここまでお読みいただき
ありがとうございました。
次回は『亦復一楽帖』の「第七図」を。
壬寅 秋分後五日
KANAME
一部引用・参考文献
・『水墨画の巨匠 竹田』第十四巻 中村真一郎/河野元昭 著
講談社 1995年
・『田能村竹田 基本画譜』 宗像健一 編著
思文閣出版 2011年
【関連記事】
2022年9月23日 投稿
2022年9月17日 投稿
2022年9月13日 投稿
2022年9月10日 投稿
2022年9月2日 投稿
2022年8月26日 投稿