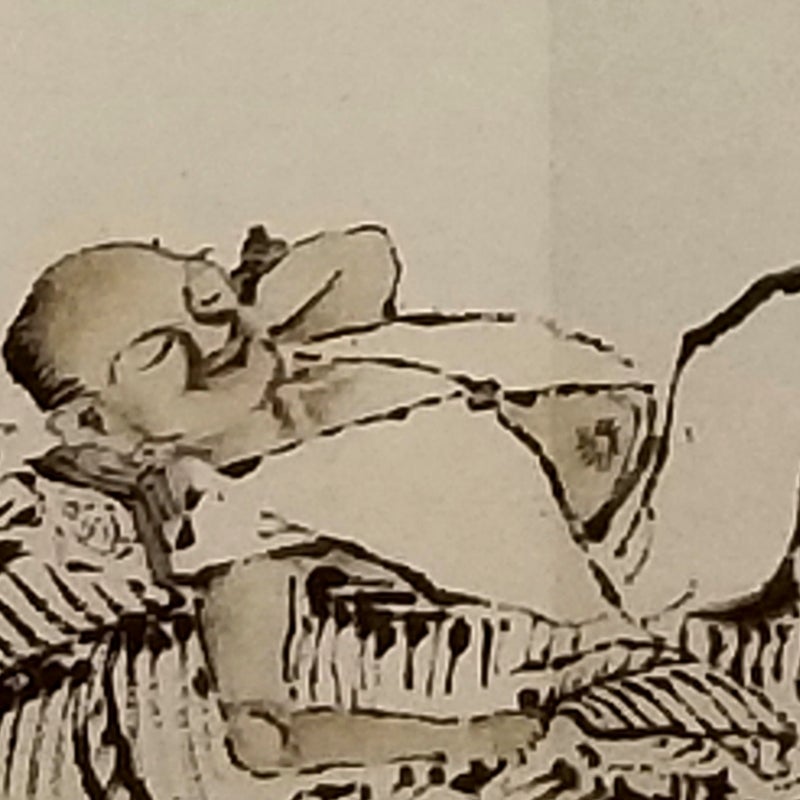“目に見える世界”から ・ ・ ・
山居が描かれています。
よく見ると、
門が開いていて、だれか顔を覗かせていますよ。
これから出掛けていくところでしょうか。
それとも人が訪ねてくるのを待っているところ?
門は画の中央部に配されていて、画面左奥には、
おやっ、二階にも人影が。
窓は開いていて、外(門のほう)を見ていますよ。
家の後方には険しくそびえ立つ山々が、
まるで大きな壁のように並んでいます。
向こうにはうっすらと景色がみえますね。
そして、
山と山の間に賛が添えられています。
何でもない山の暮らしを描いた画?
さあ、ここからですよ。
まずは賛を読んでみますね。
屏居山中有
素心友来訪
使童子候之門前
亦復一楽
山中に屏居(へいきょ)し、
素心(そしん)の友の来訪あり。
童子を使わしてこれ門前にて候(そうろ)ふ。
亦復(またまた)一楽。
山中に隠棲している私のところへ、
純朴な友がやって来るという。
童子に門前まで向かわせ、
(友がやって来るのを)うかがい待つ。
亦復一楽。
江戸時代後期の文人画(南画)家
田能村竹田(たのむらちくでん/1777-1835)の画帖
『亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)』に収録され
ている「第三図」です。
“何気ない日常のひとコマ”
「屏居(へいきょ)」とは、世を逃れ隠れ棲むこと。
「屏」という字が用いられていますが、
明代の文人袁宏道(えんこうどう)が著した、
生け花について述べた最初の書物ともいえる
『瓶史(へいし)』に、
「屏」を使用した似た表現が出てきます。
これは、
“まるで屏風のように突っ立った山々に遮られた
山深いところに棲んでいる”という意味で、
よって、家のうしろに大きく描かれた山は、
“その向こう側=俗界”との境界線を表します。
緩やかでない稜線がそれを強調していますね。
竹田が『瓶史』を愛読していたことが窺えます。
「素心(そしん)」とは、潔白、純真、清浄な心。
「素」は白=“染まっていない”の意。
「訪」、「門」、「楽」の字がわずかに大きく
書かれているようにも。
友を待つ楽しみ。
気の合う友が“やって来る前”。
その時間が楽しい …と。
“待つ間が花”ということなのでしょう。
世俗と距離を置いて暮らしていながら、
(“来るなよ”と言っておいて)
人が来るのを待つ。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
一見すると矛盾しているようですが、しかし、
心許す友は別。
むしろ来てほしい。
なんとも人間らしい心模様です。
もう一度、画全体を観てみますね。
山のほうに道は描かれていません。
道は画面手前に。
こちら(自分)から“向こう”へはけっして行くこと
はない意思表示。
と同時に、“俗界からは来てほしくない”気持ちの
表れでしょうか。
もちろんこれは現実的な暮らしというよりも、
ただただ気の合う者とだけ交わっていたい、
“竹田の精神世界”を表現した画。写意画。
“ウマイ・ヘタ”でない、画そのものが彼の世界。
古典を徹底して学んだ上に、自身の思索と体験が
乗っかり、
そこから想像と妄想の果てに生まれていった世界
が、“ことば”となり、画となって ・ ・ ・
ふつうの発想なら、
友が訪れてきて、“共に酒を酌み交わし亦一楽”
となるのでしょうが…、 竹田はちがいます。
“来る前”
“待ってる時間”が楽しいと。
“友を待つあいだ”
“まだかな、まだ来ないかな”
ついには待ち焦がれて ・ ・ ・
“お~い、ちょっと見に行ってきてくれないか”
…と。
上(二階の窓)から見ていればわかるのに、
わざわざ童子に門まで見に行かせて。
それが“亦一楽”。
仕事や付き合いのために人に会うのは、
ほんとに気が重いですよね。
(私もできるだけ人と会いたくない人間なので…)
でも、
ほんとに会いたい人、気の合う友が来るのは、
前の日から楽しい。(ワクワク・ドキドキ)
もしかしたら、待っている時間のほうが
会っているとき(その最中)よりも楽しいのかも
しれません。
極端なことを言えば、
遅れて来てくれるほうが楽しい時間は長くなる。
だれも来ることのない。“来てほしくない”
そのぶんだけ、
遠くから友が訪ねてきてくれたときの喜びは、
計り知れないものに。
そこで喫する茶は、美味しいに決まっている。
遅れて来ても、なお楽しい。
心がかよい合っているから。
ここまでお読みいただき
ありがとうございました。
次回は『亦復一楽帖』の「第四図」を。
壬寅 白露後五日
KANAME
一部引用・参考文献
・『水墨画の巨匠 竹田』第十四巻 中村真一郎/河野元昭 著
講談社 1995年
・『田能村竹田 基本画譜』 宗像健一 編著
思文閣出版 2011年
【関連記事】
2022年9月10日 投稿
2022年9月2日 投稿
2022年8月26日 投稿