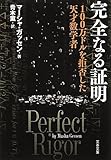何度も言っている(言い訳している)ことではありますけれど、
個人的には完全に文系頭の持ち主であると思っておりまして。
といっても、そもそも理系頭、文系頭というものがあるのかどうかは知る由もないところでして、
昨今、大学生の就職事情が大変厳しいものである(少し回復基調のようですが)となると、
大学入学の段階から理系学部に人気が集まるてな傾向を聴き及んだりしますが、
「いくら理系の方が就職に有利だと言われても、そう簡単に文系から理系にシフトできるもの?」
と個人的には至って真剣に思うところです。
が、現実にそうしたシフトはあるようで、そうなるととやかく言う自分が
単に理数系科目を不得手としているだけなのか…とも思ったり。
そうしたふうでありながら、なんとなくこうした本を手にとってしまうのでして、
例によって前置きが長いですが、「完全なる証明」という本を読んだというお話であります。
長らく解き明かされていない数学上のいくつかの難問を解決した場合には
100万ドルの懸賞金を出すとアメリカのクレイ数学研究所で発表したのが2000年のこと。
そこでミレニアム問題とも言われるようですけれど、
その対象たる問題の一つが「ポアンカレ予想」というもの。
ひと言で言うと、こういうことになるようです。
単連結な3次元閉多様体は3次元球面S3に同相である。
そして、「S3」とは {(x, y, z, ω)∈R4 | x2+y2+z2+ω2=1} なのだそうで…。
書いておいて何ですが、個人的には当然に「何のことやら?」なわけでして、
しばらく前にヒストリーチャンネルで見た「数学の歴史
」なる番組の中でも
ポアンカレ予想をやさしく説明してくれていた(つもりだった…)のですけれど、
分かったような分からんような。
本書ではさらにこれをトポロジーの入口から丁寧になぞってくれていて、
いくらか分かったつもりになったものですが、
全体を読み終えてみると「なんだったっけかな…」という具合。
そうした体たらくではありますが、はっきり言ってポアンカレ予想がピンと来なくても
十分に本書は興味深いものでありましたですよ。
とまれ、本筋としてはポアンカレ予想に取り組んで「完全なる証明」を成し遂げた
ロシアの数学者グリゴリー・ペレルマンのことが書かれているわけですけれど、
ペレルマンは1966年生まれといいますから、後に数学上の偉業を達成するに至るまでに
その数学的思考と技量に磨きをかけてきたのは、まさにソビエト連邦体制下でありましすね。
この時代、子どもたちには一様に
思想教育も含めた教育を施していたのではないかと想像したりしてましたが、
極端に言えば(ソ連型)共産主義の細かい突っ込みを気にする時間があるんなら
とにかく問題に向き合って数学的思考を養っていこう!というコンセプトの数学学校があった…
ということに、まず驚きましたですねえ。
ペレルマンはこうした学校で学んでいたのでして、
その名から想像されるとおりにユダヤ人 であるペレルマンには
(共産主義という中でも)差別が厳然としてあった普通の学校ではない学校で学べたことは
幸運なことだったのでありましょうね。
もっとも誰でも入れるわけではなく、
子どもとしても抜きんでた数学の才能が目にとまらなければならないので、
もちろん天賦の才でもあったのでしょうけれど。
それにしても、ペレルマンの成長過程には、
場面場面でユダヤ人であるがゆえの壁が立ちはだかるものの、
本人がどうにかしようというよりも、むしろ数学の師匠たちの方がどうにかしてしまって
道が切り拓かれてきたふうでもあります。
数学オリンピックの出場にしても、大学に入るにしても、研究を続けていくということにしても。
それだけペレルマンの天才は、分かる人には分かる凄さがあったというですかね。
ただ、本人がどうにかしようとしなくても…という部分を考えると、
とても一般的な生活をしていける、いわゆる社会性とかそういうものとは無縁でもあったかと。
それに、自分の持つ尺度なりに照らして、いい、悪いがはっきりしており、
そうしたことに異常にこだわるようなところもある…となれば、
なかなかに付き合いにくい人物であったとも思われますね。
自分が完全に証明したと考えて発表したポアンカレ予想に対して、
その後に一般的な論文査読がどうのとか、マスコミがへんな取り上げ方をするとか、
あれやこれやのごたごたしたことは、天才だけに訳の分からない騒ぎであって、
結局のところミレニアム問題を解決した報奨の100万ドルも受け取り拒否して、
どこかしらに隠遁したまま、現在に至る…というらしい。
後世の見立てではあるものの、
ダ・ヴィンチやベートーヴェン 、ゴッホ、そしてアインシュタインといった人たちが
アスペルガー症候群ではなかったかと言われたりしてますけれど、
その半生をなぞってくるとペレルマンもまた何らか発達障害といいますか、
そうしたところがあるやに思うところです。
時代的にはそうした分野の研究が進んでおらなかったのがペレルマンの成長期でしょうに、
いささか(かなり?)風変わりと思われる行動をも受け容れて、ペレルマンの数学の才を
思いのたけ伸ばしてやれる状況があった。
繰り返しになりますが、画一的とも思われるソ連の中にあって。
考えてみれば、個性、個性と言いながらも、日本の方がよほど画一的なのでしょうなあ。
国際的に活躍する人材が求められる…てなことをが言われると、
どこもかしこもそうした方向に舵を切る(切らされる)。
そういう人材も必要であろう反面、
もそっと異なる分野でこそ活躍できる芽をもった子どもたちもたくさんいるでしょうに…。