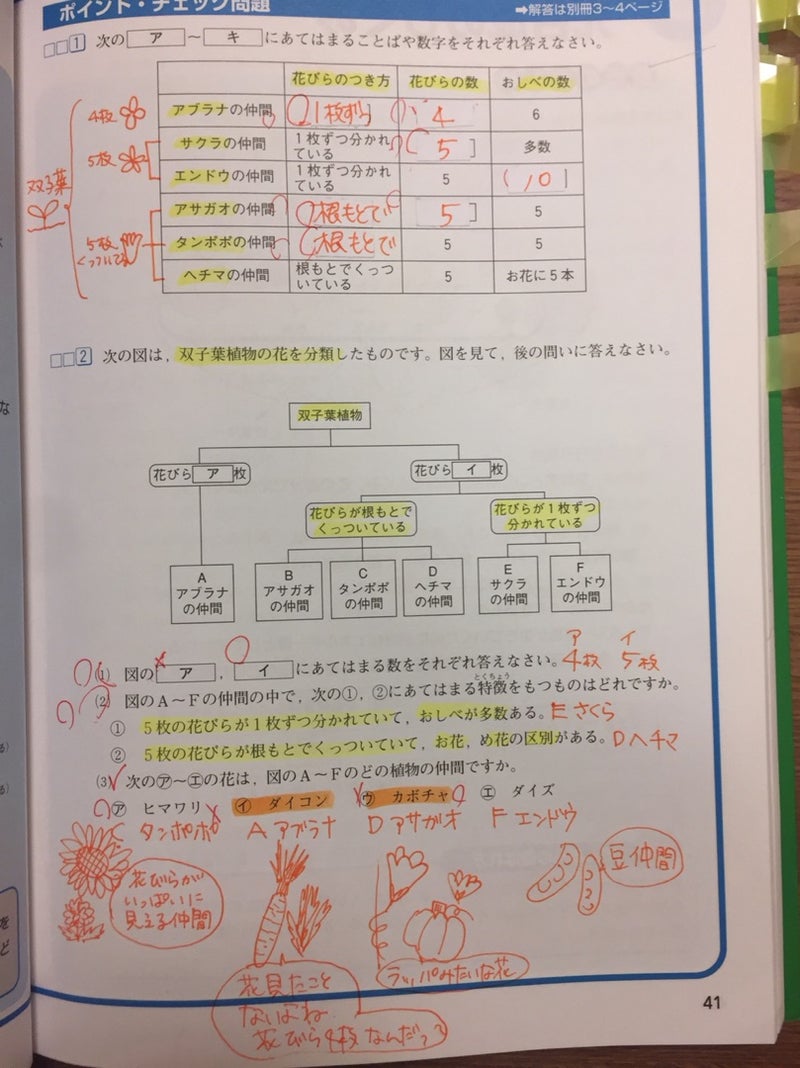老婆心コーナーで、親御さん方が特に気になってそうな定期考査についても書いておこうと思いながら、直前になってしまってソーリー…
もう…新年度ってめっちゃ忙しくて…
<定期考査について>
・入学後最初のうちは、e塾占有率の高い学校ほど、学判年間平均偏差値と相関がある
・ただし中受の貯金が効いてるのは最初のうちだけ
・入学後にしっかりと生活リズム&学習習慣をつけなければ成績は落ちる
・英数をやろう
・テスト前に課題でいっぱいいっぱいになってるのは黄信号
・勉強時間記録表、ほとんどの子が盛って書いている
・1回目の定期考査・中間テストは「初見対応力」をお手並み拝見
・返却後の分析・振り返りをしっかりするのがなにより大事
・PDCAサイクルを習慣づけられるようコーチングを
・定期考査は2回目の期末テストこそが試金石
・1学期期末テストを終えた時点で、「頭良い人」扱いされる子と、「バカ」呼ばわりされる子が出てくるという現実
・下剋上チャンスは夏休み、まだ全然追いつける追い越せる
・英数をやろう
・夏休み明けの定期考査で校内立ち位置はほぼ決まる
・ここで再登場e塾「学校別合判成績優秀者名簿」と答え合わせだ
・好成績は1回目はまぐれ、2回目は偶然、3回続けば実力と呼べる
・ただし理社で点数を稼いで総合順位を押し上げても砂上の楼閣、砂漠の蜃気楼だから気をつけよう
・英数をやろう
・最悪、英語だけはやろう
・学年相当の読書を続けて受検でつけた国語力も維持をしよう
いっこずつ見てこう。
<e塾相関>
都立中入学後の最初のうちの成績は、e塾占有率の高い学校であればあるほど、学判(e塾の月イチ試験であるところの学力判定テスト)の「年間平均偏差値」と正の関係があります。考えてみれば当たり前の話ですな!
1年間、偏差値は上がったり下がったりジグザグするのが普通なので、「年間平均偏差値」が実力だと私は思ってます。
ただしこれは貯金が効いている最初のうちだけ!
・部活がキツくて体力持たなかったり時間なくて、日々の課題こなすのもいっぱいいっぱいの自転車操業
・平日はスマホいじり倒して、休日は遊んじゃって、すっかり勉強嫌いになっちゃった
・メンタルや体壊して学校休みがち…
そんな感じで、入学前は神童と呼ばれていた子があれよあれよと…というのもこれまたよくある話…。
結局コツコツやる子がどこ行っても一番強いんですよね。
<栗山さんは過保護上等でした>
以下、n=1の私の体験談にすぎませんが、参考に取り組んだこと思い出して書いておきます。
都立中受検の場合(に限らずかもしれませんが私立受験はよう知らんので)、作文ストック作りとか親が伴走しているご家庭が多いと思うんですが、私ももうママ塾がっつりやってたのと、長男は反抗期もなくて親子関係が良好だったので、入学後の最初の定期考査もしっかりめにコーチングしました。
「中学生にもなってママにお勉強の計画手伝ってもらうなんて、自主性が育たない」ですか??
「まず本人に任せてみて失敗から学ばせる」派ですか??
お子さんの性格とか相性とかもありますから、もうそこは各家庭に合ったやり方が一番ですので、それを否定する気は一切ありません!
あと、もう反抗期始まってたり、親子関係の雲行き怪しいなら辞めた方が良いですね。手出しすると逆効果の可能性大!
私はとにかく成功体験ファースト主義!
過保護で結構コケッコ~!
うちの子は先に成功体験積ませると、自信ついて調子に乗ってやる気出すという単純男子だったので、まずはまぐれだろうが、下駄だろうが、親の入れ知恵だろうが、成功体験を目指してコーチしました。
成功体験を得ると本人もやる気出るし、それによって次の取り掛かりも楽になるし、あとあとのことを考えても圧倒的に楽~!だってことは、中受の経験からもわかっていたので。
ちなみに中1入学直後の「成功体験」とは、「上位3割以内」を目標設定していました。
長男のe塾小6の成績はこんな感じなので、「上位3割以内」は高すぎず低すぎず実現可能な目標として妥当だったと思います。
↓
<実際にやった定期テストコーチング>
・普段の授業で理解しておいて、借金を作らないことが大前提
・ワーク類は溜めずに日頃からコツコツ進めているのが大前提
・定期考査の範囲表が配られたら一緒にチェック
・計画は細かく立てない。ToDo Doing Doneの3段階見える化のみ。
・課題は早めに手をつけさせて、定期考査1週間前に終わらせる
・直前1週間は学校のワークやプリントをしっかり復習して対策
・1問1答のワークやプリントは、オレンジペンで答えを書いて赤シートで音読するのを何周も回す
・理社や口頭試問に付き合ってあげる
私が長男に言っていたのは、「課題はあくまで自宅学習時間を最低保障するためのものに過ぎない。課題を終わらせることはテスト勉強ではない。課題を終わらせてからが、テスト勉強本番」ということです。
テスト勉強は学校の配布教材を基本にしましたが、演習のために市販問題集や参考書も取り入れていました。
改訂版になってました。
↓
「塾技は良かった!」と長男も気に入ってました。
↓
<音読最強>
「オレンジペンで答え書き込んで赤シートで何周も回す」はメモチェでさんざんやったことを、入学後もやってました。↓
「穴埋めの答えの部分だけ」を頭の中で考えるんじゃなくて、「プリントの文章、全部音読しながら穴埋めも答える」という音読勉強法が、単純ながら最強です。
コツはキーワードだけじゃなくて、文章ごと音読すると、記述問題も書けるようになります。英語・理科・社会・音楽などの副教科、あらゆる科目で効果を発揮します。
音読はすごく単純で単調ですが、目と口と耳を使うので効果絶大。
それなのに、音読はめんどくさがってやりたがらないのが普通。
でもそこを励まして、やらせて、点取らせて、効果実感させると自走モードに入ってあとが楽です。
テスト前日とかの仕上げで、口頭試問に付き合ってあげるとバッチリです。
こんな感じで、赤シート回しで知識や暗記をたたき込むと、理社は面白いように点が稼げるんですけど、「英数国がイマイチで理社で総合得点稼ぐ」のは禁じ手としてました。
とにかく英数を最優先としてました。
我が家の反省としては、入学後に英数ばかりに力を入れて、国語の手を抜いちゃったのが、じわじわボディブローのように効いてきて、中3の時点で定期考査でも模試でも国語が足ひっぱるようになっちゃいました。
読書習慣が切れちゃって、ボキャブラリーを育ててなかったのが大きな原因だと思っています。
なので、読書は楽しみながら習慣にすることは、老婆心ながらおすすめしたいですね。まあ忙しいんだけどね…。
<テスト勉強の計画>
勉強計画は、カレンダー式は計画立てるのもめんどくさいし、計画倒れになるのも目に見えていたので一度もやったことありません。
長男に合っていたのは、「ToDo Doing Done」のタスク見える化計画でした。
↓
うちはコピー用紙とかに、横に「英語 数学 国語 理科 社会」×縦に「ToDo Doing Done」みたいな枠を作ってやってました。
やるべき課題や勉強を付箋にあれこれ書いて、貼って、やった順からどんどん移動していく。
優先順位を考えながら、やりたい順に手をつけていって、付箋がどんどん移動していくのが気持ちいいです。
最初と最後で風景が変わって「こんなに勉強したんだ~!」って達成感あるので、単純男子には向いていました。
長くなったので続きます~。(でも続きは気長にお待ちください…)