土曜は大学オーケストラのコンサートのエキストラだった。
この大学のオーケストラは卒業生でも無いのに、毎年エキストラで参加して、もう25年は続いている。
純粋にトラで連続25年と言うのは、もしかしたら日本でも何番目かに入るのでは無いかと内心思ってる(笑)
既に上級生が生まれる前から弾いてるのだから長いったりゃありゃしない。。良く毎年呼んでくれてるもんだと感謝している。
僕の場合、何処にも所属して無いが、こうやって10年単位で呼んで貰っている弦楽合奏団が、あと2箇所程あり、これに、大きな曲の時に呼んでくれるオケが幾つかあるので、年に飽きない程度にはオケや室内楽で演奏できるが、積極的に合奏での演奏の場は求めていない。
一番の理由は合奏の時間が増えると耳が悪くなるからだ。
室内楽は1本だからそんな事は無いが、オーケストラの場合は6~8本のテュッティになるので、どうしても音程や音質がいい加減になる。
時々なら良いが、毎週となると「弾けてる様で弾けてない」と言う状態に自分で気が付かなくなる。
何年か前に南半球のオーケストラへ行った日本のトッププレーヤのレッスンを聴講していた時に、ある学生に「君の音は僕が聴く限りでは小さいと思うけど、音が小さい人は何故音が小さいと思う?」と質問していた。
確かに、その人が言う様に彼の音は小さいと僕も思っていた。
その学生は答えられなかったが、「音が小さいと思ってないから」と言うのが答えだった。
もっと言えば「耳が悪い(自分の音を聴いて小さいと思ってない)」と言う事だった。
確かに最もな話で、自分の音を客観的に聴くと言うのは難しいものだけど、自分の音を聴くのは重要だと再認識した一瞬だった。
それでも、音程や音量に関しては自分の耳やチューナを使えばフィードバック出来るが、右手の動きに関してはこれは中々自分で確認するのは難しい。
その為、僕は既に何十年と楽器を弾いていても「鏡」の前で練習するのは今でも怠らない。
練習してて何か変だな。とか、要求されているフレーズや自分のイメージするフレーズに対して上手く弓が扱えてない場合は右手に問題がある場合が殆どなので、必ず「鏡」でチェックする。
場合によっては正面からだけでなく横からとかもチェックする。
「鏡」ほど良い先生は居ないと思っているし、例えば、上手な人(先生)の弾いている姿をイメージした時に、自分の弾いている姿と比べて何が違うのかを観察して考える事は上手くなる秘訣だ。
(プロ)スポーツだと自分の動きをビデオでチェックすると言う事は良くあると思うが、演奏も身体を使うと言う点では全く一緒だ。
「人の振り見て我が振り直す」と言う諺があるが、「我が振りを見て我が振りを直す」のは大事だろう。
これは弦楽器だけでは無く管楽器も同じだと思う。
最近の(アマチュアの)学生さんの管楽器奏者を見ると、姿勢が悪い事が非常に気になる。
立ち上がりの音が美しくない。音の箱に余裕が無い。等。。
そう言う場合は、大抵姿勢に問題がある。
下を向いて自信無さ気に猫背になって横隔膜の動きが妨げられているんだから良い音が出る筈が無い。
少なくとも背筋を伸ばして上半身がきちんと腰に乗ってる状態で腹筋や肺が自由に使える状態を作っておかないと楽器のコントロール等は出来ないだろう。
勿論、弦楽器でも同様だ。
休憩時間はともかく、演奏している場合は同様な状態を作って、手先だけでは無く両肩から自由度が高い状態を作らないとフルボウイング等無理だ。
猫背でボソボソ弾いて許されるのは定年間際の名人だけだと思って良い。
例えば、腰(下半身)に力を入れろというのは色々な分野で言われる事だが、土台に力を入れて締める事で、他の箇所の力が抜けるものである。
右手の力を抜きたければ、下半身や腰(背中)等の他の箇所へ力を入れる事で、力が抜けるものである。
自然界にはエネルギー不変の法則と言うのがあるが、演奏も全く同じだ。
pppもfffもエネルギーの投入量は同じだ。
楽器で消費されているのか身体で消費されているのかの違いで、ppp程、身体で消費するエネルギーが多くなり、fffになる程身体で消費するエネルギーを少なくしなければならない。
pppで腕がプルプルして弓が跳ねるなんてのは、エネルギーを消費している身体の箇所が悪いからだ。
「姿勢が良い」と言うのはどんな世界でも通用するもので、一流の奏者や一流のバッター等、必要な箇所に力が入って(締まって)他はリラックスしているし、構えているだけでも上手さが滲み出るものだ。
新しい首相も立っているだけで「首相」と言う貫禄が出るようにして欲しいもんだ。
その為には、ちゃんと「我が振り」をもう一度確認して土台に力を入れる必要がある。
- イチロー思考―孤高を貫き、成功をつかむ77の工夫/東邦出版
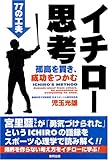
- ¥1,365
- Amazon.co.jp