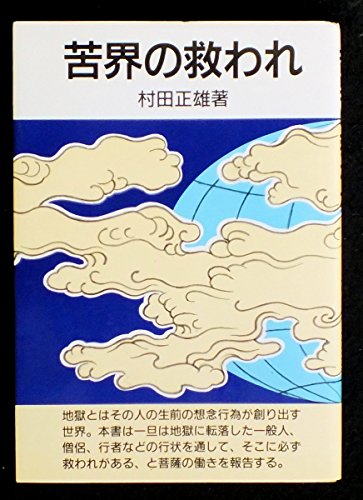久しぶりに投稿します。
前回は6月でしたから、3か月ぶりです。
この間に森美智代さん主宰のお盆の断食合宿があり、そこでいつものようにお話してきました。今日はそのときお話したことを書きたいと思います。
下、二つはその講話、冒頭で使ったスライドです。
写真のお二人は小説家の宇野千代さんとカー用品販売店チェーン、イエローハットの創業者鍵山秀三郎さんですが、最近知ったお二人の言葉に感銘を受けました。
宇野千代さんの言葉、「人間は 心の存在がすべてである 心が体を動かす 心が幸福を生む」は2か月前、旅先の山口県、岩国市のホテル駐車場にあった小さな碑に刻まれていたものです。うっかり写真を撮るのを忘れ、帰宅後、ホテルに電話し教えてもらいました。岩国は宇野千代さんの故郷。その縁でホテル駐車場にこの碑があったわけです。
宇野さんは中村天風師のお弟子さんで、「天風先生座談」という天風師の語り口のままに分かり易く天風思想をまとめられた著作がおありです。
イエローハットの鍵山さんの言葉は「経営問答塾」という氏の著作にありました。
この本は鍵山さんが経営者からの質問に答えられた「問答集」で、「社員教育はどうあるべきでしょう?」という問いに対して、「本当に頭の良い人とはいつも善いことを考えている人です。だからいつも善いことを考える社員にすることです」と答えられているのに強い印象を受けました。
イエローハットは長い間、競争相手のオートバックスに対して「弱小な二番店」のポジションにあり、一時は存続も危うい状態でしたが、いつのまにか両社のポジションは逆転、今では、株式時価総額でオートバックスを上回るようになっています。鍵山さんのこの言葉を見て、これが両社の逆転の遠因、真因でないか、とすら思わされました。
さて、宇野さんの言葉「人間は 心の存在がすべてである 心が体を動かす 心が幸福を生む」は宇野さんの師である天風師の思想のエッセンスのような言葉です。
鍵山さんの言葉「頭の良い人とはいつも善いことを考えている人」も同じように天風哲学のエッセンスと言えます。
天風師の教えは「思いがすべて。人生は思い通りになる。だから善いことのみ思え」ですが、そう聞いても素直に「その通り」と思える人は案外少ないのではないでしょうか。むしろ「人生は思い通りにいかないもの」と考える人が多いのかもしれません。しかし、現実には、この言葉のように「人生は思い通り」になっています。むしろこの世界は「思い」で出来ていると言ってよいくらいです。
そこで、今日は「人生は思い通りにいかないもの」と考えていらっしゃる方に、出来るだけ分かり易く「思い通りになっている」ことの説明をしてみたいと思います。
思いと願いは違う
まず。最初に言えることは「『思い』と『願い』は違う」ということです。
「思い」というのは折々に考える「願い」でなく、いつも心の底にあるもの、いわば「信念」の類です。「願い」も「信念化」すれば、その通りに現れますが、普通の人の「願い」は「あこがれ」のような浅いもの、または、その場かぎりのものであることが多いと思います。それでは「信念」とは何か、です。
天風師は信念とは何かについて下の「信念の奇跡」の中でこのようにお述べです。ちょっと長くなりますが、引用します。
皆さん、口じゃ「信念、信念」と言ってますよ。自分じゃそこまで深く考えてないから、頭から信念さえありゃなんとかなるだろうと思ってるような、あやふやな考え方だけなんです。英語で言うと「I believe with conviction」(確信をもって信じている)じゃなく、「I'm thinking so」(そう思います)なの。それじゃなにもならねぇがな。
思ってる、考えてるだけならば、誰だって思って考えてるよ。それはただ長生きをしたい、長生きができるだろうと「It‘s might be so」 (そうなるでしょうね)なんだもん。
こんな具合で、そうあるかもしれないってだけのことを信念だと思ってる人が多くないかい? これは本当の信念とはどんなものか、正しく理解していないからだと遠慮なく言うぜ。
私はありがたいことにインドでのヨガ修行を通じて信念の実際状態を知ることができたんだ。それまでは信念というものは積極的にがむしゃらに、事の成功なり、成就を強烈に心の中で考えりゃいいだけだと思ってたんです。ところが、信念の実際状態というものが、夜が明けるようにだんだんわかってきたら、信念でもないものを信念だと思い違いしていたことに気がついたんだ。
よーくお聞きなさいよ。信念というものは、ただ一心に積極的に、馬車馬的に、がむしゃらに、その事の成就なり、成功なり強烈に心の中に思念することじゃないんです。そういうのは強情っぱりと、言うんだよ。「そんなことしてできるか、おい、駄目だよ」って言われて、「大丈夫だよ俺は、できるという信念があるよ」。これじゃ、強情はってるだけなんだ。
いいかい。 本当の信念という階級の高い心は、精神科学的に言うと、否定や肯定から超越したものなんです。否定があったり、背定があっちゃいけないんだ。 否定や肯定という気持ちは相対的なもの。イエスとかノーとかを心の中で考えてるあいだは、その心は相対的なんです。その相対的な心境から超越した心境が絶対的な心境で、 それがすなわち信念なんです。
歌を聞かせてあげよう。そしたらわかるかもしれない。
「思はじと思ふ心は思ひなり。思はざりせば思はざるなり」
思わないでいようと思うのも思うことだ。思わなければ思わない。これを禅のほうでは、不思量底を思量せよという。
「座定して、この不思量底を思量せよ。不思量底如何が思量せん。非思量、此れすなわち坐禅の要術なり」(道元禅師「普勧座禅儀」)
不思量底をどうやって思量すればいいか。それは非思量、思いめぐらすことにとらわれない。すなわち「思う」と「思わない」の二項対立を捨て去ることだ、と言う。これが信念の実態、安定打座の精神であります。今年の夏、安定打座の精神を英語で言ったろ。
Listen to the soundless sound with your mental ears.
Put your mind out of the space and do not mind your senses.
Keep your mind still and clear in the soundless world.
心耳を澄まし、空の声聞く
心をば虚空の外に置き換えて
五感気にすな打坐の妙法
心を静かに澄ます、空の空
「大丈夫だ、できる」。これは信念じゃありません。思ってるだけだもん。信念のある人間は、事柄に対して、病にかかろうが、運命が悪かろうが、良くなるも良くならないも思ってませんよ。信念の中には、否定も肯定もないんだ。
それがパッとわかってからの私は、それはもう、なんとも言えない爽やかな気持ちになって、なにごとに対しても、たとえ自分がいつ死ぬかわからないような病にかかっても、ちっとも、そんなこと考えなくなっちゃった。もっとわかりやすく言うと、よく寝て、夢も見ないときと同じ気持ちになっちゃったんです。
それまでの私はね、心の中で自分の健康が回復しないというような否定的な気持ちがあった。また時によると、それを打ち消そうとする気持もあった。否定的な思いと「あ、これがいけねえんだ、悪くなりゃしないかってことは考えないようにして、治るほうへ心をもっていこう」とそれを打ち消す肯定的な思いが心の中でこんがらがってたんです。駄目ですよ、心の中で闘ってんだから、治らないのは当たり前なんだ。治らないような種を蒔いてたんだもん。
それがいま言ったような、なんにも考えなくなった、それが信念だというふうになってから、そりゃもう薄紙はがすなんていうのは嘘みたい、厚紙をはがすように良くなっちゃったんです。そのうえ、なんでもできるようになっちゃったんです。
多くの人は、潜在意識がもつ驚くべき力に蓋しちゃってるんだ。蓋して、それが出てこないから、「ない」と思う間違った考え方をしてるんです。
潜在意識という素晴らしいものの中に、生まれながら蓄えてもってきた潜在勢力というものがあるんだぜ。信念が絶対的なもの、 要するに、 肯定も否定もなくなるような心になると、潜在意識の中に生まれながら与えられた潜在勢力が出てくる。
どうだ、驚いたろ。これらが今後何千年か何百年かのちに、心を求める人の大きな教えになりゃしないかと思う。世に言う「心鏡払拭」とか「本然への復帰」とかってことは方法論に過ぎない。そんなことはせずとも、潜在意識の活動作用を妨害しさえしなかったらば、それでいいんだよ。それを心の鏡をしょっちゅう拭いてなきゃなんねえとか、本然に復帰しようとすると、その方法に心が囚われていると、また肯定や否定(=迷い)が働きだすんです。
「信念の奇跡」というものをもう少しわかりやすく言うぞ。よろしいか。潜在意識は、心のスクリーンの上に描かれた映像のとおりに、それを実現させる働きをもっている。それを優れた人でないと、そういうことができないと思ってるところに、非常な損失があるんだ。それには、自己暗示をしっかりしたものにするための想像の訓練をすることだ。
あなた方はねぇ、くだらねえことを想像することは、もう徹底的にやってますわ。怖ろしいこととか心配になることを想像するときには、はっきりと自分の心の中に描き出しているじゃねえか。重病にかかったり、なにか心配事にでくわすと、それを徹底的に破滅に陥ったときまでの映像を心の中に描いているだろう。これは無駄なことなんだ。これをいいほうにするんだ。
私なんかは楽しいことや嬉しいことを考えるときは、もうそれがそのまんま実際に目で見てると同じような状態で映像が出てくるぜ。考えてごらん。潜在意識という、もっとも安心のできて信頼性の高い凄まじい力が、あなた方の命の中にあるんだよ。
晴れ晴れしい、楽しいことだけを心に思わせることにして、もちろん雑念妄念を考えないでいると、今までと打って変わって、我ながら見違えるような自分がつくられるんです。
そうなると、本当に神秘的だと言いたいくらいな感化作用が即座にあらわれてくるんだぜ。長年医者にかかっても治らない病をもってた私が病を忘れて、病がぐんぐん良くなったんだ。それで今でも、九十すぎてこうやって講演してるじゃねぇか。
ただ死ぬときは死ぬんだ。死ぬことは決まってるんだから、考えなくたっていいだろうと、そういう悟りを開いたんだ。
とにかく、人生を生きがいのあるものにするには、想像力を応用して自分の念願宿願を絶え間なくはっきりと心に描くと同様に、自己暗示も絶え間なく、連続的に反復するんだよ。それにはもう、一番いい方法を教わっているだろ。(中略)
あなた方は「ああなりたい」「こうなりたい」「ああなってほしい」「こうなってほしい」ということを、のべつ心の中で、自分でも考えきれないほど朝から晩までしょっちゅう考えているだろ。ただ、「ああなりたい」「こうなりたい」じゃいけないんだよ。「ああなりたい」「こうなりたい」ことを、ひとつの現実の絵にして自分の心の中にはっきり描かなきゃいけないんだ。そうしてそれを絶え間なく、オリンピックの聖火のように、絶えず燃やし続けるんです。 (引用おわり)
どうでしょう。まだ難しいでしょうか。もう少し説明します。このお話で天風師は道元禅師の次の言葉を紹介されています。
「座定して、この不思量底を思量せよ。 不思量底如何が思量せん。非思量、此れすなわち坐禅の要術なり」
ここに「不思量底」とありますが、これが天風師のこのお話のキーワードです。
顕在意識と潜在意識、そして魂
私見ですが、この言葉には2つの意味があると思います。
一つは「思量の底」にある「不思量」の領域です。これは文字通り、ここで天風師がおっしゃっている「潜在意識」です。
意識には二種類、顕在意識と潜在意識があります。顕在意識は「脳」が考えている意識です。潜在意識は「心」が考えている意識です。
「脳」というのは肉体に付属するものですから、「顕在意識」はこの肉体が生まれてから現在に至る体験や記憶がベースとなって「思い、考えていること」です。
しかし、潜在意識とは肉体でなく「魂(たましい)」に存在する意識、思いです。
それについて、お盆の合宿ではユング心理学を本格的に日本に紹介された下の河合隼雄さんの言葉を紹介しました。
その言葉は以下の書籍の中にあります。
ユングはフロイトと並ぶ近代心理学の祖ですが、フロイトとは違い、難治の分裂症患者の治療に当たったことから、潜在意識とは肉体に宿る意識でなく、魂に宿る意識であると考えるようになりました。以下同著よりの転載です。
精神分析を創始したフロイトは無意識を問題にした。彼の理論は因果律的な決定論として展開された。彼はノイローゼの「原因」が個人の生活史のなかにあり、その原因をはっきりと意識することによって患者は癒されるとした。よって治療者はそのような原因を見出すための技法と理論を知っており、それによって患者の病いを癒すのである。
これに対して、ユングは彼が精神分裂病者の治療にあたることが多かったため、フロイトの考えに全面的には同調し難いと感じるようになった。何故なら、分裂病者に対して、その「原因」を過去の生活史に見出すことは困難であったからである。仮にそれらしきことは見出せても、それが決定的なものであるかどうかは疑わしかった。
ユングは分裂病者のような深い問題をもつ患者に接しているうちに、人間の「たましい (die Seele) 」ということを考えざるを得なくなった。彼は「たましい」は時間、と空間によって定位できないが、分裂病の多くの症状を個人の生活史や、何らかの物質的原因に還元して考えるのではなく、「たましい」のはたらきとして見る方が妥当ではないか、と考えるに至ったのだ。
ユングは「たましい」を宗教ではなく、あくまで心理学として研究しようとした。
すなわち彼は、固定した方法や理論、つまり儀式や教義を確定するのではなく、個々の場合に応じて現れる現象を観察、記録しようと試みたのである。(中略)
彼がたましいの現象について見出したもっとも大切なこととして、共時性 (syn-chronicity)を上げることが出来る。
それを端的に言えば、たましいの現象には因果律によって把握できぬものがあるということである。それは単なる「偶然」とは言えないものだった。それまでも「意味のある偶然の一致」と呼ばれ、そこに何らかの意味を考えさせられるような「偶然」は存在した。
それが起こる原因への考察が自身の研究と精神病治療に役立つのでないか、と考えるようになったユングは、まだ充分に考えのまとまらないまま、この考えのその一端をアインシュタインに話をした。
その時アインシュタインは、「それは極めて重要なことだから必ずその考えの発展を怠らないようにせよ」とアドバイスしたという。そして、このアドバイスがユングの背中を押した。(引用おわり)
潜在意識の存在は仏教では「末那識」や「阿頼耶識」という形で説かれていますが、これをフロイトやユングに始まる心理学では「潜在意識」として、その存在や働きを明らかにしてきました。しかし上の引用にあるようにフロイトは肉体に宿る「潜在意識」を考えたために、生まれてから今に至る間の「心理的抑圧」が、様々な精神疾患の原因であると考えたわけです。
河合さんの説明にもあるようにユングもそれを全否定はしませんでしたが、それでは説明がつかないことがあまりに多くあり、肉体だけでなく、「魂」の領域に踏み込まざるをえなくなったわけです。ちなみに上の文中にある不思議な偶然の一致、「共時性」をユングは深いところで他者と繋がっている「魂」の働きであると考えました。
霊・魂・魄
「霊(れい)・魂(こん)・魄(ぱく)」という言葉がありますが、「魂(たましい)」の世界とは「霊」「魂」の世界です。「霊」とは「魂」のさらに奥にあるものですが、普通「魂」というときにはこの二つをまとめ「霊魂」を意味します。そしてこの霊魂は「死」によって消滅することなく、永遠に存在し続けます。こう考えるとき、この世で起こる理不尽なことに合理的な説明がつくことになります。すべては原因、結果の因果律で説明ができるからです。(ちなみに魄(ぱく)が肉体です。)
「どのように説明できるか」については以下のブログに書きました。ご興味あれば一読ください。
話を天風師のお話に戻します。先の「信念の奇跡」からの引用で天風師がおっしゃっているのは「『顕在意識』で思っているだけではダメだ」ということです。望ましい現実を実現したいなら「潜在意識にその思いを浸透させ、埋め込まねばならない」。これが、天風師がここでおっしゃっていることです。
潜在意識には潜在勢力があり、これが現実を創造しているのだから、「潜在勢力を活用せよ」とおしゃっているのです。
その活用法として、天風師は「想像力を応用して自分の念願宿願を絶え間なくはっきりと心に描くと同様に、自己暗示も絶え間なく、連続的に反復せよ」、さらに「『ああなりたい』『こうなりたい』ことを、ひとつの現実の絵にして自分の心の中にはっきり描かなきゃいけないんだ。そうしてそれを絶え間なく、オリンピックの聖火のように、絶えず燃やし続けよ」とお述べです。
これを天風哲学では「観念要素の更改法」と呼びます。「観念要素」とは潜在意識に染み付いている「観念=思い」で、これを転換(更改)することが「運命を拓く」ことになる、というのが天風哲学の要諦です。
そして奥に潜んでいるこの潜在意識は、現れである顕在意識に常に大きな影響を与えています。
天風師は江戸時代の禅僧、沢庵の「心こそ、心迷わす、心なれ、心に心、心許すな」という言葉をたびたび口になさっていますが、これは心の統御、コントロールが如何に難事中の難事であるかを説いた言葉です。
要は、「いくら良いことだけを考えよう」と思っても、それを否定するようなマイナスの思いが雲霞(うんか)の如く湧き上がってくるのです。よって顕在意識の力で「心」を統御するのは容易でない、ということです。顕在意識が潜在意識の強い影響下にあるからです。心とは暴れ馬のようなものだ、ということを沢庵の言葉は示しています。
よって天風師の教えは頭ではわかっても、普通の人(私もそうです)になかなか実行できるものではありません。
天風師の教えは暴れ馬をある程度乗りこなせる上級者=上根の人向けの教えだと思います。
師の「観念要素の更改法」は天風師が先の講話であげた禅宗のような自力行です。自力であるがゆえに一定の「力量」が求められます。
それは自身「天風哲学の大学院」と呼ばれた「神人冥合法(しんじんみょうごうほう)=安定打座法(あんじょうだざほう)」にも言えます。
「座定して、この不思量底を思量せよ。不思量底如何が思量せん。非思量、此れすなわち坐禅の要術なり」の「不思量底」とは「潜在意識」である、というのが先に述べたことですが、もう一つは文字通り「非思量」、要はモノを思わない状態、禅でいうところの「空」の状態になることを指していると思います。これは潜在意識を超えたその奥の領域の話です。先の「霊・魂・魄」で言えば「魂」を超えた「霊」の世界の領域です。しかし、ここに至る空観の難しさはちょっと座禅のマネごとをしたことのある人はわかるでしょう。
この難しい「空」の状態を初心者が易しく体験できるのが天風師の「安定座打法」で、そのYoutubeがありましたので、以下に貼り付けます。座禅のような姿勢でブザーの音に耳を澄ませます。突然ブザーの音が止み、静寂が現れます。その静寂に意識をゆだねると一瞬の「空」を体験できる、というものです。
なお、天風師は「神人冥合法、安定打座法」を「盛大なる人生」にご自身の体験通じて述べておられます。これは私の過去のブログでもこれについて紹介していますので、そのうちの2つを以下に貼り付けておきます。ご興味があればこれらも一読ください。
私がここで言いたいことは、「観念要素の更改法」も「安定打座法」も本当に素晴らしいのですが、暴れ馬である「心」をある程度乗りこなせる「上根」の人向けの自力行で、私もそうですが、普通の人「下根、中根」の衆生にとってはそう容易いものではない、ということです。
さて長くなっていますので、そろそろ今日お伝えしたいことの結論を書きます。私は毎朝の習慣として、五井先生の会の古い会報を少しづつ拝読しているのですが、今朝読んだ昭和44年の会報にちょうどお伝えしたいことが掲載されていました。
会の長老で優れた霊能者でいらした村田正雄先生の「苦界の救われ」の連載からの一文です。
今朝読んだのは前号の続き、ある大きな仏教宗派の管長であった方の死後の世界がどのようなものであるか、について書かれたものです。以下はその一文よりの引用です。(以下転載)
人々がこの世で生活をなしつづけてゆく上に地位や名誉やその他いろいろな肩書等があって、それがその人の社会的地位の高さや働きの場を表わしている場合が多いものであります。こうした地位や名誉が霊界に移行した場合、どのようになるものだろうか、とお考えになる方もあろうと思われます。たとえばこの世での地位も高く、お金持ちで恵れた人は霊界ではやっぱりそのような、豊かで高位におられるのだろうか?
およそ霊界は、心のままが姿や形となって現われ出る世界なのであります。いかにこの世での地位や名誉が高かろうと、その地位にふさわしい愛行や善行が踏みおこなわれていたかいないかによって決定されるもので、常日頃の心のままの世界にと移行するものであります。
五井先生は現世の現われは過去世のものが80%であるとおっしゃっておられます。そして過去世で積まれた徳不徳の現われが現世での幸不幸、病気災難となって現われては消え去ろうとするもの、と教えられております。
心、心こそ、否、心の在り方こそ一番大切なものであります。世界平和の祈りはこうした心の在り方を、最高上位にと移してくれるものであります。そして心の在り方がその人の言行となってひとりでに現われてくるものであります。人はみな心のままに行い、現わしてゆくものなのです。(転載おわり)
この後、その管長さんの死後の世界が描かれるのですが、この連載はのちに書籍化されるので、ご興味があれば以下をご覧ください。
さて、ここで村田先生は五井先生の「現世の現れは過去世のものが80%である」というお言葉を紹介されていますが、五井先生はこれについて「現世に現れていることで顕在意識の反映であるのは20%どころか5%にも満たない」ともおっしゃり、「95%は過去世の反映、現れである」とまでおっしゃっています。
五井先生はこのようにお話です。
今、意識、想念するのは、過去の想念である潜んでいる潜在意識が、ある機縁で思い出され、表面に浮び上がり、顕在意識、現実となって現れるのです。顕在意識だけで意識、想念することは出来ません。
ですから、現在三十歳の人なら、誕生して三十年間の間の想念行為体験が、想念の奥にひそんでいます。もっと深くいえば、三十年プラス過去世の体験が、顕在意識の奥に積み重なって潜んでいます。表面に顕われているこころは、ほんの僅かで、潜んでいるこころは、その何億倍も、何兆倍もどれだけの積み重ねであるかわからぬ程に、積み重なって、潜んでいるのです。
人間の魂は永遠に存在しますから、何百年、何千年、またはそれ以上の想念行為が魂に積み重なり、染み込んでいます。その現れが「現在の人生」ですから、実は私たちの人生とは「過去」が写っている「人生」なのです。
それは夜空を見上げて星々を見ているのと同じです。澄んだ夜空を見上げればたくさんの星々を見ることができます。しかし私たちが見ているのは星々の「現在の姿」ではありません。一番近い恒星でも4.2光年の距離にあります。一番遠い恒星は確認されているもので、280億光年のかなたにあります。夜空を見上げるときに我々が見ているのはすべて「過去の姿」です。
おなじように私たちが現世で経験しているのも大半は過去の現れです。今の思い、行為で創造できるものもありますが、それはほんのわずかです。
では、どうしようないのかですが、これについて村田先生は先の一文で以下のようにお述べです。
五井先生は、過去世で積まれた徳不徳の現われが現世での幸不幸、病気災難となって現われては消え去ろうとするもの、と教えられております。各自の過去世よりふんで来た道は、今はどうにもなりません。それで一番大切なことは、善くても悪くても、今の自分では及ばない世界のことであって、一切を消えてゆく姿と観じ切ったところから、新しき未来の世界が、輝くような素晴しき世界が生まれるのである、と心に定めることであります。そこに人の救われがあるのではないでしょうか。
お盆の合宿では、冒頭書いた宇野千代さんの言葉「人間は心の存在がすべてである 心が体を動かす 心が幸福を生む」とイエローハットの鍵山さんの言「本当に頭の良い人とは、善いことをいつも考える人」という言葉を紹介しました。
同じことを先の一文の中で村田先生はこう仰せです。再掲します。
心、心こそ、否、心の在り方こそ一番大切なものであります。世界平和の祈りはこうした心の在り方を、最高上位にと移してくれるものであります。そして心の在り方がその人の言行となってひとりでに現われてくるものであります。人はみな心のままに行い、現わしてゆくものなのです。
最高に善いこと、善い思いとは「世界人類が平和でありますように」という五井先生の提唱された祈り言葉です。これを日常の祈りとして習慣化すれば、知らず知らずのうちに、高い境涯に昇ってゆき、幸せな人生に中にいることに気付くようになります。
これは自力行でなく、守護の神霊にお任せする他力行で、私のような下根、中根のものにとっても実行可能な「易行道」です。
私は、若いころから様々な教えに学んできましたが、この五井先生の教えに出会い、ようやく心、魂の安寧を得ることが出来ました。
合宿でもお話ししましたが、五井先生を教えてくださったのは恩師、甲田光雄先生です。私は、甲田先生から教えて頂いた「西式健康法」によって身体を、「五井先生の教え」によって魂を救われました。甲田先生にそことをお伝えしたとき、先生は本当にうれしそうに破顔一笑なさいました。これは忘れがたい私の一番の思い出の一つです。甲田先生も晩年のご著書で「五井先生によって救われた」と何度も仰せでした。
以下はこのブログでも何度か紹介した甲田先生がお亡くなりになる3か月前に頂戴した御遺筆で、今は森さんのご自宅兼合宿所の「あわあわ」にあります。
これも何度も紹介していますが、世界平和の祈りの行い方については過去のブログに書きました。ここまで読まれて、やってみようと思う方がいらっしゃったら、以下のブログを一読ください。
以上、長文になったので、ここで本稿を閉じます。
今日のブログが読者の皆さんのお役に立つものであれば幸いです。
世界人類が平和でありますように