ところが今は違います。どの日を休日の学校公開にするのか、各学校で決めろというのですから、当然学校のある日がバラバラになります。その結果、日程調整に苦労させられるはめになったのは、小学生スポーツ団体だけではないはずです。教員の自主的な研究団体にも影響がでているはずです。
この記事は、現場の教員である私が言うべきことではないのは百も承知で、あえて書いています。公ではなく個人の立場として、この統一感のない教育行政は良いとは思えません。土日曜日の授業をしないといけないのならば、第何土日を授業とせよと統一すべきです。どこかの行政区が“はじめの一歩”を踏み出してくれないかと期待をしています。
さて、話題を前向きに変えましょう。
ミカサ杯予選の組み合わせは、辰巳ジャンプのサイトにアップしました。こちらでもリンクしておきます。
「平成23年度ミカサ杯教育大会・東京第3支部江東中央ブロック予選」
辰巳ジャンプは、いよいよ6年ぶりの都大会出場を目標に出発します。何が何でも勝ちます。そして晴れの大舞台で、思い切りバレーボールを楽しみましょう。
昨日は会議の後、指導者有志で忘年会を行いました。
その中で、支部長と「夢実現方法」の話題になりました。支部長曰く、「テレビ寺子屋」を見ていたら、夢実現の方法について講師が語っていたとのこと。その内容は私がこれまでの3年間に研究してきたことの一部でした。そこで、良い機会ですからこのブログでまとめておこうと思いました。
(1)夢は心に秘めたら実現しない。自分の夢がひらめいた途端に誰かに語ること。知恵を逃がさないため紙に書き留めること。
(2)これまでの自分自身を振り返り、自分史をまとめ、客観視する。
(3)未来の大きな目標(夢)をできるだけ「ビジュアル化」「イメージ化」する。
(4)イメージした目標を言葉に書き直す。(言語化する)
(5)言語化の際、文章は現在系で肯定的に書く。
(6)紙に書いた目標(夢)を目に付くところに貼っておく。
(7)未来の目標を達成するために何をしたら良いのか、1年ごとに逆算して考える。(逆思考という。)
(8)さらに細かくスモールステップで計画を立てる。
(9)その目標(夢)が達成されたら、誰が喜ぶのか、“何のため”にそれをやるのか明らかにする。
(10)心に定まった目標(夢)を100人の人に語って聞かせる。
ここまでやると「夢実現脳」が活性化します。また自分だけでなく周りの環境(人的環境・社会的環境・自然的環境)が動き出します。
今回は細かい説明は抜きにして、エッセンスだけを書いてみました。詳しく知りたい方は、勇気を出して私に話しかけてみてください。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
このドリルで指導することができるようになると、子どもたちが作文を書くのが楽になります。マインドマップのかき方については、学校や団体として私を講師に呼んで下されば、2時間ほどでお伝えさせていただきます。
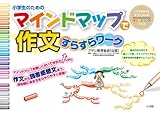 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |