「どういった設定をすれば子どもたちの声が出るか」という実験です。
現状分析として、うちの子どもたちはバレーボール経験が浅いことと、元来がおとなしい性格なこともあって、ここぞという時に声が出なくなる傾向にあります。対人パスをやっている時も、けっこう声は出ているのですが、私が求めているボリュームではありません。
そこでひと工夫。
「今日は変わった練習をするよ。“しりとり”をしながら対人パスをやってごらん。」
子どもたちは目を戸惑いながらも目を輝かす。さっそく始めたパス練習は大騒ぎになりました。何しろ20人近い子がいっせいにしりとりを始めたので、相手が何を言ったのか聞こえない。聞こえないから大きな声を出す。目いっぱいのボリュームで声を出しながら練習するので、体育館内は本当ににぎやかになりました。
対人パスが半分終わったところで、
「今度はマジカルバナナでやるよ。バナナといったら黄色、黄色といったらレモン、レモンといったらすっぱい、すっぱいといったらお酢、という感じに言葉の連想をしながらのパス練習です。」
結果は同じように大騒ぎ。しかも意味のある言葉を相手に伝えよう、相手の言葉を聞き取ろうとしているので、しっかりコミュニケーションも取れている。
最後に、
「いつも通りにパス練習してみて。」
と指示を出しましたが、それまでに大きな声を出してきたので、もちろん普通にやっても元気いっぱいな声だしをすることができていました。
私たち指導者は、どうしても直接的な指示を出しがちです。声を出させたい時に、次のような言葉を投げかけます。
「もっと声を出せ!」
「どうして声を出さないんだ!」
「声を出さないと危ないぞ」
「ピンチになったら声を出せ!」
「元気にプレーしろ!」
すべて直接的な声かけです。これをくり返すと、子どもたちの自尊感情を下げていきます。ますます声が出なくなる。そうすると「どうしてうちの子どもたちは声が出ないんだろう」と指導者が嘆きだします。指導者の思いは無意識の領域で敏感に子どもたちに伝わりますので、子どもたちの姿は指導者が話している、または思っている通りになっていきます。「ピグマリオン効果」ともいわれる働きです。(ピグマリオン効果は心理学的に完全に実証されているものではなく、多くの人の経験から、その通りだと納得されているものです。)
TOSSの向山先生が1980年代から主張している教育技術に「子どもに○○させたかったら、△△させる。」という法則があります。直接的な指示はあまり効果がないばかりか、指導者と子どもたちの関係をぎくしゃくさせます。ここに紹介した指導法則をじょうずに使うことができれば、子どもたちは指導者が期待している以上に声を出してくれるようになるでしょう。
この件で悩んでいる方は、ぜひ使ってみて下さい。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
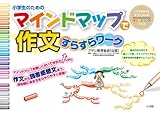 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |