今の私の立場としては、勤務校の教員を全力で育成する使命があると自覚しています。なので、今日の研究授業に至るまでに、よりレベルの高い研究にするために指導・助言をしてきました。
研究授業は、光村図書の国語教科書の中に新しく取り入れられた「百年後のふるさとを守る」を中心教材にして行われました。しかし、研究授業前日の授業に入って参観し、ちょっとまずい感じだなと・・・・・「このままの指導方法で授業が進むと、浜口儀兵衛の生き方を通して自分の生き方を考えるという“ねらい”を達成できなくなる」と判断し、緊急アドバイスをしました。
①この教材は、浜口儀兵衛の考え方や生き方を学び、自分なりの考えを持つためには、「自分ならどうするだろうか?」「自分の生き方に役立つことはないだろうか?」という「読みの視点」を持っていることが必要。
②昨年度に研究したのは「物語文の読解」だった。その学習方法を「伝記文」に同じように使うのは無理がある。
③この授業のねらいは「自分と浜口儀兵衛との生き方に相違に気づき、自分もより良い生き方をしようと考える」ことができたかどうかということである。
④児童の学び合いを最大限に引き出すためには、勇気をもって昨年の研究で行った「授業モデル」を変更することも大事である。
学年担任も、どうも授業がうまくいかない、このやり方で指導していると時間が足りないと悩んでいましたので、昼休み中にA4版2枚のアドバイスレポートを作成し、放課後相談に乗りました。
アドバイスのポイントは「焦点化」と「スリム化」でした。
①焦点化
なんでもかんでも考えて良いとしてしまうと児童の思考が散漫になる。
授業もどんな意見を取り上げていったらよいのかブレまくる。
だから今回は、「儀兵衛の考え方と行動」と「自分基準(自分ならどうするだろうか)」を比較することに思考を絞り込んで授業すべきである。
②スリム化
どんなにたくさんのことを教えようと頑張っても、授業は45分間しかない。必要最小限の指導内容に絞り込んで、確実に子どもたちの思考を拾っていく授業をする必要がある。1時間の授業で欲張り過ぎると、ねらいを達成できなくなる。
この他、私からの様々なアドバイスを受けて、担当学年の先生たちは、夜の9時すぎまで授業内容の検討をしてくださったそうです。その努力の結果、研究授業当日(アドバイスの翌日)の授業はだれが見ても素晴らしい内容となりました。
子どもたちの思考が「浜口儀兵衛の行動についてどう思うか」に焦点化されたことによって、ワークシートへの意見書き込みもたくさん行われ、その後の学習交流も非常に活発な意見交換が行われました。
研究授業、研究協議会の後、担任の先生たちは私のところに来てくれて、こんなことを言ってくれました。
「昨日の授業をした時には、全然うまくいかなくって、終わった時に『井上先生、助けて!』という気持ちでした。放課後、先生からアドバイスされたことをもとに必死に考えて、授業を変えることができました。そして今日の授業では子どもたちがどんどん意見交換してくれたので、私は感動しました。」
私からはこんな言葉を、若手の先生の心に刻まれるようにという思いで、残させていただきました。
「今日の授業には、授業の神様が降臨したんだよ。降りてきたね!本当に。こういう授業ってあるんだよ。教師の力を超えた何かが起こる授業だ。神様が降りてくるためには、教師の努力があればこそなんだけどね。良い経験を積みましたね。」
お隣のクラスのベテランの先生からも、こんな言葉をいただきました。
「今回の研究授業は、私たちが本当に勉強になりました。そして授業のことを勉強することが大変なことではなくて、大変なんだけど楽しいことなんだと感じました。こんな研究を続けていきたいですね。」
その通りなんです。私たち教師は「授業のプロ」です。プロというのはその道の楽しみ方を一番知っている人の事を言うのだと思います。今回の研究授業にかかわらせていただくことで、「授業研究は楽しい!」と思ってもらえたことだけでも、私にとっては大きな成功だったと感じます。
世界中の先生方の「授業力向上」のために、今日もまた、明日もまた、自分なりに行動していく決意です。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
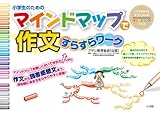 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |