我が区の場合、教育委員会からひな形や参考事例などの資料がいっさい出ませんので、どの学校の教務主任も非常に頭を悩ませて作成に当たっているのが現状です。本校も多分にもれず、昨年度までは業者から出されている年間指導計画に少し修正を加えて教育委員会に提出していました。その厚さは国語辞典2冊分くらいあるほどで、そんなものを校内に全員配布しても邪魔なだけ。だからデジタルデータのみ校務LANに保存してあります。
しかし、今年度は「先生方が使えるものを作る」と一念発起して、全教科を作り直しました。一人で作ったものなので完璧なものではなく、早くも修正をしないといけない部分を何人かの先生にご指摘頂いています。ぜひ日常的に活用していただき、直した方が良いところに赤を入れておいて下さい。来年の2~3月には、先生方に担当教科の年間指導計画・評価計画を作り直していただくことになります。みんなの目で見て、本校の実態により合ったものを作って下さい。
さて、この年間指導計画の中には「評価規準」も並列しておきました。本来は毎時間の評価規準が必要なのですが、それをやると先述の通り、辞書のようなものになってしまいますので、単元の評価規準を載せる程度にしてあります。この「評価規準」の考え方を確認させて下さい。
「評価規準」・・・・・井上が授業の中で意識していること
毎時間の授業の中で、児童に達成させたい「ねらい」にそって、どのような状態になれば達成されるのかを定めたのが評価規準となります。ですから、通知表をつけるための「基準」ではなく、我々教師がどのような授業をするかどうかを判断するための「規準」となります。
例えば、国語の授業で「筆者の考えに対する自分の考えをもち、友達と交流して確かめ合っている。」という評価規準を教師が持っていれば、当然、学習シートブックに自分の考えを書き、その後、意見交換をすることができていればねらいを達成できていると判断します。逆にそれが難しい児童がいれば適切な支援を与えていく。次の授業に入る前に、少しでも授業の評価規準に近づけるように、いっしょに課題を乗り越えていく。学級全体として評価規準を達成できていないようであれば、授業の方法を大きく修正する必要もあるでしょう。
このように、私たちの授業を見直していくために「評価規準」があると考えても良いと考えられます。
「先生は、こども達をどのように判断して指導しているのですか?」という質問に対する説明も評価規準を把握していることで責任を果たすことができると思います。
ちなみに、ウィキペディアの記事を転載させていただきます。
到達度評価をするにあたって設定した到達目標(=観点・内容)を評価規準といい、到達目標に対してどの程度到達できたかを判断する指標(=目安)を評価基準という。どちらも「ひょうかきじゅん」と読むが、意味は明確に異なるので注意が必要である。
言葉を区別するために、規準を「のりじゅん」、基準を「もとじゅん」と読むことがある。
例えば「鉄棒の練習」を評価する場合、
・逆上がりができるようになる
が評価規準、
•補助板を使わずに逆上がりができた
•補助板を使って逆上がりができた
•補助板を使っても逆上がりができなかった
が評価基準である。
評価規準や評価基準を明確にすることで、評価方法が明確になり、また生徒に評価を返す際にも、生徒自身で自分がどこまで達成できているのかを確認することができるという利点がある。一方で、評価規準や評価基準の設定や判断は教師によるところが大きい。異なる2人の教師が同じ学習場面で同様の指導することを想定した場合、一方は全員が達成できることをねらった評価規準を設定し全員が達成できた、もう一方は7割程度の生徒が達成できるような評価規準を設定し、およそ半分の生徒が達成できなかった、というような状況は十分起こりうる。そのため教師には、評価規準・評価基準の設定方法や、評価の精度についての研修が求められている。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
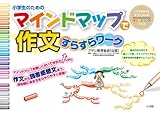 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |