私(井上)が12月に一般公開の研究授業を行います。
(主催)
江東区小学校教育研究会・情報教育部
(日時)
12月2日(水)
公開授業 13:45~14:30
研究協議会 14:45~16:30
(会場)
江東区立香取小学校
東京都江東区亀戸4-26-22
(研究テーマ)
「情報を適切に活用できる児童の育成」
~新学習指導要領の『思考力』『判断力』『表現力』を伸ばすために~
(学年・教科)
6年・国語(教材文は宮沢賢治の「やまなし」の予定)
(研究概要)
江東区小学校教育研究会・情報教育部の研究授業として行います。
江東区情報教育部では昨年度までの2年間、全国に先駆けて江東区が全校に3台ずつ配置した「電子黒板セット」の活用を推進するための授業を公開してきました。ICT機器である「電子黒板」を教師や児童がどのように活用するか、その可能性を追求してきました。この2年間の「電子黒板活用推進授業」の成果は、各校で活用される先生がどんどん増えたことで一応の役割を果たしたとしました。
そこで、今年からは電子黒板やICT機器という機械面にとらわれることなく、広い意味での「情報」というテーマに焦点を当てることにしました。
7月、香取小学校で行った授業では、「サウンドスケープ=音さがしの授業」で耳から感じる情報をつかみ、言葉で表現していくということを、マインドマップに表現することで試みました。
(授業者はトニー・ブザン公認マインドマップ(R)研修フェロー第4期の花井教諭でした。)
→この時の授業の様子はこちらの記事です。
9月の実技研修会では私が講師となり、様々な思考法の中から「マンダラート」と「速射マインドマップ」について研修しました。
10月7日(水)、第三砂町小学校で行われる研究授業では1年生の「音楽」を行います。タンタンタン♪というリズムやタタタタタンというリズムを、日本語に合わせて表現することで、「音情報」に関する耕しを行います。
(なお、授業を行うのはトニー・ブザン公認マインドマップ(R)フェロー第3期の山崎教諭です。この授業も一般公開されます。)
11月4日(水)、第一亀戸小学校で行われる研究授業も1年生の「音楽」で行います。授業内容は現在調整中ですが、授業者からの、
「サウンドスケープという考え方を何とか応用できないものか研究してみたいんですが。」
という言葉を受けて、私が「サウンドスケープ」について学び始めたわけです。
(授業を行うのは、マインドマップ(R)認定コーチの森川教諭です。)
この3回の授業の流れを受けて、12月2日(水)に私が研究授業を行います。
今のところ、
「サウンドスケープ」+「マインドマップ」+「学び合い」=○○○???
でチャレンジするという何が飛び出すか分からない玉手箱状態ですが、10月末までには何とか形にして、再度アナウンスをするつもりです。
1月13日(水)には、数矢小学校の4年生総合的な学習で「二分の一成人式」に向けての取材活動やアイデア作り、プレゼンテーション作成などの準備作業場面を研究授業で公開します。もしかしたら「マンダラート」を活用してアイデア作りをするかもしれません。
【参考文献】
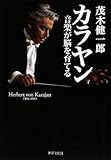 | カラヤン Herbert von Karajan ―音楽が脳を育てる (CD付き:茂木健一郎選曲 脳を育てる名曲11曲58分) 茂木 健一郎(もぎ けんいちろう) 世界文化社 このアイテムの詳細を見る |
 | 音さがしの本 ≪増補版≫ リトル・サウンド・エデュケーション R.マリー シェーファー,今田 匡彦 春秋社 このアイテムの詳細を見る |
 | 世界の調律 サウンドスケープとはなにか (平凡社ライブラリー) R.マリー・シェーファー 平凡社 このアイテムの詳細を見る |
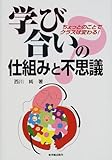 | 学び合いの仕組みと不思議―ちょっとのことでクラスは変わる 西川 純 東洋館出版社 このアイテムの詳細を見る |