『怪談話がうまい教師の学級は荒れない!』
その理由を説明します。
怪談話というのは完全な架空の話です。架空ということは、全く実態のない情報空間だけの世界に臨場感を持たせる話になります。話がうまければうまいほど臨場感が高まり、子どもの脳にはイメージが広がっていきます。
また、怪談話をしている時には不思議とカーテンを閉めたくなり、暗い空間の中に入っていきます。この空間は光や視界を遮断し、聞こえてくる語り手の声や周囲の音に対して非常に敏感な状態になっていきます。この暗い部屋の中で、これから起こるであろう怖い体験に向けて、子ども達の期待感や不安感は否応なしに高まり、神経が敏感になっていきます。
こうして、居もしないお化けや霊の存在に真実味が増していきます。
子ども達は、この「霊界」という非現実的な世界をぜひとも見たいと思っているのですが、それがなかなか手に入らない、見ることができない「プライミング」という状態になります。
心の中では耳から聞こえてくる情報を頼りにし、「怖い」という意識を高めていきます。人によっては「聞きたくない」と耳に手を当てたり、泣き出すことでその場からの逃避をはかる子も現れます。
楽しみにしている子は何を期待しているのかというと、ドキドキ感、ワクワク感、スリルたっぷりの一時を味わえることなどに期待しているのでしょう。
これによって教室内に起こることを説明します。
怖い話をみんなで聞いているという状況から、情報空間・物理空間・心理空間・精神空間を「共有」している状態が生まれ、非常に臨場感の高い状態になります。これをとても簡単に作り出すことができるのが怪談話です。
雰囲気を作り出した後で語り手が話し出すわけですから、聞き手は語り手に「同調」してしまう現象が起きてきます。不安や恐怖の中で語り手に対する依頼心は極めて高くなることでしょう。
そして、最後にクライマックス。
ほとんどの怪談話の語り手は、聞き手を驚かすという行動に出ます。聞き手は語り手の思うがままに恐怖のどん底に陥れられます。これによって、語り手は教室空間を完全に支配し、思うがままに動かしていける力を持つことになります。
こうして、怪談話を上手に語れる教師は、「ハイパーラポール」という強烈な信頼関係を生み出す力を持っているのではないか。そんなことを考えてみました。
【お薦めの本】
学校の怪談も怖いのですが、それ以上に小泉八雲(ラフカディオ・ハン)が書いたこの話も怖いです。一度は読んでみる価値、あると思います!
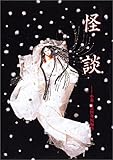 | 怪談―小泉八雲怪奇短編集 (偕成社文庫) 小泉 八雲 偕成社 このアイテムの詳細を見る |
blogramランキング参加中!