元寇について指導しました。
まず始めにさっさとマインドマップを板書して、ブランクブランチ(空いている枝)を埋めていきながら、元寇について全員が理解することをゴールにしました。
(板書したマインドマップ)

あとは、
「分からなかったらどんどん教え合いなさい。」
「立ち歩いてもかまわないんですよ。」
「全員が説明できるようにするんですよ。」
「自分だけできたんじゃ目標達成じゃないんだよ。」
ということをたま~に伝える。
そして、最後に学習したことをもとにして、ブランチを空けてあったマインドマップを埋めるような形で意見を次々に出してもらって授業終了。

子ども達のノートにも、それぞれ足りなかった内容を書き足してもれなく元寇を理解した1時間となりました。
「学び合い」の授業観の中で重要な要素は、「傍観者を作らない」ということです。通常の学習スタイルで授業を進めると、子どもによって学習状況が次のように分かれていきます。
「課題解決者」・・・5割
「モニター」・・・・4割
「傍観者」・・・・・1割
「課題解決者」とは自ら積極的に学習を進める者。ところが理科の実験を例にあげると、グループの中で、この課題解決者だけが学習をしていて、「モニター」はやりたくても手を出せずに見ているだけ。「傍観者」に至っては、関心も持てずにただいるだけの子です。
これによって、主に課題解決者だけが学習を達成し、傍観者は授業が苦痛なだけになります。
この子ども同士の人間関係は、成績優秀な子ばかりを集めた進学校でも同様な割合で出現するというデータがあるそうです。能力の差ではなく、これまでの教育(授業)で私たち教える側が持っていた授業観・子ども観によって、「課題解決者」「モニター」「傍観者」という役割を生み出さざるを得ない状況だったというわけです。
「学び合い」の授業観・子ども観によって、この無意識の役割認識を打ち破ることはできます。そして学級の全員が一致協力してお互いの学力を向上させていくという相乗効果も生まれます。
マインドマップは子どもたちの思考を“楽に楽しく”させてくれる道具ですから、これだけでも子どもたちは集中して授業に取り組みます。
良いものを二つ使うことで、お互いの良さを相殺させないようにしないといけないのですが、舵取りを上手にやれば、2倍ではなく何十倍の授業効果が現れてくることでしょう。
私的には12月に予定している江東区の研究授業に、ここ数年間に学んできた授業方法を集約していくつもりで進んでいきます。
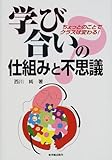 | 学び合いの仕組みと不思議―ちょっとのことでクラスは変わる 西川 純 東洋館出版社 このアイテムの詳細を見る |
blogramランキング参加中!