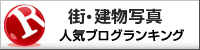昨日の続きです。
今回は椿坂から天守前です。
椿坂です。
坂の上に太鼓門跡下図⑦の枡形
があります。
太鼓門の内側を黄色く塗りました。
黄色い部分が帯曲輪です。
本丸とは仕切り石垣で区切られ
ています。本丸に入るには表門
(鉄門)か、上図⑩付近にある
裏門を通る必要があります。
解説板です。
太鼓門は渡り櫓で、石垣の上には
多聞櫓(長屋)がありました。
太鼓門枡形内です。
石垣の上には多聞櫓がありました。
右に曲がると太鼓門でしたが、今
は門がありません。
枡形を出て帯曲輪内から太鼓門
跡を見ると
太鼓櫓跡です。
もう少し離れてみると
左側に帯曲輪側から多聞櫓へ上る
石段があります。
この石垣の向こう側は枡形内です。
上図の案内所・トイレ付近から見た
天守です。
この反対側に武者走りがあります。
天守の石垣は野面積で、蒲生家の
時代に造られました。
下図にある鶴ヶ城稲荷です。
鶴ヶ城稲荷神社は約600年前に、
城がつくられた頃から、守護神とし
て祀られていたと伝えられており、
御祭神は宇迦魂命(ウカノミタマノ
ミコト)です。伝説によると、築城
(1384年)で東黒川館の縄張り
に苦心した芦名直盛が勧請先の
田中稲荷神社に祈願したところ、
霊夢を見て目覚めてみると、降り
積もった雪の上に狐の足跡があ
ったので、それをしるべとして築
城の縄張りを決め、名城を築く
ことが出来たと伝えられていま
す。
戊辰戦争の時に新政府軍が
天守に砲弾を撃ち込むので、
藩主松平容保指揮所が表門
(鉄門)になりました。
上図A付近から天守を見ると
上図A付近から見た天守です。
カメラを左に回しB方向を見ると
ここが本丸に入る裏門跡です。
下図にあるように、この仕切り石垣
の上には多聞櫓があったようです。
下図B付近から右にある石垣です。
この右側が裏門入口です。
この門は埋門で他の門より低い
造でした。
蒲生家時代は表門でした。
加藤家時代に上図の表門(鉄門)
が出来て裏門になりました。
Cの所に行くと
上図C付近から天守方向です。
天守への入口があります。
天守台の石垣が野面積という
のがいいですね。大手門にあ
ったような切り込みハギ石垣
より排水性がいいので、耐久
性も高いそうです。
蒲生氏郷はここに七重天守
を建てていました。
蒲生家時代の絵図です。
ほぼ松平家時代と同じです。
今回はここまでで、明日に続きます。
読者募集中ですので、読者登録はここのリンクです。
希望があれば、読者相互登録出来ます。
毎日午後8時半~9時頃に更新しています。
登録では「相手わかるように」に設定して読者登録してください。
読者様のブログは拝見に行き、「いいね」やブログ村・ブログラン
キングは出来るだけ押しに行きます。
Ctrlキーを押したままで、ポチしたら画面が飛ばされません。
お手数ですが、よろしく。![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ