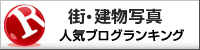予想外にもアメリカ大統領選挙で、トランプ候補が当選でした。
暴言放題でしたので、アメリカさえ良かったらいいという。暴力的
な面のある富豪です。これから日本がどうなるか心配です。日本
の支配階級の中にも、日本を最高にするために戦争でも何でも
するという人達もいるので、そんな人たちと気が合う感じで怖い
ですね。少年時代は素行不良で、音楽の先生を殴ったといいま
す。酒は飲まない、喫煙しない真面目な面もあります。当選後は
余裕なのか、周辺国とも仲良く協力すると演説していますが、ど
うなるのか心配です。会社経営で苦労をしているので、物事を
3手先まで読める人であって欲しいですね。
昨日の続きです。
今日は南宗寺塔頭の天慶院の紹介です。残念ながらここも写真撮影
は禁止です。
龍興山天慶院は、もと海眼庵と称し、臨済宗大徳寺派の寺院です。
天正年間(信長、秀吉時代)町衆の尊敬をうけた笑嶺宗訴(大徳寺
107世、南宗寺2世住侍)が一僧尼(南宗寺開山大林和尚の弟子で
武野紹鴎の門人)より献上をうけ、開祖として住したのち、弟子の
仙獄和尚(大徳寺122世、南宗寺6世)に附与したものです。本院は、
千利休との関係が深く、堺の歴史文化を著した江戸時代の本『全堺
詳志 ぜんかいしょうし(高志芝厳たかししがん 著』によれば、「千
利休堺住居ノ時、此庵ノ檀家ナリ」と明記されています。 大坂夏の
陣後(澤庵和尚時代)当庵も現在地に復興されましたが、元禄10年
(1697)大拙義戒(だいせつぎかい)和尚(本源院3世)が、高木重
三郎の寄捨を受け、没後100年となる千利休供養塔を海眼庵内に
再興しました(昭和31年(1956)本坊内庭園に移置)。 その後、
享保3年(1718)高志芝厳が別野を寄進して改築し、名を天慶院
と改めました。
方丈に付属する茶室「大黒庵」は、もと京都四条に武野紹鴎が営
んだものを基とし、圍式三畳台目、四畳半のうち一畳分を床とし、
前板を入れて仏壇を設け、円窓を切っています。これは祖堂形式
の先駆的造作で、非常に貴重なものです。
現在の建物は平成14年(2002)(雲峰和尚時代)に解体し、当
時の古材を各所に用いて復元されました。
(堺市のWebページより引用)
下図⑭の天慶院の山門です。
南宗寺の伽藍配置図です。
千利休が檀家であったお寺です。利休はあまり書物を残していないので、
利休の偉業は弟子の宗二が記録した「山上宗二記」で伝えられています。
「一期一会」の言葉も、著書『山上宗二記』の中の「茶湯者覚悟十躰」に、
利休の言葉として「路地ヘ入ルヨリ出ヅルマデ、一期ニ一度ノ会ノヤウニ、
亭主ヲ敬ヒ畏(かしこまる)ベシ」という一文を残しています。「一期」はもと
仏教語であり、人が生まれてから死ぬまでの間、すなわち一生を指します。
井伊直弼が要約して作った言葉です。この言葉はもともとは、中国の禅の
開祖の言葉から引用されています。この意味は「これからも何度でも会う
ことはあるだろうが、しかし、二度とは会えないかもしれないという覚悟で
人には接しなさい」と戒める言葉です。
門を入った所です。
玄関です。
右側に露地が見えますので、撮影させてもらいました。
奥の方に山上宗二の供養塔が見えます。
この露地の先を、左に曲がるとすぐに大黒庵です。
拡大した山上宗二の供養塔です。(Web上からの引用です)
山上宗二の墓がどこにもないので、ここに供養塔を建てたそうです。
山門横にある山上宗二の石碑です。
天正12年(1584年)に偉そうにした発言で、秀吉の怒りを買い浪人になります。
この後、前田利家に仕えますが、天正14年(1586年)にも再び秀吉を怒らせて、
高野山へ逃れ、天正16年(1588年)頃から自筆の秘伝書『山上宗二記』の写本
を諸方に授けています。その後は小田原に下って北条氏に仕えます。天正18年
(1590年)の秀吉の小田原征伐の際には、利休を介して秀吉との面会が叶い、
秀吉が再登用しようとしますが、仕えていた北条幻庵に義理立てしたため秀吉の
怒りを買い、耳と鼻を削がれた上で打ち首にされました。享年46でした。秀吉が
晩期の信長みたいになっています。3度も秀吉から怒られたのは、性格が合わな
かったのかもですね。
(ウイッキペディアより引用)
方丈に廊下で、直接つながる茶室「大黒庵」があります。
この茶室は利休の師匠である武野紹鴎のもので、京都
四条の夷堂にありました。1718年に高志七左衛門の
屋敷からこの大慶院(旧海眼院)に移築したものです。
配布していたパンフレットの解説板です。(大黒庵の外観と室内)
上の写真のように離れではなく、方丈に廊下で接続しています。
躙り口(にじりぐち)ではなく大きな貴人口になっています。これは
お客様専用の入口です。亭主などは茶道口から入ります。武家
屋敷の式台に当たるのが貴人口です。
大黒庵の構造図です。(Web上からの引用です)
圍式三畳台目、四畳半のうち一畳分を床とし、前板を入
れて仏壇を設け、円窓を切っています。これは祖堂形式
の先駆的造作です。具体的には、貴人口正面に円窓床。
一般的な円窓床(えんそうどこ)は、床の正面の大平壁
(おおひらかべ)に、円い窓をあけ障子を入れた床の間
のことです。大黒庵の円窓床は、さらに複雑な構成で、
前板を入れて仏壇を設けて円窓を切り、引分障子を立
て、障子を開くと、その奥の掛物を拝見できるようになっ
ています。炉を切る半畳を挟む、点前畳と客畳の配置が
秀逸で、亭主と正客の位置関係が合理的です。
堺の大商人であった武野紹鴎(革屋)や千利休(魚屋)
は、茶室で商談をしたというので、茶室は応接間でもあり
ました。
下の地図に武野紹鴎と千利休の屋敷跡が、
宿院の辺りにあります。
堺の町全体図です。(上が北)
堺の古地図(1728年)です。地図の中央に宿院とあります。(左が北)
最後に、前から欲しかった魚眼レンズを買いました。
たまに、広角レンズがあればと思うことがありまして、
今回完全マニュアルレンズのためか安かったので買
いました。
これからの紅葉写真撮影で使います。
焦点距離6.5mmで開放F値3.5のフイッシュ
アイレンズです。
ニコンのフイッシュアイレンズは高価なので、今
まで買って無かったのですが、これは外国製で
3万円程度でした。ネット評価が5.0でしたの
で信用しました。
インコのピピちゃん動画お借りしました。
鏡の前で「ぼく黄色じゃないよ!」自問自答(約3分)
今日はここまでです。明日は大安寺の紹介です。
読者募集中ですので、読者登録お願いします。
希望があれば、相互登録します。相互アメンバーも募集中です。
どちらもチェックを外して「読者とわかるように」に設定して登録してください。
できましたら、お願いですが、![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ