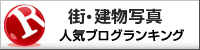昨日の続きです。
板葺宮伝承地から橘寺に歩きました。
途中の明日香村役場です。
明日香村役場です。ここは蘇我入鹿を暗殺した、
飛鳥板葺宮正門跡の前から撮影しました。(下図)
飛鳥京絵図
橘寺は上図のとおり川原寺の南に建てられています。
この位置関係から、橘寺は川原寺と対を成す尼寺とし
て建立された可能性があります。
橘寺方向に歩くと、飛鳥川の向こうに橘寺が見えてきました。
飛鳥川を橋の上から撮影しました。
さらに歩くと
聖徳太子ご誕生所の石碑があります。
飛鳥寺の東門(正門)前です。右は無料駐車場です。
日本書紀によると、中国へ不老不死の薬を求めた田道間守(たじま
もり)が、日本に持ち帰った「橘(ミカンの原種)」が植えられたことか
ら、この土地を橘と呼ぶようになったのだそうです。同時に黒砂糖も
持ち帰ったため、今でも「お菓子の祖神」として崇められています。
和菓子屋に橘屋という屋号が多いのもそのためです
橘寺は、創建時より東面して建てられていました。同時期の寺院は
中国の「王者南面」の思想を受け仏教寺院は南面して建てられるの
が通常でしたが、橘寺はこれに反して東面して建立されています。
南側が山地の立地条件からやむを得ずそうしたのか、あるいは他
に理由があったか未だ不明です。
橘寺東門です。左に受付があります。
拝観料(大人350円)を支払い、東門から入りました。
狛犬が新しいです。以前は古い狛犬があったのですが、
最近盗難があるので、倉庫に保管したのでしょう。
なかに入ると
右に本坊です。
赤い線が創建時の伽藍でした。
その部分を拡大すると
昭和28年~32年に石田茂作氏が発掘調査した。
中門、塔、金堂、講堂が東西に一直線にならぶ四天王寺式
伽藍配置であることが推定された。これに基づく橘寺創建時
伽藍配置は上図のとおりです。但し、廻廊が金堂の裏で閉じ
る可能性もあり、この場合は山田寺伽藍配置ともいえます。
当時橘と言われたこの地に、橘の宮という欽明天皇の別宮
があり、その第四皇子であった用明天皇と穴穂部間人皇女
を父母として、572年にこの別宮で生まれました。
606年天皇の仰せで、勝鬘経を3日間御講賛になった時に
ハスの花が庭に1mも積もり(蓮華塚)、南の山に千の仏頭
が現れ光明を放ち(下図の仏頭山)、太子の冠から日月星
の光が輝き(三光石)、不思議なことがいろいろ起こった。
天皇は驚きこの御殿を改造して、お寺にするように太子に
命じました。それで橘樹寺(橘寺)が出来ました。(聖徳太子
建立七ケ寺の一つ)
当初は東西870m、南北650mの広さがありました。
当初の橘寺
1148年雷のため五重塔が焼失します。
1506年には多武峰の兵に焼かれて、ほとんど焼失します。
江戸時代には僧舎が一棟のみでした。
次は観音堂です
元は本堂であった観音堂です。1864年に現在の本堂(太子堂)
が出来たので、今の位置に移築されました。
観音堂の六臂如意輪観世音菩薩様です。
観音堂修復のお願い。
次は五重塔跡です
五重塔跡の心柱跡です。直径90cm・深さ10cm
の心楚には、円穴の三方に添柱穴もあり、五重塔
は高さが約38mありました。
右が阿字池で、左が三光石です。
三光石です。日・月・星の光を放ちました。
本堂の太子堂から見た蓮華塚(左奥)です。つつじが咲いています。
右端に半分見えるのが二面石(次回説明)です。
聖徳太子が勝鬘経を3日間御講賛になった時に、ハスの花が降り
ましたので、その花を蓮池塚に埋めました。大化の改新でこの塚
の広さ約100㎡を一畝と定め、面積の基準として田畑が整理され
ました。なので、畝割塚とも言います。
長くなるので、今日はここまでです。
この続きは明日UPします。
読者募集中ですので、読者登録お願いします。
希望があれば、相互登録します。
御手数ですが。ついでにぽちっと押すだけ