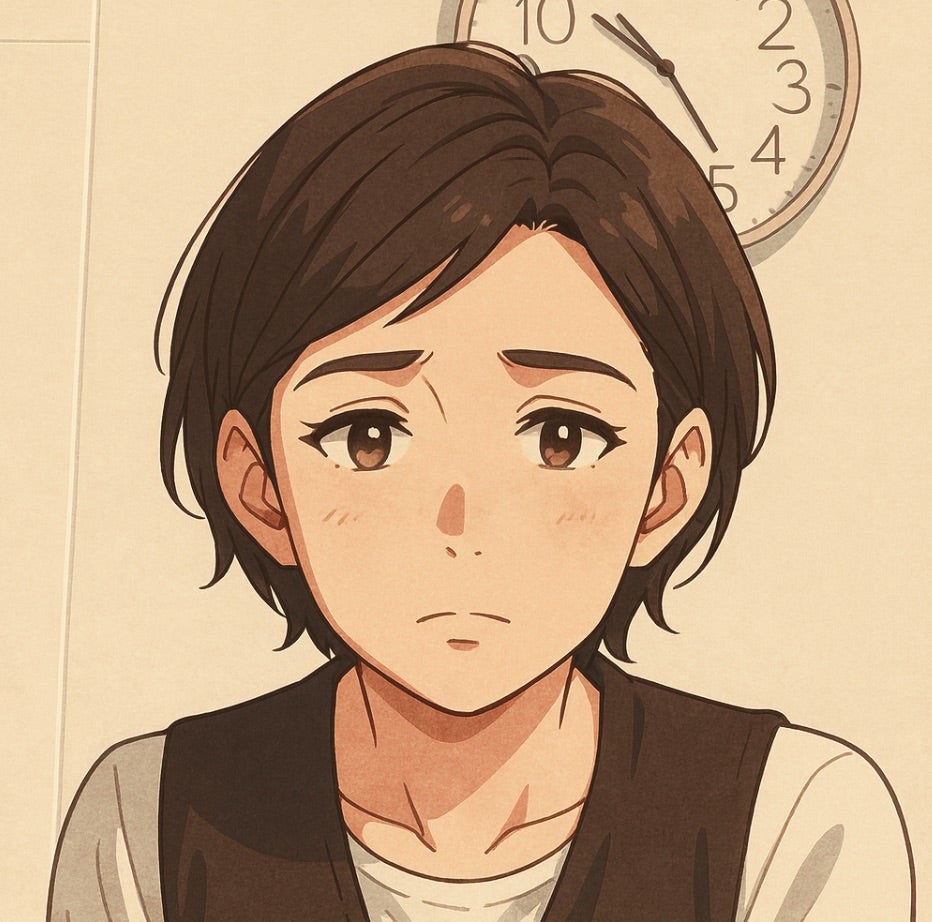前の記事はこちらから
1歳になった息子を連れて、
年末年始に義実家へ帰省しました。
新幹線で2時間くらい。
息子を連れての旅は、泣かないか
毎回ドキドキハラハラしていました。
おやつをたくさん用意して
ひたすら食べさせていました…
ドア近くやトイレの近くの席を選んだり
周りに迷惑をかけないか、
すごく気にしていました。
普段はマンションで、
息子と2人きりの時間を過ごしているので
義父母や親戚が息子を見ていてくれるのは、
少しだけ身体が休まる時間でした。
ただ、人見知りの激しい息子。
後追いしてきてしまう。
義母が抱っこしようとすると、
大泣きしてしまう…。
結局、気になってしまって、
完全には休めない。
そんな感じで、義実家への滞在が終わり、
自宅に戻って
また、日中は息子と2人きりの生活が始まりました。
息子が歩くようになっていたので、
ベビーカーに乗せて、
歩いていける範囲の、
学区外の支援センターのイベントにも行ってみたりもしました。
でも、もうすでにグループが出来ていて、
完全アウェーな感じがしてしまって、
結局、しんどくなって、
学区外の支援センターには行かなくなってしまいます。
息子と、ショッピングモールや
公園に行っていた方が気楽だなと思うけれども
ママグループも楽しそうだなとも思っていました。
その中で、知り合って話をするようになる人も
いたけれども、やっぱり、学生の頃の友達とは違う。
ママ友って、難しいなと感じていました。
仲良くなりたいけど、同時に気も使う。
楽しいときもあるけれども、やっぱり疲れもする。
このころは、
自分のペースもよくつかめずにいて
何かしなきゃとばかり焦っていた気がします…。
離乳食も本格的にはじまりました。
アトピーと診断されたのもあって
出来るだけ、手作りで、無添加でと
こだわりだしたのも、このころです。
自然食品のお店が、歩いていけるところにあったので
よくウォーキングもかねて、行っていました。
ステロイドをあまり使いたくなくて、
スキンケアや、食事療法など
いいと言われるものを、
いろいろと試し始めました。
皮膚科も、いいと聞けば、
あちこち行ってみていました。
テレビは見せたらダメというのを信じて、
テレビを一切みせないようにもしました。
絵本をたくさん読んで
公園も連れて行って
散歩も行って
子育て支援センターにも行って
食事にも
洋服の素材にもいちいち気をつけていました。
実家にあった布おむつをもらってきて
おむつなし育児にも挑戦していました。
今思うと、
相当無理していたと思います。
自分の時間がないと思って、
自分の時間を作らなきゃとしていまい
息子が寝てから、
夜遅くまで雑誌を読んだり、
本やブログを読んだり、
夜更かしするようになっていきました。
そうこうしているうちに
息子が1歳半を迎えました。
そして、ここから、7年にわたるワンオペ育児が始まるのです…。
つづきはこちらから