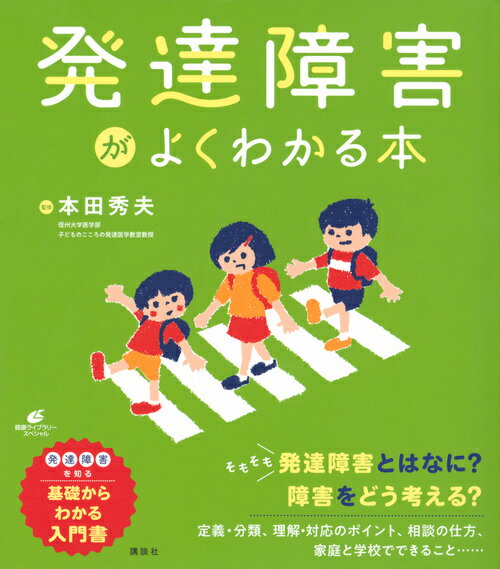こんにちは、凸凹君のママです。
本田秀夫先生の記事で、学校の先生方にも知っておいて欲しいな~!、と思った記事がありました。


最近は「発達障害」が知られてきていて小学校の先生方なら知識ゼロという人は少ないと思いますが、どうしても知識や経験の差は大きいです。
凸凹君の小学校(自治体?)では特別支援学級の対象が知的障害のみとなっているため、発達障害児は普通学級にしか所属できません。
このような制度で学校運営するのならば、なおさら普通学級の先生方にもある程度の知識を(学校や自治体側が)持たせる必要があるのではないかと思います。
そうしないと先生方も対応が大変ですよね、って意味で。
そして、知識としては「ASD」「ADHD」「LD」それぞれの特性や一般的な対応方法は知られてきていると思いますが、重複のケースがある(というか多い)こと、その場合は特性の出方や対応方法が変わってくることは、普通学級の先生レベルにはまだあまり知られていないような気がします。
上の記事では重複の例がいくつか紹介されていますが、それもすべてではなく、同じ重複でも個人差があったりして結局は子ども一人ひとりに適切な対応は異なります。
また、重複によって一見すると一部の特性が見えにくくなるケースがあることもあまり知られていないなと感じます。
極端な場合、例えば「こだわりがあまり見られないからASDではない」というような否定材料にされてしまったり。
凸凹君も一見するとこだわりが薄いように見えるので、たまに言われます。
実際は、ADHDの気の散りやすさで瞬間瞬間こだわりポイントが切り替わっているだけ。
見えにくいだけで、特性は確かに彼の中に存在しているんですけどね。
支援関係者だと気付いてもらえることが多いです。
重複、難しいですよね。
(参考)
上記記事、6回連載のようですが記事が2回分ずつしかリンクされていなくて、超探しにくかった!![]()
なので、↓に各記事のリンク貼っておきます。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回