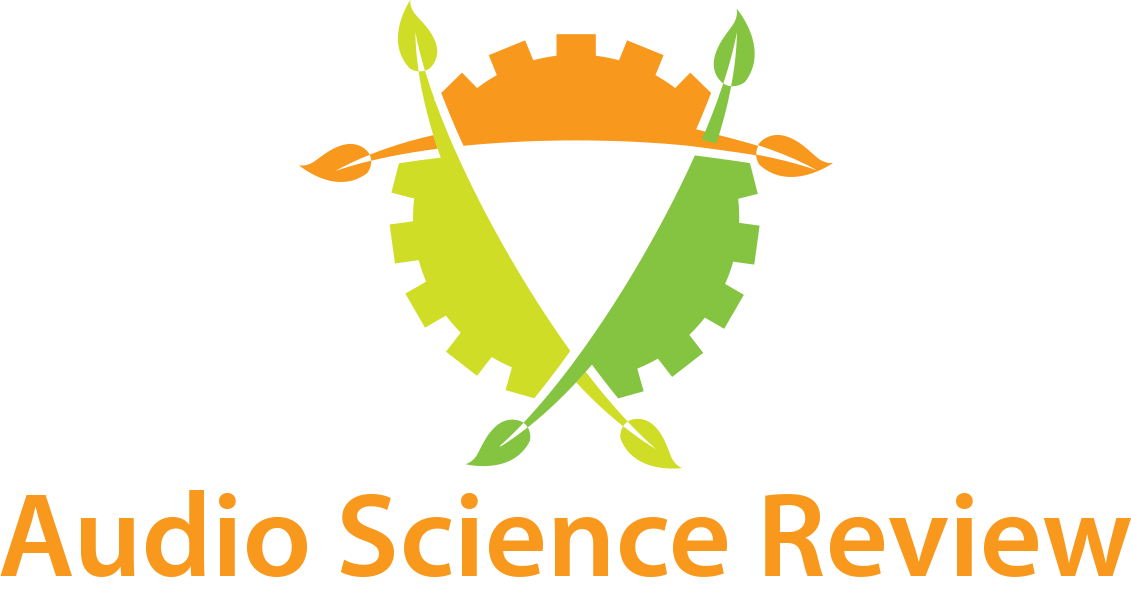ネットワークディスクレコーダ iPro WJ-NU101にネットワークカメラAXIS F9111-R Mk II をONVIFで設定する話です。
今回、iProのレコーダにAXISのカメラで記録したい と相談を受けたので、検証の結果判明した設定の仕方を時系列に手順として残します。
ONVIF・・・オンビフ、Open Network Video Interface Forum、ネットワークカメラのプロトコルの共通規格
ONVIF対応製品は日本でも増えてきているのですが、筆者は今回が初めてONVIFの設定と向き合った形となります。異なるメーカ同士でONVIF設定を行うのは大変なんだなぁと伝われば幸いです・・・
機器の再起動時にiProのレコーダがカメラに対しRTSPをプルしないためか、ブラックアウトします。 ネットワークの疎通後にカメラ側を再起動する事で復活するのですが、自動で復旧しないためRTSPでの運用を諦めました。
AXISのカメラ側でのRTSP H.265ストリーム設定例
パスなし(iProレコーダはこちらを使用)
rtsp://<IP_Address>/axis-media/media.amp?streamprofile=<ProfileName>
パスあり(VLC直接再生)
rtsp://<User_Name>:<Pass>@<IP_Address>/axis-media/media.amp?streamprofile=<ProfileName>
でプルすることが出来る
デフォルトRTSPストリームは
rtsp://<IP_Address>/axis-media/media.amp
※H.265非対応
iProのレコーダ側でのRTSPでの設定例。これでは電源遮断後に自動復旧しなかった。各設定が済み、とりあえずこれで行くか!と決めた後に再起動テストでNGとなりONVIFで記録する手段を探す事となった
映像の消失ではなく黒い映像を取得し続ける為、どうやらストリームの欠損扱いにならず、画は来ていると誤認しているような動作です。どんな設備であれ、法定点検で半年に一度は電源遮断が起きますのでこれではNG・・・。(電源立ち上げディレイでカメラ側を5分遅らせてもNG、レコーダ側を5分遅らせてもNGとの結果)
AXISのRTSP設定については以下に詳しく書いてあります。
Blog内参考リンク:
上記のリンクで扱っている説明とは異なり、AXIS F9111-R Mk IIはさらにプロファイル名を任意に設定が可能です。デフォルト設定ではRTSPでH.265をプル出来ない為、確実に欲しいストリームがある場合は要プロファイル作成です。
RTSPが使えなかったので、残る手段はONVIFでの設定です。
1.AXIS IP UtilityでカメラのIPアドレスを探し、目的の固定IPアドレスを振る 設定を行うPCのNIC(ネットワーク)の設定でIPアドレスを自動取得にしAPIPA(リンクローカルアドレス)で目的のカメラのIP設定を行います。AXIS IP Utilityを立ち上げると自動で同一ネットワーク内のカメラが検出されます。
AXIS IP Utility上でIPアドレスを変更することもできますが、リンクローカルアドレスを叩いてWebブラウザからIPアドレス変更を掛けた方が早いのでこちらの手順がお勧めです。
AXIS IP Utilityでカメラが検出される
AXIS IP Utility上でもIPアドレスの変更は可能だが、1台につき10分かかるので直接ブラウザからの変更をお勧めする
ネットワークカメラ周辺機器は必ずユーザ名とパスワードを最初に設定する
Webブラウザ上でのIP設定画面。今回はIPv6は不要なのでチェックボックスは外した
2.WS-Discovery(port 3702)機能を有効にし、ONVIF検出を有効にする。ONVIFアカウントを管理者権限で作成する AXIS F9111-Rは初期状態ではWS-Discoveryが有効になっていない
AXIS F9111-Rは初期状態ではWS-Discoveryが有効になっていない為、iProのレコーダでONVIF機器として検出することが出来ない
AXISのカメラ側でWS-Discoveryを有効にする。かつてはこれは有効だったがセキュリティの都合なのか今後デフォルトオフが当たり前になるのかもしれない・・・(手持ちの旧モデルは表のメニューからは触れなかった)
AXIS F9111-RはデフォルトでONVIFアカウントが無い為、管理者権限でアカウントを作成
ONVIFアカウントの管理者権限
WS-Discoveryが有効になるとiProレコーダでカメラが検出される。が、これだけでは設定はできないのであった・・・
3.iProのレコーダとAXISのカメラの時刻を同期させるか、AXIS側のIEEE 802.1X EAP-TLS認証をオフにする iProのレコーダをセットアップして新規カメラを検出しIPアドレス、ユーザ名、パスワードを入力して設定・・・と行きたいところですが、AXIS F9111-RはデフォルトでIEEE 802.1X EAP-TLS認証が有効になっている為、iProのレコーダとAXISのカメラの内部時計(RTC)が完全一致していないと設定が出来ません。
尚、iPro WJ-NU101はNTPのサーバ(リレー)機能を有する為、AXISのカメラをNTPクライアントとし配下に置く事も可能ですが、iProのレコーダはiPro製品であれば自動的に独自プロトコルで時刻が合うため、普段iProのレコーダを触っている方はNTPサーバの設定には不慣れかもしれませんので本記事では扱いません。システムの時刻同期の全体像が分からない場合は不用意にローカルNTPサーバを立てるべきではありません。
※本来、NTPとはローカル運用を行うものではありません。ですが、筆者はローカル環境運用設定を主としているのでシステム内での時刻同期は基本的に設定します。
※もしかしたら、ONVIFのサーバ・クライアント間で時刻同期を行うかもしれませんが、今回はそこまでの調査はしていません。調査している最中も時刻の微々たる誤差で通信遮断が起き、原因の特定に時間を要しました。(手癖で行うNTPサーバ・クライアント設定が切り分けの際に枷になったパターン。iProのレコーダ、NTPサーバとしてちゃんと機能した記憶が無い・・・)
Blog内参考リンク:
iProのレコーダの設定画面。このままでは設定が完了しない。(カメラ側がレコーダの要求プロファイルに答えない)
iProのレコーダとAXISのカメラの内部時計(RTC)が完全一致していないとiProのレコーダ側で設定が取得できない。※WS-Username tokenに答えない
iProレコーダで「カメラ」→「高度な設定」→「ONVIF設定」へ進む
iProのレコーダのONVIF詳細設定のNetwork Informationで赤枠のIPアドレスが取得出来る = WS-Username tokenに返答している、と捉えて構わないようだ。返答が無い場合はここが表示されない。試しにカメラの時刻を1分ずらすと疎通は遮断された。要求は秒単位での合致であると推測する
取得できなかった場合の表記
AXIS F9111-R Mk IIはデフォルトでIEEE 802.1X EAP-TLS認証がオンになっている
NTPサーバがいないローカル環境であれば認証は無しにしておく方が無難
設定を行っているPCの時間に合わせて設定を行うことも可能だが、機器同士の時間がずれると再び認証が通らなくなる
iProのレコーダで映像が取得できれば設定はOK
4.iProのレコーダ側からAXISのカメラにONVIFプロファイルを作成要求をし反映を確認し完了 以上の設定がうまくいけば、AXISのカメラ内にiProのレコーダから要求のあったONVIFプロファイルが追加されます。但し、H.264からH.265への変更や、音声ありからなし、などの変更は反映されませんでした。プロファイルの変更を行う場合はAXISのカメラ内に作成されたONVIFプロファイルを一度削除してから再度作り直す方が間違いがありません。
iProのレコーダから要求されたONVIFプロファイルがAXISのカメラに追加されている
iProのレコーダはファームウェアバージョンのよってはONVIF 2ストリーム対応をしている。参考:iPro WJ-NU101 ファームウェアリリースノート
iProのレコーダからONVIF-Dualを設定する
AXISのカメラにONVIFのプロファイルが2つ作成される。要求プロファイルと合致しているか必ず確認を行う事
単画面・録画用のONVIFプロファイル1
分割表示用のONVIFプロファイル2
音声を追加する場合はiProレコーダの「録画設定」で録音をOnにし、G.711を選択する
iProのレコーダでG.711を設定するとAXIS側でPCMU(= G.711)が選択される。今時であればもう少し音質の良いフォーマットに設定したい
ストリームの要求はあくまでも要求 実際に単画面表示をしている・音声が復調できる、分割表示をしている・音声が復調できる、各ストリームの記録・再生に問題がない事を確認
それにしても、ONVIFの設定は難易度が高い話だなぁと思います。
同じ事で悩む方むけに本記事を残します。
おまけ
ONVIF Device Test Toolがあると基本的なONVIFの機能の試験が可能です。可能なんですが、これはONVIFの協賛企業にだけ配布されているツールの様で一般には手に入りません・・・。今回の記事を書くにあたり、大変参考になりました。
ONVIF対応の認証を得るために使用するツールの為、全機能が試せます。
ONVIF Device Test Tool
IEEE 802.1X EAP-TLS認証がオンの場合、機器間の時刻同期が必要になる。ONVIF Device Test Tool上でカメラの時刻をPC時刻と同期する「Sync Time」機能があり、この同期を行わないとWS-Username tokenに答えてくれない。今回の設定を探る上で大変参考になった
時刻同期が不一致の為、WS-Username tokenが通らないエラー。HTTP/1.1 400 Bad Request。これが手がかりになり、原因を探れた