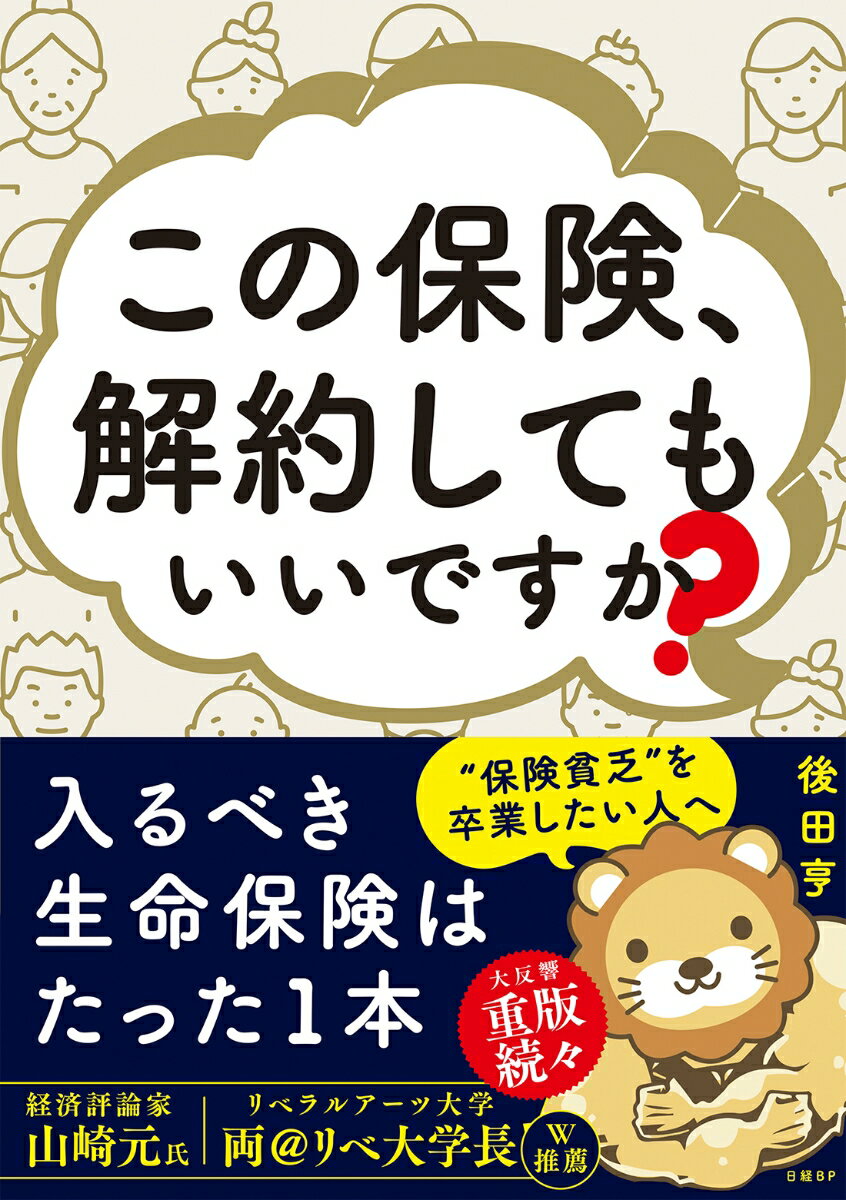こんばんは![]()
親の確定申告を通じて医療費・介護費が高額であることを改めて実感した、40歳代・女性(勤務医) カメコです。
老後の費用が心配・・・![]() と暗い気持ちになりましたが、やみくもに不安を覚えるのは良くないと思い、前回は実際かかるであろう数字を概算してみました。
と暗い気持ちになりましたが、やみくもに不安を覚えるのは良くないと思い、前回は実際かかるであろう数字を概算してみました。
85歳まで生きることを前提として、80歳から85歳までは何らかの介護が必要になると予想。
そのうえで65歳~85歳までの医療費と介護費を計算したところ、1000万円~1300万円という数値が叩き出されました![]() (計算ミスがなければ・・・)
(計算ミスがなければ・・・)
そこで、あえて今回は、『その費用を賄うのに今の保険は必要か?』という議題について考察したいと思います。
まず前提として、医療と介護を分けて考える必要があります。
こんなよくあるパターンで考えてみたいと思います。
『82歳、脳梗塞で入院。リハビリでだいぶ改善したが、右上下肢に麻痺が残る。
歩くことは不安定で杖を使用。排泄や入浴は一部介助が必要な状態。
自宅退院へ向けて準備を整えることとなった。認知機能は年相応。』
まず、この患者さんに対する入院中の治療は医療保険を使用します。
しかし、退院するためにはさまざまな準備が必要です。
例えば電動ベッドを借りる、自宅に手すりを付けるといったハード面を整えることも必要です。
また、退院後は通所リハビリテーションの利用や訪問介護が必要となるかもしれません。
そして、これら諸々を用意するためには、最初に『要介護認定』を受ける必要があります。
(詳細はここでは割愛しますが、興味のある方はこちらをどうぞ![]() )
)
認定審査により『要支援1、2、要介護1、2、3、4、5』の7段階のどれかに認定されます。
(注:介護が必要ないと認定されることもあります。)
この認定の結果をもとに、介護度に応じた上限額の中で必要な介護サービスを受けていくことになります。
これを賄うのが介護保険というわけですね。
(介護度と上限額などについて興味ある方はこちらをどうぞ![]() )
)
さて、前置きが長くなりましたが、『その費用を賄うのに今の保険は必要か?』について。
そもそも、なぜこんなことを考えるに至ったか。
・・・私の保険、めちゃくちゃ高いんです~![]()
![]()
入ったのが40歳だったということもありますが、な、なんと、月12,685円!!
ちなみにこの保険は終身保険ですが、一生涯この金額を払い続けることが前提です・・・。
(しかも掛け捨て![]() )
)
そこで、貯蓄に目覚めた私は考えました。
『保険に払っている分を今から積み立てていけば、老後の医療費は余裕で貯まるのでは![]() ・・・?』
・・・?』
最近読んだこの本の影響もあります![]()
この本ですが、会話形式で書いてあるためあっという間に読み終わります。
読んでみて、納得する部分が非常に多かったです。
(ただ難を言うと、『解約したほうがいい』と言い切るためには根拠として載せているデータが少ないな、という印象ですが・・・)
昨日の計算によると、65歳~85歳までにかかる医療費は、多めに見積もって平均月2万円。
癌で手術を受けたり、脳梗塞になって治療を受けたりで臨時の出費があった場合も、高額医療費制度の恩恵があれば8万7430円。
(注:高額医療費制度を利用する場合、年収の多少によりこの限りではありません。実際はもっと安くなる高齢者のほうが多いかも。)
この概算を見る限り、今から保険分を蓄えていたら今の保険は不要な気がするのです。
唯一の気がかりは、今の保険料控除が使えなくなるのは惜しい!!ということでしょうか。
というわけで、次回は『お得に保険料控除を使う方法はないものか?』について考えてみようと思います。
よろしかったらまた覗いてくださいね![]()