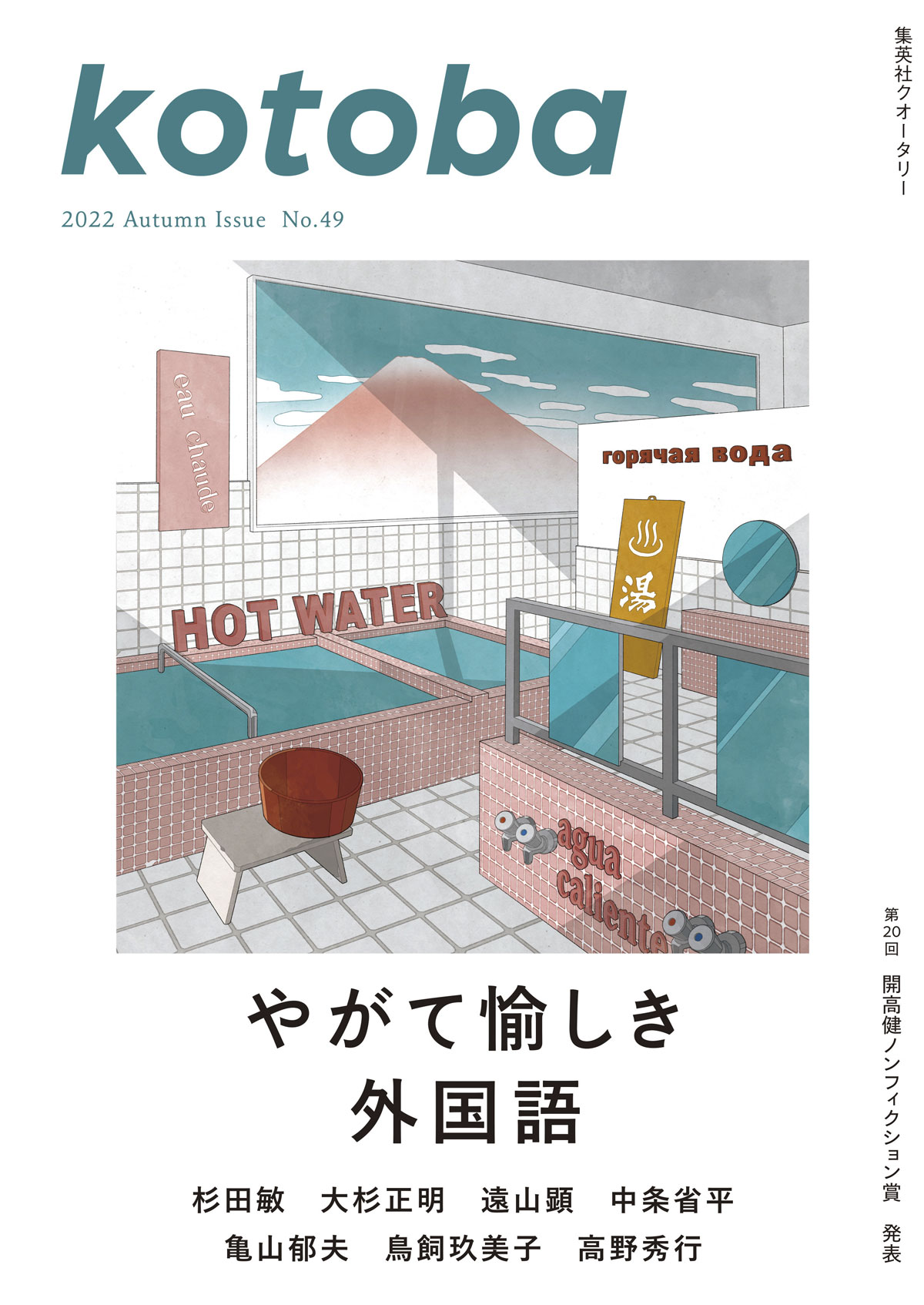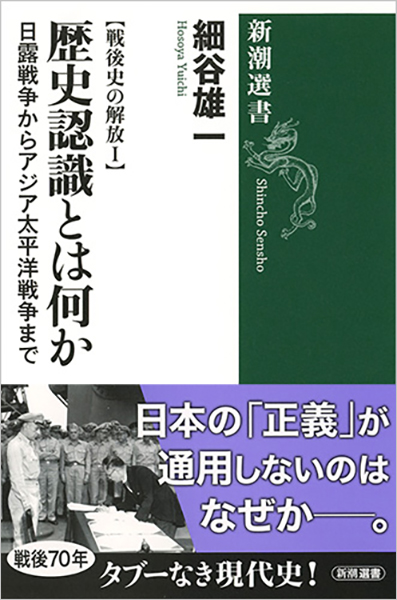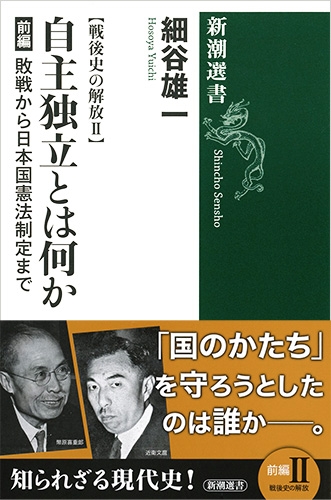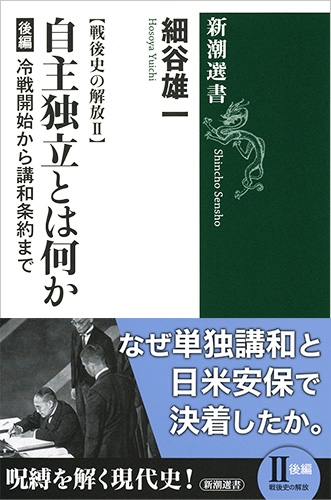でもって、プーチン下げも止まらない! そんな報道を繰り返していて、またそれを真に受けていて、それで戦争が終わるんですかね。
世の中、そうと言えるかもしれないけれど、そうとは言えないかもしれない、ということが往々にしてあるものでして。
今回は、少しずつ、時間をさかのぼって見ていこうと思います。
まずは通信社の報道から。「ロイター」。
●「枕詞」で印象操作
[キーウ/クラマトルスク(ウクライナ) 6日 ロイター] -
ロシア国防相は6日、ウクライナで侵攻を続けるロシア軍部隊が現地時間正午から36時間の停戦に入ったと発表した。プーチン大統領の「クリスマス停戦」指示を踏まえた措置だが、ウクライナ側は応じておらず、「一方的停戦」となっている。
プーチン大統領は5日、ロシア正教のクリスマスに合わせ36時間の停戦を指示。しかし、ウクライナのゼレンスキー大統領は「ロシアはドンバスにおけるわれわれの兵士の前進を食い止め、武器や戦力をわれわれの拠点に近づけるためにクリスマスを隠れみのとして利用しようとしている」と批判した。
しかし目撃者の情報によると、ウクライナ東部ドネツク地域の前線近辺では、親ロシア派の拠点から停戦発効後に砲弾が発射されたという。一方、ロシア国営タス通信によると、親ロシア派当局者は、ウクライナ側が停戦発効後にドネツク地域で砲撃を行ったと非難している。
ロイターは、停戦発効後の戦闘の状況を確認できていない。
ロシア(プーチン)のやることはいつだって「一方的」で、だから何をしても批判され非難されてしまうんだなあと。
加えて、「も」を付ければ垂れ流しで良いんですか、確認できてないんですか、と突っ込まずにはいらえません。
[モスクワ 5日 ロイター] -
ロシアのプーチン大統領は5日、ロシア正教のクリスマスに合わせ6日正午(日本時間6日午後6時)から36時間、ウクライナでの停戦を命じた。
ロシア正教会最高位のキリル総主教のクリスマス停戦の呼びかけを踏まえた措置という。
ウクライナ大統領府のポドリャク顧問は、プーチン大統領による36時間の停戦提案を「偽善」と述べ、反発。「ロシアが占領地から撤退して初めて『停戦』が可能となる」として拒否した。
これに先立ち、ロシア正教会のキリル総主教がウクライナ側にも停戦を呼びかけていたが、ポドリャク顧問は「皮肉な罠でプロパガンダの要素」と退けていた。
インタファクス通信によると、ロシア大統領府(クレムリン)のペスコフ報道官は5日、ロシアの停戦提案に対するポドリャク顧問の拒否が「ウクライナ大統領の見解を反映しているかどうか判断するのは難しい」と述べた。
そもそも、ロシア(プーチン)のやることは、まずは「偽善」で「罠」でなければならない、のかな。
つい、2週間ほど前には「クリスマス停戦」を期待する声が、少なからずあったように思うのだけれども。
お次は週刊誌。「Newsweek日本版」です。
●「世界がしびれた」
ロシアの侵攻当初、首都キーフ(キエフ)陥落は時間の問題だと、多くの専門家は思っていた。だが、ゼレンスキーは国外退避を勧める米政府の申し入れをきっぱり断った。
「私がいま必要としているのは弾薬であり(退避のための)乗り物ではない」という答えに世界がしびれた。
偉大なリーダーは、人民の熱意に共感し、それを政策に反映させる。また、往々にして漠然とした人々の信念を説得力のある形で表現して、大衆を鼓舞する。
確信と誠実な思いと目的を伝えて、困難な中でも人々が希望に手を伸ばすよう促す。
ゼレンスキーのこうした資質が、2023年もウクライナと世界を動かすカギになることは間違いない。
※ゼレンスキー「必要なのは弾薬であり乗り物ではない」に世界がしびれた
→https://www.newsweekjapan.jp/glenn/2022/12/post-97.php
「世界がしびれた」と言うのだけれども、したら、ワタクシはその「世界」に入れてもらえないってこと?
ちなみに、誌面ではこんな感じです。
書いたのは、グレン・カールという人で「元CIA工作員」。
う〜ん、こんな単純な「解説」をしていて良いのかしら。それとも、こういう文章を書いていること自体、何かの「工作」でしょうか。
掲載号はこちら。
ウクライナ戦争が変えた世界の針路を読む。8賢人の論考&キーパーソン10人
2023 WHO’S NEXT
ロン・デサンティス(フロリダ州知事)/レジェップ・タイップ・エルドアン(トルコ大統領)/エフゲニー・プリゴジン(プーチンの側近)/ウォロディミル・ゼレンスキー(ウクライナ大統領)/李強(中国次期首相候補)/グレッチェン・ウィットマー(ミシガン州知事)/リシ・スナク(英首相)/ニコラ・スタージョン(スコットランド首相)/モリス・チャン(TSMC創業者)/イーロン・マスク(テスラ、ツイッターCEO)
※2022年12月27日/2023年1月 3日号(12/20発売)
→https://www.newsweekjapan.jp/magazine/423327.php
一方、季刊誌ではこんなの「も」ありました。「kotoba」。
●世界観の違い
ウクライナの侵攻問題で、もう完全に変わったなと思ったのは、若い国際政治学者がマンガ世代なんですね。彼らのなかでは、世界が劇画化されているんです。塹壕でウクライナ兵が苦しんでいる映像を見ると感情移入するけれど、ロシア兵はただの敵でしかない。善悪で割り切って世界を見ていく。我々の世代とは世界観が違うんです。ウクライナ問題をめぐる論争は、世界観の違い、文学と政治の違いだと思います。
善悪で割り切っている若い人たちは、ロシアがなぜ侵略したのかなどの微妙なところについては、どうだっていいじゃない、関係ないよと言う。古い世代は、なぜ侵略したかにこだわります。これからの時代は、なぜ侵攻したかを問うてはいけない、そんなことを問うと善が後退するんじゃないか、ということになってくる。これが、21世紀の特徴なんじゃないかと思います。自分たちのことしか考えない人が増えて、多文化共生、多言語共生の考え方が恐ろしいぐらい後退している印象を受けます。
我々の世代までは、微妙な、解決しがたい何かというものに価値があっったけれども、もう、そういうものの価値がなくなる時代が来たんだなと実感しますね。ということは、文学の死なんですよ。だから本当は、まったく別次元の文学が生まれないといけないんです。
インタビュー記事。話しているのはロシア文学者の亀山郁夫さん。名古屋外国語大学学長、世田谷文学館館長、東京外国語大学名誉教授、だそうです。
世代論で括るのはどうかな、と思いますし、「若い政治学者」が、具体的に誰を指しているのか分かりませんが・・・
本当は割り切れないことを、あえて割り切って分かった気になって安心する、種類の人が増えているような、そんな気配は、確かにあります。
掲載誌。
特集 やがて愉しき外国語
私たちはなぜ外国語を学ぶのか?
日本人はどうして英語にこだわるのか?
英語以外の外国語を勉強する意味とは?
デジタル時代に、そもそも外国語学習は必要なのか?
外国語学習についての疑問への答えを探し、日本ではなかなか実感できない、言語の多様性についても考える。
最後は「戦前」に書かれた本から。『戦後史の開放Ⅰ』。
●「事実認識」とは?
歴史的事実とは、均一の濃度で塗られた一つの色ではなく、むしろさまざまな色が混ざり、見る角度や、光の加減によって多くの異なる色彩を見せるのに似ている。同じ色を見て、それを「緑」と言うものもあれば、「青」と言うものもある。どちらも正しい場合もあれば、どちらか一つがより正しい場合もある。国際政治における正義もまた、単調な色彩で描けるものではない。にも拘わらず、それがどのような色彩であるかを、正確に把握することが求められている。それゆえに、歴史認識を語る場合には、広い視野と深い知識、そして多様な要因をバランスよく総合する、知的な努力が求められる。それは、自らに都合が良くないような事実も真摯に受けとめる勇気と誠実さが求められる。 (P.35)
歴史家がありとあらゆる史料を読むことができないとすれば、歴史家は史料を取捨選択して用いざるを得なくなり、そこに一定の偏りや、解釈の違い、見解の対立が生じる余地が生まれる。あるテーマについて、人間が一生に読むことができる分量以上の史料が存在しているとすれば、いかなる歴史家といえども完全なる「歴史的事実」を明らかにすることはできないはずだ。にもかかわらず、日本では、史料に基づいて「知ることのできる事実はすべて見つけ出すことができる」というような信仰がいまだに生き続けている。「知ることのできる事実はすべて見つけ出す」という努力をすることと、それを達成することは異なる。歴史家である以上は、歴史的事実により多くの光を当て、より鮮明にそれを描く義務がある。しかしながら、それを誰かが達成できるかといえば、そうではない。 (P.41)
(ワタクシから見て)「若い国際政治学者」さんなのだけれども「そりゃ、ごもっとも」と言うしかない記述です。こういうことを、ちゃんと書いてたんですけどねえ。
ちなみに、2015年に出版されたものです。
歴史認識にしろ現実認識にしろ、という話だと思います。
なぜ今も昔も日本の「正義」は世界で通用しないのか――国際社会との「ずれ」の根源に迫る歴史シリーズ第一弾。日露、第一次大戦の勝利によって、世界の列強の仲間入りを果たした日本。しかし、戦間期に生じた新しい潮流を見誤り、五大国から転落していく。その三〇年の軌跡を描き、日本人の認識構造の欠陥を読みとく。
この本自体は、〈「知ることのできる事実はすべて見つけ出す」という努力〉の跡が見える、そういう意味で良いものだと思います。
参考までに、目次も。
はじめに
桑田佳祐の嘆き/高坂正堯の警告/戦後史の視野
序章 束縛された戦後史
1 村山談話の帰結
歴史を見つめ直す/村山富市の決意/分裂する歴史認識/歴史問題の解決は可能か/歴史問題は国内から/敗戦を受け入れる困難
2 歴史学を再考する
歴史理論で観る世界/「実際に何が起こったか」/エヴァンズの反論/歴史学の黄昏/歴史に翻弄される政治/運動としての歴史
3 戦後史を解放する
イデオロギーによる束縛/反米史観と陰謀史観/堕落する歴史/「一九四五年」からの解放/世界の存在しない日本史/日本が存在しない世界史/戦後史の解放へ
第1章 戦後史の源流
1 戦後史への視座
戦後史をどのように語るか/大量殺戮の世紀
2 平和主義の源流
「近代の発明」/平和運動の胎動/ツヴァイクの不安/第一次世界大戦の衝撃/国際秩序の変革/吉野作造と原敬/牧野伸顕と伊東巳代治/「サイレント・パートナー」/人種平等という夢/人種差別撤廃をめぐる挫折/英米批判の系譜
3 国際秩序の破壊者として
戦争のない世界を目指して/国際公益と国益/国際人道法の衰退/国際思想の転換/権力政治と平和主義/若き天皇の不安/満州事変の勃発/平和の破壊/権力政治への回帰
第2章 破壊される平和
1 錦州から真珠湾へ
空からの恐怖/方向感覚を失った日本/ノモンハン戦争の衝撃/独ソ不可侵条約/清沢洌の洞察/第二次大戦の幕開け/チャーチルの登場/近衛文麿の弱さ/「根のない花」としての外交政策/第二次世界大戦の転換点/「対英米戦を辞せず」/南部仏印進駐の決定/幣原喜重郎の警告/幻の図上演習/大西洋憲章/戦後世界の基本原理/民族自決と「アジア解放」/迷走する軍部/天皇の疑問/セクショナリズムという病理/コーデル・ハルとジョセフ・グルー/対英米戦の幕開け/過小評価されるアメリカ
2 第二次世界大戦の諸相
アジア太平洋での戦争/日本のアジア支配/グローバルな戦争/テヘランとカイロ/戦局の転換点/日本の戦争目的/東條英機の家族的秩序観/重光葵と「大東亜宣言」/脱植民地化へ向かうアジア
3 戦争の終幕
欧州戦線の終幕/国連創設への動き/国際連合の発足/国際組織による平和/孤立する日本/鈴木貫太郎の指導力/ポツダム首脳会談/ポツダム宣言/原爆投下の決断/アジア太平洋戦争の終結終章 国際主義の回復は可能か
破壊と破滅/国際社会との齟齬/軍国主義批判の陥穽/国際主義の回復/世界の中の日本
あとがき
註
関連年表
これも参考までに。シリーズものです。
●それでも、変わらないものこそ、
こうしてみると「情報」にも、賞味期限が長い短いは、確かにあって。
「世の中が変わったから」とか「これまでの常識は通用しないよ」とか、そんなことを口にする人がいます。
けれど、種々諸々いろんなことが根底から覆るなんてことは、そうそう無いわけで。
それはつまり「未知で新型」なるもの、それに付随するあれやこれやを、より高値で、より大量に、売りたいだけじゃないかなと思うわけで。
マナーとかエチケットとかルールとか常識とかもね、自分で考えるのを放棄した人が、それでも相手を黙らせるために持ち出してるだけだから。
善悪、正邪、自分の基準を持つのは大切だけれども、それを人に強要したり、世界に当てはめたりすると、それは色々間違いの元になるんじゃないかと。
ま、つまり、そういうことです。
🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥
関係あるような、ないような過去記事。お時間あれば。
年末年始、断捨離。
売りました。
残しました。
町へ出ます。