今日はね、発達症(発達障害)について書いてみようと思います。
4年生を担任していたとき、「うーちゃん」という男の子がいました。
私は発達について診断できる立場にはないのですが、おそらく自閉症スペクトラムの傾向がある子ではないかな、と感じていました。
当時、自分のHPに書いていた日記です。
● 船が気になる ●
うーちゃんは,ぷくぷくしていて,おっとりした男の子。
顔はまん丸,細い目にへの字眉。
甲高い声で いろんな話をしてくれる楽しい子。
話し方は、とても 丁寧。「です」「ます」調。
でも,気になることがあると,授業中でも席を立ってしまう。
「先生,ぼくの作った船 こわれましたぁ。」
「あらら,困ったねぇ。
でもね,うーちゃん。授業中だから席についてね。
船を見るのは,休み時間にしましょう。」
「はい・・・。」
うーちゃんは,眉を ますます 八の字にして,悲しい顔で 席に戻る。
これを,日に 何度も 繰り返す。
「うーちゃん,図工で作った船が 気になるんだね。」
と私が聞くと,
「そうなんです。船のマストが 倒れてしまうんです。」
と,また,悲しそうな顔で答える。
「授業中に,船が気になっても,席を立たないで ガマンできるかな。」
「はい…。」
が,しかし,15分後,うーちゃんは また 船のところに 歩いていくのだった。
「先生,船 こわれていませんでしたぁ(ニコニコ)!」
「あぁ・・・そう。よかったね。…。でね,うーちゃん,授業中は…」
また,同じ説明を することになる。
本音を言うと,もっと厳しく 叱りたくなってしまうことも ある。
でも,うーちゃんは ガミガミ 怒られたからといって,行動が 変わる子ではないのだ。
叱られた意味が あまり理解できず,困った顔をする。
でもって,怒られて いやな気分 だったことだけを 覚えているような ふしがある。
3年生になった今も,まだまだ,話が通じないことが 多い。
でもね,うーちゃん。
キミは,いつも一生懸命。
船は,キミの力作だものね。
気になる気持ちも わかるよ。
ちょっとトンチンカンなときも 多いけど,その懸命な姿が 大好きだよ。
だんだんと TPOを考えて 行動できるように,一緒に 考えていこうね。
うーちゃんは,ぷくぷくしていて,おっとりした男の子。
顔はまん丸,細い目にへの字眉。
甲高い声で いろんな話をしてくれる楽しい子。
話し方は、とても 丁寧。「です」「ます」調。
でも,気になることがあると,授業中でも席を立ってしまう。
「先生,ぼくの作った船 こわれましたぁ。」
「あらら,困ったねぇ。
でもね,うーちゃん。授業中だから席についてね。
船を見るのは,休み時間にしましょう。」
「はい・・・。」
うーちゃんは,眉を ますます 八の字にして,悲しい顔で 席に戻る。
これを,日に 何度も 繰り返す。
「うーちゃん,図工で作った船が 気になるんだね。」
と私が聞くと,
「そうなんです。船のマストが 倒れてしまうんです。」
と,また,悲しそうな顔で答える。
「授業中に,船が気になっても,席を立たないで ガマンできるかな。」
「はい…。」
が,しかし,15分後,うーちゃんは また 船のところに 歩いていくのだった。
「先生,船 こわれていませんでしたぁ(ニコニコ)!」
「あぁ・・・そう。よかったね。…。でね,うーちゃん,授業中は…」
また,同じ説明を することになる。
本音を言うと,もっと厳しく 叱りたくなってしまうことも ある。
でも,うーちゃんは ガミガミ 怒られたからといって,行動が 変わる子ではないのだ。
叱られた意味が あまり理解できず,困った顔をする。
でもって,怒られて いやな気分 だったことだけを 覚えているような ふしがある。
3年生になった今も,まだまだ,話が通じないことが 多い。
でもね,うーちゃん。
キミは,いつも一生懸命。
船は,キミの力作だものね。
気になる気持ちも わかるよ。
ちょっとトンチンカンなときも 多いけど,その懸命な姿が 大好きだよ。
だんだんと TPOを考えて 行動できるように,一緒に 考えていこうね。
ここで私が伝えたいのは、障害があるとかないとかは、重要ではなく、
発達症(発達障害)の傾向があっても「ふつうのコミュニケーションで十分対応できる」ということです。
当時、私は コミュニケーションについて学んではいませんでしたが、
「こういう傾向のある子なんだな」
と受け入れることで、特に大変さを感じずに、指導ができました。
ここでうーちゃんを、
「きちんとさせよう」
「ずっと席に座っていられるようにしよう」
「自分の理想とする『いい子』に変えよう」
と思っていたら、お互いにストレスだらけだったことでしょう。
うーちゃんは、うーちゃんでいい。
でも、先生としてのお願いはシンプルに伝えよう。
そう思うことで、お互いに楽にいられました。
この年度は、他にもグレーゾーンの子が4人いて 個性豊か。
32人中4人だったので、割合は高かったのですが、私自身 とても勉強になった年でした。
うーちゃんの話は、他にもいろいろとあります。
大好きな子どもたち~発達障害週間1
大好きな子どもたち~発達障害週間2
大好きな子どもたち~発達障害週間3
大好きな子どもたち~発達障害週間4
大好きな子どもたち~発達障害週間5
大好きな子どもたち~発達障害週間6
大好きな子どもたち~発達障害週間7
大好きな子どもたち~発達障害週間8
ずいぶん昔のアメンバー記事ですが、よろしかったら ご覧ください。
そんなことを書こうと思ったのは、さとう式で有名な佐藤先生の記事を拝見したからです。
発達障害や 認知症 意識の無い人との コミュニケーション
「発達障害 関係ない
痴呆 関係ない
むしろ 発達障害や 痴呆のコミュニケーションから
私達は 原始的なコミュニケーションを学ぶ必要があります。」
とあります。
私も同感です。
障害というと、特別な才能を伸ばすとか、すごい潜在能力がある、
というところに目を向けたがる方も多いのですが、(それも大事ですが)、
それ以上に「ふつうのコミュニケーション」について 考えていく機会でもあると感じています。
叱るより聞くでうまくいく 子どもの心のコーチング/KADOKAWA/中経出版
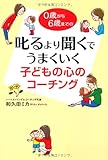
¥1,296
Amazon.co.jp
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング [ 和久田ミカ ]

¥1,296
楽天
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング 0歳から6歳までの[本/雑誌] / 和久田ミカ/著

¥1,296
楽天¥
