「あさイチ」の中で、幼稚園のときに「忘れ物が多い」と注意を受け落ち込んだ、
というエピソードが紹介されていました。
この話には、前後がございまして その辺をお話したいな~と思います。
長くてごめんなさい。
娘が幼稚園の頃、登園しぶりの時期がありました。
お友達からいじわるをされたり、忘れ物を注意されたり、担任の先生が自分には冷たいように感じたり…
いろんなことが重なったようです。
ある日、園長先生から お呼びたてがありました。正直、
「えーー、やだ~!」
って思ったので、はっきり お断りしたのですが、どうしても お話がしたいから来て、とのこと。
しょうがなく、次の日に伺うと、
「担任からの話ですが、忘れ物や なくし物が多く、困っているようです。」
という話でした。
そのときの私の勝手な印象ですが、園長先生の言い方が「えらそー」に感じて、カチーンときました。
そこで、
「忘れ物が多いんですね。すみません。
でも、私は、忘れ物をして”忘れました”と 言えることも 生きる力だと思っています。」
と 申し上げちゃいました。
先生ってね~、(全員じゃないんだけど)自分が上に立ってないと いやなのね。
私も、教師だったからねん。
園長先生の「正しさ」に対抗して、私の「正しさ」で応戦したというわけです。
今思えば、よくまあ、そんなこと言ったわね~って思いますが…。
すると、園長先生の顔が こわばり、
「でもね、お母さん。
気にしてしまう子もいるので、忘れ物を しないように 気をつけてくださいね。
お母さんが 気をつけてあげないと 子どもは 用意できませんから。」
そのあと、いかに 親の不注意で こどもが傷つくか、という
最初は 黙って聞いていたのですが、ふつふつと 疑問がわいてきました。
園長先生の言っていることは、正しいかもしれない。ごもっとも。
正しいけど、ひとつ腑に落ちないことが…
「忘れ物、そんなに 多いんですか?」
思い切って 聞いてみました。
たまにはすると思うけど、注意を受けるほどじゃないと思うんだけどなあ…。
園長先生は 一瞬視線をそらし、
「詳しいことは 担任へ 確認してください。」
とおっしゃいました。
あらまー、そんな不確かな状態で、私を呼び出しているのね…。
なんだか、ぐっと 気持ちが こみ上げてきました。
すーはー すーはー すーはー
私は 何を感じてるんだろう。
私は 何を伝えたいのだろう。
私は 何をわかってほしいと思ってるのだろう。
心の中を探ってみて、正直な気持ちをお話しました。
「園長先生。私ね、今 涙出そう。
なんかね、がんばってないから もっと がんばりなさい、って 言われているように 聞こえるの。」
「いえいえ、そうじゃなくてね、完璧なお母さんは いないけどね。・・・」
「でもね、私 ダメな母親だって 言われてるようで、悲しい…」
「そんな つもりで 言ったんじゃなくてね。お子さんの気持ちを考えて、と。」
で、また同じような話に戻り、しばらく聞いていましたが、腑に落ちず。
「もう一度 お聞きしますけど、娘は どのくらい忘れ物をしているんですか?」
「それは、担任のほうに・・・」
「園長せんせ~い、ダメだよ~。
ちゃんと 確認してないのに そんな風に言われたら、傷つくよ~。悲しいよ~!もー!!」
と 我慢できなくて 先生の手を握りながら タメ口きいちゃいました。
ここで どんよりとした雰囲気が、少し変わったように記憶しています。
悲しい、傷つく、こんなふうに感じる、と 口に出したら、私自身の心持ちが楽になったこともあったかなあ。
園長先生とは 最後に和解し、笑顔で ごあいさつ。
そのあと、担任の先生とも話して、丸く収まりました。
(まあ、担任の先生に対して、思うところがあるんだったら直接言ってよ、と思う気持ちもありましたが…)
このエピソードを通じて 感じたのは、
正しさと 正しさがぶつかると、交わることはない、
ということ。
いかに自分が正しのか、
いかに自分の方が正義なのか、
いかに自分の方が上なのか、
そういったことを 証明するための話し合いは、平行線でしかないのです。
だからね。
あさイチでもやってたけど、

NHK「あさイチ」HPより
まず相手を信頼しないことには、話し合いにならないのですね。
相手を見下していたら、それが伝わります。
また、保護者と先生の話し合いの目的が
「どちらが悪いか」
や
「相手を自分の思い通りに動かそうとする」
になると、まず進まないです。
私自身も経験しましたが、特に
「先生が謝るべきだ!!!!」
ここに 執着すると、関係がこじれます。
私自身が教師だったときには、謝る要素がない、と感じていることに対して
(反対に 私が迷惑をかけられたと感じることについて)
「謝ってください!責任を感じないんですか!?」
とキレられて、なんとお答えしてよいやら、困ったことがあります。
子どもの意思ならともかく、たいていは 保護者自身の思いだったりします。
いろんな感情が入り混じると、「子どもの思いが不在」の話し合いになります。
なのでね。
クレームを言う相手を「信頼」し「尊重」してなかったら、まあ、泥沼になります。
そして、やっかいなことに、「信頼」とか「尊重」っていうスキルは ないのです。
自分のふだんからの「あり方」が そのまんま出ちゃうの。
いくら口でいいことを言っても、なんとなく 相手をバカにしてるのが 伝わったり、
えらそうに していても、劣等感の強さが 卑屈さとして現れたり。
ごまかせないのですよねん。
でも、そう書いてしまったら 身もふたもないので、クレームをつける(つけられる)ときに まずすることは、
「まずは相手の話を 黙って最後まで聞くこと」
言い訳だと感じてもいい。
おかしいと思ってもいい。
とにかく、何を伝えたいのかに よーく耳を傾けること。
それだけでも、場の雰囲気は変わります。
途中で、
「そうなんですね」
「そう感じられたのですね」
「なるほど」
とあいづちを打てたら、さらに 話が進めやすくなります。
自分の思いを伝えよう、わかってもらおう、って
お互いに そればっかり考えているから、こじれるんです。(体験者は語る)
もしも、ここで
「ええええ~、ムリ~、先生の(または保護者の)話なんて聞きたくない!」
って思うなら、相手を低く見ているのですよ。
話を聞く価値なんかない、とか、自分の方が正しい、とか、なめられたくない、とか…ね(*^_^*)
それが「あり方」です。
あーーー、長くなっちゃったので、この辺でおしまい。
少しでも参考になれば幸いです。
いろんな意見があると思いますので、コメント欄は閉じますね。
叱るより聞くでうまくいく 子どもの心のコーチング/KADOKAWA/中経出版
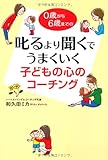
¥1,296
Amazon.co.jp
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング [ 和久田ミカ ]

¥1,296
楽天
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング 0歳から6歳までの[本/雑誌] / 和久田ミカ/著

¥1,296
楽天¥
