今日は一日東京。とある会社の取材を受けます(*^_^*)

さてさて。
ある大学教授が、このようなお話をされたそうです。
「私が 欧米で教鞭をとっていたとき、学生たちは、
『私はこう考えるのですが、先生はどうお考えになりますか?』
と質問してきた。
でも、日本に戻ってきて 学生たちに接し、そのちがいに驚いた。
『どう考えたらいいですか?』
と問いかけ、自分なりの答えを練ろうとしない。」
そうだよねえ、と思いました。
学校教育では、先生の言ったことが正解。
その正解に照らし合わせて 自分の考えを組み立てることが よくあります。
もちろんね、それが悪いということではないの。
授業には 必ず「ねらい(目標)」があって、それに向かって 教えていくから、わかりやすい。
私も教師だった頃は、理解が深まるよう、前の日にいろいろと考えて授業に臨みました。
知識や方法を教える上では、とても大事なことだと思います。
ただ、このような授業の体系が多くなると、自分の考えを伝えるのは 苦手になりがちになるかも。
どうしても「自分がどう思うか」よりも「正解はなんだろう?」と考えていくから。
特に、道徳なんかはそうねん。
暗黙の了解で「答え」が決まってるから、正直、意味あるのかな~って思うときもありました。
なんとな~く、予定調和の答え合わせ、みたいな雰囲気があります。
話は変わり、教師時代の話。
6年生の家庭科でディベートをしたことがあったんだけど、子どもたちには 新鮮だったみたい。
ひとつのお題を出して、「賛成グループ」「反対グループ」にわかれて、討論をします。
なぜ賛成なのか、なぜ反対なのか、意見を出し合うのね。
途中で 考えが変わったら、グループを変わるのもあり。
「先生!どっちが正しいのか、自分で決めていいの?おもしろいなあ」
そんなことを言っていた子もいたっけ。
正解を先生が決めない、勝ち負けもない、っていうのが 痛快だったみたいで、すごく盛り上がりました。
もう10年以上前の話ですけどね(*^_^*)
これからは、先生たちも 変わっていかねばならないですね。
「先生」=「正しい」=「異論を唱えてはいけない」
という時代は終わりました。
先月「AERA Kids(秋の号)」の取材を受けたときも、そう思ったなぁ。
記者の方が 保護者の立場で質問を投げかけてくださるんだけど、20年前なら、疑問にもならなかったことばかり。
昔は「先生がそういうのなら」と、教師の言葉に 異論をぶつけてくる方は少なかったですねん。
状況が変わってきたなあと思ったのは、15年ぐらい前かなあ。
今は さらにシビアになっているんだなあ、と 取材を通じて感じました。
くわしくは書けないのですが、9月ごろ発売の「AERA Kids」をご覧になってみてね。
あ、話がそれた。
結論はね、
・これからの教育は「正解」をゴールにするだけでは、思考力が落ちる
・「教師」=「正しさを教える人」だけでは、対応できないことが増えてきている
ということかな。
昔は 日本人の価値観が ここまで多様じゃなかったから、正しさを教えることって 大事だった。
でも、今は 日本人の価値観も多様化し、国際化の波もザブンザブン来てる。
もっと思考力が鍛えられる授業もほしいな~と思いますです。
教師の人にも コーチングを学んでほしいな。
コーチングは 思考力が鍛えられますよ。
コーチング以外では、山田ズーニーさんの本がおすすめ。
伝わる・揺さぶる!文章を書く (PHP新書)/PHP研究所

¥713
Amazon.co.jp
あなたの話はなぜ「通じない」のか (ちくま文庫)/筑摩書房
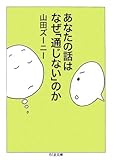
¥562
Amazon.co.jp
この2冊は、特に好き

コーチングと基本的に考え方は同じだなあって思います。
叱るより聞くでうまくいく 子どもの心のコーチング/KADOKAWA/中経出版
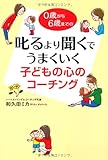
¥1,296
Amazon.co.jp
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング [ 和久田ミカ ]

¥1,296
楽天
叱るより聞くでうまくいく子どもの心のコーチング 0歳から6歳までの[本/雑誌] / 和久田ミカ/著

¥1,296
楽天
