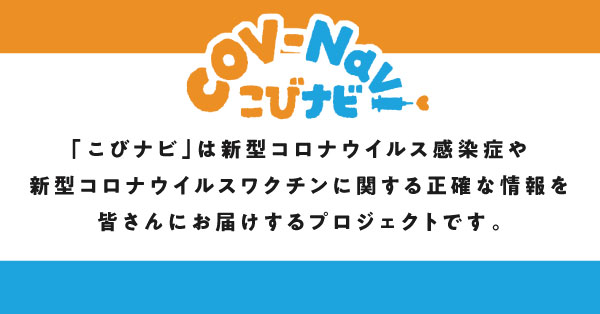2018年に新たにがんと診断された人は、980,856人です。
一生のうちにがんと診断される罹患率は、男65.0%、女50.2%で、日本人の2人に1人です。
死因の1位であり、身近で非常に怖い病気と言えるでしょう。
一方、診断と治療法は進歩しており、早期発見・早期治療で9割は治癒します。
しこり、引きつり、違和感など、1~2㎝の早期がんなら切除で済みます。
3㎝以上のがんになると、移転が始まります。
すべて国立がん研究センター2020年8月発表分データよりEXCEL集計)(()内5年生存率。大腸を、結腸と直腸に分けた場合、男女共、結腸側がやや多い。
総合で6位~は、膵臓、7位肝臓、8位悪性リンパ、9位腎臓、10位食道、11位皮膚、12位膀胱、
13位口腔・咽頭、14位胆嚢、15位甲状腺、16位白血病、17位多発性骨髄腫、18位脳・中枢、19位喉頭です。
2019年にがんで死亡した人は、376,425人です(男26.7%、女17.8%)。罹患の4割近くが死亡。

罹患より死亡が10%以下なのは、皮膚7%(5年後生存率94.6%)、甲状腺9.9%(同左94.7%)の2つ。
新型コロナウイルスの感染確認者16万人弱に対する死亡者は、1.0%です。
1.がんのリスクを高めるもの、2.予防法、3. 低い検診率と対策を説明します。
1.がんのリスクを高めるもの
●喫煙や生活習慣
喫煙は最大の死亡要因でありながら、いまだ成人喫煙率は、男性27,1%、女性7.6%(2019)です。
国民健康・栄養調査では、働き盛りの男性(40~44歳)の喫煙率は、41.1%(女性14.2%)と高いです。
タバコには、毒性物資が4000種類も含まれて、例えばニコチンは、脳神経に依存性を起こし、体内で発がん物質に変わります。
タールは、60種もの発がん物質が含まれ、肺を黒くし、体中を血液に乗って、食道、胃、大腸、口腔、鼻腔、咽頭、膵臓、肝臓、腎臓などさまざまな部位で、がんを誘発します。
WHOのニコチンスクリーニングテストは、健康保険で受けられます。以下10点のうち5点以上が依存者です。
①つもりより実際多い②減らそうとしてもダメ③減らそうとして禁断症状④イライラ、神経質、集中できない、うつ、頭痛、眠気、むかつき、脈遅い、手の震え、食欲、体重増⑤④を消すため、吸い始めた⑥重い病気でも吸った⑦健康に悪いと知って吸った⑧精神に悪いと知って吸った⑨依存の自覚⑩吸えない仕事・付き合いを避けた
日本人のがん死亡原因の20~27%は、喫煙によるものです。喫煙によるがん死亡リスクは男性で2倍、女性で1.6倍になります。
副流煙が、2.2倍もの肺がんリスクを負っています。閉経前の乳がんになるリスクは、2.6倍です。子供は、壁やカーテン、髪、衣服から肺機能に影響を受けます。
加熱式タバコは、ほぼ、たばこと同じニコチン量を含みます。
慢性閉塞性肺疾患(COPDたばこ病)は、推定患者500万人中、治療者はまだ261万人と少なく、死亡率は増加中であり、男性死因の8位です(2017)。2013年、厚労省の健康日本21(第二次)でも、COPDの認知率の向上が課題の1つになりました。空気の通り道である気道が狭くなったり、肺の動きが悪くなったりして呼吸がしにくくなり、ささいなことで息切れがします。WHOの死亡順位は4位(2008)でしたが、2030年には、30%増加し、3位になると推測されています。
生活習慣を含めたがん死亡原因別で見れば、20%以上が喫煙で12万人(肺)、2位はピロリ菌で3万人(胃)、3位はC型肝炎2.2万人、以下、酒、塩分、B型肝炎、運動不足、野菜不足と続きます(2011)。
リスク別死亡者のトップ3は、喫煙12.9万人(うち6割はがん)、高血圧10.3万人、運動不足5,2万人です(2007)。
●塩分
日本人の高い塩分摂取量が、胃がんのリスクを2.3倍に上げています。
日本人は普段の食生活で1日10gの塩分を摂っていますが、WHOの目標値は1日5g未満です。
塩分過剰から、高血圧や動脈硬化を招き、脳卒中や心筋梗塞の危険も高めます。
寒くて塩蔵品を嗜好する青森県の平均年齢が全国で一番低いのも、うなずけます。
しょうゆ・味噌など塩蔵品の汁だけでなく、麺にも塩分が含まれています。
加工食品には、多くの塩分が含まれています。
●過度の飲酒
国立がん研究センターによると、男性の場合で、1日当たりエチルアルコール量で23g~46g(日本酒で1~2合)以上を飲む人は、ときどき飲む程度の人に比べ、1.6倍、がん発生率が高くなります。部位別には、食道がん4.6倍、大腸がん2.1倍、女性では乳がんのリスクが1.8倍になります。過度の飲酒は、喉頭がん、咽頭がん、喉頭がん、肝がんなどの原因にもなります。
アルコール依存症を招き、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病のリスクも高めます。
過度な飲酒は、血液を固まりやすくし、心筋梗塞や脳梗塞の他、脳出血、くも膜下出血など出血性の脳卒中を起こしやすくなります。
●熱すぎる食べ物
食道がん、口腔がん、咽頭がんのリスクがほぼ確実と判定されています(国立がん研究センター)。
粘膜がやけどし、炎症を起こし、細胞が傷つき、がん化を促します。
あまりに熱い食べ物、飲み物は、できるだけ冷ましてから口に入れます。
●加工肉や赤身肉の摂り過ぎ
ハムやベーコン、ソーセージなどの加工肉は、大腸がんのリスクを上げる可能性が、国際がん研究機関から指摘されています。
塩分も多く、高血圧を助長します。
普段、料理や弁当で重宝の食材ですが、食べ過ぎに注意します。牛肉、豚肉、羊肉の赤肉が大腸がんのリスクを高めるには、ほぼ確実と指摘されています。
鶏や魚は含みません。
動物性脂肪やヘム鉄が多く、消化時の代謝物が大腸壁の細胞に影響を及ぼすようです。
赤肉は1週間の調理後重量で500gを超えないように推奨されていますが、日本人ではここまで多く食べる人は少なく、血液を作る鉄やビタミンB12 、亜鉛など必要栄養素も含まれます。
①魚も肉もバランスよい食生活にします。
②野菜や果物などで、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを不足しないようにバランスよく食べましょう。
●日本に多い細菌、ウイルス
B型、C型の肝炎ウイルスによる肝がん、ヒトパピローマウイルスHPVによる子宮頸がん、ピロリ菌による胃がんです。ほかにもEBウイルスによる悪性リンパ腫や鼻・咽頭がん、ヒトT細胞白血病ウイルスによる白血病や悪性リンパ腫があります。
全世界で持続性感染が関連するがんの割合は18%と推計されていますが、アメリカをはじめとする先進国では9%ほどで、発展途上国では23%となっています。
しかし、日本は、先進国の中でも高めの約20%となっていて、B型やC型の肝炎ウイルスや、胃がんのもとになるピロリ菌感染者が多さを表しています。
●環境汚染物質(ヒ素、ダイオキシン、カドミウム)、放射線、紫外線
過剰に心配しなくてもよいのですが、これらも発がん因子です。
2. がんの予防法
「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」の5つの生活習慣を実践すれば、がんのリスクは半減すると言われています。
●禁煙
禁煙すれば、その瞬間から病気が遠ざかっていきます。
発がんリスクは3分の2から2分の1程度まで下がります。
すでにメタボリック・シンドローム判定されている人には、禁煙への積極的指導がなされます。
体中に血に乗って飛び散る、がんだけでなく、脳卒中や心疾患、糖尿病、呼吸器疾患などの生活習慣病の予防や改善に役立ちます。
禁煙に遅すぎることはなく、24時間後には心臓発作の危険が低下、数日で味覚や臭覚が回復し、1か月をすぎたあたりから、咳や痰の改善が見られます。
禁煙宣言を目につくところに張り、2~3日はニコチン切れでイライラしますが、離脱症状は3~5分後に治まります。朝の一服代わりに、顔を洗う、歯磨きをする、ガムを噛むなど、すぐにできることで紛らわしましょう。
「1本だけ」の誘惑に負けないことです。
どうしても吸ってしまう人は、保険適用の禁煙外来で、内服薬、禁煙パッチ、ガムなどを使います。
●運動
国立がんセンターが45~74歳の8万人を対象に行った研究では、身体活動(運動)量の多い人は、少ない人よりも発がんリスクは低く出ました。
特に、男性では結腸がん、肝がん、膵がん、女性では、乳がん、子宮体がん、胃がんのリスクが低下していました。
次に紹介する肥満を改善することもがん予防につながります。
肥満の継尿病で、インスリンが働きにくい状態は、がんのリスクを高めると言われており、運動によって、インスリンの効きやすい「内臓脂肪燃焼系」の体質にすることが、がんに予防的に働きます。
日常体内で発生する活性酸素は、細胞を酸化させて、発がんを促します。
食事でも抗酸化物質を含むものは抗老化物質としてもてはやされます。
適度な運動も、活性酸素の発生を抑え、免疫機能が調整されます。
ただし、過度な運動をすると活性酸素の発生も高めてしまうので、注意が必要です。疲労物質と言われる乳酸も発生します。
疲れた日は翌日するとか、1日で止めてしまわず、1週間単位でならしてみて週3以上とか、とにかく続けることが大切です。
長く続けて成果が出ても、2週間しないと、元に戻ってしまうことを思い出してください。汗と努力を無駄にしない!
●肥満解消
肥満度の指標であるBMI(体重㎏÷身長m÷身長m)が増加すると、大腸がんや乳がん、肝がんのリスクが高まります。
日本の7つの研究結果では、BMIが30以上になっても、低すぎても、がんによる死亡リスクが20~30%高くなります。
中高年ではBMIを、男性で21~27、女性で21~25の範囲に体重調整しましょう。
家事や歩いて買い物などの生活活動に加え、10~20分の軽い筋力トレーニングに続けて、有酸素運動のウオーキングなどの組み合わせが有効です。
今までのブログで手を変え、品を変え、紹介してきたなかで、「肩甲骨はがし」「スクワット」「ランジ」などの無酸素筋トレに、「エアロビクス」「踏み台昇降運動」「ガニガニ体操」などの有酸素運動で、狭い室内でも完結する組み合わせが、多数、ありましたね。
◎Youtubeを有効活用しましょう。スマホの画面をテレビへ、ケーブル1本で簡単に有線接続できます。
テレビ側の入力に差します。あとはテレビのリモコンで入力切替ボタンを押すだけです。しろうとでも、できます。
スマホの画面がテレビに出ます。但し、同時に充電はできません。
スマホ機種によって異なる本体下部の接続端子の規格がUSB TYPE CかUSB microBか確認します。

Appleは純正品がよいようです。HDMI出力に対応しているケーブル(2mは欲しい)を選びます。
6Z-HGTU-DT63が、多機能型TypeCでAmazon1980円です。
下の記事が参考になります。
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/sim/gurashi/tips_0039/
●減塩
塩蔵品の摂り過ぎは、胃がんのリスクを高めます。
そもそも日本人は、日常生活で塩分を1日10gと、WHO目標の1日5gの2倍摂取しています。
意識して、何か1品に濃い味を集中させ、他を塩分控えめにしましょう。
しょうゆ、みそ、つゆなどの調味料には、塩分が多く含まれます。次のことも実行しましょう。
①調味料は、毎回、計って使います。
目分量では、つい使いすぎます。調味料そのものを、減塩タイプにしましょう。
②味付けは、酸味・香辛料・香辛野菜・うまみを活用します。
素材の持ち味を生かし、酢やこしょう、唐辛子、みょうが、しょうが、わさび、かつお、昆布、煮干し、などから取ったダシで風味を増せば、塩分控えめでもおいしく食べられます。
③汁物は具沢山にし、塩の溶け込んでいるスープやみそ汁を減らします。
④麺類のスープ・汁は残します。
●適度な飲酒
厚生労働省は、「100%のエチルアルコール10g=1ドリンク」とし、男性で1日平均4ドリンク、女性で2ドリンクを超えないように、しています。女性は、飲酒の影響を受けやすく、注意が必要です。
適度であれば、血液中の善玉コレステロールを増やし、血液を固まりにくくし、動脈硬化を防ぎ、血栓という血液の固まりができるのを防いで、心筋梗塞や脳梗塞を防いでくれます。
本当にチビチビと舐めるように、少量、泡盛を飲むのが、沖縄の最長寿だった人の秘訣でした。
もし、飲み会で適量を超えてしまったり、毎日飲んでいる人には適量を守るのは、難しいですが、「超えたら数日は我慢する」など1週間単位で、適量を守っていきましょう。つまみには、唐揚げやフライなど脂っこいものや締めのラーメンで食べすぎるのを避けるため、前もっておにぎり1個食べておきましょう。
つまみには、低エネルギーで食物繊維の膜でアルコール吸収を抑え、分解する肝臓の負担を減らす、豆腐、枝豆、野菜などを選びましょう。
また、飲酒の前後には、コップ1杯の水を飲んで、水溶性のアルコールを流しだしてしまいましょう。
●細菌、ウイルス除去
がんの原因となる細菌やウイルスを除去しましょう。
B型、C型の肝炎ウイルスによる肝がん、ヒトパピローマウイルスHPVによる子宮頸がん、ピロリ菌による胃がん、EBウイルスによる悪性リンパ腫や鼻・咽頭がん、ヒトT細胞白血病ウイルスによる白血病や悪性リンパ腫を発生させています。
日本は、先進国の中でも高めの約20%の持続性感染となっていて、B型やC型の肝炎ウイルスや、胃がんのもとになるピロリ菌感染の有無を、自主的に検査を受け、除去することが大切です。
3.低い検診率と対策
●低い検診率
がんは1981年以降、日本人の死亡原因1位を占め、2018年には、約38万人ががんで死亡しています。
急速な高齢化でがん罹患率は高まる一方、診断と治療法は進歩しており、早期発見・早期治療が可能になっています。
全がんの5年生存率は平均6割で、早期がんなら、9割は治癒します。
1~2㎝の早期がんなら、切除で済みます。3㎝以上のがんだと、転移する可能性が出てきます。
しこり、引きつり、違和感などあったら、早期診察が大切です。
しかし、自治体の対策型がん検診は、受診率は40%台と高くありません。東京23区内では、10%台のところもあります。
「忙しくて時間がない」「大して重要でない」と平気にアンケートに答えています。

残念ながら、健康保険での胃・大腸・肺・乳房・子宮頸部の5大検診は、大まかながんの疑いの振るい分けしか行われず、精密検査は含まれていません。(40~69歳、国立がん研究センター)
●対策
要精密検査となった場合に初めて自費で(保険適用)行えます。
①胃がんのヘリコプター・ピロリ菌の感染治療 / 委縮性胃炎→抗菌薬による除菌治療
②大腸がんの内視鏡検査(女性に多い)
③肺がん末消型の胸部CT検査・気管支鏡検査、経皮/胸腔生検(初潮が11歳未満、閉経が55歳以上、出産が30歳以上、出産経験がない、遺伝)
④乳がんの超音波検査やMRI検査・針生検
⑤子宮頸がんの膣拡大鏡検査によるHTV(ヒトパピローマウイルス16型、18型)感染の有無検査→陽性ならワクチン
⑥5大がん検診ではないが、B型・C型肝炎ウイルス検査/肥満・アルコール摂取者への肝がん経過観察→抗ウイルス療法、肝庇護療法、免疫療法、HCVの体内から排除/血液検査・CTやMRI検査
例えば、ストレスの多い現代生活の中で1度や2度、胃潰瘍になっている人は多く、自然に直った後の胃襞の凸凹にピロリ菌は、2人に1人の割合で感染しています。
自治体の対策型がん検診には、ピロリ菌検査は含まれていないため、胃内視鏡検査の際、申し出て+αの自費負担で胃の襞に潜むピロリ菌の生体組織をつまみとって検査します。
もしくは、近年は主流のチューブ式ビニール袋に呼気を吐く、尿素呼気検査をします。
ピロリ菌がいたら、胃酸分泌抑制薬と2種の抗菌薬を1日2回、7日間服用し、2週間経過後、ピロリ菌が除菌できたかどうか、もう一度、呼気検査をします。
1回目の除菌療法の成功率は約80%で、ダメなら、抗菌薬の1つを変え、二次除菌療法を行えば、ほとんどの場合、除菌できます。
厚生労働省は2013年に「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」に対するピロリ菌除菌療法を保険診療で行うことを決めましたが、胃炎や胃潰瘍になっている最中でないと適用されません。
WHOでは、2005年に、たばこ規制条約が発効し、世界で禁煙法が広がっています。
2004年に日本もこの条約をすでに批准しています。アメリカでは、州単位で屋内の全面禁煙化が進んでいます。
日本も、2016年にがん対策基本法が改正され、国、自治体、医師会、本人ががん対策の充実、強化に努力するべき責務が明記されています。
受動喫煙の対策を強化する改正健康増進法が2019年から2020年にかけて施行されました。
がんでなくならないように積極的に最善の治癒をする努力義務があり、国民はがんに対する正しい知識を持ち、予防する責務があります。
最後に、がん研究振興財団の、がんを防ぐための新12カ条をまとめとして、掲げます。 以上です。
庭はヤブミョウガが、白い花を一斉につけています。ミョウガのように
香ばしい花の芽を、雨後の土から出すことはありません。ただ、
葉っぱがミョウガに似ているだけの多年草の雑草です。
母が大事に育てていたトレニアが、庭の隅で咲いていました。
一生懸命に暑いときも雑草を抜き、花の種を植えていました。
地味で可憐な花ですが、暑さに強いです。残っていました!
ちょっとピンボケになっちゃけど、鮮やかな青色の花の
ツユクサです。雨後の露の滴った庭に咲きます。
太い株になって越年もするようになりました。普通は1年草。
夕刊を取りに行ったら、郵便受にヤモリがへばりついていました。
ちゃちょの築64年のような古い木造家屋にいて、
蚊やゾウリムシなどを食べてくれる。かわいいよ。
見つけると縁起がいいって言われてるよ!やったね!
コロナは新規感染者数こそ減ってきているけど、横ばいの累積患者数。
病床ひっ迫が解消できずに、家庭内感染や自宅孤独死も
増えてるね。9月12日の緊急事態宣言は、数県減るだけで30日まで延長。
若い世代の感染が増えています。
こんなときこそ、心を冷静に、SNSの誇大なデマに惑わされずに、ワクチン
打とうね!肩への筋肉注射だから2~3日しびれるけど、経過観察フォロー
があるから大丈夫。良心的な医師集団が立ち上げた「こびナビ」でチェックしてね。
みんな、元気でね。じゃ。またね。