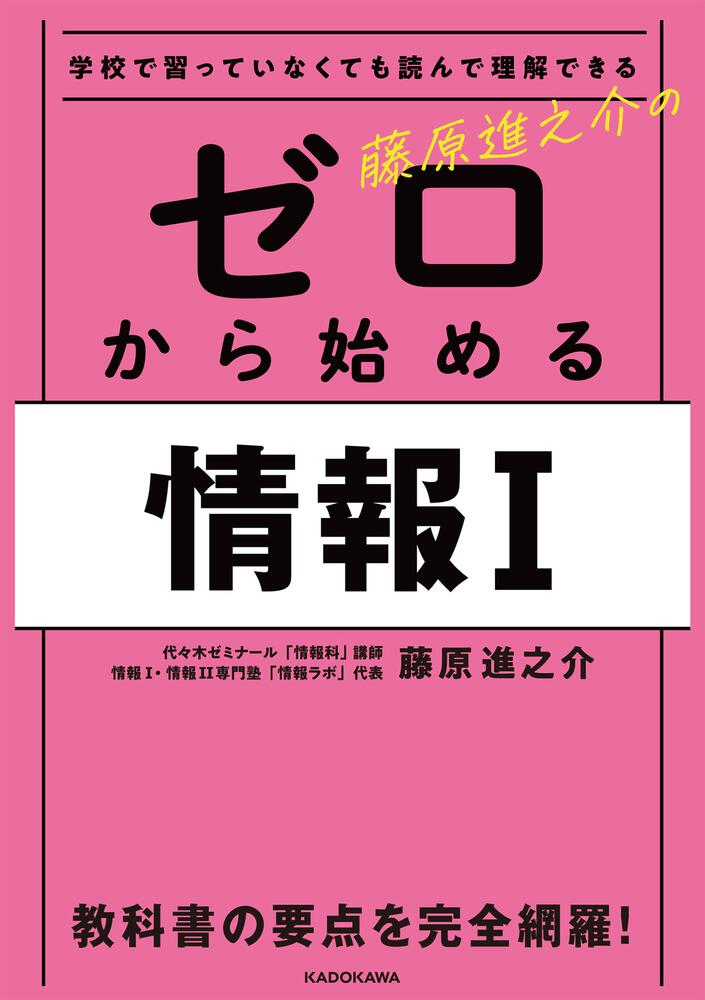*あくまでも個人の感想です。
2025年から、大学入試では新課程に対応した内容になります。共通テストでは文系の数学の範囲が増えるとか些細な変更点はいろいろありますが、自分は文系理系問わず全部勉強しろ派なので割愛します。
そんなわけで、新課程の共通テストの目玉といえば、新設される「情報I」だと思います。ほとんどの国公立大学では共通テストで必須科目になっているので、国公立大学志望者は試験対策をすることになります。どういう科目なんだろう、と自分も興味があるので、高校生向け参考書を買って読んでみました。
買った本
学校で習っていなくても読んで理解できる 藤原進之介の ゼロから始める情報I
内容
第1章 情報社会の問題解決
第2章 情報デザイン
第3章 コンピュータとプログラミング
第4章 情報通信ネットワークとデータの活用
総論としては、大学1年生向けにやる情報処理の内容かな?という感じです。理系の学生をやるなら、これくらいは基礎知識として知っておいて欲しい、ということを詰め込んだ科目と言いましょうか。文系の学生に必要か?と言う人が出そうですが、入学試験に出さなかったら勉強しないでしょう(笑)??
第1章はメディアリテラシーや情報セキュリティのお話など。社会人をやっている人は昨今、所属組織から教育されるやつです。働いている社会人にとってはほとんど常識的な内容ですが、これを高校生が学ぶ意味は充分にあると思います。
16節の「問題解決の考え方」にはPDCAサイクルなんかも出てきたりします。賢い高校生なら、自分の受験勉強にもPDCAサイクルを応用できるかも?!
第2章は10進法、2進法、16進法の話に始まるデジタル技術のイントロ的な内容です。2進法の理屈が分からない人には理解不能な話が多いですが、今や中学受験でも算数で2進法の問題が出題されるので、中学受験生に馬鹿にされないように頑張りましょう!
第3章はコンピュータの構成や動作原理、プログラムのお話です。第2章で出てきた2進法の考えを実体ある機械で使う為の、論理回路(AND、OR、NOT、NANDなど)の話が出てきます。このあたりで数学の苦手な学生は挫折しそうな気がします(苦笑)。
後半はプログラムの考え方の内容ですが…これって紙ベースで勉強するものではなく、実際にプログラム実習しないと理解できないのでは?と自分は思います。自動車教習所でどれだけ座学をやろうが、実際に車を運転しないと身に付かないようなものです(笑)。
第4章はネットワーク技術や統計解析のお話。通信プロトコルの話など、自分の理解が怪しいものがいろいろありました(苦笑)。統計解析の話は、昨今は中学高校の数学でこの分野が重点化されているので、数学で理解していれば問題ないと思われます。
以上、つたない感想文を書いてきましたが、共通テストの試験科目としては、普通の高校生が片手間にやって高得点が取れる科目ではないと思います。数学の素養がある生徒にとってはそこまで難しくないけど、高校で文系を選ぶ学生には結構ヘビーな科目になるだろうな〜という感じです。まあ頑張れ、としか言いようがありませんが。
試作問題のリンク
P.S.
ホントに「数学こそが正義」の時代が来るのかな、という気もします(笑)。