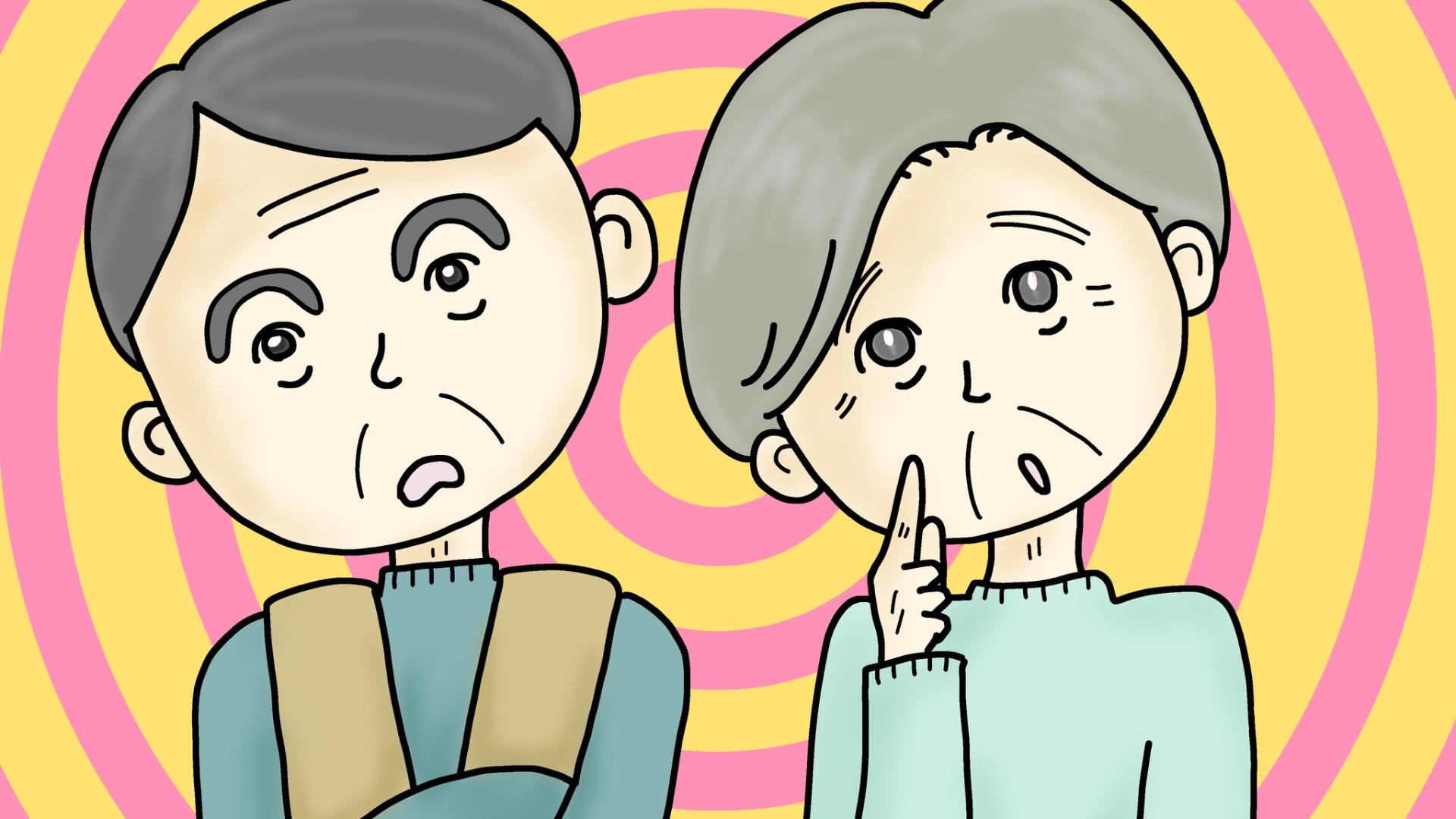(1)認知症という言葉の魔力
利用者や家族と話していると、何か気に入らない事をされるだけで「認知症」というレッテルを貼りたがる。分からなくはない。認知症は高齢者のメインテーマといえるものだし、言葉の魔力に踊らされる人は多いだろう。近所の話題でも、あそこの家の人が認知症になって、ああでもない、こうでもないという話題はもはや日常との言えるのではないかと思う。
それ程までに認知症という言葉は魔力があるのだろうか?
答えは「YES」である。
それも一般的に認知症というと、昔の人は「ボケ老人」という言葉があったように、惚けて無気力、忘れっぽくなったと思えば急に怒り出すなどの、人格も以前と変わってしまったという事をイメージすることが多いのではないだろうかと予想する。
そしてその先にはどこかに押し込められて死ぬまで糞尿にまみれ、なんてことを想像する人もいるのではないかと思う。そこまで考えれば、認知症というのは恐ろしい。
(2)性格や生き方が出る
さて記事のように「ささいなことを気にする人」「怒りやすく、短気な人誠実でない人」「協調性のない人」「生活習慣が乱れている人」「自分で全てこなしてしまう人」が認知症になったら苦労する性格として挙げられているが、これらは認知症でなくても「生きにくい」人であろうと思う。
今回、認知症というのがテーマとして挙げられているが、精神病というのは今までの性格が凝縮して表に出てきた症状が多いと思う。
私の利用者でも起こりやすい人がいる。本人は「家系で癇癪持ち」と自分が癇癪持ちであることを正当化しているが、はっきり言えば他人を攻撃することに正当性はない。
その時の会話で「分からなくなったら癇癪起こすのも理解でいるでしょう?」と言われたが私の答えは「NO」である。
一人でいるときに勝手に起こるのは良い。しかしその矛先が他人に向くのはいかなる場合でも正しくないと思う。それを介護の研修では「そういう人だと理解して」などと耳障りの良いことを言うが、理由もなく怒鳴られたり、場合によっては暴力を受けるという事を許容する必要はない。例え認知症であったとしても、他人に暴力をふるったら犯罪として裁かれるべきだと思っている。
そういう人は逆に「高齢だから」「認知症だから」という言葉を巧みに使う、いわゆる自分は弱者だから許されるだろうという甘えがある。よくジャーナリストでも「弱者の代弁者」などという人がいるが、そういう人は弱者を盾に自分の事しか考えていない、弱者ビジネスであると思う。福祉というのは弱者救済の仕事でもあるが、なんでも受け入れるべきではないと思う。
(3)穏やかな性格、云々
記事にあるような性格というのは、大体において真面目に生きてきたとか、ちゃんとしているという人だろうと思う。人間関係の中で生きてきたわけだから、例え「協調性がない」とはいえ、大なり小なり人間関係を意識していると思う。つまりこれらの人は生きることに諦めていない人と思う。
例えば、どうでもよいと思っている人については、その人が何をしようが関係ないだろう。どうでもよいと思っていることについて、どうなっても関係ないと興味もないだろう。
つまり年を取り、死に近づくことは生きることの執着を無くし、些末なことはどうでもよいと割り切るという事なのだろうと思う。穏やかな性格というのは、そんな些細なことは気にしない、人生の大局を見れていることだと思う。しかし人間関係の中でその境地に達するのは難しい。人からの非難や評判はどうしても気になるし、人に迷惑をかけたくないという気持ちも出てくる。それは教育上、絶対に必要なことであるが、現役を終え、死への道を進むうえでは、それも手放していかなくてはならない。
穏やかに生きるというのはそうした執着を手放すことなのだと思う。
いつ死んでもよいという人は無敵であると思う所以はここにある。