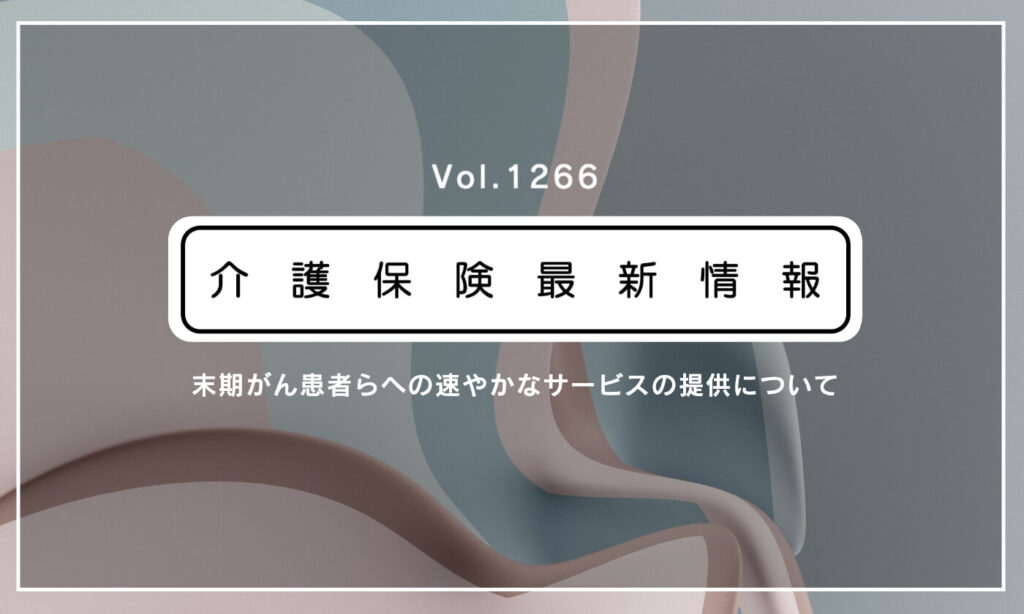(1)調査は必要か
介護保険サービスを受ける際には要介護認定を受ける必要があり、55項目の調査項目がある。
多分、大したこと無いよなと思う人が大半であろう。しかし高齢者にはそれなりの負担がかかるものだ。
それでも介護保険の財源は無限にあるわけではないから、要介護度によって給付の上限額が決まるし、要支援などは給付制限もある。
ケアマネとしては、要介護度に関わらず介護サービスの量が必要な人もいれば、要介護度が重くてもさほど必要のない人もいるから、ある程度任せて欲しいとも思うが、そうすると不正請求の温床にもなりかねないという痛しかゆしの所もある。
(2)認定調査の概要
要介護認定には以下の群と項目がある。
第1群 身体機能・起居動作 13項目
第2群 生活機能 12項目
第3群 認知機能 9項目
第4群 精神・行動障害 15項目
第5群 社会生活への適応 6項目
その他「特別な医療」として透析やストーマの処置、気管切開などが項目となる。
調査員は役所のほか、委託を受けた所、はたまた我々ケアマネも研修を受けて調査を行う。
(3)調査の問題点
①高齢者のハッタリ
高齢者の中には調査員が来ると聞いて頑張ってしまう人も少なくない。出来ない事なのに「出来ます!(キリッ)」と言われると、家族の同席が無くその時の情報が無いと自立になってしまう。そうすると要介護度は正確に出ない。
②要介護度は選べない
家族や医師、我々ケアマネも「要介護〇くらいは出るかな」と思うし、主治医意見書に「要介護〇程度がと相当である」みたいな事を書かれる医師もいるという。しかしそれは審査会が決めることでガッカリという事も良くある話だ。
要介護〇を見込んで「この位ヘルパーさんが来てくれるかな」と思っていても低ければそれだけ着てはもらえないという事も。
③判定が遅い
ひどい時には有効期間が終わってから判定が下りることもある。役所では毎日審査会が行われるようだが、それでも追いつかないというのが現状のようだ。
そうすると我々ケアマネはどう動いてよいか予測しながら「暫定プラン」を作ることになるし、それが無いと減算の対象にもなる。
こちらとしては判定が下りないのは役所の責任で所と言いたくなるのだが、それは通らなないという理不尽なことである。
さらに、要介護と要支援の狭間にいる人はどうすれば良いか判断に苦しむ。大体は要介護の低い方で考えるが、サービスをいっぱい使っている人は判定が下りるまで我慢してもらい事になる。
(4)更新は必要かという根本問題
コロナ禍では調査員の訪問も行わず、前回の判定をそのまま使うという事になった。要介護度の変更の時だけ調査員が動く形になったが、更新が行われない事で特に問題は無かったと思う。
確かに判定が重くなって使えるサービスが変わるのに、ケアマネの判断で申請しないとなれば問題だが、それは解決できると思う。
個人的には必要な時だけ調査してもらえばよいのではないかと思うけど。