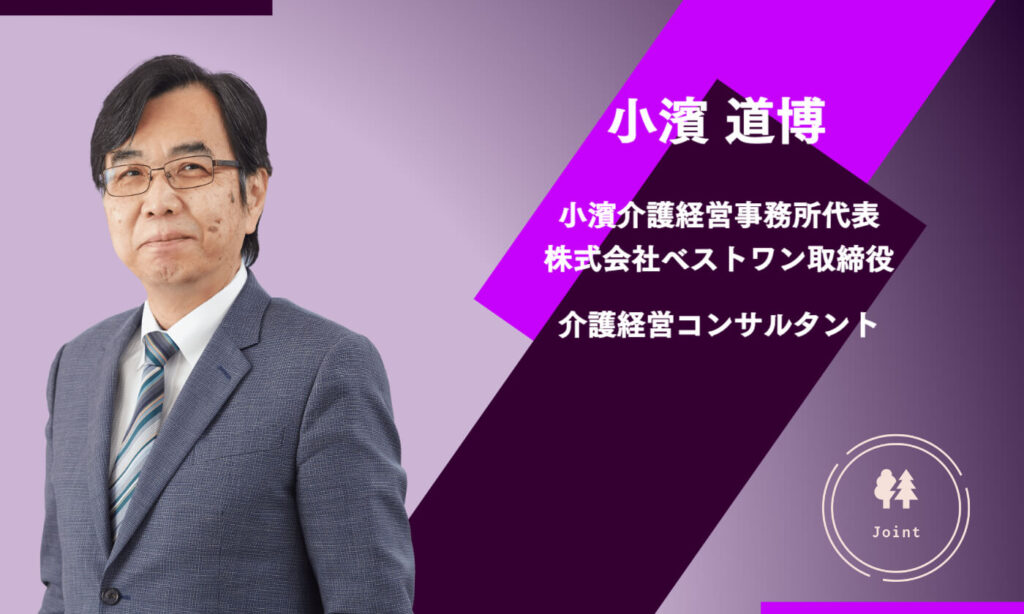(1)誰のためのルールか
介護事業というは保険事業だからきちんとルールに則って行うのは原則。ルールを守らなかったらそれだけのペナルティが課せられるのも当たり前。
でもそのルールとやらは何を基準に作られたものだろうかというのは大いに疑問である。
例えば寝屋川市のケース
このケースはケアマネの契約時に「複数の指定居宅サービス事業所を紹介するよう求めることができる」と運営基準で定められていたものを「多様な・・・」となっていたため、数千万円の返戻を求められ裁判になったケースである。
うん、違いは分かりますか?
「複数の」を「多様な」に言い換えただけで利用者に何か不利益を与えますか?という事。
(2)言葉尻を捉え、事業所の責任にする
さらに我が社であったのは、書類を掲示しなければならないものをファイルにまとめといておいたことが「閲覧」という事で指摘を受けたことがある。
運営指導でタチが悪いのは、こうした指摘事項について行政処分の前に過誤という形で返金させることだ。
ちなみに我が社でも指摘事項については役所に法的根拠の提示を求めたが、全く応じてもらえなかった。
行政の側はとにかく処分する事しか考えていない。
そう言うと「そんなことは無い」と反発が来そうだが、指導マニュアルに「事業者がきちんと納得する事」と書いてあるのに説明もしないのは事実である。さらに言えば、今回指摘していなくても次回は指摘するかもしれないという事も頻繁にあるようだ。
(3)戦う姿勢が無ければ去るのみ
こういうことに対しては、例え無謬性と言われる行政でも争う姿勢が必要なのだろうと思う。
誰のためのルールかと言えば利用者の為である。その利益を侵害していないのに丸々報酬を返せと言っているのだ。
こういうことだからやる気も失せる。
介護の世界は頑張ってもこうした下らない事で苦労も水の泡と消える、報われなくない世界なのだ。