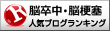
脳卒中・脳梗塞ランキング
まとめ−8−1‐3Мメソッド−原因に対する治療方法の発見
昨年の2024年10/27に気付いたことですが、麻痺側の骨盤が起きて、腰・お尻・背中下部の張り・コリが消えて来ると、腰(重心移動・臍下丹田)から歩行が始まって来る感じになりました。ぶん回し歩行の時は、腰の動きがないので、足(太もも筋肉)から歩行しようとしていたのです。
これか、ギコチない歩き方の一番の原因だと思います。
そして、更に腰(重心移動・臍下丹田)から歩行が始まるには、腰・お尻周りの改善が必要不可欠だと体験したので理解しました。
健常者では当たり前の事でしょうが、脳卒中経験者の回復過程で体験した人でないと分からない感覚だと思います。
参考→動画−入院生活(約2018年前)の歩行→現在の歩行(散歩・2023年07/03)
https://ameblo.jp/hapikuni/entry-12810612802.html
参考→
2−わんコと一瞬の大阪旅行−2の2
(歩行動画あり・2024年10/31)
https://ameblo.jp/hapikuni/entry-12873356922.html
参考→まとめ−6(正常歩行への回復についての考察)
https://ameblo.jp/hapikuni/entry-12852841716.html
⭕️前回のブログにも記載しましたが、
骨盤起こし+セルフ整体・腰回され体操・動的ストレッチは重心から(腰から)の歩行始動するためにあったのだと思いました。
意図せずに適っていたのです。
参考→3Мメソッドまとめ−3+ぶん回し歩行の完全回復に直結する方法動画あり(私的考案)
https://ameblo.jp/hapikuni/entry-12863321174.html
しかし、この重心移動から歩行を開始出来るようになる回復過程で
一度、1日ほど離れた部位の代償性の痛み(私の健側の左腰)も経験しました。
ここで、麻痺側と健側の腰痛について考えてみます。
腰痛には、時間と部位の観点から2種類があります。
①疲労している腰の腰痛(超回復のための筋肉痛=麻痺側の腰)
②離れた腰の部位の腰痛(代償性の筋肉痛み=健側の腰)
……………………………………………………
① 腰痛(私の麻痺側の右腰)は、腰が回復して、次の段階に進むために必要な超回復の筋肉痛だったと思います。
●備考→超回復→筋肉の部位ごとに超回復の時間は異なりますが、胸筋、背筋は72時間、上腕二頭筋、上腕三頭筋、三角筋は48時間、腹筋やふくらはぎの筋肉は24時間程度で回復します。
今回は右腰の麻痺側の筋肉痛は、筋肉使用後の疲労による炎症後に起きる筋肉が再生される前の超回復のための痛みだったと考えられます。
② 他に離れた部位の代償性の痛み(私の健側の左腰)もある場合があります。
●備考→代償性=身体機能の一部が失われた場合に、本来その機能を果たす部位とは別の部位が、その機能を補完するように機能すること。
以上ですが、それでは何故に代償性の痛みが出てしまうのか?
という事を考えてみます。
ズバリ、私は、分離運動が出来ない身体の状態で共同運動になってしまい離れた部位に代償性の痛みが発生するのだと考えています。
もっと言えば、脳卒中経験者の運動障害の歩行を、「歩行歩行分析に基づいて動作訓練だけで治そう」とするから発生するのでしょう。
先ずは、筋肉を解し柔らかくして関節の可動域を拡大してから、動作訓練を実施すると代償性の痛みも失くなると思います。
まとめると、
①麻痺側の筋肉が硬く短縮化した状態→解決方法は、ビューティーローラーで筋肉を解し柔らかくする事が重要です。
②関節の可動域が制限されている状態→解決方法は、ストレッチで筋肉を伸ばして関節周りも解し柔らかくして可動域を拡大する事が重要です。
You Tubeなどで正常な歩行にするには?という動画が多数ありますが、いづれも、筋肉を徹底的に解し柔らかくしてからという事の言及もなく、歩行分析に基づいて動作訓練で治そうとしていますが、歩行の完全回復は難しいでしょう。
骨盤を起こしてから、腰・お尻・背中下部・脚の筋肉などのコリ・張り・麻痺感を失くせば、脳卒中の程度にもよりますが、歩き方をイメージ出来る脳卒中経験者であれば、自然と正常歩行になって行くと信じています。
◎分離運動と共同運動の例→
例‐脳卒中発症後は麻痺側の肩を挙げる動作をやると肩だけ挙げること(=分離運動)は出来ずに、肩・腕・肘も一緒に動く(=共同運動)ようになってしまいますから、この間違った動作の情報が、脳にインプットされるから止めた方が良いという意見があります。
私が考えると、麻痺側の手足が動くようになるということは、弛緩性麻痺後の期間が過ぎて、脳からの麻痺側の手足を動かす運動指令が出て、錐体路(皮質脊髄路)・錐体外路が機能して来ていることを意味しますから、短縮化して硬くなった筋肉(拘縮)を是正しないから、肩だけという分離運動が出来ずに、共同運動になってしまうのです。
脳の可塑性は、脳が支配している麻痺側の短縮化した筋肉を解し柔らかくして動き易い環境にする事が一番重要です。動けない状態で動かそうとするから無理なのです。だから分離運動が出来ずに共同運動になってしまうのです。
つまり、スムーズに肩が上がるには、
①硬くなり短縮化・拘縮した筋肉を解し柔らかくすること
②肩関節と周囲の関節(肩甲上腕関節・肩甲胸郭関節・肩鎖関節・胸鎖関節・脊柱)がスムーズに動く必要があります。
周囲の関節(特に胸鎖関節)の可動域が制限されているから共同運動になってしまうのであって、胸鎖関節の可動域拡大と肩腕の筋肉を解し柔らかくすると、肩だけ挙げるという(分離運動)も可能になるでしょう。
次に、
◎歩行分析による意識的な歩行動作訓練では回復が困難な理由は、
正常歩行のメカニズムを分析して知識としてなら意味があると思いますが、その知識を意識し続けて歩行することは困難だからです。
理想は充分に麻痺側の下半身と腕の筋肉を徹底的に柔らかくしてから、始めは意識した正常な歩行訓練をして、その際に悪癖や足を痛めないように注意して実施します。そうすると後に無意識でも出来るようになると思います。
更にその上、下行性連動(頭から脚へ下への方向)として腕の振りが良くなると歩行動作も良くなるでしょう。
何故なら、一度歩こうと行動を始めると後は無意識にコントロールされて歩行が進むからです。
おそらく、一見すると正常に見える意識した歩行は無意識になると、麻痺側の足・お尻の硬い筋肉と麻痺側の腕が後方へ振る動作が出来ない事が邪魔をしてぶん回し歩行に戻るからです。
以前にも書きましたが、一度、歩こうと意識すると、後は、無意識で、大脳の一次運動野や運動前野と呼ばれる部位と小脳の間の「ループ回路」が歩行を担うからです。硬い筋肉での歩行は、無意識になった途端に、筋肉の硬さが動きの邪魔をしてぶん回し歩行に戻ってしまうでしょう。
参考図→大脳〜小脳ループ回路・ぱられるゴリラ
また、
私の経験では、歩き方の訓練や歩き方のコツなどでは完全麻痺からの完全回復は治らないと思います。
軽度〜中程度の最初から麻痺側の手足がある程度動く人には、
(筋肉を解し柔らかくするともっと早期に回復するでしょうが、、)効果があると思います。
しかし、私のように医師の診断で、右半身の感覚無し、右手足が全く動かすことが出来ない右半身完全麻痺から、歩行訓練や歩き方のコツによって完全回復をさせる事は困難でしょう。
実際に全く麻痺側の手足が動かないで車椅子状態の完全麻痺からの完全回復の脳卒中経験者は殆どいないことからも分かります。
私は極端に言えば、筋肉を解し柔らかくするだけでぶん回し歩行などのギコチない歩きは回復すると思っています。
理学療法士さんのリハビリの指導によって杖無し歩行が出来るようになったら、スポーツジムでビューティローラーを使用して筋肉を解し柔らかくする事が完全回復への道に繋がる1つの手段だと思います。
次回は、私の最近の歩行姿の動画を撮影してアップしたいのですが、寒い日が続いていますので、早朝、わんコとの散歩の時にコートを着ているために脚を見せる動画の撮影はなかなか出来ていませんが、近々、アップする予定です。
自分では、身体の動きも感覚も、完全回復まで後一歩の段階に来ていると思っています。












