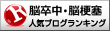
脳卒中・脳梗塞ランキング
脳卒中(脳出血・脳梗塞)と有酸素運動・無酸素運動‐2+脳の可塑性
一方、
無酸素運動は酸素を使用せず短時間で行う強度の高い運動です。
無酸素運動は酸素を体内に取り込まずに、強い負荷を短時間・継続してかける運動のことです。筋トレや短距離走、ウェイトリフティングなどです。

参考図→無酸素運動‐澤木内科糖尿病クリニック
●筋トレを行うと、筋肉は激しい運動によって収縮して硬くなります。
速さで言うと→
6.4km/h以上で走るのがランニングです。 一般の人なら息が切れるくらいの速さで走るので、ランニングは無酸素運動になります。
最大心拍数で言うと→
カルボーネン法では「220-年齢」が最大心拍数ですから、最大心拍数の40~60%の心拍数で走るジョギングは、効率的に脂肪燃焼が行われる有酸素運動になります。
60%以上はランニング・マラソンです。ランニング時に無酸素運動となるのは、最大心拍数80%以上のかなり負荷の高い運動です(かなりキツイ!という状態です)
マラソンランナーはマラソン後の翌日は足がパンパンに張り硬くなっているそうで、足の筋肉を解し柔らかくするマッサージをしているそうです。無酸素・有酸素運動に関わらず
筋肉は疲労すると硬くなって行くのです。
マラソンなど過酷な激しい運動をすると筋肉の中では酸素が不足し、酸素を消費しないエネルギー代謝(=嫌気性代謝)が起こり、筋肉の中にあるグリコーゲンから筋肉のエネルギーであるATPを生成します。この時に生成過程で乳酸が作られます。
カルボーネン法では「220-年齢」が最大心拍数ですから、
例えば、60歳の最大心拍数は160となります。
カルボーネン法での無酸素運動の心拍数は、
心拍数が220−(あなたの年齢)=(答え)
(答え)の最大心拍数(80〜100%)=答え✕0.81〜1.0=あなたの最大心拍数(無酸素運動)
例) 60歳の人
220−(60歳)=160
160×81%=129.6(無酸素運動)
160×100%=160(無酸素運動)
129.6〜160この範囲で運動すると無酸素運動になりますが、
人間の心拍数は一般に1分間に60〜100回です。 興奮したり運動すれば健常者では120〜130回位になることもあるとのことです。
脳卒中経験者は安全に運動するために60歳の経験者は120〜130以下で運動する事が望ましいのかも知れません。
無責任ですが、私は心拍数を測りながらトレーニングした経験がないので分かりません。
それで、負荷(重り)を上げて、何とか出来るなら、心拍数が上がっていますので無酸素運動の目安としています。
無酸素運動をすると、一部のタンパク質が分解されます。そして、筋肉に負荷をかけ続けると、筋肉の再生が促進され、筋肉量や筋力の増加に繋がります。無酸素運動後、筋肉はタンパク質合成を始めますが、食事やプロテインからタンパク質を取り入れることで、このタンパク質合成をより促進することができます。
タンパク質合成の場面では、サテライト細胞と称される特別な細胞が活躍しています。
サテライト細胞は普段、筋細胞の近くで活動せず休止していますが、無酸素運動を行うとサテライト細胞も活動を始めます。
活性化されたサテライト細胞は無酸素運動中に損傷した筋細胞と結合し、増殖を繰り返すことで筋肉の再生に必要なタンパク質の合成を手伝います。
限界に追い込む動作を繰り返すことで筋肥大に繋がります。筋肥大は言葉通り筋肉が大きくなることですが、厳密にいうと筋肉を構成する筋繊維が損傷と修復を繰り返しながら太さや重さが増加することを指します。
筋肉量の増加がもたらすメリットには基礎代謝量の増加が挙げられます。
基礎代謝量とは、何もせずとも消費される生命維持(呼吸・体温維持など)に必要な最小限のエネルギーのことです。
そのうち骨格筋(運動によって主に鍛えられる随意筋)が消費するエネルギー量の割合は約20%とされています。そのため、筋肉量が増えると自然に基礎代謝量も増えて太りにくい体質となり、肥満などの生活習慣病予防にも繋がります。
筋トレは筋肉の機能と量のどちらも向上させます。そして、筋トレは加齢による筋肉量の減少(サルコペニア)を防止する効果も期待できます。
サルコペニアは様々な疾患のリスクや生存率などと密接に関連することが明らかになっており、筋肉量の維持は健康維持において重要です。そして、筋トレはその大事な筋肉量を維持・増加させる運動と言えます。
無酸素運動は、筋力を向上させますが、やり方を間違えると筋肉が傷付き硬くなるので注意が必要です。
脳卒中経験者など体力に自信がない人は、軽い有酸素運動【私は心拍数が上がらないビューティローラー(受動的に筋肉が動かされる運動様の作用あり)が一番の選択】から始めるのがおすすめです。
筋トレなどの無酸素運動の程度(ゾーン)は、最大心拍数の80%以上が目安です。
●5段階の心拍ゾーン
心拍ゾーンは最大心拍数を100%としたとき、50~100%の範囲で5段階に分類できます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
① 50~60%
呼吸が乱れず普段どおり会話できる→有酸素運動の基礎作り
② 60~70%
少し呼吸が乱れるものの会話はできる→心肺機能向上の基礎作り・高強度トレーニング後のリカバリーにも最適
③ 70~80%
呼吸が深くなり会話が困難になる→心肺機能向上・持久力向上
④ 80~90%
呼吸が荒くなり会話ができない→無酸素運動能力向上・スピード向上
⑤ 90~100%
呼吸するので精一杯→瞬発力向上・筋持久力向上
ゾーン③と④が有酸素運動と無酸素運動の境目です。
脳卒中経験者は、もっとハードルを下げる必要があるでしょう、
一方で、筋トレなどの無酸素運動(エネルギーを作る際に酸素を必要としない)では、エネルギー源として体内の糖を使います。
無酸素運動は短時間で大きな筋力が発揮され、瞬発力や筋力などが向上しやすいです。
トレーニングをおこなう目的が筋肥大の場合、
筋肥大(筋力アップ)には、
エネルギー源として体内の糖(筋肉に蓄えられている糖質の一種である筋グリコーゲン)を使う無酸素運動が効果的です。
参考→Glico+ULLR MAG+名古屋の整体院・赤月堂+東京都千代田区神田・かんだ駅前整骨院+
VALX
参考図→有酸素・無酸素運動エネルギー‐東武スポーツクラブ プレオンせんげんだい
何度も書いたように脳でトラブルを起こしたことは不幸ですが、幸運でもあるのです。
それは脳の可塑性(環境に応じて変化する能力)です。
私は、脳の可塑性により、脳は筋肉を動かし、マウントを取りたがっていると考えています。
ビューティローラーを使用して、筋肉を解し柔らかくする事により
末端の線維化(拘縮)で硬くなって動けずにいる状態から、動き易い環境にして、邪魔されて回復が出来ない状態から解放させて
且つ、筋肉がなるべく硬くならない(疲労・やり過ぎ・心拍数上げに注意)ように配慮して、
有酸素・無酸素運動の反復運動により、新しい回路を太くして、同時に筋力アップを計って行く事が重要だと考えています。
私は末端・筋肉を柔らかい状態の動き易い環境にする事が一番大切で、脳の可塑性を引き出すと考えています。
運動前にはビューティローラー使用(≒有酸素運動)をお勧めします。
参考→痙縮とビューティローラー-2(私の考える脳の可塑性−19)→ビューティローラー振動周波数と痙縮について
3Mメソッドには、麻痺側の手足が動き始める事の意味・評価が重要です。
発症後に障害を受けた脳の半球と反対の半球の片代わり(例‐左半球なら右半球)
もありますが、
脳の可塑性で辛うじて生き残っているペナンブラ領域に新しい回路が作成されて運動野と繋がり指令が出て、麻痺側が自分の意思で動き始めると脊髄〜末端の間の異常である痙縮が次第に減少して行くと私は考えています。
備考→通常は交差支配が約90%支配で、右半球→右半身運動のストレート支配=約10%)
そして、また次第に脳卒中の後遺症の運動障害の一番の原因が拘縮に移行して行くとも考えています。
結局、何を言いたいかと言うと、無酸素運動は特に、有酸素運動でも、リハビリを一生懸命に頑張ってやると、筋肉が疲労して硬くなり動き難くなってしまうという事です。
つまり、回復が停滞するリハビリの壁に突き当たってしまいます。
参考→脳神経の交叉支配と脳神経の再生について−3
https://ameblo.jp/hapikuni/entry-12839477136.html
