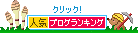三連休初日の昨日は、御守や御朱印を求めて多くの方がお参りされました。
さて、当社には、石鳥居が4基あるのですが、今回の能登半島地震ではなんとか倒壊を免れました。
ですが、当社を含め宮司を兼務する10神社で、鳥居の亀裂や灯籠・狛犬の倒壊などの被害が生じました。
<画像は地震で倒れた本殿前の対の春日灯籠で、その10日後修復>
それで、当社の御影石製の第一鳥居は、昭和7年に当時の氏子総代の代表で、当地きっての旧家である伊東吉太郎氏の奉納によるものです。
そして、正参道の長くて急な第一石段を昇ると、踊り場手前に第二鳥居が現れます。
第ニ鳥居は、台輪下の両柱がステンレス製の型枠で補強されていて、奇異に感じるかもしれませんが、そのことは後述します。
この鳥居は、昭和11年に金沢市二日市郷友会によって寄進されたものです。
当県の小松市で産する滝ヶ原石で造られた鳥居で、「昭和十一年四月建之」とあります。
で、両柱上部がステンレス製の型枠で補強されているのは、平成3年9月に列島全体に甚大な被害を与えた大風19号と、同5年2月7日に発生した能登半島沖地震によって、亀裂が入ったためです。
平成5年5月に補強工事をおこなったのですが、特注のステン製型枠を取り付けるため足場を組むなど、けっこう費用がかさみました。
しかし、そのおかげで、今回の大地震では額束のズレだけで事なきを得ました。
修理を担当した石材店さんの話では、このステンレス補強がなければ、鳥居は倒壊したかもしれないと申していました。
第ニ鳥居のある踊り場から、さらに石段を駆け上がると社殿前にたどり着くのですが、昇り切ったところに第三鳥居があります。
この第三鳥居は、先述した伊東家出身の伊東哲(さとし)画伯〔明治24年―昭和54年〕によって、昭和5年3月に奉納された御影石製鳥居です。
伊東哲画伯は、東京美術学校在学中に文展(※日展の前身の官展)に初入選し、その後も入選を続けたのですが、第八回帝展で歌人・柳原白蓮(やなぎはらびゃくれん)を描いた「沈思の歌星」が売名行為と非難されたことに嫌気がさし、画壇から離れました。
その後、同郷の親戚で金沢市今町出身の八田與一技師の依頼で日本統治下の台湾に渡り、ダム建設の記録画の制作に従事しました。
<伊東哲(さとし)画伯が描いた八田技師の肖像画(写)>
また、金沢ふるさと偉人館では、平成16年5月より八田技師のコーナーが設けられました。
「創造的技術に挑んだ人たち」というコーナーで常設展示され、写真パネルや似顔絵とともに功績を紹介しています。
ちなみに、柳原白蓮は、九条武子、江木欣々(えぎきんきん)と共に大正三美人の一人に数えられた女性で、平成26年のNHK朝ドラの「花子とアン」で、女優の仲間由紀恵さんがその役を演じて話題になりました。
話を元に戻しますが、当社遙拝所の鳥居も地震で無事でしたが…。
社前の灯籠が倒壊し、これも石材店に修復していただきました。
明治25年に氏子中より奉納されたこの戸室石(とむろいし)製の鳥居は、実は別の場所に建っていたのですが、昭和30年初め頃にトラックによる衝突事故で崩壊し、その後ここに移築されました。
最上部の笠木・鳥木の部分と下の部分の色が違うのは、柱や貫などを別の材質(小松産の日華石)で補ったためです。
元々、この鳥居はどこにあったのかと申しますと、旧北国街道沿いから本社へと続く参道のT字路の分岐点に建っていたのですが、現在は社標しか残っていません。
この社標は、「郷社 波自加彌神社」「大正十三年八月吉日 和田末松」とあり、大正13年3月19日に郷社に昇格したことを記念し、氏子の和田氏が奉納されたものです。
揮毫(きごう)は、内務大臣・商工大臣・文部大臣を歴任した、金沢出身の政治家で実業家の中橋徳五郎氏によるものです。
なので、上部は金沢城の石垣でも使われている戸室石で、それから下は日華石と合体させたもので、当時トラック会社に弁償してもらったのだそうです。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!