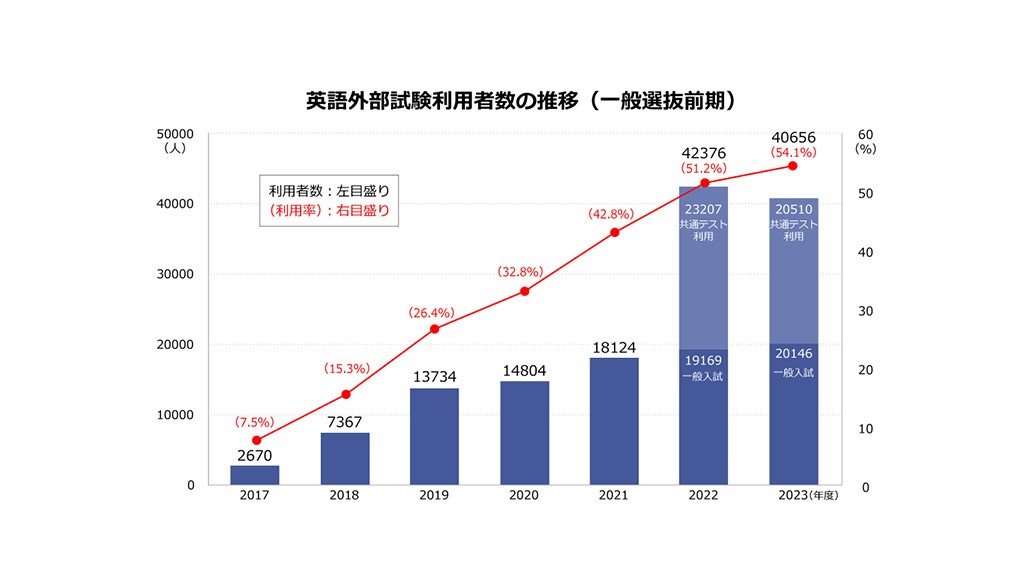てんどー先生の早慶上理・MARCH・日東駒専における直近9年間の倍率推移と考察を見て、どこもピーク時と最低時との倍率差がエグいです。
個人的に一番大変だなーと思った年はお兄ちゃんの一つ上、2020年入試でしょうか。
滑り止まらない話を何度聞いたことか。
それでも、2021年から導入される共通テストを敬遠したせいか、3月入試まで粘る人が多くいました。
この年から現役指向が高まりだしましたねー。
昨年まで大盛況だった予備校に、浪人生が急に来なくなったのも確かこの頃からだと思います。
数年前の代ゼミに引き続き、駿台、河合の校舎も縮小傾向にあります。
2021年は倍率は低いものの、共通テストとコロナのせいで現役指向に地元指向がプラスとなり、受験生は心理的に大変だったと思います。確かに少子化と浪人生減による恩恵はありましたけどね…。
そして、2022、2023年と有名大学がこぞって合格者数を増やしたおかげか、以下のような状況に。
サンデー毎日では、各予備校関係者が集まり2023年入試を総括する座談会が掲載されました。
大学全体で見ると、今年の入試は実際どうだったのでしょうか。
” 4月21日現在で集計した数値によると、受験人口自体が全体で2%減少しています。これとの比較で見ていくと、私立大全体の一般選抜の志願者が前年比97%なので、受験人口の減少とほぼ連動した減少幅になっていると言えます。一般方式と共通テスト利用方式を比較してみると、前者は96に対し、後者は99で、共通テスト利用方式の方が減少幅は小さかった。
難易度グループ別に見ると、首都圏は早慶上理(早稲田大、慶應義塾大、上智大、東京理科大)が99。MARCH(明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大)、成蹊大・成城大・明治学院大・國學院大・武蔵大のグループ、日東駒専(日本大、東洋大、駒澤大、専修大)の各グループはいずれも指数98と、ほぼ前年並み、あるいは受験人口の減少幅と同じような数値でした。これに対し、芝浦工業大、東京電機大などの「理系10大学」は103と増加しており、やはり理高文低の傾向が表れていると言えます。女子大は13大学をグルーピングしているのですが、指数93と落ち込みは大きくなっています。
西日本に目を向けると、関関同立(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)は104、産近甲龍(京都産業大、近畿大、甲南大、龍谷大)は101で、近畿エリアでは難関私立大は堅調に志願者を集めています。一方、地方の各地区の拠点大、例えば北海道の北星学園大や北海学園大は86、愛知の南山大・愛知大・中京大・名城大は95。首都圏・近畿圏に比べ、それ以外の地域にある私立大は減少率が著しい”
以下は、河合塾が毎年まとめている主要大学グループの入試結果で、2023年のものです。
2023年の入試では、日東駒専産近甲龍ぐらいまでは堅調に志願者を集めていたようですが、首都圏・近畿圏以外の地域は減少気味だったのですね。
地方私大からジワジワと迫り来る少子化の波…。
地方国公立も、今年は2次募集が多かった印象です。
ただ首都圏でも志願者を集められず、苦戦していた大学は多々あったようで…。
「はっきり言って偏差値40まで来ると誰でも受かります」
というわけで、マスクド先生からは滑り止めを確保するなら総合型選抜等で年内に合格するより、3月入試を狙え発言が出てしまう状況にまでなっています。
大東亜帝国は特に共通テスト利用後期の倍率が低い!
見ると一倍台がたくさんありました。
コバショー先生も1年間頑張れば偏差値40ぐらいの大学には行けると。
なぜなら入試問題が高校レベルだから。
要するに教科書の内容ができれば大丈夫。
偏差値50ぐらいからが大学受験レベルの問題が出題されます。
日東駒専からは国語に現代文だけではなく、古典も入ってきますね。
負担感がちょっとだけマシマシに。
ただ今年、弟さんの受験結果を見て個人的に思ったのは、来年も日東駒専の過去問が8月までに7割取れていればGMARCHがかなり射程圏内に、冬時点でも7割以上得点できれば日東駒専を含む偏差値50ぐらいの大学は堅いと思います。
年々易化しているから余計ですね。
というわけで、全く勉強していない受験生は、今からでも頑張って、できるだけ冬、いや受験直前までに日大レベル7割を取りましょうか!
サンデー毎日の座談会でも言っていましたが、頑張れば頑張った分だけ自然と大学の方から近づいてきてくれますよー。