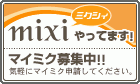建国に思いをはせて
奉祝 紀元節

この国が建国されて、今年で2672年。皇紀2672年です。
初代天皇・神武天皇は何を成し遂げたくて、どんなお気持ちでこの国を建てられたのか。
今の自分にはまだわかりません。
しかしわかったことがひとつあります。
それはこの国が世界に類を見ない2672年も続く、それだけ強い想いだったということです。
私たちが今こうやって生きていられるのはこの国のおかげであるし、その国をつくったのが神武天皇です。そして、神武天皇が創った国、その想いをずっとお 護りくださっている歴代の天皇陛下と御皇室、先人の皆々様、そして私たちひとり一人の御先祖様の偉業を讃え、感謝し、安泰に国が続いていることをお祝いし ます。いままでも、これからも。
私たちひとり一人のことを知らなくても、ずっと遠い昔から私たちを護ってきてくれた人がたくさんいます。
このことだけでも十分に有難いことで、嬉しいことで、心強いことではありませんか?
私はそんな国・日本がたまらなく好きです。
ありがとう日本!
【あなたの町に水戸黄門が行く】
*********************************************
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のり(思考とその過程、行動)を綴ります!!
読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
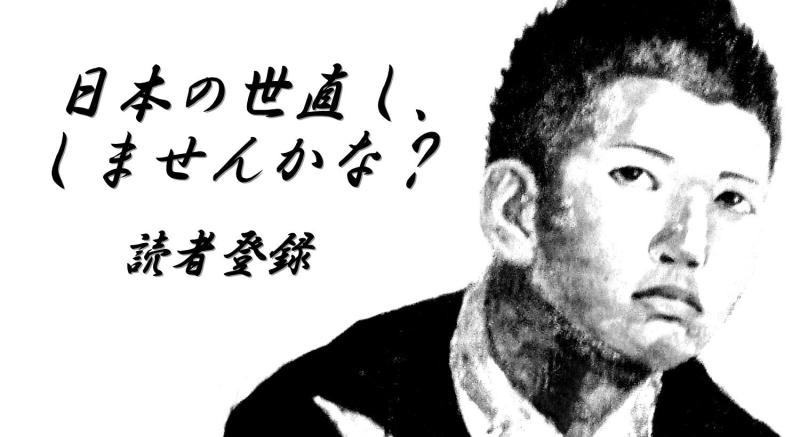
Follow me!!
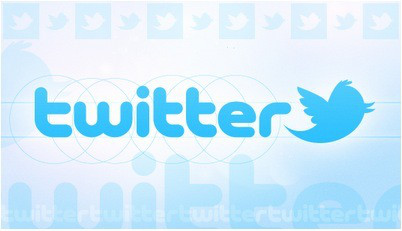
mixiもよろしくです!
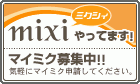
日本の世直しには、まず…
お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか?
ようやく暑さも落ち着き、過ごしやすい季節になりましたね。
でも風邪がちらほらと流行っているそうで、マスク着用、人ごみに行かない、帰宅したらうがいと手洗いは必須ですね。私も気を付けます。
「日本の世直し」。これを何度も当ブログの中で申し上げています。
現在の段階でこれに込められているメッセージは、 『日本人が今よりも自国の歴史・伝統・文化を知り、誇りを持って、日本を創りあげていこう!』ということです。
「日本ってやっぱりダメだなぁ…」
ニュースを見れば暗い話ばっかり、お先真っ暗、明日にでも日本は潰れるみたいなことばかり。
それがニュースだけの話であればいいのですが、それに影響を受けて人々がそういうことを日常会話に出して、どんどん伝染していってしまい、それが本当のようになりつつあるようにも思えます。
『現在』だけ見れば、確かに暗い世の中かもしれません。
でも『過去』はどうだったのでしょうか?それも現在からさかのぼって50年だけではなく、日本という国の成立までさかのぼって見ていくと、決して最初からお先真っ暗な国ではないと思います。
逆にいつも明るい国だったというわけでもなく、苦しい時期も当然ありました。しかし、苦難を乗り越えて「日本」という国号は成立から現在までずっと続いてきました。

(見えにくいと思いますので、画像をクリックすると拡大されて見ることができます。)
義務教育の中で日本史の学習をしてきたと思いますが、日本は幾度となく国難を迎えています。
しかし、いつの時代もそれを乗り越えてきています。これだけ長い歴史を紡いできた日本(ちなみに我が国は現存する中で最古の国家)は、苦難に立ち向かい克服する術を歴史として刻んで蓄積してきており、国難に打ち勝つことは世界で一番得意としているはずで、むしろそれが日本人の誇るべき民族性のひとつであると思います。
したがって、大地震の復旧・復興、原発事故など、現在にある問題を必ず乗り越えることができると私は確信しています。
これらの問題を乗り越えるのは一部の人だけでは無理があります。約1億2千万人の日本人が考え、一致団結して、行動しなければ変えていくことはできません。
そして今の日本には戦後復興のあとの高度経済成長における所得増大などのような『国家目的(国民が総力を挙げてつくりあげるべき国の姿)』が見えていません。だから今の日本には未来にかける想いというのがなく、何でもやることが後手になり、その場限りの判断と行動、いきあたりばったり。
私はこの国の目指すべき国家像というものを、日本人みんなで考えて、決めて、行動に移して、その目指すところへ向かうことの火付け役になりたい、これが世直しの一つだと思っています。
しかし、私はまだまだこうして発する言葉が具体的でなく、うまく伝わっているとは思いません。なぜなら、それは言葉の定義や意味付けということができていないからです。
たとえば「世直し」という言葉。
今、私の目の前にどなたでも来られて「世直しとは何か?/世直しとなるのはなぜだろうか?/世直しは何をすることなのか?」と言われても、自分も相手も納得する答えを導くことは現在の段階では難しいです。
つまり、それは普段から自分が発する言葉というものは勝手な思い込みとイメージでつくりあげられたものに過ぎないからです。さらに言えば、何も考えていないということです。
言葉こそは格好良くて、いかにも高尚に見えるかもしれないけれど、感覚だとかニュアンスだけで伝わればいいと口にして、聞いた人それぞれが意味の捉え違いをしてはその言葉というものが独り歩きしているだけ。
人は言葉によってコミュニケーションをとっています。会話の中で言葉の意味というものを互いに無意識にとらえながら会話が成立しているのが日常です。
意識してみてください。単語一つとっても定義や意味というものは人それぞれバラバラのはずです。それでもってニュアンスだけで話し、聞いているということになると表面上は会話が成立しているように見えますが、深く会話を掘り下げていくと言葉の意味に食い違いがあるということがあると思います。
独特な表現、話し手にしかわからない表現がでてきたときは流したり、あやふやなまま納得せずに「どういう意味?」と聞きかえすことというのがミスのないコミュニケーションをとるうえで重要なことだと思います。
「世直し」という言葉も、独特な表現であり、話し手である私にしかわからない表現です。だから、相手に聞かれる前にその意味をきちんと用意しておく。その目の前の相手に分かる言葉で。
「世」とは何か?「直す」とは何で、「世直し」とはどういう状態なのか?
今回の記事のタイトルは「日本の世直しには、まず」とありますが、世直しをはじめるうえで「世直し」の定義をきちんとかためることが、世直しの第一歩であると私は考えます。
以前にも申し上げました通り、このブログは「日本の世直し」に向けたプロセスを描くものです。考えたことをあますところなくブログという場をお借りして社会全体に述べていき、自分の考えを訴えかけていくものです。
このブログの開設した目的に従って、次回のブログより、「世直しの定義」をテーマに、世直しのそもそもの定義を文献を中心に考察していきます。とても長い記事になると思いますので、区切りのいいところで区切る形でシリーズものにして掲載させていただきます。
長い文章でしたが、最後まで読んでくださってありがとうございます。
【あなたの町に水戸黄門が行く】
*********************************************
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のり(思考とその過程、行動)を綴ります!!
読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
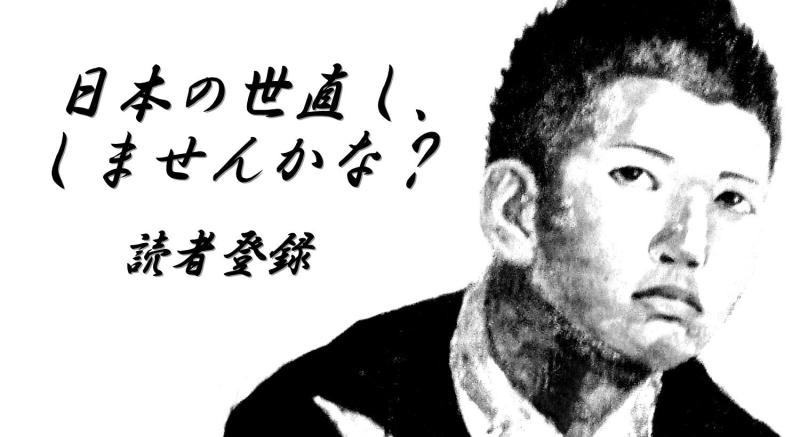
Follow me!!
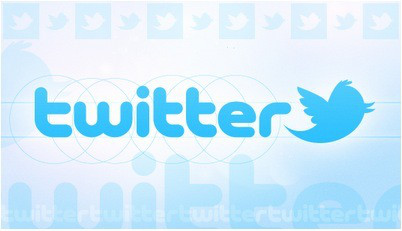
mixiもよろしくです!
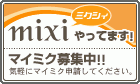
モノに命を与える
昨日9月14日もとっても暑い1日でした。気温は何度だったか知りませんが、真夏のような一日で汗が滝のようなという表現では語ることができないくらい汗が出まして、本当にどれだけ水分補給をしたんだろう?体の水が一度入れ替わるくらいかな~?(←んなわけねぇだろw)と、そんな一日でした。
でも、9月に入ってから7月、8月と違うのは、朝と夕方が涼しいこと。気温もそうですが、この季節の夕暮れの色が好きです。町全体がオレンジ色に染まっていくというか、秋色に染まっていくというか、そんな情景に何だかちょっぴり切なくなってしまうこの頃です。
読者の皆様、秋といえば何を思い浮かべますか?たとえば、「食欲の秋」とか「読書の秋」とかそういう感じで何を思い浮かべますか?
私が真っ先に思い浮かんだのは「収穫の秋」、お米の収穫です。家の田んぼも刈り終って、田んぼ一面はコンバイン(稲刈り機)で細断されたワラが一面に散らばっています。つい先日まで腰の高さまで伸びて、穂が垂れ、黄色に色づいた稲は跡形もなくなってしまいました。しばらくすると、新米が食卓に並ぶことになります。ご飯党の私にとって楽しみです★
今日のお話は稲が刈り取られた田んぼを見て、発見したこととそこからいろいろと考えたことを書いていきたいと思います。発見したことは「刈り取られた稲はその後も含めて、捨てるところが一切ない!」ということで、生活のあらゆる場面で利用されていることです。
私の家では自分たちが食べる分だけの小さな畑をやっているのですが、そこで知ったことを主な例として挙げていきたいと思います。
刈り取られた稲をおおまかに部分わけしますと、地面に「根」と「株元」が地面に残り、「わら」と「もみ」が取れます。そのうち、もみを脱穀すると、「もみ殻」と「玄米」に分かれ、玄米を精米すると「ぬか」と「白米」に分かれます。食べるプロセスで捨てられると思われがちなものが実はいろんなところに役立っているんです。
まず根と株はそのまま放置すれば腐って、そのまま次の年に田んぼをするときにいい肥やしになります。
わらは馬とか牛のエサになったり、寝床になったり、また畑作のときに「敷きわら」といって、これを畝のうえに敷くと雑草が生えるのを防いだり、乾燥することを防いだり、土を適温に保つ効果があるそうです。またこれがないと納豆が作れませんね。
もみ殻はというと、畑にまくと、水はけがよくなりますし、土壌が柔らかくなり野菜の根がよく張れるそうです。そのまま肥料などとして使うこともできますが、それをすると野菜の根っこが痛むそうです。燃やして炭にすることで燻炭(くんたん)になるんですが、炭ですから土壌の浄化作用、嫌なニオイの除去に効果があるそうです。
お次はぬか。これもまた使い道がたくさんあって、漬物から化粧品にまでなりますし、乾煎りしてコマセという撒き餌に混ぜれば釣りのエサにもなります。
とても粗い説明でしたが、捨てるところがないことがお分かりいただけたでしょうか?たぶんググったり、その道に詳しい人に聞けばよりたくさんのことがわかると思います。
捨てるところがないというのはとてもいいことです。ゴミにすればそれまでですが、これに人が目的を持たせて、適材適所をすれば、その持ち味というのでしょうか、それがいろんなところで活きるのであります。「資源を再利用しましょう!」というリサイクル、最近ならリユースっていうのも出てきましたけど、だいたい私が生まれて(20年前くらい?)すぐに言われるようになったのかと思います。実は日本人はもう遥か昔から資源活用に知恵を絞ってきた歴史を持っていますし、これはDNAに刻み込まれていると思います。
最近の研究で江戸は環境都市 だったということが明らかになってよく知られるようになっていますが、それよりも1000年以上も昔からリサイクルあるいはリユースをよく考えられていました。その話には、こんなエピソードがあります。ちょっと長くなりますけど、見てください。
伊勢神宮というのが三重県にあります。よく「お伊勢さん」なんて愛称で呼んでる人がいると思うんですが、この伊勢神宮には式年遷宮というお祭りがあります。
式年遷宮っていうのは、20年ごとに内宮(皇大神宮)・外宮(豊受大神宮)の2つの正宮の御正殿、御社殿をお造り替えて御神座をお遷しするという儀式で、神宮にあるものの100近くになるんでしょうか、これを造り替えるという大がかりなものです。
ただ単にこれだけ聞くと、「今の家なんて50年とかモノによっては100年もつのに、20年で建て替えなんて、どんだけ贅沢なんだ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではない。
御神体が納められている御正殿を支える柱、棟持柱というそうなんですが、とっても大きいもので、これが2本あって御正殿にとっても重要な柱であります。建て替えるときに、これを捨てないのです。捨てずにかんなをかけて、新品のようにきれいにして、これを宇治橋(伊勢神宮に入るときに必ず通る橋)と橋のところにある鳥居に生まれ変わります。
鳥居が建て替わるということは、したがって鳥居に使った木材がそこから除かれるということになりますが、これも捨てません。桑名市などの伊勢の玄関口の鳥居として生まれ変わります。
これも20年たてば、建て替えですがこれも捨てません。今度もかんなをかけて、次は全国の神社のところへ御神木となるそうです。頂いた神社は鳥居、社殿として使い、朽ちるまでずっとずっと使い続けます。
これが飛鳥時代から今日にいたるまでずっと続けられています。モノを大切にするという精神は何も江戸時代からではなく、それよりもはるかずっと昔からのことなのです。
参考文献:竹田恒泰「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」,PHP新書,2011年
材料を使いまわすことと、稲刈りの後に出た一見使いどころもなさそうなものを使い道のなさそうなものを使うことは違うかもしれませんが、共通していることは「モノに命を与え、活き続かせる」ということです。
生きていたものを何かの材料にしたときにそれは生命活動を失うと思うのですが、そこに「命」を与えるのはどういうことかというと、人間が生きていくために必要なものに生まれ変わることによって再び生命活動とは違う、人間が生きていくための必要なツールとしての命が新たに与えられるということです。そもそも、そんなことのために生まれてきたわけではないのに、命を奪ってまで使うのは本来申し訳ないことであり、だからこそ大切に使うことがせめてもの償いなのではないのか、と今の時点ではこう思うのであります。
今までこんなことを考えてなかったのはあれですが、逆にそういう立場から見て、捨てずに使い道を与えるということは本当にすごいと思いました。
なぜそれが可能になったのかというと、日本が大昔からほかの国から攻め込まれることが他国に比べてとても少なく、国のかたちが変わることなく、ずっと平和に過ごせてきたからだと思います。というのは、国同士の戦争で歴史が途絶えて、それ以上歴史が刻むことができず、その国の現在もほろんだ時点で止まってしまい、文化として残らないこともよくある話で、それがないということは、より多くの知識や技術が伝承されてきたと考えるのが妥当だからです。
また弥生時代からずっと稲作を続けてきたようですが、一度も絶えることなく続けてきたからこそ、どうしたら限りある資源の中で豊かに生きれるのかと先人たちが知恵を絞ってきた絶えることない歴史があったからこそ、現在に稲作で得られた資源の有効活用が太古の昔から日夜研究されて、それがその一番とんがっている場所、最先端として今に伝わっているのだと強く思います。これを私が生まれるずっとずっと昔から、脳みそに汗をかくくらい考えて、失敗に失敗を重ねて、知識や技術を確立させてきた先人を尊敬します。
そして忘れてはいけないのが、「いろんなものに神様が宿る」という考え方です。これに関して書くとさらに長くなりますし、別個の記事として書きたいので、私自身もっと勉強してから書きたいと思います。
「モノを大事にする」、「無駄にしない」、もっといえば「モノに使命を与えることによって活き続かせる」ということが大量生産・大量消費の時代になっても、今回は田んぼや畑を例として書きましたが、そこでもきちんとその分野の伝統が受け継がれていることに、この歳になって気づけてよかったと思います。
いかん!熱中して書いてたら、朝の6時ですよって、もうすぐ仕事ですよ!
今日はこの辺でお邪魔します。
読者の皆様、拙い記事でしたが最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【あなたの町に水戸黄門が行く】
*********************************************
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のり(思考とその過程、行動)を綴ります!!
読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
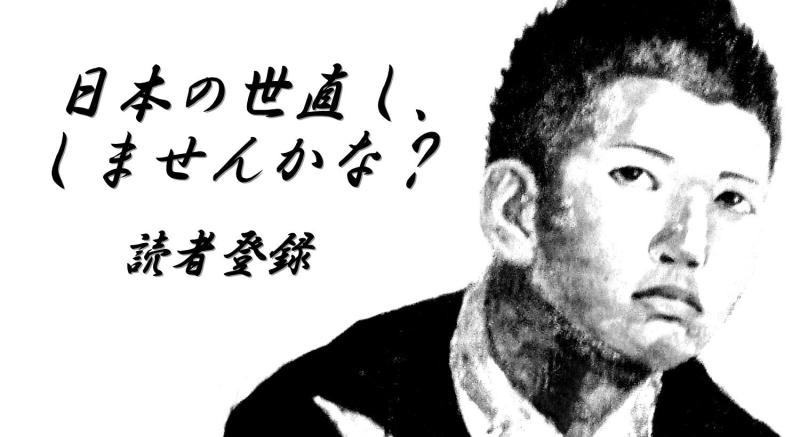
Follow me!!
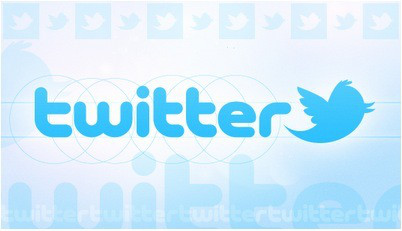
mixiもよろしくです!
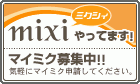
ほっとひといきつきます
今日は私のブログの読者様でありますココロイラストレーターmamuamu さんの作品を紹介します!
mamuamuさんとは、昨年10月に開催されたAll genre fusion party!! -Utopia-の時からお世話になってます★
そんな彼女はイラストレーター、ココロイラストレーターといって「見た人に笑顔になってもらいたい♪」ことを思って、イラストやポストカード、絵本などを制作したり、さまざまなアーティストの方たちとコラボして、グループ展を開いたり、服をつくったりとアクティブに活動されています。
そんな私もイベント成功の記念にイラストを描いてもらったことがありまして、とっても気に入ってまして、以前大阪に住んでいる時は玄関に飾ってて、今でも実家の玄関に飾らせてもらってます!それから私もmamuamuさんのファンであります!

つい先日、我が家にmamuamuさんの作品が届きました。
マグカップであります!!

「ほっとひといき」がテーマのこの作品、カップのところにイラストとかわいらしい言葉が描かれています♪

なんとマグカップひとつ一つ手焼きで作っているとのことで、本当にクオリティにこだわっております!
働いて半年の職場で、マイカップがなかったため、マグカップがほしいと思っていたところにブログにこの作品の紹介があって、やっぱり使うなら知ってる人で心のこもったものを使いたいと思っていたので、注文させてもらいました、。mamuamuさん、このマグカップをありがたく使わせてもらいます!
いやぁ、いいですね!ひとつひとつメッセージもついていて、1時間の休み時間にほっとひといきするのには最高です★やっぱり持つべきは友ですね!ありがとう、mamuさん!
ポストカードもいただきました!こちらもありがたく使わせてもらいます!

これ以外にもmamuamuさんのココロのこもった作品がいっぱいあります!
たくさんのイラスト、作品に触れられたい方はコチラ!きっとあなたも笑顔になれますよ★
*ココロの絵本*
【あなたの町に水戸黄門が行く】
*********************************************
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のり(思考とその過程、行動)を綴ります!!
読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
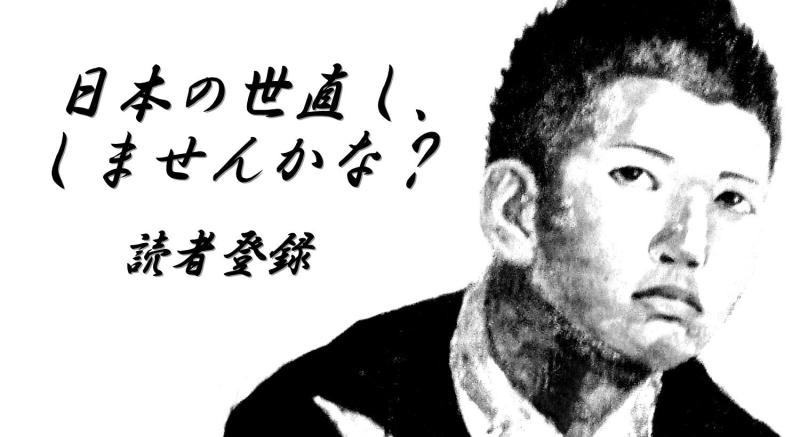
Follow me!!
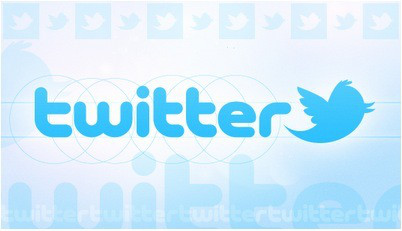
mixiもよろしくです!
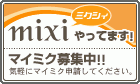
開設1周年総会
【「あなたの町に水戸黄門が行く」への軌跡】を開設して、本日で1年が経過しました。
大学3回生の冬に幕末から日露戦争、大東亜戦争と現代までの歴史に触れ、そのうえで現代の日本を見て「いまの日本と日本人は敗戦を境に何か大切なものをなくしてしまっているのではないのか?」と本気で考えるようになり、『日本を世直ししたい!』という漠然とした夢を持ちました。それは平成22年3月7日のことでした。
それから半年後、このブログを始めました。
なぜ始めたのかって?
「私が考える日本の世直しとは何か」や「そのために考えるべきことは何か」、「現代版・水戸黄門とは何か」、「東日本大震災の復旧・復興・再生に対して私ができること」など、自分の夢を言葉にし、カタチにしていく為にはじめました。
日本の世直しとはどんなプランであったとしても私一人では決してできるものではなく、日本中の人の力があってこそ成し遂げられるものと考えています。
それに向けて自分の考えとそのプロセスを明らかにしなければなりませんし、自分でもきちんと記録をつけていかなくてはなりません。したがって数あるメディアの中で「ブログ」を用いることが自分のなりたい姿にあっていたので、日本の世直しにむけて考えたことすべてを記すこととしました。
大学生の間にも他愛もない日常をブログで書いていたのですが、見る人もいなくて飽きてしまってやめてしまいまして、それから何回もチャレンジするけど、3日坊主で… o..TL(ダメポ
こうやって夢を持って1年半、ブログをはじめて1年が経過しました。
夢、あるいは目的という言葉でいいのでしょうか?これがあるのとないとでは継続できるか否かが決まってしまうということに気づくことができました。
そして今日まで続けることができたのは、ブログを見てくださる人が大勢いたこと、コメントを書いてくださったこと、メールもいただいたこと、「興味深い!」と読者登録があったことなどが本当に嬉しくて、それが支えになっていたからでした。ありがとうございます!
また近頃、「水戸勇佑」という名前から検索してこのブログにたどり着いて見に来られた方がたくさんいらっしゃいました!私のことをわざわざ探しに来る方もいらっしゃることに驚いたのと同時に、ものすごく嬉しく思います★ 指が無意識に動くままに私の名前を検索してその結果に「まさか!?」と思われた方もいるかもしれません。むしろ驚いたのは私のほうではなく、私の名前で検索してこのブログをご覧になっている画面の前のあなたかもしれません。
ネットには本当に膨大な量の情報があふれていますが、その中から私を見つけてくださって、ありがとうございます。少なくとも、私はこれをご縁だと思っていますからね♪
今までこのブログに一度でも来られた方でも、ずっと見てくださっている方でも、全部何から何までご縁というものであると思います。
読者の皆様、この場をお借りしまして御礼申し上げます。
有難うございます!!
● これからの【「あなたの町に水戸黄門が行く」への軌跡】
今までは思考の基礎を整えるためのそのプロセスの記事を重点的に書いてきました。
現在の私は「日本の世直し」という途方もないことをやっていくことに対して、行動によって得られる成果よりも行動するために必要な気づきや学びといった目に見えない成果とインプットに価値を置いています。
人間はすべからず「知覚→決定→行動」のプロセスをたどります。
ご飯を食べるという行動は、お腹が減ったと感じ、どれくらいお腹が減った、何が食べたいと考えたうえでたくさんある選択肢から食べたいものをピックアップし、食べたいものを決定し、行動に移します。 何の考えもなしにご飯は食べられないのです。設計図なしには家は建たないのです。やはり行動する前に人間はどうしても思考するようにできているのです。肝心なのはどれだけ深く考えたのか(=先のことを読み、逆算して今何をしなければならないのかがわかっている状態)であるのではないかと思います。
何の考えもなしにできるのは、熱いものに触った時に思わず手を引っ込めてしまう脊髄反射くらいではないでしょうか?
私の考える「日本の世直し」も同じことです。日本のどこにどんな問題(ゴールとのギャップ)があるのか、課題(問題の真因)がどこにあるのかを正確にとらえて、それに対して解決あるいは克服のアプローチ法を考え、その中からベストの方法を選択肢を選び、行動に移します。
そのために学ぶべきことを現在洗い出し中で、洗い出しのプロセスと結果の明示を2周年までの1年間はこれを重点項目のひとつとして実行します。
世直しの「軌跡」ですから、やはりプロセスが大事なのがこのブログの方針です。どんどん記事を追うごとに思考が洗練されていく、ブログを見るだけでも世直しのイメージが浮かぶ、頭の中で絵が描ける、その色を強くしていくことのできる書き方に工夫をすることも重点項目であります。
それを受けて私はこのブログを書くうえで気をつけていることがあります。それは「芸能人が書くようなブログは書かない」ということであります。(何も芸能人のブログが悪いというわけではありません)
たとえば本を読んだその書評を書くなら「○○ってゆう小説を読んだ。物語にでてくる主人公の気持ちめっちゃわかる~!」というその人にしかわからない感想ではなく、それを受けて自分にとってどのような影響があって、何を考え、何を伝えたいのかを細かく、言葉の遣い方に気を付けながら書かないといけないと思います。
自分一人しか見ないことを前提とした日記と不特定多数の人がみるブログは根本的に違う。
自分しか見ないのであれば「豚骨ラーメンに厚切りのチャーシューが5枚入ってて麺は太麺でかためか柔らか目を選べて、とってもスープがこってり云々」と、そんなに細かく書かなくても、「豚骨ラーメン食べた、おいしかった」くらいの記事を見ただけで当時の記憶をよみがえらせて「あ~おいしかったなぁ」と思い出すことができるだけでいいはずです。
しかしブログになると不特定多数の人が見ますから、ただ単においしいと書くだけでは意味がない。どうおいしかったのか、それで何が変わったのか、せめてアクセス、営業時間などというのを書かずに「おススメのお店★」あるいは「逸品!」と書いたところで、それがいくらおいしいラーメンであったり焼肉であったりしても伝わらない。これはブログに限らずtwitterでも。
こういうのがクチコミとなってそのお店の売り上げにも影響する時代ですから、ブログ一つでも世の中が動かせる時代なんですよね。それによってその記事を書いた人の記事も何かで取り上げられるかもしれないし、芸能人じゃなくてもファッションリーダー的存在であったり、人気ブロガーにだってなれるはずです。
書いた人と見る人の持っている価値観自体がそもそも違うから、書いた人の「おいしかったー!!!」と見る人の「おいしかったー!!!」は違うはずです。語尾の!が増えれば増えるほど、見ている人の頭の中に?が増えるだけですね。
多くの芸能人のブログを見ていると、「○○さんと会った~話が深かった~」とか「どこどこで○○食べた!おいしかった!」という感想だけのブログが多いことに気づくでしょうか。
彼らはそれでいいんです。なぜならドラマとかバラエティ番組を通してメディアに露出することでファンを形成しているからです。ブログを公開するだけでファンの人ならアクセスするでしょうし、簡単なブログでもファンは彼らの日常をうかがい知るこができ、ニーズが満たされるから芸能人のブログがブログとして成立するのではないでしょうか?
では名前も知れていない私たちはどうするのか?
そんな私たちが「○○さんと会った~話が深かった」では伝わらないことに気づくはずです。その人を紹介するなら、まずその人がどんな素性の人なのかを明らかにして、話の内容としては「私は○○についてこう思っていたんだけど、△△さんは○○について、ここの部分の考え方が違った。△△さんの場合・・・」と書いていけば、印象は違うはずではないかと思うんです。
書いた人の考えていることが具体的であれば、そのやり取りを見た人からしたら「この人はこれについてこう考えているのかぁ」と第三者評価が加わって、評価する人が増えれば増えるほどそれが信用(ブランド)につながるんじゃないかなぁと私は思います。プラス評価をつける人が増えれば増える人はブランド力、「あの人ならこのこと任せられるんじゃないのか?」ということになるのではないでしょうか?
前置きがかなり長くなりましたが、ただ単に「日本の世直し」のことについて考えたことの結論だけを書くのではなく、どういう流れでその結論になったのかというプロセスを明らかにしたいと思います。
そうでなければその結論に対してブログを見た人が評価を下せないからで、評価が下せないということは読んだ人はそれに対して何の思考も何の行動もしないし、そうなればブログに書く意味がないということであり、したがって世直しにならないということです。
思考のプロセスを明らかにしないということは、数学の試験で途中式を省いていきなり答えを出して採点で先生に赤ペンではねられるのと一緒です。当てずっぽう、何も考えていないと捉えられるからです。
「いかに日本の将来を考えて、そのために将来どのような行動をしていくのか」これを綴っていくのが、【「あなたの町に水戸黄門が行く」への軌跡】です。これからも、このブログと私ともどもよろしくお願いいたします。
*********************************************
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のり(思考とその過程、行動)を綴ります!!
読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
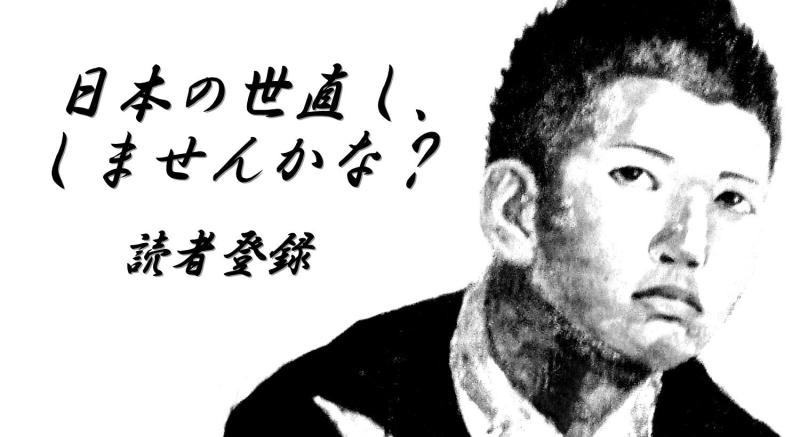
Follow me!!
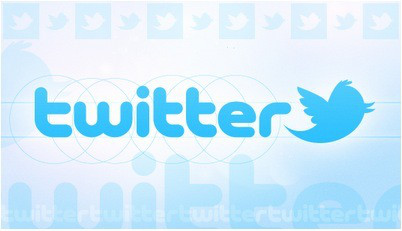
mixiもよろしくです!
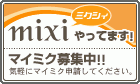
失われたものは「日常」
今日は7月17日と30日~31日にかけて宮城県石巻市を訪れたときのことを書きたいと思います。
あと数日で東日本大震災発生から半年が経過します。
冒頭に書きました17日は東北六魂祭 へ、30~31日の2日間は石川県の災害ボランティアとして被災地の石巻に行きました。
日を別けて、それぞれの日程で違う内容でも、被災地へ行った目的はひとつです。
「被災地の現状を知り、復旧・復興・再生にむけて自分に何ができるのかを考える為」であります。
現地に行き、被災地の人とお話をして、町を見て、そこにあるすべてから将来の東北と日本のためにできることのヒントが何かひとつでもあると信じて、その想いで行きました。
● 六魂祭を訪れて
お祭りからは2ヵ月が経過し、当時大地震からは4ヵ月が経過していました。
この六魂祭は仙台市で2日間にわたり開催されました。
わずか4ヵ月間で東北6県のお祭りを一堂に会したお祭りを企画して、実行したこと自体が凄いと思いました。少なくとも震災から1ヵ月はそれどころではなかったのではないかなと考えて、実際に企画したのは3ヵ月くらいではないかと私は考えています。そう考えると、6県との連絡、全国への宣伝など、とてつもないスピードで企画を詰めたと考えると本当にすごい。それを可能にしたエネルギーというのも、本当に人の「魂」のなせる業だと思います。
震災で多くの大切な人の命が奪われて、思い出の詰まった家が流されて心が痛まれても、人の「魂」がここまですごいお祭りを創りあげたことに、感激したと同時にお祭りを開催してくださったことに感謝しました。ありがとうございました。
実際に行った時の写真はこちらです。
ねぶた祭(青森)

竿燈まつり(秋田)

盛岡さんさ踊り(岩手)

花笠まつり(山形)

わらじまつり(福島)

● 政宗公の見つめる先
パレードを見終えて、側の広場の屋台を食べ歩きしてから仙台城へ向かいました。
ここには資料館と併設のお土産館があり、その近くには護国神社、そして伊達政宗公の像があります。

政宗公の像は見晴台にあって、仙台市と海側を一望できる場所であります。 私は政宗公の像を背にして、政宗公が見ている先と同じ方向を眺めました。
市街地は地震の影響を感じさせないものでしたが、私はそのずっとずっと先、きちんと見えるかどうかわからない先のほうを見ました。私の目には津波で荒らされた場所が見えたような気がしました。政宗公と同じ視線で見て「仙台を創りあげた政宗公はどんな気持ちで見てるんだろう」って考えました。
氾濫することで有名だった宮城を南北に伸びる北上川を治め、その周辺を豊かな農地に変え、その農地で作られた米は最盛期において江戸の流通米の半分を占めるくらいになっていました。その基礎を築いたのがこの政宗公であります。
東北は米どころといわれる所以は伊達藩が担った部分というのは大きくて、その恩恵が現代まで受け継がれていると思うと、400年たっても名君として慕われる大人物がいることが、いかにすごいことかと思いました。町のいたるところ、政宗公にちなむものばかりなのがうなづけます。
その政宗公がずっと見つめる先、どんな気持ちで見ているんだろうととても考えさせられました。こうして仙台を後にしました。
● 7月30日~31日 災害ボランティアとして石巻市へ
東日本大震災が発生してから被災地へボランティア活動に赴く人たちが多くいらっしゃいます。個人で行く人、都道府県の助成を受けて行く人。私は後者として参加させていただきました。
ここでボランティアのおおまかな流れをお話ししたいと思います。
まずボランティアとは何事も自分でリスクを負うということを覚悟しなくてはならないということです。
私なりに考えたのですが、なぜなら被災地において一番優先すべきなのは被災者の人命であるからです。そしてボランティアよりも先に、災害や救助のことを熟知した自衛隊などのプロフェッショナルが現地入りして活動します。それに比べてボランティアは知識や経験、手持ちの資源といったもので不十分なのです。
被災地は二次災害の危険、さらにいうならば現地入りしたボランティア自身もそれに巻き込まれる危険もあります。何かあった時に地元の人や自衛隊なども現地とは何ら関係のない人にまで手をまわす余裕は本来ないのです。
でもボランティアが災害に巻き込まれたときは地元の人などのお世話にならざるを得ません。その場合、ボランティアには自己解決する手立てはありません。本来地元の人が割かなくてもいい場所に労力を割くことになりますから、迷惑になる可能性があるのです。そもそも、そうなるとボランティアにいく意味などないのです。
したがってそうならないような作業をやることがボランティアの心得となるはずです。
だからボランティアはそこで何から何まで自分でリスクを負って行かなくてはならないのです。そうなると、食料や水、泊るところ、もしもの時の保険などなどありとあらゆるものを自分で揃える必要があります。
過去にあったそうですが、阪神大震災のときに多くの人がボランティアとして訪れました。しかし手ぶらで来る人もいて、「ボランティアで来たから泊るところ、食料をください」と言う人もいたそうです。被災者のお世話で手一杯で、言い方が悪いかもしれませんが何の準備もなく、みなしご同然でやってくる人に対して構っている余裕は現地の人にないのです。
私の場合、県の助成(交通費のみ)を受けて、それ以外はすべて自費ですし、道具も全部自分で揃えます。もちろん保険にも自分で加入します。
「何かあった時に自分でお尻が拭ける」その覚悟がないとボランティアをやってはならないのだと私は思います。
この2日間は、がれき撤去の作業をしました。現場は海から2キロ離れた場所にあり、やはりここまで津波が来たであろう痕跡がありました。壁はえぐられ、家の中まで土砂が流れ込み、少し高い壁には津波がここまで押し寄せた跡が残っていました。家ごと根こそぎ引っこ抜かれて流されて、傾いたまま残っているものもありました。
周りをみれば街路樹や庭木も塩害で茶色に枯れていました。しかし塩害とはいうものの、そこらで生えている雑草は健在でした。
● 雑草の中に
撤去作業中、一輪車を押している時にふと雑草の生えている草むらに目を落とした時に一帯で作業をしている50人ほどの人に聞こえるように私は大きな声をあげて
「ここにトマトが生えてます!!!」
一応、農業系の仕事をしていますのでやはり意識があるのでただの雑草と区別がつくようにできているようです。ある種の職業病でしょうか。
すると何人か近寄ってきて見に来ましたが、実もつけていないトマトを見ても誰もトマトとは気づきませんでした。
トマトを育てたことのある人なら、トマトは実をつけていなくても葉や茎からでも実と同じ匂いがすることを知っていると思います。そこで、私はトマトの葉を一枚ちぎって、少し揉んで隣の人に匂いを嗅いでもらいました。匂いですぐにトマトだとわかってもらえました。
私はこの塩害で作物が育てるのが難しいといわれる土地にトマトが負けずに生えているのが素晴らしいと思い、地元に持ち帰ろうとしましたが、思いとどまりました。
なぜなら、このトマトはここに生えているから強く、素晴らしいものであって、それを人間ひとりの勝手な気持ちで持ち出したところで、被災地の塩害のある場所にトマトが生えていたという事実は伝わっても、その生命の力強さというものは伝わらない。本来育たないと思われている場所に、それが育っている。この姿こそがこのトマトの本来の姿であり、だからこそ強くて、あること自体が素晴らしくて、美しいものである。トマトはそのままにしていきました。
今になって写真に収めればと後悔しているのですが、もし石巻に縁があって訪れる人がいましたらば、その場所に訪れてそのトマトを見てほしいと思います。生命の力強さ、素晴らしさを少しでも感じられるものと思います。
またその場所の詳しい場所、それから写真が見つかったらまたUPしたいと思います。
● 被災者の方にとって一番の喜び
2日間の作業は被災地の人と話す機会がありませんでした。道端で通りすがって「おはようございます」「こんにちは」と声をかけることしかありませんでした。ここまでは。
汗だくになるような作業が終わると、誰しも思うことは「お風呂に入りたい!」ということで、被災地を後にする前にその地元にあるパワー温泉リフレ に立ち寄りました。そこでようやく被災地の方と話す機会がありました。その人は男性で歳は77、8でしょうか、白髪でメガネをかけてて私よりも少し背の高い、優しそうな顔をした方でした。
2日間の作業の話を中心に話をしていまして、そのおじいさんは「瓦礫とかモノをどかしてくれるのもうれしいけど、もっと嬉しいのは声をかけてくれることだなぁ」ってお話ししていたことがとても印象に残っています。
もしかしたら、その人は地震で家を失ったかもしれないし、大切な方を亡くされているかもしれない。そうでなくても、地震でいつもの日常が失われています。
家が壊されたかもしれない、家族と離ればなれかもしれない、ご近所さんもいないかもしれない、明日また大きな余震がくるかもしれない・・・。でも誰かが横にいると、声をかけられたら安心するんだろうなぁとその時私は感じました。
失われた日常の中でも、いつも通りの日常としてできるものは「言葉を交わすこと」だと思います。それが「おはようございます」でも「こんにちは」のような挨拶でも、それが人とのコミュニケーションを良くしますし、やっぱり気持ちよくあいさつをされると誰でも嬉しいものですよね。
そして別れ際に「また石巻に来てください」。この言葉もとっても印象に残っています。物見遊山で来たと思われても仕方がない私に対して、温かく接してくださる、こんなに温かい人がいる町は、本当に素晴らしい町だと思う。必ず元通りに、さらに素晴らしい町となって蘇ると信じて疑いません。
「必ず行きます!」
地震発生から約半年。復旧・復興という言葉がよく使われます。
この意味、考えたことがありますか?
難しい話はまた今度に譲るとして、
この言葉を平たくいうと、その本質は
「失われた当たり前を取り戻し、創りあげること」そして「続けること」
この2回の東北に行ったことで、自分なりの答えが出たように思います。
*********************************************
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のり(思考とその過程、行動)を綴ります!!
読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
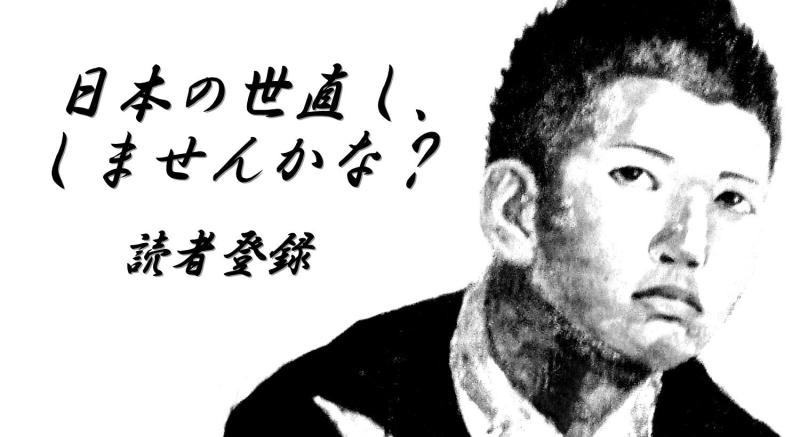
Follow me!!
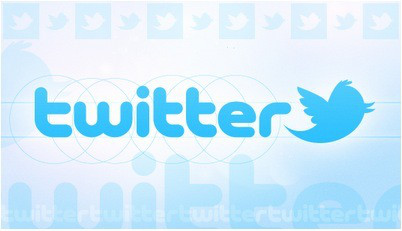
mixiもよろしくです!
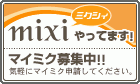
消された歌に込められた壮大な物語 その1
またブログ更新怠ってしまいまして申し訳ありません。
昨日は今月16日~17日の仙台・定禅寺通り付近で開催さていた六魂祭に行っておりました。行ってきた話は明後日のブログにてお話ししようと思います。
今日は祝日、海の日です。海の日は以前までは7月20日なのですが、2003年の祝日法改正、いわゆるハッピーマンデー制度によって直近の月曜日が海の日になりました。
海の日ということなので、今日は「海」をテーマにお話ししたいと思います。
読者のみなさん。突然ですが、この歌を知ってますか?
♪我は海の子白浪の さわぐいそべの松原に
煙たなびくとまやこそ 我がなつかしき住家なれ。
そう、みなさんご存知の「われは海の子」です。小学校の音楽の授業で学び、TVCMなどでもなじみの深い歌であります。
ではこの歌、歌詞が何番まであると思いますか?
習ったのは小学生のことだから、1番だけ、もしくは1番もちょっと怪しい方が多いのではないでしょうか?だいぶ昔のことだから、仕方がありませんよね。(という私も3ヵ月前まで1番の途中までしか歌詞を知りませんでした笑)
教科書を開くと3番まで載っております。ではみなさんの頭の中にある「われは海の子」のメロディでちょっとだけ口ずさんでみてください。
- ≪1番≫
- 我は海の子白浪(しらなみ)の
- さわぐいそべの松原に
- 煙たなびくとまやこそ
- 我がなつかしき住家(すみか)なれ。
≪2番≫
浪(なみ)を子守の歌と聞き
千里寄せくる海の氣を
吸ひてわらべとなりにけり。
≪3番≫
高く鼻つくいその香(か)に
不斷(ふだん)の花のかをりあり。
なぎさの松に吹く風を
いみじき樂(がく)と我は聞く。
これが教科書に載っている「われは海の子」です。
ちょっと昔の言葉で書かれているので、わかりにくい部分がありますので、1~3番を自分なりに解釈したものを載せます。
≪1番≫
私は海の子です。潮騒(波の音)が聞こえる渚の松原に、煙が出ている質素なあの家が、私のなつかしい生家です。
≪2番≫
産湯に海水を使って、潮騒を子守唄と聞いて育ち、遠くから打ち寄せてくる波の力によって少年になりました。
≪3番≫
独特の磯の香りは絶え間なく香ってくる花の香り。海辺の松林に吹く風は、私にとって音楽のように聞こえます。
この歌詞に出てくる「われ(私)」にはもちろん両親がいたのでしょうけど、漁に出かけて親がいない(あくまでも推測ですが笑)間にも子守唄を歌ったり、子ども強く育て、「私」にとってもうひとつの親として海があったことが伝わってきたのではないでしょうか。一言でまとめると、「われ(私)」は海によって少年まで育ちましたということになります。
生まれて少年まで育つプロセスをここで歌われているから、小学生に教えるにはちょうどいい歌詞だったので小学校で教えるようになったのかもしれません。
「あれ?ちょっと待って?!ここでお話おわりなの?」と思いませんか?
生まれたときから少年になるまでのストーリーを書いてるんなら、どうして大人になるところまで書かないのはもったいない!
そう思われる読者の方も中にいらっしゃるのではないかと思います。
実はこの歌には続きがあるのです。
後述しますが、戦後さまざまな理由があってこの後の歌詞は削除されてしまい、歌われることがなくなってしまったのです。下に少年から青年へと育つ「海の子」の姿を描いた続きの歌詞を載せます。ちなみにメロディは1番から全部同じです。
≪4番≫
丈餘のろかい操りて
行手定めぬ浪まくら
百尋千尋海の底
遊びなれたる庭廣し。
≪5番≫
幾年こゝにきたへたる
鐵より堅きかひなあり。
吹く鹽風に黑みたる
はだは赤銅さながらに。
≪6番≫
浪にたゞよふ氷山も
來らば來れ恐れんや。
海まき上ぐるたつまきも
起らば起れ驚かじ。
これが3番からの続きの歌詞です。
≪4番≫
舟を操ってあてもなく、波にのってどこまでもいきます。とても深い海の底までも、私にとって海は遊びなれた広い庭のようです。
≪5番≫
何年もこの海で鍛えたこの腕は鉄よりも硬く、潮風にさらされた私の肌は真っ黒く日に焼けてしまいました。
≪6番≫
氷山が流れてこようとも、来るなら来いと恐れはしない。海を巻き上げるほどの竜巻が起ころうとも、起こしてみろと驚きはしない。
ついに少年は海に出て、波にのってどこまでも行くことができるように海を自由に操り、それとともに体が鍛えられ、肌も焼け、氷山も竜巻も怖がらずにむしろ挑んでいくくらいの、心身ともにどんどんたくましく成長する青年の姿がそこにありました。1~3番では少年時代のゆっくりとしたイメージがここにきて変わったのではないでしょうか?
でもこの「われは海の子」、これで終わりではないのです。
実はまだ続きがあるのです。
まことに勝手で申し訳ありませんが、夜も更け明日の仕事に影響が出そうなので、また記事を書きながらとても1晩で書ける内容ではないことに書いている途中で気づきました、。またこれ以上書くと読者の方もさぞかし疲れたと思いますので、キーボードを打つのをやめて、この続きは明日のブログにしたいと思います。
それでは皆様、おやすみなさい。
*********************************************
20年かけて日本の世直しを実現する!
「水戸黄門プロジェクト」
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のりを綴ります!!
なお読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
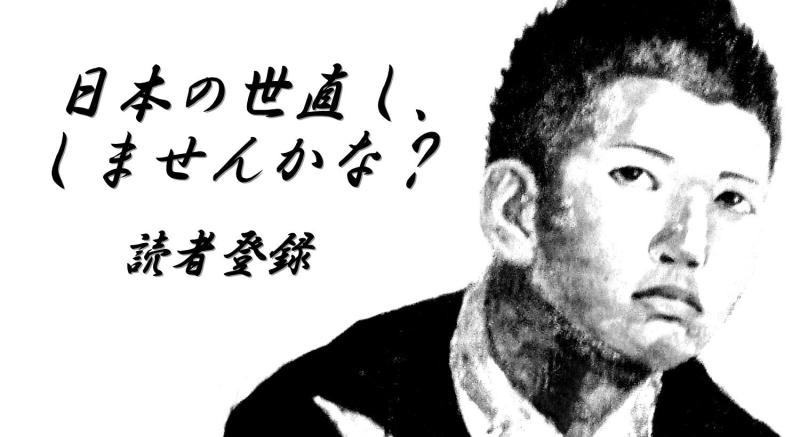
Follow me!!
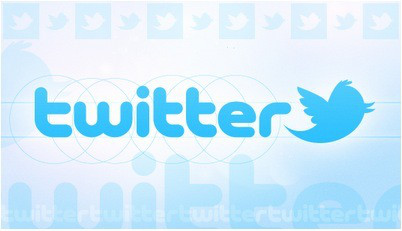
mixiもよろしくです!
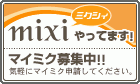
雪割草
最近ブログ更新できなくてすみません。
ブログ更新をお楽しみにしてる方、お待たせいたしました。
今日は先週の金曜日にお客様から頂いた「雪割草」のことを書きたいと思います。
3月末に大学を卒業して、4月1日に新社会人として働き始めて3ヵ月が経過しました。働き始めてから400人くらいのお客様とお会いする中で、お会いした瞬間に意気投合したお客様がいます。
そのお客様はというと植物がとっても好きな方で、何度かおうちにお邪魔した時にたくさんの木や草花をみせていただき、その中で大切に育ててこられた「雪割草」を頂きました。
【いただいた雪割草の写真】

写真だけを見ると「三つ葉のクローバー」と答えた方はハズレ(笑)
似てるようで違うんです。
■ 雪割草とは ― wikipediaより
ユキワリソウ(雪割草 学名:Primula modesta)は、サクラソウ科サクラソウ属の多年草。高山植物で日本全土の亜高山帯から高山帯に自生する。 高さは10cmほど。葉はへら形で、表面は緑色でしわが多く、裏面は淡黄の粉がある。花は3から10個の淡い紅紫色の合弁花。花期は6~8月。
春の雪解けのころに雪を割って伸びてくることから雪割草という名がついていますが、これは通称で葉が三角形に近い形であることから和名は「三角草」です。
雪を割って太陽に向かっていく草花って、本当に生命の力強さを感じますし、春の訪れを感じさせる草花です。
そして花期に咲かせる花はコチラ

国際雪割草協会より
いただいた雪割草から花が出てくるのが楽しみです。
こんな貴重なものをいただけるなんて、私はとっても嬉しいです。
ありがとうございます。
何か変化がある都度、また雪割草についてわかったことがあったらブログにて更新していきますね!
*********************************************
20年かけて日本の世直しを実現する!
「水戸黄門プロジェクト」
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のりを綴ります!!
なお読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
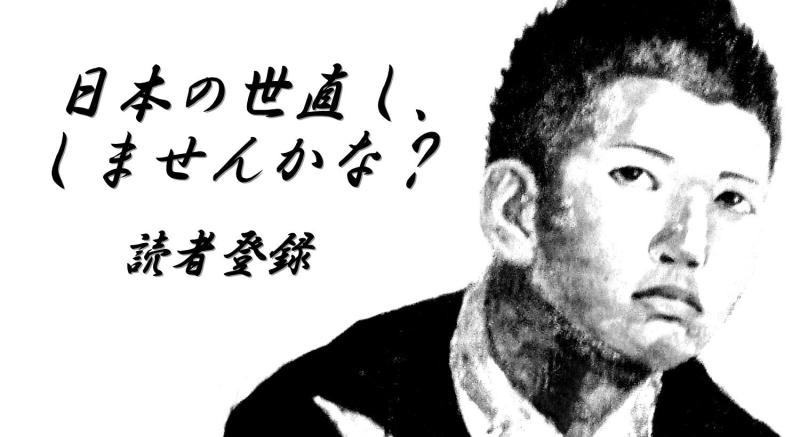
Follow me!!
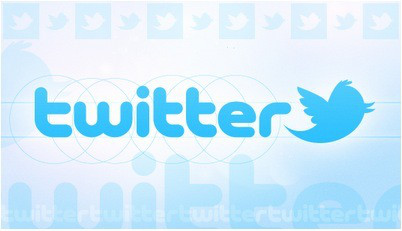
mixiもよろしくです!
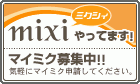
【告知】『日本の未来を考える~日本再活性のために、今、若者ができること~』
おはようございます。
この場をお借りして、友人が企画している講演会の告知をさせていただきます。
【日本の将来、今の積み重ね】
「KSIA一周年記念事業」~日本の未来を考える~
~日本再活性のために、今、若者ができること~
今年3月に東日本を襲った大地震、津波、そして原発事故。多くの方が犠牲となり、また多くの方がとても胸を痛め、罹災された方たちに「私たちにもできることは何か?」と考えたことがあると思います。
罹災地の復興には数年ではなく10~30年の歳月を必要とし、世代を超えて多くの人が力を合わせていかなくてはなりません。被災地の復興に、この先一番必要とされているのは復興に必要なお金だけでなく、これから日本の将来を担い、結婚し家庭を持ち、世代をつなげていく若者のエネルギーが期待されているのではないでしょうか。
そこでKSIA(一般社団法人 関西学生発イノベーション創出協議会)は罹災地、ならびに日本の再活性化のために、これからの日本に必要とされる若者の「今、できることは何か?」に焦点を当て講演会を開催し、この国のトップとして日本を見てきた元首相・鳩山由紀夫氏をお招きして、
■この国のトップとして見てきた「日本」について考えたこと、「日本を担う若者が持つべき視点とは?」
■東日本大震災、原発事故を通して私たちが描くこの国の将来とは?
をテーマにお話されます。
元首相がマスコミを通さずに、目の前で講演される機会はまたとありませんし、とても大きなテーマを扱った講演会で「今できることは何か?」と得られた気付きは、まさに「一生もの」であると思います!
この機会をお見逃し無く!
では、以下詳細です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この度はKSIA一周年記念事業~日本の未来を考える~日本再活性のために、今、若者ができること~
24歳の所感
本日5月8日、わたくし水戸勇佑は24歳を迎えました。
昭和62年の5月8日、日本という国、水戸という家に生を受けて、両親から「勇佑」という名前をいただき、今日に至りました。これまで無事で生きることができたのは、家族をはじめ、友人、これまで出会った人すべてのおかげであります。ありがとうございます。
今日のブログは「24歳の所感」と題して、24歳になった今の気持ちをお話したいと思います。
24歳になって1時間と15分が経過してブログを書き始めましたが、その間にいろんなことが頭の中を駆け巡りました。はじめに浮かんだこと、両親への感謝の気持ちです。今までは心のどこかで「誰かに祝ってほしい」ということを思っていたのですが、そんな気持ちよりも「お父さん、お母さん、ありがとう」ということを素直に感じました。
どうして今まで祝ってもらうことを望むばかりだったのに、今度は「ありがとう」という気持ちになったのかというと、働き始めて、家族がいるということが、いつも私を見守ってくれていることが、それこそ本当に「有り難いこと」であると感じるようになったからです。
社会人1年目の私。甘えとか妥協とか、そういうものが許されない厳しい環境に突然飛び込んで、日々の実践の中で目標を達成したときは達成感があるし、うまくいかなかったときは、「マイナス思考」という自分の悪い癖が出て、心が折れそうになったりすることもあります。
1ヵ月働いて仕事がうまくいくことなんて本当に数える程度で、うまくいかないことがほとんど。迷いながら仕事をしていて、気付けば夜9時になっても仕事が続いていたりします。
ところが、どんなに帰りが遅くなっても親は私を待っていてくれています。それも仕事がある日は欠かさず。
帰りが遅いということは両親に心配をかけているわけで申し訳ないと思っています。
それに普通なら「まあそのうち帰ってくるやろ」と寝てしまうところを、帰りを待っていてくれている。どんな親切なアカの他人でも待っていてくれないですよね。それが世界に60億の人がいる中で待っていてくれるのは、間違いなく自分の家族だけなんだろうなぁと思います。そういう意味で「有り難い」のですよね、家族の存在って。
家族がいつもしてくれていることに対して「ありがとう」といっても、親父や母は「家族なんだから当たり前、気にするな」というでしょう。でも何でもない、意識しなければ忘れてしまいそうな当たり前のようなことに対して感謝の気持ち、ありがたいと思えることがとても大事なことだと私は思いますし、いつも待っている親に何かできることがないかと考えなければなりませんね。
そう思うと、早く仕事になれて、職場から早く帰ってきて帰りを待っている両親を安心させることが明日からでもすぐできそうなことですね。それでもって疲れた顔ではなくて、元気な顔で「ただいまー!」って帰ってくることが仕事に出て行って帰ってくる子供に一番期待していることかもしれませんね。
会社は利益を生み出す場所であるゆえに厳しい。でも家に帰れば、家族がいて無条件に温かい。そんな家庭と家族があることが奇跡です。家庭と家族があるのは当たり前かもしれないけど、その当たり前を幸せに感じられるかどうか、感謝できるかどうか。己の誕生日に、とても大事なことに気付けたのではないかと思います。
家族がいるだけで、嬉しい。
24回目の誕生日にひしひしと感じたことです。
*********************************************
20年かけて日本の世直しを実現する!
「水戸黄門プロジェクト」
現代版・水戸黄門になって
日本を世直しする、その道のりを綴ります!!
なお読者になってくださる方を募集してます!!
もちろん助さん、格さんも募集してますよ★
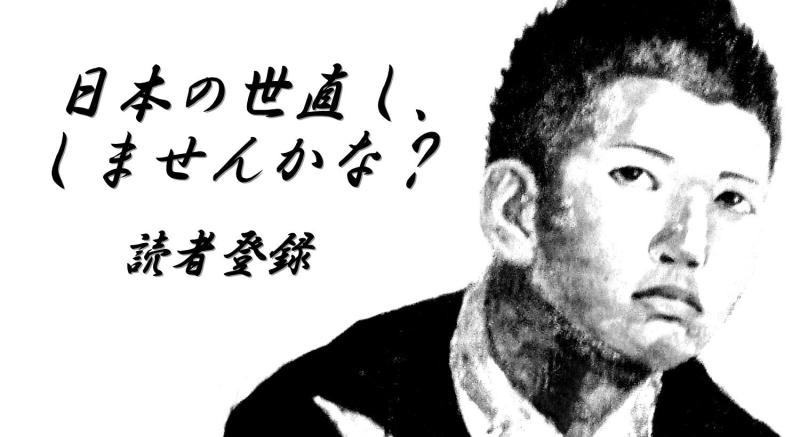
Follow me!!
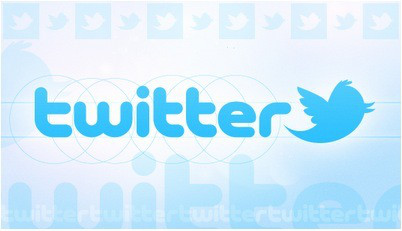
mixiもよろしくです!