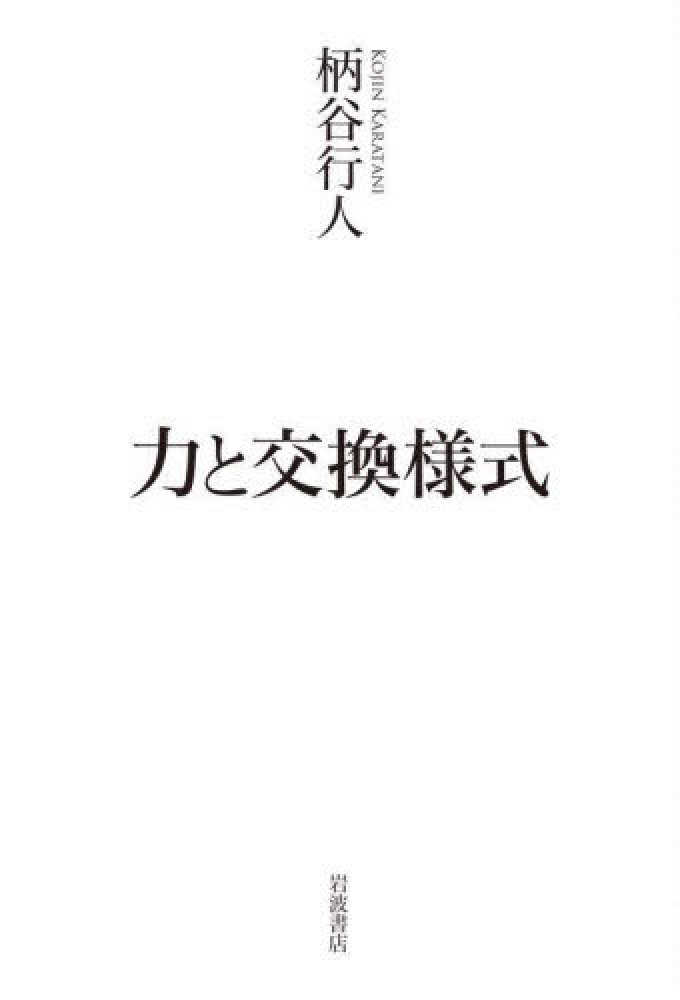ジュネーヴの国際連合欧州本部前にある『壊れた椅子』2019年撮影。
1997年に対人地雷廃棄条約(オタワ条約)締結を促すため彫刻家
ダニエル・ベルセが製作しハンディキャップ・インターナショナル他の
プロジェクトとして設置。地雷とクラスター爆弾の廃棄を訴えている。
【84】 社会構成体史のスキーム
――「交換様式D」とは何か?
重要なのは、定住前の「遊動民」の状態と、定住後の「氏族社会」――つまり交換様式A――との違いです。
『アルカイックな社会』の『支配的な原理である〔…〕交換様式A(贈与の互酬性)〔…〕は、太古からあった遊動的な狩猟採集民のバンド社会には存在しなかった。そこでは、生産物は〔…〕共同寄託(プール)され平等に分配された。これは純粋贈与であって、お返しを強いる互酬贈与ではない。そのため、個人を規制する集団の力が弱く、婚姻関係も永続的ではなかった。したがって、各人は自由であるとともに平等であった。
互酬性原理に基づく氏族社会は、遊動民が定着したのちに形成されたのである。定住によって富の蓄積が可能となるが、そのことは富や権力の差異、階級分解をもたらさずにいない。氏族社会はその危険性を、贈与・返礼の義務によって封じ込めた。〔…〕このため、氏族社会においては人々は平等ではあるが共同体に強く拘束され、自由な個人として存在することができないのである。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,pp.238-239.
柄谷氏は、狩猟採集民の社会では生産物が共同でプールされていた、と考えていますが、必ずしもそう考える必要はありません。なぜなら、共同貯蔵・管理が行なわれる場合には、管理者による私物化が避けられない。むしろ、そのような体制は不平等化の契機となるからです。このことはすでに何度か指摘しました。
「遊動民」の社会で重要なのは、共同のプールがあったかどうかではなく、各人の所有と消費を平等にするような進化論的圧力が、つねに働いていたということです。
しかし、「遊動民」社会での贈与・分配が、「互酬贈与」ではなく純粋な贈与で、集団の規制力が弱かったというのは、まったくそのとおりでしょう。
ソ連時代、《ボリバー(闘争)》コルホーズで指導するピオニール(赤色少年団)
一般作物栽培班長・社会主義労働英雄ワシーリイ・エフィモヴィチ・
プリヴェゼンツェフ氏〔1894-1981〕。 ©Wikimedia.
ところで問題は、マルクス/エンゲルスが未来の「共産主義」社会を構想するにあたって、「遊動民」社会ではなく、氏族社会をモデルにしたことにあります。柄谷氏によれば、それは、彼らがモーガンの描く氏族社会に依拠したためです。そこから帰結したのは、「生産手段の共有」を、共産主義ないし社会主義の決定的条件とする考え方です。「生産様式」を社会構成体史のカナメとする「唯物史観」の観点からは、そうならざるをえない。
しかし、「交換様式」の観点では、「遊動民」社会と「氏族社会」の違いはたいへんに大きいのです。「すなわち純粋贈与と互酬的贈与の違い、いいかえれば、個人が自由であるか互酬性によって縛られているかの違いは決定的に大きい。」「このように束縛を強いる氏族社会を始原に置くことの難点は、〔…〕そこからは〔…〕生産手段の共有にのみ力点をおく全体主義的社会が生じることになる」点にある(『哲学の起源』,pp.239-240)。これを別の言い方でいえば、「氏族社会」にあるのは、支配服従の関係を発生させない・対等に束縛しあうという意味での「自由」であって、個人の・他人からの自由(ソクラテスの自由,イソノミア)ではないのです。
加えて、マルクス/エンゲルス/レーニン流の「社会主義」では、「生産手段の共有にのみ力点をおく」結果として、生産手段を管理する国家官僚・党官僚が実権を握ることになり、生産者の自由が制限される以外は資本主義と変らない社会になってしまうのです。それは、「首長・祭司」層が生産物の共同のプールを管理し、その分配を牛耳る定住後の氏族社会(とくに穀物定住社会)をモデルとしたことの必然的帰結です。
『Dは、Aあるいは共同体の単なる回復ではない。Aを高次元で回復するということは、先ずAを否定すること無しにはありえないのである。』
柄谷行人『哲学の起源』,pp.240-39,41-42.
『高次元というのは、Aあるいは共同体の原理を、一度否定することを通してそれを回復することを意味します。〔…〕
マルクスが “高次元で” と言う場合、それが過去のもの(祖型)を一度否定することによってのみ実現される、ということを意味するのです。
まったく新しい歴史上の創造物が、〔…〕古い社会生活の諸形態〔…〕の写しと思い違いされることは、その通常の運命である。〔…〕この新しいコミューン〔1870年の「パリ・コミューン」――ギトン註〕は、〔…〕中世のコミューンの再現だと思い違いされた。〔マルクス『フランスにおける内乱』〕
〔…〕マルクスが言わんとするのは、パリ・コミューンは中世のコミューンの “高次元での回復” だということです。それはむしろ、中世のコミューンと似て非なるものである。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.25,35-36.
つまり、「Dは、Aの高次元での回復である」と柄谷氏が言う「高次元」とは、「先ずAを否定すること」だというのです。「A」の核心は、原遊動状態にあった「平等」が強迫的に回帰して形成された互酬義務(「お返し」をしなければならない)の束縛にあります。でも、こんな束縛は「原遊動」状態には無かったのですから、ほんとうに「原遊動」を回復するのであれば、このような束縛は無くさなければならない。
(柄谷氏がここでは忘れてしまっていることを)さらに言えば、「A」にある「自由」は、成員相互間に権力を発生させない・支配も服従もしないという行動規範によって、ある意味たがいに束縛しあう「自由」であって、そうした共同体的拘束からの個人の「自由・自立」(イソノミア)ではありません。
しかしながら、人は、意識的に、そのような束縛は不合理だから無くそうと願って無くすのではない。「Aを否定することもまた、人間の意志を超えたものとして」現れる。たとえば、「神あるいは天の」啓示として、「ダイモン」の命令として、それはやってくる。すなわち、歴史的には「Dは、呪術的=互酬的な宗教を否定する・普遍宗教として」,あるいはソクラテスの「ダイモン」として、先ず到来したのです(『哲学の起源』,p.240)。
ソ連時代のプロパガンダ・ポスター「コルホーズに行け」。©Wikimedia.
『普遍宗教は、交換様式Dを実現しようするものであるから、本性的に社会主義的な運動であった。』しかし、『19世紀半ば〔…〕以後、社会主義運動は宗教性を否定して “科学的” となった。が、そのような社会主義は、結局交換様式BやCが支配的であるような社会しか実現しなかったため、魅力を失ってしまった。』
柄谷行人『哲学の起源』,pp.240-241.
この考えは甘い※と私は思う。最終的に社会主義の評判を地に落としたのは、「BやCが支配的であるような社会しかできなかった」からではありません。そのような社会(資本主義社会!)のほうがまだマシだと痛感したからこそ、「社会主義」国の人びとは「社会主義」を打倒したのです。人びとに社会主義を忌み嫌うようにさせたのは、ソ連のスターリン専制、とりわけそこで行なわれた「大粛清・虐刹」の事実であり、巧妙に隠蔽されたそれらが白日の下に暴露されたことです。しかも、スターリン政権による陰謀・陥穽と「虐刹」の機構は、コミンテルンを通じて各国共産党幹部をも巻き込んで共謀・加担させたので、悪事の尖兵は世界中の左翼政権・政党に拡散してしまったのです。もちろん日本共産党(たとえば野坂参三)も日本社会党(当時)も例外ではない。これで評判が落ちなかったら、どうかしています。
註※ 柄谷氏が甘いわけではない。氏は、レーニンらの「ロシア10月革命」の実体は「軍事クーデター」であるとして、厳しい評価を下しています。それは、「民衆の自然発生的蜂起」から生じた「2月革命」の成果を「根こそぎ」奪い、「史上空前の専制国家の出現をもたらした。」「このような専制国家が生まれたのは、…ロシアにおいて “ひどくくずれた” 共同体があったことに原因がある」(『力と交換様式』,pp.307,340,346)。
スターリン専制を支えたのは「交換様式BやCが支配的であるような社会」などではありません。そんな社会は、地球上すべての資本主義国にもありました。しかし、スターリンが行なったような専制は、ナチスの「第三帝国」を除けば、当時世界中どこにもありませんでした。スターリン専制を支えたのは「B」でも「C」でもなく、「A」です。かつてツァーリ専制の基盤となった農村共同体の性格が、共産党支配の下で復活して、スターリン専制の基盤となったのです。つまり「A」の(低次元での)復活が、「B」を特別な専制形態としたのです。(ナチスの専制もまたAの低次元での復活に基いていますが、これは最終回(31)で触れる予定です)
私見ですが、農村共同体(Bの下に統合されたA)のこうした「二面的性格」を、社会科学のなかで最初に指摘したのは、大塚久雄氏(『共同体の基礎理論』)だと思います。それを柄谷理論に近づけて言うと、アジア的農村共同体は、一面では「自由対等」原理によって「国家」に抵抗しますが、他面では構成員を緊縛して「国家」の人民支配を媒介します。また、『哲学の起源』「附録」で強調されていたように、もともと「A」には、構成員の経済的「自由」を抑圧して「平等」性へ回帰させようとする傾向がありました。
柄谷氏は、『力と交換様式』では、「自由対等」原理のほうをもっぱら強調しているために、「A」が構成員の自由を抑圧する面が看過されて、原遊動的な「自由平等」に回帰しようとする「D」との違いが曖昧になってしまったのだと思います。
以前に「ザスーリチ草稿」を検討した際に指摘したように(⇒:マルクス解体(5)〔16〕(4))、マルクスは、ロシアのミール共同体について、その抑圧面(専制の基盤)の認識が甘かったのです。認識が欠落していた、と言ってもよいほどです。(「ザスーリチ草稿」が再発見されたのはロシア革命後ですが、レーニンらは、19世紀のロシアの雑誌に出ていたマルクスとマルクス派の論調には、革命前から同調していました。たとえば、『ロシアにおける資本主義の発展』)
こうして、最終的には、共産党による「クラーク撲滅」運動の結果、ミール共同体が復活し、スターリン専制を支えたのだと考えられます。そして、1970年代以後の各国「社会主義」の崩壊過程で、集団農場がまっさきに解体したのも、経済的能率うんぬん以上に、この抑圧面が嫌われたことが大きいのではないでしょうか。
ちなみに柄谷氏も、「D」の「高次元」の内容を、折り折りには述べています。それは、「共同体からの個人の自立」ということです。専制の基盤としての「共同体」は、これを抑圧する方向に働いたのです。「共同体からの個人の自立」の・「D」における先駆者として、『哲学の起源』ではソクラテスの思想が論究されていました。
『交換様式BとCが支配的である限り、それらを超えようとする衝迫が絶えることはない。つまり、何らかのかたちで交換様式Dが追求される。〔…〕
普遍宗教は、国家や共同体〔交換様式BやA〕に従属する宗教への批判、いいかえれば祭司・神官の支配に対する批判から生まれる。だが、〔…〕そのような批判は〔…〕宗教の枠組に回収されてしまわざるをえない。つまり新たな祭司・神官の支配に帰着する。いいかえれば、宗教は国家に回収されてしまう〔…〕
そこで私は、〔…〕交換様式Dが宗教というかたちをとることなしに現れることはないのか、と考え〔…〕その最初の事例を、イオニアの政治と思想に見いだした。』
柄谷行人『哲学の起源』,p.241.
【85】 危機における「D」の到来
――「平和連合」と「世界共和国」
『国家や資本を揚棄すること、〔…〕それを可能にするのは、高次元でのAの回復、すなわちDの力によってのみである。
ところがDは、Aとは違って、人が願望し、あるいは企画することによって実現されるようなものではない。それはいわば “向こうから” 来るのだ。
この問題は、〔…〕古来、神学的な問題、すなわち「終末」や「反復」の問題として語られてきたことと相似するものである。つまり「終末」とは、Aの “反復”、いいかえればAの “高次元での回復” としてDが到来する、ということを意味する。
マルクス以前にもそれを考えた者がいた。カントである。彼は社会の歴史を、自然の「隠微な計画」として見た。つまりそこに、人間でも神でもない何かの働きを見いだしたのである。〔…〕彼はそれを「自然」と呼んだ。〔…〕そこに謎が残ったままであった。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.395-396.
「Dは、人が願望しあるいは企画することによって実現されるものではない。それは、いわば “向こうから来る”」――という柄谷氏の言い方は、しばしば誤解を招いています。意識的・計画的な政治運動や協同組合活動,アソシエーショニズムなどに対して、「やっても無駄」と宣告しているかのように受け取られるからです。
しかし、柄谷氏自身、2000年以来「ニュー・アソシエーショニスト運動」(NAM)に献身しています。組織体としての「NAM」は 2002年に解散しましたが、その後も現在まで、運動じたいは続いているそうです。柄谷氏の上記の発言は、運動をすることと矛盾するような不可知論や神秘主義を唱えているのではなく、もっと常識的なことを言っているのです。それは、↓次の文を読めば明らかだと思います:
『2019年末から顕在化したコロナ疫病の流行があったため、多くのアソシエーションは、これまで経験したことのない類の困難に直面することになった。〔…〕しかし、この間、アソシエーショニスト運動は見直されてきたのではあるまいか。生産,流通,金融などの現在の諸システムの問題点が浮き彫りになったためだろう、多くの人が自給自足や地域のネットワークなどの重要性に気づき始めたようだ。〔…〕
私は、未来の社会は「向こうから来る」と言ってきた。これは、自分の意図や企画を超えて起こる、という意味である。実際、NAMを立ち上げたのも、その一環として「批評空間社」という出版社を立ち上げたのも、依頼を断れなかったり、事情にせまられたりして、しかたなくという流れのなかであった。つまり、それらは「向こうから来た」のである。同様の意味で、コロナをきっかけに、困難とともに、新たなアソシエーションの可能性が向こうから来た、といえるのではないだろうか。』
柄谷行人『ニュー・アソシエーショニスト宣言』,2021,作品社,p.11.
つまり、「向こうから来る」とは、企画したとおりに事が運ぶわけではない、というほどの意味です。計画したようにならないこともあるし、逆に、予想もしなかった成果が得られたり、予期しないことが起きて運動が飛躍的に発展することもある。世界大戦のような、誰の予想をも上回る惨禍を惹き起してしまうこともあるが、その結果として国際的な平和組織や軍縮条約が結ばれたり、専制国家が倒れて民主国家になったり植民地が解放されたり、といったことも起きるわけです。
‥だから時の流れに任せるのがよい、などと言えないことは勿論でしょう。大戦が起きる前から、平和組織の試みや専制支配への抵抗、植民地の独立運動などが行なわれていたからこそ、それらは実現したのです。
マルクスに『先行する重要な著作がある。カントの『永遠平和のために』〔1795年〕である。これはフランス革命〔1789-95年〕ののち、周辺の諸国による干渉とそれに対する革命防衛戦争がおこることを予期して書かれた論著である。〔…〕
彼は当時、世界戦争が迫っていることを予感していたのだ。彼の考えでは、それまであった「平和条約」は、いわば休戦協定であって、戦争をなくすようなものではない。条約はいつでも破られるし、むしろ条約が戦争の原因になってしまう。そこで彼は、「平和条約 pactum pacis」にかわって「平和連合 foedus pacificum」を提起した。〔…〕後者は、「すべての戦争が永遠に終結するのをめざす」ものである。〔…〕
国際法は、自由な国家の連合に基礎をおくべきこと〔…〕
諸国家がそれぞれ自分の正義を主張するしかたは、〔…〕裁判所がある場合のように訴訟という形をとることは不可能で〔当時は、国際的な裁判所や仲裁機関は存在しなかった――ギトン註〕、戦争によらざるをえない。だが、戦争によって、〔…〕勝利によって、どちらが正義か決まるわけではなく、また平和条約によって、なるほど今回の戦争は終結するが、戦争状態(いつも新しい口実を見つけようとしている状態)は終結したわけではない。〔…〕
それでもなお、道徳的な立法を行なう最高権力の座にある理性は、争論を解決する手段として戦争を行なうことを断固として禁じ、平和状態を直接の義務とする。が、この平和状態は、諸民族のあいだの条約によらずには、樹立も保障もできないのである。以上の理由から、平和連合と呼ぶべき特殊な連合が存在しなければならない。〔…〕
この連合が求めるのは、何らかの国家権力を手に入れることではなくて、もっぱら、ある国家と、その国家と連合した他の諸国家の自由を維持し、保障することであって、しかも諸国家はそのために、(自然状態にある人間のように)公法や公法の下での強制に服従する必要はないのである。〔…〕こうして、国際法の理念にしたがって、諸国家の自由な状態が保障され、連合は〔…〕次第に遠くにまで拡がっていくのである。〔…〕
そもそも国民〔ギトン註――個人〕のあいだには市民的な社会的連合があって権利を保障し、国家のあいだでは国家連合が権利を保障するはずである。しかしこうした自由な国家連合が存在しないのならば、どのようにして自国の権利を〔…〕基礎づけることができるというのだろうか。〔カント,宇都宮芳明・訳『永遠平和のために』,岩波文庫,1985,pp.39,43-46.〕※』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.286-287.
註※ 柄谷氏の引用箇所の前後に拡張し、また、光文社古典新訳文庫版を参照して、訳文を適宜改めた。
日本語には「和平条約」ないし「講和条約」という便利な言葉があります。戦争が終わった後で交戦国間で締結する「平和条約」は、実際のところは「和平条約」にすぎません。
他方、カントが提唱した「平和連合」のほうは、第1次大戦後に「パリ不戦条約」となって結実し、それを実効力あらしめるために「国際連盟」が設立されました。
しかし、カントの考えでは、上で述べられている・国家のような権力を持たない「平和連合」は、あくまでも過渡的な次善の体制でした。カントは、“理性” が最高の座に立って裁定を下せば、諸国はそれに従う、というような非現実的なことを考えていたわけではありません。最終的には、強制的な権力と合理性をそなえた「世界共和国」が成立して、諸国家はそのなかに解消するのが、――遠い将来のことだけれども――理想だと考えていました。
『他国との関係のもとにある国家が、法の定められていない状態、戦争だけが支配する状態から脱け出すには、理性的に考えるかぎり、次の方法しか残されていない〔…〕国家も個々の人間と同じように〔…〕未開な状態における自由を放棄して、公的な強制法に服し、つねに大きくなりながら・ついには地上のすべての民族を含むようになる国際国家を設立するほかには道が無いのである。』
カント,中山元・訳『永遠平和のために/啓蒙とは何か 他3編』,2006,光文社古典新訳文庫,p.183.
これ↑を見ると、カントは、ホッブズが自然状態の「万人の戦い」を終らせるために絶対主義国家への服従を提唱したように、諸国家・諸国民は自らの権利を放棄して「世界共和国」に服従するのが最高の理想だと考えていたことが判ります。もちろん、カントの場合には、「世界共和国」は、理性に基く完全な自由・平等〔といっても法的意味での〕の共和体制でなければならないのですが。
じっさい、カントの「平和連合」をモデルとして設立された「国際連盟」には、戦争を抑止する力が乏しく、アメリカのように最初から加入しない国、また日本帝国のように勝手なことをやって脱退する国が続出したので、まもなく世界は第2次大戦に突入したことは周知のとおりです。
その反省のもとに、第2次大戦後に設立されたのが「国際連合」です。「国際連盟」に実効力が無かったのは、カントの言う「国家権力を手に入れる」ことを求めないという理想主義が、現実の抑止力としては無力だったということにほかなりません。そこで、第2次大戦後の「国際連合」は、最初からアメリカ,ソ連などの大国の利害を調停する役割(安全保障理事会など)を濃厚に持つ機構として作られました。そのため、今度は逆に、その面から(常任理事国の拒否権発動など)しばしば機能不全に陥っています。なかなか理想通りにはならないのが現状なのです。
ところで、柄谷氏がカントの「永遠平和」論に注目するのは、それが「交換様式D」の現れ方について重要な示唆を与えてくれるからです。
『カントの考えでは、諸国家の連合(アソシエーション)は、人間がその意志によって作るようなものではないし、また、その意志によって斥けられるようなものではない。それを作る主体〔…〕は、人間であ』ると『同時に、人間が意識しないような何かである。それをカントは「自然」と呼んだ。〔…〕
自然は人間を』して『いろいろな試みをさせるが、最終的には、多くの荒廃や国家の転覆を経て、さらに国力をことごとく内部から消耗させた後に、これほど多くの悲惨な経験をしなくとも理性ならば告げることのできたこと、つまり野蛮人の無法状態から抜け出して国際同盟を結ぶ方向へ追いこむのである。〔『世界市民的見地における普遍史の理念』「第7命題」, in:『カント全集』,14,岩波書店,2000,p.13.〕
人類の歴史を全体として考察すると、自然がその隠微な計画を遂行する過程と見なすことができる。ところで、この場合に自然の計画というのは、――各国家をして、国内的に完全であるばかりでなく、さらにこの目的のために対外的にも完全であるような国家組織を設定するということにほかならない。〔op.cit.「第8命題」, in:『啓蒙とは何か 他4篇』,1950,岩波文庫,p.42.〕
自然の計画の旨とするところは、全人類のなかに完全な公民的連合を形成せしめるにある。〔op.cit.「第9命題」, in:『啓蒙とは何か 他4篇』,1950,岩波文庫,p.45.〕
このように言うとき、カントは世界史を、〔…〕自然が「隠微な計画」を実現する過程として見たのだ。彼がここで言う「自然」は、「神」の言い換えではない。〔…〕神が作ったものではなく、人間が作ったものだが、にもかかわらずそれが人間を超えた「力」として働くことを示唆した〔…〕。それを「自然」と呼んだとき、カントは、私が言う「交換様式」(D)のようなものを感知していたと考えられる。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.287-291.
つまり、カントの考えでは、人類は無限の進歩に向ってたゆみなく前進してゆく‥‥というわけではないのです。もしも人類が「理性」のカタマリであったなら、そう言えたかもしれません。しかし、「理性」よりはるかに強い「欲望」に引きずられて人類は互いに争い合い、たえまなく戦争をして、その結果、いちじるしい惨禍を身に受けることになる。そうした経験を通して初めて、国家の主権も個人の権利も制限して「平和連合」を結び、戦争を防がなければならない、ということに気づくのです。人類の来た道は決してまっすぐではなく、このように縺れてジグザグな隘路の積み重ねでした。それでも、太古からの歩みを遙けく見通せば、あたかもある一定の方向に向っているかのように、見えなくもないのです。
それはまるで、人類史全体を見据えている何者かが宇宙にいて、人類がそちらのほうへ行くように、恐るべき災いを次々と起こして追いやっているかのようです。それを、カントは「自然」と呼ぶ。しかしそれは、自然環境に備わっている法則でも、神でもなく、人類自身が意図せずに作り出した「力」にほかならないのです。
『カント〔…〕は社会の歴史を、自然の「隠微な計画」として見た。つまりそこに、人間でも神でもない何かの働きを見いだしたのである。〔…〕彼はそれを「自然」と呼んだ。〔…〕
私の考えでは、自然の「隠微な計画」とは交換様式Dの働きを意味する。たとえば、カントが『永遠平和のために』で提起した「世界共和国」の構想は、人間が考案したものにすぎないように見える。その意味で交換様式A〔の回復をめざすユートピアニズムやアソシエーショニズム――ギトン註〕と類似する。したがって、無力である。
ゆえに彼の提案した国際連合〔「平和連合」構想――ギトン註〕は、以来2世紀にわたって常に軽視されてきた。しかしそれは消えることなく〔ギトン註――「国際連盟」「国際連合」の設立となって〕回帰してきた。今後にも改めて回帰するだろう。そしてそのときそれは、AというよりもDとして現れる、といってよい。
そこで私は最後に一言いっておきたい。今後に、戦争と恐慌、つまり、BとCが必然的にもたらす危機が幾度も生じるだろう。しかし、それゆえにこそ、“Aの高次元での回復” としてのDが必ず到来する、と。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.396.
柄谷氏は、「D」としての「世界共和国」に、ヘゲモニー「国家」とその「資本」が世界を支配する・現状の世界システムに対して衝撃を与えるような、何らかの《力》を見ているようです。それは、国家と資本の “廃絶” に至ることはないとしても、その《力》は何度も現れ、そうして現状の「資本=ネーション=国家」群を、それらとは大きく異なったものに変化させてゆくことになる。
しかし、その一方で、カントの「世界共和国」は、柄谷氏が引用する断片を見ても、「理性の法」を実現しうるだけの強い権力と公正さを備えた・完璧な国家であるように見えます。
国家の “揚棄” か? 完璧な国家への権力集中か? ‥‥ここにはギャップがあります。したがって、ここで考察を終らせると、私たちは迷宮のなかに放り出されてしまう。
そこで、このレヴューは、あと2回つづきます。そのなかで、とりあえずの出発点として踏みしめられるだけの・何らかのヒントが得られることを期待したいと思うのです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!