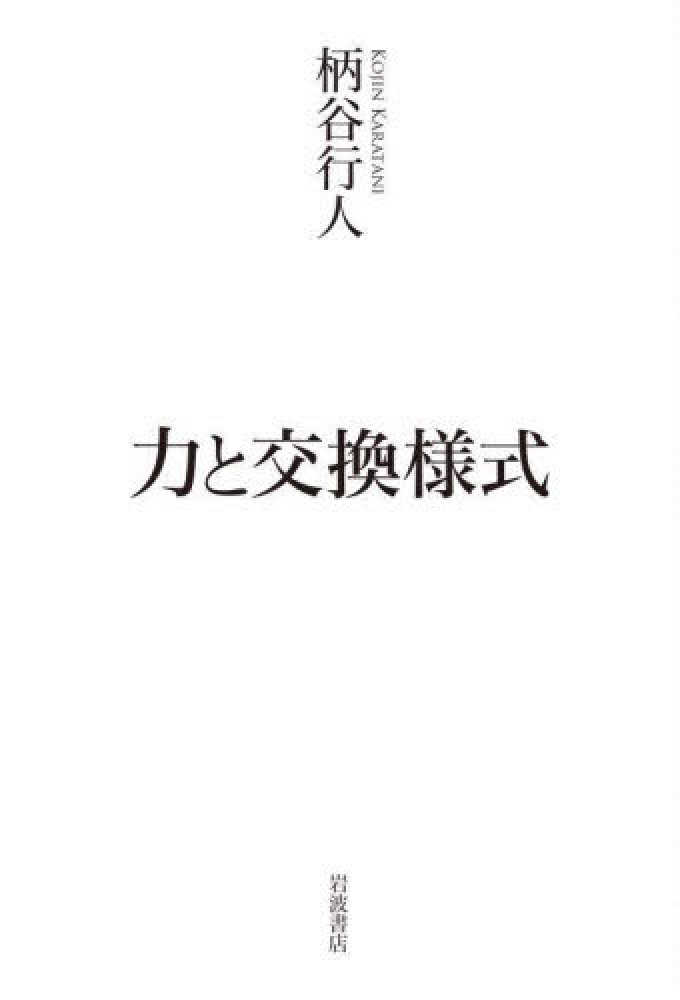有島記念館前の「有島武郎像」(上),「狩太共生農団入口」碑(下左),
「農場解放記念碑」(下右)。北海道ニセコ町有島。1922年有島武郎は自有
の有島農場を小作人に解放した。以後、元小作人らは「狩太共生農団」と
改称、組合共有の農場として協同経営し、戦時中の困難をも乗り越えた。
ところが戦後、米軍は農場の存続を認めたにも拘らず、日本政府は農団を
共産主義と決めつけ解散を命じた。現在は記念館と多数の旧跡が残る。
【82】 「B」に屈服する「科学的社会主義」
「ユートピアン社会主義」とは、「交換様式Aにもとづく社会を拡大することである。」「科学的社会主義」とは、「それを先ず、交換様式Bの力によって実現することである。通常は、それがマルクス=レーニン主義として知られてきた」が、「1991年ソ連邦の崩壊によって〔…〕回復不能なほどに失墜してしまった。」そこで、それに代わって広がったのが、「議会制民主主義を通して、国家の力を制限しつつ、同時に資本主義を制限しようという考え」、つまり「社会民主主義」である(柄谷,p.393)。つまり、「社会民主主義」は、「Aの拡大」を「B」すなわち国家権力の力で実現しようとする点では、「マルクス=レーニン主義」と何ら異ならない。
エンゲルスは、1880年に『ユートピアから科学への社会主義の発展』を出版して名声を博し、一躍マルクスと並ぶ革命運動の指導者となった。日本では、この本の題名が『空想から科学へ』という誤解を招く言い方に変えられてしまった。それにしても、エンゲルス自身がこの時に「科学的」社会主義構想の実現手段として考えていたのは、あくまでも「社会民主主義」のやり方だった。
しかし、「社会民主主義」にしろ、「マルクス=レーニン主義」にしろ、このような「科学的社会主義」の「考えには本来、限界がある。」(柄谷,a.a.O.)
科学的社会主義は、『国家や資本主義経済を、人びとの自由な意志によって制御できるものであるかのように見なしている。しかし、交換様式の観点から見れば、CやBは人間の意志を超えた「力」をもつ。民主主義的な国家体制において、人々は自由になったと考えているが、CやBの「力」に対して、いっそう屈従的になったにすぎない。そして、そのことに気づきもしない。しかもそれ〔気づかないこと――ギトン註〕が “科学的” な見方だと考えている。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.393.
現代の民主主義体制のもとで人びとは「いっそう屈従的になった」と柄谷氏は指摘していますが、これは、交換様式Bを、階級的支配などではなく、国民の国家への自主的な「服従」に力点をおいて理解する氏の考え方からすれば当然のことと思われます。つまり、私たちは「民主主義」を尊重するという観念のもとに国家に「服従」している。たまにそれに逆らう者が現れると、自民党から共産党まで「民主主義を守れ」の大合唱が起こって、不正な拘禁も是認されてしまう。「民主主義を守れ」は、「国家を守れ。どんな不正にも私たちは服従します」の言い換えにすぎません。これが「交換様式に伴なう観念の力」です。観念による “間接強制” が意識されないだけ、江戸幕府の専制よりも、明治政府の強権よりも、私たちはいっそう屈従的になっています。
同じことは交換様式Cにも言えるでしょう。こちらの場合には、「観念の力」は、資本をあがめる「物神崇拝」です。
ニュー・ラナーク↑はスコットランドの村。18世紀末に水力を利用した紡績工場
と労働者住宅が建てられ、産業革命の先進地となったが、19世紀初めから協同組合
経営となり、組合員のひとりロバート・オーウェンによる労働者の福祉・教育を
重視した社会改良的経営によって広く知られるようになった。©Wikimedia.
『それらと比べると、Aにもとづく「ユートピアン社会主義」は、たんなる空想と見なされている。そして古い話だと思われている。だが、〔…〕Aにもとづく「ユートピアン社会主義」は、CとBの “力” から人を相対的に自立させる在り方として、今なお健在である。〔…〕
たとえば、ロバート・オーウェンが創始した「協同組合」は、今もさまざまなかたちで存在し、機能している。また同様のことが、フーリエが創始した「産業的協同体」(ファランジュ)についても言える。
さらに、〔…〕プルードンが唱えたアソシエーショニズム〔…〕は、アソシエーションを拡大し、国家や資本を必要としないような社会を創り出そうとするものである。〔…〕彼が唱えた人民銀行や相互主義的交換組織なども、現在、世界各地に存在している。〔…〕一例として、1980年代にマイケル・リントンが提唱した LETS〔local exchange trading system 地域交換取引制度〕を挙げておく。〔…〕地域通貨によって脱資本主義的な社会システムを創出するものである。また、私自身が 2000年以来、そのようなアソシエーショニストの運動をささやかながら続けている。詳しくは、『ニュー・アソシエーショニスト宣言』,2021,作品社.を参照されたい。〔…〕
もう一つ例を挙げれば、後進資本主義国でまだ残っている農村共同体を、「協同体」(アソシエーション)すなわち・個人が自由独立性をもつような共同体に変える試みがある。交換様式でいえば、それはBやCの下で半ば埋もれているAを取り戻そうとするものである。スペインの協同組合モンドラゴンの〔…〕ように大規模に行われている例もある。また米国では、再洗礼派の集団アーミッシュがA的な共同体を広げている。〔…〕
アーミッシュは厳格ではあるが、つねにメンバーの自由意志を重んじる。たとえば、洗礼を受けるかどうかは完全に各自の選択にゆだねられ〔…〕子供には、8年間の通学期間のあと、無期限の猶予期間が用意され〔…〕この間に一般社会の生活を経験して、その上で洗礼について決める。しかし、9割近くが洗礼を受け、また生涯アーミッシュとして生きる。その結果、彼らの人口は 20年ごとに倍増している。〔堤純子『アーミッシュの老いと終焉』,未知谷,2021〕』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.393-394,414(6)(7).
柄谷氏の分類を図式化すると、つぎのようになるでしょう:
ニューヨーク州モリスタウン近郊のアーミッシュの村。©Wikimedia.
日本では、「科学的社会主義」がまだしも現実的なものであるのに対し、「ユートピアニズム」は空想的で、実際に行なわれるようなものではないという誤った常識が、今も支配しています。しかしそれは 50年以上前の常識です。現在では、「ユートピアニズム」のほうが、局地分散しているとはいえ、世界中で行なわれているのに対し、「科学的社会主義」のほうは、2つとも現実性を喪失してしまっています。
「マルクス=レーニン主義」が掛け声以上のものでないのは、言うまでもないでしょう。大陸中国も北朝鮮もロシアも、現在では単なる「不自由な資本主義国」です。「社会民主主義」も、SPD執権下のドイツを見ればわかるように、より公正・公平な資本主義をめざすものにすぎません。「社会民主主義」が無意味だというのではありません。ただ、それは、福祉国家資本主義のひとつの在り方なのです。というのは、「社会民主主義」に基いて、「国家」に依拠して再分配や差別解消の政策を実施すればするほど、ますます「国家」の力を強めることになり、人びとはますます強く「国家」と資本に服従することとなるからです。現代の「社会民主主義」は、資本主義をより良くし、できればより長く延命させるための運動です。それ以上でも以下でもありません。
そして、もうひとつ注意しておきたいのは、柄谷氏はこれらをすべて、――「科学的」社会主義にしろユートピアニズムにしろ――「交換様式Aにもとづく運動」「Aにもとづく社会を拡大すること」「交換様式Aを取り戻そうとするもの」と位置付けていることです。つまり、これらは「D」ではない。Aの「高次元における回復」ではないのです。
というのは、これらには「原遊動Uの強迫的回帰」という性格が見られません。また、いずれも意識的・計画的な運動であって、そこに、これらの運動の長所も、また限界もあるのです。
『Aに依拠する対抗運動〔↑上図「ユートピアニズム」の諸流――ギトン註〕が概してローカルにとどまり、BやCに十分に対抗できるようなものとなりえない〔…〕ことも、否定しえない事実である。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.394.
そこで、この「Aの拡大」を、「国家」つまり「B」に依拠して進めようという「科学的社会主義」の主張が出てくるわけですが、このやり方では、「国家」はますます強くなっていくことになります。「B」:つまり「国家」の支配力と人びとの「国家」への無意識な屈従は、どんどん大きくなってとどまるところを知りません。その結果、AはBに「取りこまれる。具体的に言えばネーション=国家が存続」し強化される。ネーションとネーションが衝突して、戦争も起きやすくなる。「国家」の制御のもとに入ったはずの資本「Cもやがて復活」して、「国家」の軛を脱して猛威を振るうようになる。「国家」は総力をあげて再分配政策(ばら撒き)をしているのに、格差がどんどん開いていく、という結果になるのです。
『では、国家や資本を揚棄すること、すなわち、交換様式で言えばBやCを揚棄することはできないのだろうか。できない。というのは、揚棄しようとすること自体が、それらを回復させてしまうからだ。
唯一可能なのは、Aにもとづく社会を形成することである。が、それはローカルにとどまる。BやCの力に抑えこまれ、広がることができないからだ。
ゆえに、それ〔国家と資本の揚棄――ギトン註〕を可能にするのは、高次元でのAの回復、すなわちDの力によってのみである。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.395.
こうして、いよいよDが語られる時が来ました。私たちはすでに、本書の最後の節に入っています。
しかし、柄谷氏の結論に向かう前に、ここでもういちど、「交換様式A・B・C・D」の理論を整理しておきたいと思います。
『力と交換様式』の 10年前に書かれた『哲学の起源』には、末尾に、その時点での柄谷氏の理論構想を要約して述べた「附録」がついています。次節では、この「附録」を見ながら、この間の「柄谷理論」の変化発展をあとづけ、「交換様式論」を、より立体的なパースペクティヴのもとに見ることとします。
【83】 社会構成体史のスキーム
――柄谷構想の変遷
最初に見ておきたいのは、“4象限” の図です。↓こちらは、『哲学の起源』に掲げられているものですが、「D」の位置に注目してほしいと思います。「D」は「A」のすぐ下に来ています。「A」の対角の位置にあるのは「C」です。
この位置関係には、論理的な意味があると思われます。縦軸が「不自由⇔自由」,横軸が「不平等⇔平等」を表わすと解釈できるからです。つまり、「A」(氏族社会)とは、平等だが自由ではない状態。「C」(貨幣・商品交換)は、自由だが平等ではない。「B」(国家)は自由でも平等でもない。そこで、自由かつ平等な状態ないし原理は、「D」の位置に求めなければならない、ということになります。だから、「D」の実体は「Ⅹ」になっています。
『力と交換様式』には、図は掲げられていません。紹介本の『柄谷行人「力と交換様式」を読む』に掲げられた図は『哲学の起源』と同様ですが、「D」の「Ⅹ」が、「Aの高次元での回復」という説明になっています。
これらを踏まえて加筆したのが、次の図です:
しかし、この図も完全ではありません。柄谷氏が本書『力と交換様式』に4象限図を掲載しなかったのは理由があると思います。たとえば、4象限図では、「A」は「平等・不自由」の領域になっていますが、氏族社会は必ずしも「不自由」ではないのです。原初の氏族社会の成員は、相互のあいだに権力を発生させない・支配も服従もしないという意味での「自由・対等」の行動規範を互いに保持していました。それによって氏族社会は、「国家」の形成を防ぎ、外来「国家」からの併呑圧力に対して抵抗していたのです。
柄谷氏はこの点を、前著『哲学の起源』のあと本書執筆までの間に、モーガン『古代社会』とマルクスによるその摘要を再読することによって発見したのだと思います。ですから、「4象限図」は、あくまでも参考図であって「柄谷理論」の正確な反映ではありません。なぜなら、「柄谷理論」にとって本質的に重要な「原遊動性(U)」は4象限図には表わしようがないからです。
以下、『哲学の起源』の「附録」を見ていきますが、まずはかなり細かい点からチェックしていくことになります。
『共同体や家族の内部で見られるのは、〔…〕贈与とお返しという互酬交換、すなわち交換様式Aである。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,pp.235-236.
本書『力と交換様式』では、「A」すなわち「互酬交換」は、共同体と共同体の間で、つまり「共同体の外部でのみ」行なわれるもので、氏族共同体の内部にはそれは無かったと述べられていました。しかし、この点は、前著のほうが正確だったと思います。柄谷氏は、本書ではマルセル・モースに引きずられたのだと思います。
「交換様式A」は、氏族共同体の内部でも、共同体の間でも行われていました。とくに共同体内の「A」は、贈与分配と弱者扶助による《平等化》という・氏族社会を維持するうえで重要な機能を果たしています。そのことが、氏族社会が「国家」(B)に抵抗する基盤ともなっています。
倒されたレーニン像。ルーマニア・ブカレストの広場に 1990年まで立っていたが
今はモゴショアヤ城教会の裏庭に棄てられている。2009年撮影。©Wikimedia.
『交換様式Dは、交換様式Aが交換様式B・Cによって解体されたのちに、それを高次元で回復するものである。いいかえれば、互酬原理によって成り立つ社会が国家の支配や貨幣経済の浸透によって解体されたとき、そこにあった互酬的=相互扶助的な関係を高次元で回復するものがDである。
Dに関して重要な点は、第1に、A・B・Cと異なり、想像的な次元に存在するということである。またDはたとえ想像的なものであるとしても、たんなる人間の願望や想像ではなく、むしろ人間の意志に反して生まれてくるものである。
以上の点は、交換様式Dがまず普遍宗教において開示された〔…〕ことを示唆するものである。』
柄谷行人『哲学の起源』,2012,岩波書店,p.236.
前半部分は、本書『力と交換様式』でも、「交換様式D〔…〕とは、BとCによって封じ込められたAの “高次元での回復” にほかならない。」(p.158)と言っているのと同じで、それをわかりやすく説明していると言えます。
しかし、問題は後半です。「交換様式A,B,C」が生産関係と同様に社会の「経済的ベース」であって、そこから「観念的な力」を生じさせるものであるのに対し、「交換様式D」は「想像的な次元に存在する」が、「たんなる…願望や想像ではなく、むしろ人間の意志に反して生まれてくる」と言う。たいへん不可解な説明なのです。
「D」は、「経済的ベース」を欠いた「観念的な力」だというのでしょうか? だとすると、「交換様式論」のほかの部分と整合しないように見えます。「経済的ベース」から「観念的な力」が生じる、というのが「交換様式論」の理論的前提だからです。
あるいは、こう考えられるでしょうか? 歴史上繰り返し現れてきた「D」は、いわば、いつか到来する第4象限の交換様式(自由かつ平等)の前触れであった。それはいまだ、現実の経済関係とはなっていない。なっている場合にも、局地分散的であったり、他の経済関係の下に包摂された弱い萌芽であったりして、ほとんど影響力をもたない。しかし、観念の上では、それを「見る」人には、眼の前の現実以上に現実的なもの、あるいは必然的に到来するものと感じられる。だからといって、それはその人限りの「単なる願望や想像」ではない。個人の主観とはしばしば相反するような、客観的・実体的基盤を有している。フロイトはそれを人間の前意識的な「超自我」で説明し、ブロッホはそれを、やや神秘的なレトリックで「未だ生成しないもの」「中断された太古の道」などと表現した。
それをあえて「経済的ベース」の論理で言うならば、「BとCによって封じ込められているA」ないし「U」が反復噴出しようとする圧力が、それらの “高次元での回復” を求めて強迫的な観念として現れる。それが「D」だ。そのようなしかたで、「D」もまた「経済的ベース」に基礎をもっているのだ、と。
それでは、本書『力と交換様式』では、どんな説明になっているでしょうか?
『晩年のマルクスとエンゲルスは』、「科学的社会主義」とは『異なる観点から共産主義を見ようとした。〔…〕マルクスはその鍵を氏族社会に、エンゲルスは〔…〕原始キリスト教に見いだしたのである。〔…〕彼らがこの時考えたのは、事実上交換様式Dという問題であった。Dは、A・B・Cが経験的に実在するように見えるのに対して、たんに観念的・想像的なもののように見える。実際、それは宗教的・神学的な問題として扱われてきた。しかし、〔…〕Dが宗教的だというのは〔…〕正確ではない。なぜなら、いわゆる宗教には交換様式A・B・C・Dが同時に含まれているからだ。
今日世界宗教と見なされる諸宗教、諸宗派はすべて、交換様式Dに根ざしていると言ってよい。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.389-390.
「Dは、A・B・Cが経験的に実在するように見えるのに対して、たんに観念的・想像的なもののように見える。」……「見える」というあいまいな言い方でお茶を濁してしまっています。「見える」けれども、じつは「経験的実在性」をもっているのだ、というのでしょうか? そうでないのでしょうか? そのあとは話が宗教にそれて行ってしまいます。
ともかく、柄谷氏は本書では、前著とは違って、「想像的な次元に存在する」とは断定していません。そして、「宗教的だというのは」不正確だと言っていますが、それでは、宗教以外のどんな現れ方をするのか? 観念的でも想像的でもない現実的なものとなって現れることが、果たしてあるのか? 観念として現れるとしても、現実的・物質的な次元と何らかの関係を持ってはいないのか? ‥‥そうした点の追究に向かって行かないのが、たいへんに不満です。
柄谷氏の本書での説明は謎を残しています。これらの点の展開を期待しながら、『哲学の起源』「附録」を読み進めていくこととしましょう。
次は、各時代社会における諸交換様式のあいだの関係。どれかがドミナントになって他様式を規制し抑圧・変形します。
古代・中世の『国家社会では、交換様式Bが支配的であるが、ここには交換様式AもCも存在する。たとえば農村共同体が存在し、都市には商工業が発達する。ただ、それらは交換様式B、すなわち専制国家ないし封建的国家によって統制されている。
つぎに、近代資本制社会では交換様式Cが支配的となるが、それまでの交換様式A・Bも存続する。ただし、変形されたかたちで。すなわち、封建国家における賦役や貢納は、近代国家において兵役や課税に変形され、解体された農業共同体は「想像の共同体」としてのネーションに変形される。かくして、資本=ネーション=国家という接合体が形成される。それが現在の社会構成体である。〔…〕
社会構成体は単独で存在するのではなく、他の社会構成体との関係において、つまり「世界システム」において存在する。したがって、社会構成体の歴史は、世界システムの歴史として見なければならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.236-237.
これは、『哲学の起源』に掲げられた図ですが、図2「資本=ネーション=国家の構造」は、ひとつの社会の中で交換様式が組み合わさった接合体、すなわち「社会構成体」の一つの例です。これは、近現代に特徴的な社会構成体です。
「世界システム」とは、地球上にさまざまな社会構成体が――近代ならば国ごとに――あって、相互に関係を結んでいる、支配・服従したり相克したりしている、そういう全体構造です。時代によっては、複数の「世界システム」が、互いに他を圧しようとして相克している場合もあります。
「ミニ世界システム」は、多数の氏族共同体あるいは部族どうしが「互酬交換」によって結びついている社会。連邦のような政治的統一体を形成している場合も、形成しないでバラバラな場合もあります。基本的に「国家」以前の社会です。
「世界帝国」システムでは、中心にある強大な専制国家が、権威による支配(冊封)、互酬的な物資交換(朝貢貿易)、軍事的征服統制などによって、周辺の諸「国家」や「ミニ世界」を覊束しています。倭国は、もともとは「世界帝国」中国の亜周辺にある「ミニ世界」の一つでしたが、中国の王朝から紫綬金印を受けて権威付けられたり、遣唐使交易を行なったりして次第に「世界帝国」システムに編入されていき、その過程で自らも「専制国家」の体制を整えていきました。
近代の世界史も、「資本=ネーション=国家」の集合体である「近代世界システム」が、解体しつつある「世界帝国」や「ミニ世界」を蚕食して自らのうちに取りこんでゆく過程であったと言うことができます。
『最後に、それ〔「資本=ネーション=国家」からなる近代世界システム――ギトン註〕を超える新たなシステムが考えられる。それは、交換様式Dによって形成される世界システムである。カントが「世界共和国」と呼んだものは、これである。』
柄谷行人『哲学の起源』,pp.237-238.
「交換様式D」について、さきほどは、「想像的な次元に存在する」としていましたが、それは、“現在までのところは、そう言うほかはない” ということなのでしょうか。ここでは、現在のドミナントとしてある「近代世界システム」を超える「新たな世界システム」は、「カントが[世界共和国]と呼んだもの」、すなわち「交換様式Dによって形成される世界システム」である、としているのです。
この議論からすると、やはり「交換様式D」は、「想像的次元」にだけある観念的なもの・と考えるわけにはいかなくなります。観念的次元にだけある「世界システム」――などというものは、理解しがたいからです。そんなものがありうるとしたら、ひと頃はやった “世界連邦政府” のような怪しげな架空世界になってしまいます。
カントの「世界共和国」構想については、『力と交換様式』に戻った後、最終節で検討することになります。それはたんなる観念上のものではありません。
ここでは、「交換様式D」は、たんなる「想像的次元」のものではない、その政治経済的・物質的基礎こそ解明してゆく必要がある――ということを確認して、前著「附録」の読解を続けたいと思います。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!